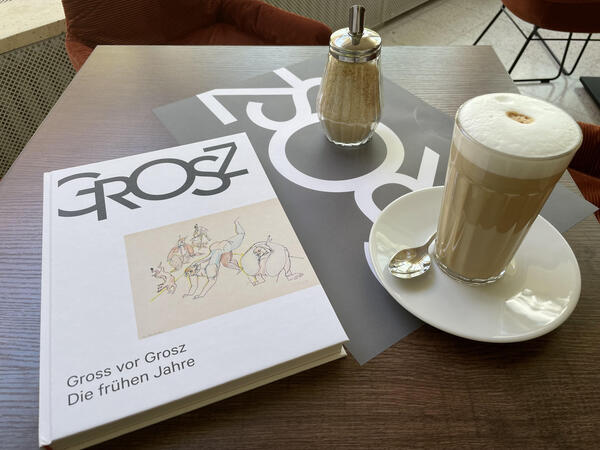ジョージ・グロスの/と現在 ベルリン、ダス・クライネ・グロス・ムゼウム訪問
今、ベルリンの西の名所ポツダマープラッツ(ポツダム広場)界隈にいるとしよう。時間は昼を過ぎたころ。冷戦期には壁があり、その一部が──記念碑かつ観光資源として──残っているこの広場を中心に、観光客や住民、多くの人々が思い思いの時間を過ごしている。20世紀前半にはデパート、ヴェルトハイムの一つがあった場所に建つモール・オブ・ベルリンではショッピングを楽しめる。ドイツ・キネマテークの展示室で、ドイツ映画の軌跡を辿るのもいいだろう。ヴィム・ヴェンダースの映画『ベルリン・天使の詩』(1987)で有名なベルリン州立図書館には、新型コロナウイルス感染症対策規制があったころはインターネットで事前予約をしなければ入れなかったが、今は利用証さえあればすぐに入れる。ベルリン・フィルハーモニーの本拠地では、日中の小さなコンサートや館内ツアーが開かれているかもしれない。絵画館では、13世紀から18世紀までの絵画をゆったりと堪能できる。2015年以降の改装ののち、2021年8月にリニューアルオープンした新ナショナルギャラリーで、20世紀前半、特に1920年代のドイツ絵画を鑑賞するのもおすすめだ。──さて、こうした施設にいるのであれば、そこから出て、ポツダマープラッツを東西に貫くポツダマーシュトラーセ(ポツダム通り)を南西へ進もう。歩くと少し遠いので、バスに乗ったほうがいいだろう。景色が少しずつ変化する。巨大な文化施設は姿を消し、小さなカフェやパン屋、肉とスパイスの匂いが漂う中東系の飲食店、アジア系の料理店などが軒を連ねるようになる。異なる国にルーツを持つ多様な人々が集まる、現代ベルリンの下町だ。通りが電車の高架と交わるところでバスを降りて、ビューロウシュトラーセ(ビューロウ通り)を西へ歩いていくと、人の背丈よりも高い白い塀に囲まれ、内側には竹などの木々が生い茂っている場所が姿を現す──ベルリンで生まれ、1920年代ベルリンを生き、ベルリンで死去した画家ジョージ・グロス(1893-1959)に捧げられた美術館、ダス・クライネ・グロス・ムゼウムDas Kleine Grosz Museumだ[図1、図2]。
[図1]ダス・クライネ・グロス・ムゼウムの門。通りから、なかはほとんど見えない。(2023年1月15日筆者撮影)
[図2]門から敷地内に入ると、小道がダス・クライネ・グロス・ムゼウム入口に続く。(2023年1月15日筆者撮影)
*
この美術館は社団法人ジョージ・グロス協会ベルリンが所管機関となり、2022年5月に開館した*1。筆者は幸運にもベルリン留学*2中にこの美術館の開館を迎え、2022年6月と2023年1月に訪問することができた。開館から一年以上が経過し、特別展もすでに三つが開催された今、筆者の経験を踏まえ、特別展にも目を向けつつ、この美術館の紹介と、今後への期待を込めた考察をしてみたい。
*1 当該美術館に関する基本情報は、ダス・クライネ・グロス・ムゼウムのウェブサイト(https://www.daskleinegroszmuseum.berlin)を参照。本研究ノートで参照するウェブサイトの最終閲覧日はすべて2023年8月30日。
*2 日本学術振興会若手研究者海外挑戦プログラムおよびJST 次世代研究者挑戦的研究プログラム JPMJSP2110の支援を受けた。
さて、この美術館の名称を邦訳するのであれば、グロス小美術館といったところになるだろう。この名称には一捻りどころか三捻りある。第一に、これは言葉遊びになっている。「グロスGrosz」はもちろん画家の名字だが、その発音はドイツ語の「大きいgroß」に似ている。それゆえ、「小さいklein」が入ることで、「グロスGrosz」は音として二重の意味を喚起し、名称全体としては、小さな「大きな/グロス」美術館となる*3。第二に、この名称には元ネタがある。1917年のグロスの画集『クライネ・グロス・マッペKleine Grosz Mappe』である。先に筆者がこの美術館を「グロス小美術館」と訳したのは、この画集が『グロッス小画帳』*4や『グロス小品集』*5と邦訳されており、それに合わせようと思ったからである。美術館の名称が、この画集にオマージュを捧げたものとなっていることは、この美術館が目指す方向性とも関わるため、後述することとなる。
*3 この言葉遊びに関して、以下にも言及および解説がある。Ed Cunningham: “A minuscule (but very charming) museum just opened in an old Berlin petrol station. The Kleine Grosz Museum is entirely dedicated to the works of caricaturist George Grosz,” Time Out, 24 May 2022, https://www.timeout.com/news/a-minuscule-but-very-charming-museum-just-opened-in-an-old-berlin-petrol-station-052422(Time Out Tokyo Editorsによる邦訳ページもある。「ドイツのベルリンにジョージ・グロスの美術館がオープン:「20世紀最大の風刺画家」の人生と作品を紹介」Time Out、2022年5月30日、https://www.timeout.jp/tokyo/ja/news/das-kleine-grosz-museum-in-berlin-053022).中村真人「1枚の写真から始まる ベルリン 発掘の散歩術 ジョージ・グロスの小さくて大きな美術館」News Digestドイツニュースダイジェスト、2023年2月7日、http://www.newsdigest.de/newsde/regions/berlin/13445-1187/。
*4 宇佐美幸彦『ジョージ・グロッス──ベルリン・ダダイストの軌跡』関西大学出版部、1988年、78頁。
*5 水沢勉(編)『ジョージ・グロス:20世紀最大の風刺画家:ベルリン−ニューヨーク』朝日新聞社、2000年、192頁。本画集名の表記があるグロスの年譜の翻訳は、木村理恵子による。
第三に、この美術館は本当に小さい。元々は歴史あるガソリンスタンドであり、現在は塀で囲まれた敷地のなかに、細長く狭い展示室を一階と二階に各一部屋設けた建物と、ガソリンスタンドを改築したカフェ、そして庭を密集させている[図3]。その展示室の少なさ、狭さから推察されるように、展示品も多くはない。なお、この狭さゆえだろう、ベルリンの新型コロナウイルス感染症対策が緩和されたのちも今日に至るまで、この美術館への入館にはインターネット予約が必須である。名称に含まれる「小さいklein」は単なる言葉遊びではないことを頭の片隅に留め置き、訪問する際には注意されたい。
[図3]きれいな赤で塗られたガソリンスタンドの屋根が残る庭。(2023年1月15日筆者撮影)
では、このように凝った名称の美術館の展示は、どのようになっているのだろうか。グロス個人の美術館はこれまで存在しなかったとはいえ、グロス研究にはある程度蓄積があり、展覧会も各地で開催されてきた。それらを踏まえた上で、この美術館はグロスの多岐にわたる制作物をいかに展示し、何を目指しているのか。
展示は、一階の常設展「ジョージ・グロス 人生と作品」から始まる。ここで作品として展示されているのは、主に素描画と水彩画である。それに加えて、タッチ式のスクリーンも用意されており、特に素描画の実際の受容形態であったグロスの画集をスクリーン上に見ることができる。これらは落ち着きのある青色を基調とした展示室に、時系列に──「A GrossからGroszへ:子ども時代と青年期」、「B 政治化と急進化:第一次世界大戦」、「C ダダ」、「D ヴァイマル共和国:政党活動としての芸術」、「E 複製されたグロス」、「F アメリカでの再出発」、「G 「アメリカの夢」への失望」──並んでいる。ドイツの帝政期から第一次世界大戦、ヴァイマル時代、ナチの時代、第二次世界大戦、戦後の混乱へという、激動の時代を生きたグロスの軌跡、そしてその制作物の変遷を、鑑賞者はこの部屋で辿ることとなる。グロスの制作物のなかでも、彼を代表するのは、第一次世界大戦期からダダとしての活動期を含むヴァイマル時代のそれだろう。そこには、虚栄に満ちた大都市ベルリン、そしてそこにグロスが見出した人々のグロテスクに戯画化された顔が溢れている。こうした風刺画のなかで、政府や軍といった巨大権力、労働者階級を食い物にする富裕層、そしてしばしばナチをも揶揄し、批判していた画家グロスは、1932年にアメリカへ実質的に亡命した。それ以降の制作物もここで展示されており、その作風の変化を見ることができる。なお、グロスのアメリカ滞在期の制作物に登場する「スティック・メン(棒人間)The Stick Men」は、常設展のみならず特別展「ジョージ・グロス スティック・メン」(2023年5月25日から10月30日まで)でも取り上げられている。
常設展の大まかな内容を書くにあたり、筆者は「巨大権力や富裕層などを批判していた画家」や「1932年にアメリカへ」といった説明を付け加えたが、実際には、展示室にそうした詳細な情報は記されていない。グロス本人や制作物に関するキャプションは必要最小限に限定されている(特別展のカタログなど用意された資料や、美術館のウェブサイトには詳細な情報が載っている)。展示物に合わせて壁に書かれているのは、上述のAからGまでの時期区分と、各制作物の題と制作年、素材と所有者の情報だけである。文章を加えることでグロスと彼の制作物についての知識を伝達するというよりも、実際の制作物──しかも画集に印刷されたコピーではなく、オリジナル──を見せることを重視する美術館側の戦略がはたらいているのだろう。たしかにそれは、書籍では実現不可能な贅沢な展示であり、細かな筆跡や色斑まで目視できる貴重な機会や、個々の鑑賞者にその見方や感じ方が任される、自由で開かれた鑑賞をもたらす。
しかし、グロスの制作物に限って言えば、その意味内容まで踏み込んで展示および鑑賞するために、制作時期の社会状況やグロスの政治的活動に関する解説がある程度は必要ではないだろうか。というのも、上述のように当時の権力や富裕層を揶揄したり、批判したりするグロスの素描画や水彩画は、その意味内容の点で、多かれ少なかれ当時の社会的・政治的文脈に依存しているからである。これまでのグロスに関する研究や言及においても、当時の状況の参照は、グロスと彼の制作物を論じるにあたり欠かせないものであった*6。そして、軍に対して批判的なグロスの画集『神は我らとともにGott mit uns』(1920)を前にしたジャーナリスト、クルト・トゥホルスキー(1890-1935)が、「もし素描画が殺すことができれば、プロイセン軍は確実に死んでいる。(ちなみに素描画は殺すことができるのだ。)」*7という独特の表現で賞賛したように、グロスが描くものの意味内容が理解されたとき、それは攻撃力の高いある種の武器として、あるいは武器であったものとして現前する*8。当時の文脈の解説をすることなく、意味内容を括弧に入れた上で、グロスの制作物を展示することは、それ特有の武器としての攻撃力を見落とすことになってしまうのではないだろうか。
*6 代表的なグロスの伝記的研究としては以下のものが挙げられる。Hans Hess: George Grosz, Dresden, VEB Verlag der Kunst, 1982 (c 1974). 芸術と社会、芸術と政治が緊密な関係にあったヴァイマル時代のドイツ美術史のなかでも、グロスはその代表的画家の一人として取り上げられてきた。以下などを参照。Wolfgang Hütt: Deutsche Malerei und Graphik 1750-1945, Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1986, S. 358-369; Harald Olbrich (Hrsg.): Geschichte der deutschen Kunst 1918-1945, Leipzig, E. A. Seemann Verlag, 1990, S. 255-259; Rosa von der Schulenburg: «Künstler als Reformer und Kritiker», in: Barbara Lange (Hrsg.): Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland Band 8. Vom Expressionismus bis Heute, München•Berlin•London•New York, Prestel Verlag, 2006, S. 472.
*7 Peter Panter (Kurt Tucholsky): «Dada», in: Berliner Tageblatt, 20.07.1920, zit. nach: Bärbel Boldt, Gisela Enzmann-Kraiker und Christian Jäger (Hrsg.): Kurt Tucholsky Gesamtausgabe Band 4: Texte 1920, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Verlag, 1996, S. 312.
*8 グロス自身も「武器Waffe」という比喩を用いている。「残忍な中世や現代の人間の愚かさに対して、図画Zeichenkunstは有効な武器eine wirksame Waffeたりうる──明快な意志と鍛えられた手がそれを行使するのであれば」(George Grosz: «Kurzer Abriß», in: Künstlerische und kulturelle Manifestationen, Ulm-Donau, Hermelin-Verlag, 1924, S. 24.)。比較的最近の先行文献にも、以下のように、社会批判的な武器としてグロスの素描画を論じるものがある。Anne-Marie Werner: «Die Zeichnung als „Waffe“», in: Ausstellungskatalog George Grosz. Kunst als Sozialkritik. Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafien, Dillingen/Saar, Krüger Druck + Verlag, 2007, S. 9-19.
このような疑問を頭の片隅に残しつつ、特別展のための展示室となっている二階へ階段を上がる。この美術館における第一回特別展は「Groszの前のGross 初年代」(2022年5月13日から10月17日まで)であり、自らの名前をGroszと書く前、著名な画家となる前の、本名Grossの頃の若きグロスとその制作物に光が当てられた。それに続く第二回特別展「1922年 ジョージ・グロス、ソヴィエトロシアへ旅する」(2022年11月23日から2023年4月30日まで)では、1922年のソヴィエトロシア訪問を基軸に、グロスと共産党の関係が丁寧に辿られた。そして、第三回特別展は上述した、アメリカ滞在期の「スティック・メン」に焦点を絞ったものとなっている(筆者は第三回特別展のみ未訪問)。
特別展のための展示室では、一階の常設展と打って変わって、展示物の間に比較的詳細な解説が加えられている。そのなかに、この美術館の方向性を示唆するものがあった。第一回特別展における、画集『クライネ・グロス・マッペ』に関する解説である。この解説文と内容は同じだが、一部言葉が補足されることでより親切な文になっているものが特別展カタログに記載されているため、そちらから引用しよう。
遅くともこの画集から、この芸術家の一般に有名な制作物が始まる。『クライネ・グロス・マッペ』は、ジョージ・グロスの絵と政治的メッセージの広範な作用の始まりである──そして、それゆえに、この画集はこれら作品と作用/活動Werk und Wirkenに捧げられた美術館の名称に影響を及ぼした。つまり、ダス・クライネ・グロス・ムゼウムである*9。
画集『クライネ・グロス・マッペ』は、画家としてのグロスの軌跡の最初を飾るものであり、そこからグロス、そして彼の(特に政治的に作用する)制作物は始まった。このようにこの画集を解した上で、名称を引き継いだダス・クライネ・グロス・ムゼウムは、まさにその画集のような存在、つまり、グロスや彼の制作物に関する議論が新たに始まり、今後に影響を与える場となることを目指している。このとき、グロスの経歴や制作物のなかの一端に焦点を絞った特別展は、新たな議論を始めるための試みとなる。
*9 Pay Matthis Karstens und Juerg Judin: «„Schreiben Sie doch bitte Grosz statt Gross“ Wie aus Georg Ehrenfried Gross der politische Künstler George Grosz wurde», in: Das kleine Grosz Museum (Hrsg.): Ausstellungskatalog Gross vor Grosz. Die frühen Jahren, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther und Franz, 2022, S. 143.
ここで、新たな議論に対して古いものと暗に措定されているものはなにか。それは、もっぱら当時の社会的・政治的文脈のなかで「研ぎ澄まされ、政治的・社会的に関与し、社会を綿密に観察する芸術家」*10としてグロスを論じ、そのようなグロスが生み出した武器として制作物を語る、もはや紋切り型となった議論である。上述したように、常設展ではグロスの政治的活動や、彼の制作物の攻撃力が看過されているように思われるが、議論の新旧の点から評するのであれば、常設展はこれまでのグロスに関する議論にありがちであった社会的・政治的文脈を含め、あらゆる文脈をあえて一旦取り払い、ただ時系列にグロスとその制作物を整理および把握する場として機能しているといえる。それにより多様な議論の可能性を開いた上で、この美術館は特別展にてグロスとその制作物に、具体的な観点から光を当て、新たに議論を始めようとしているのである*11。
*10 Klaus Lederer: «Geleitwort», in: Das kleine Grosz Museum (Hrsg.): 2022, S. 7.
*11 「新たな観点から」グロスと彼の作品を提示することは、キュレーターのパイ・カルステンスへの以下のインタビューおよびそのレポートでも言及されている。Pay Karstens im Gespräch mit Sigrid Brinkmann: «Georg Grosz-Museum in Berlin. Dada an der Tankstelle», Deutschlandfunk Kultur, 01.02.2022, https://www.deutschlandfunkkultur.de/tankstelle-wird-zu-georg-grosz-museum-100.html.
このように、もっぱら社会的・政治的文脈を重視する議論を相対化する試みは、実のところ、社会の下層へと関心を寄せた1920年代ドイツの左派の画家たちと彼らの制作物に関する、最新の展覧会の傾向と共鳴している。ナチの時代や東西の分断の時期を経て、1920年代から一世紀が過ぎた今日、そうした絵画は徐々に、社会的・政治的文脈のなかで論じられるにとどまらなくなってきたようだ。筆者の念頭にあるのは、2022年5月11日から9月5日までポンピドゥー・センター(パリ)で、その後同年10月13日から2023年2月19日までルイジアナ近代美術館(コペンハーゲン近郊フムレベック)で開催された展覧会である*12。1920年代のドイツ文化を「新即物主義」の観点から包括的に取り上げるという意欲的なこの展覧会では、「下方への眼差し」と題されたセクションが用意された。そこでは、「あらゆる支配的な資本の影の側面を暴露したいという願望」に駆られ、「技術的進歩から排除されている、あるいは過大な要求をされている、ほとんど知覚されない人々」*13に関心を寄せる画家たちの絵画が、労働者階級の人々の生活を切り取った同時代の写真および映画とともに展示された。こうした絵画、そして写真と映画が社会的・政治的文脈のなかで生成し、作用していたことはもちろん否定されず、展覧会カタログでも十分に説明されている*14。しかし、絵画・写真・映画をまとめて展示したこのセクションで強調されたのは、その点ではなく、社会の「下方への眼差し」や関心が多様なメディアに広がっていたこと、あるいはそうした関心のために多様なメディアが用いられたことである。ここで、それら絵画は、社会の下層を捉えんとしたさまざまなメディアの一部として新たに光を当てられたのである。
*12 各美術館のウェブサイト内には、当該展覧会用のページがある。ポンピドゥー・センター当該展覧会ページ(https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/dEOe6u0)、ルイジアナ近代美術館当該展覧会ページ(https://louisiana.dk/udstilling/det-kolde-oeje-tyskland-i-1920erne/)参照。
*13 Angela Lampe (Hrsg.): Ausstellungskatalog Die neue Sachlichkeit - Deutschland - 1920er Jahre - August Sander, München, Schirmer/Mosel Verlag, 2022, S. 257. この展覧会はドイツでは開催されなかったものの、ドイツ語版の展覧会カタログは刊行された。筆者はドイツ語版カタログを参照している。
*14 Christian Joschke: «Die kalte Revolution: der „Blick nach unten“ der Neuen Sachlichkeit» (Aus dem Französischen von Saskia Bontjes van Beek), in: Lampe (Hrsg.): 2022, S. 258-265.
グロスの美術館に話を戻すと、多様な観点からの特別展を企画することで、この美術館は、社会的・政治的文脈のなかで社会批判者として論じられてきたグロス、そしてその武器とされてきた彼の制作物の、多様な側面を照らし出し、議論を新たな段階へと押し進める。第一回特別展カタログの前書きには次のように書かれている。
グロスは単に、自らの時代の特徴的な芸術家、卓越した政治風刺画家、厭人家、博愛主義者、アメリカの崇拝者、最終的にはアメリカの市民であっただけではない。彼は指標となる芸術家集団にも属し(ほんの数例を挙げると、ベルリン・ダダ、ノヴェンバーグルッペ、新即物主義)、同時代の多くの重要人物たちと協働していた。そうしたところから、彼の作品と作用/活動sein Werk und Wirkenをめぐって一つの宇宙ein ganzer Kosmosが生じたのであり、その宇宙を私たちはこれから五年をかけて、十の特別展で探り出し紹介する*15。
二つの特別展が終わり、三つ目の特別展が開催中の現在、残り七つの企画が予定されている。その詳細な情報はまだ明かされていないが、それら特別展は「宇宙」の新たな側面をさらに照らし、議論をさらに開くものものであることが期待される。
*15 Ralph Jentsch, Ralf Kemper und Timon Meyer: «Vorwort», in: Das kleine Grosz Museum (Hrsg.): 2022, S.9.
*
さて、この期待をもう少し膨らませてみたい。現在までの三つの特別展は、一階の常設展で時系列に示されたグロス存命中の時期のなかから、具体的な観点を拾い上げていた。しかし、上の引用箇所には「彼の作品」のみならず、作用や活動といった意味をも持つWirkenとも書かれていることから、作品の「作用」までを考慮に入れると、その「宇宙」はグロスが死去した1959年で終わるものではないだろう。実際、グロス自身、自らの制作物が将来において受容されることに意識的であった。より正確には、将来における理解に希望を託していた。1933年の手紙のなかで、ナチのプロパガンダとしての展覧会にて自身の素描画がボルシェビズムのレッテルを貼られ展示されたことを受けて、彼は次のように書いている。
そしてこれらの私の絵は、のちの世代に観てもらえるでしょう、ちょうど私たちがゴヤの不朽の残虐な場面を観るのと同じように。「私はそれ見た、体験した。これが私のドイツだった、これが真実だった」──ヒトラーがさらになにかをしようとも、これは残り続けるでしょう──that’s all!*16
「のちの世代」──1933年当時のグロスはまだ知る由もないが、今日から見れば、第二次世界大戦後の人々や、冷戦期の人々、そして冷戦後の人々──は、いかにグロスの制作物を観たのか、それらはいかに意味づけされ、作用したのか。「宇宙」はどのように広がったのか。1959年以降にも光を当てるような特別展があってもいいだろう。
*16 George Grosz: Brief an Felix Weil am 21.07.1933, zit. nach: Herbert Knust (Hrsg.): George Grosz Briefe 1913-1959, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Verlag, 1979, S. 179.
さらに、現在の私たちも、グロスの制作物を観る「のちの世代」に属している。では、私たちは現在において、そのいかなる作用の可能性を引き出すことができるだろうか。これに関して、グロスが名前を挙げているゴヤ(1746-1828)、その「残虐な場面」の絵の現在地を参考にしつつ考えてみたい。ゴヤの作品のなかでも、グロスの素描画と同じく線描で、画集のような連作のかたちをとっており、とりわけ残虐な情景に溢れているのは連作「戦争の惨禍」(1810-1814)だろう。「私はそれを見た、体験した」という記述からも、「私は見た」などの各題を伴うこの連作が想起される。そして、ゴヤのこの連作は今日──残念なことではあるが──現在の戦争、ロシアによるウクライナへの攻撃を照らしている。ウィーンのアルベルティーナで2022年8月21日まで開かれていた展覧会「戦争の惨禍:ゴヤと現在」では、ウクライナ出身の写真家Mykhaylo Palinchak(1985-)による、ウクライナの現在の様子──破壊された住居や街、死者、ウクライナに留まる人々、ウクライナから逃れる人々──を捉えた写真と、ゴヤの「戦争の惨禍」が同じ展示室内に並べて展示された*17。もちろん、これと同じようにグロスの素描画や水彩画を展示すべきだと主張したいのではない。しかし、社会や世界の歪みや腐敗を描いたグロスの制作物もまた、現在を照射しうるのではないだろうか*18。その可能性を引き出す場として、グロスと彼の制作物に捧げられ、さまざまな人々が暮らす現代のベルリンの下町に設立されたダス・クライネ・グロス・ムゼウムほどふさわしい場所はないように思われる。
*17 アルベルティーナのウェブサイト内にある当該展覧会ページ(https://www.albertina.at/ausstellungen/die-schrecken-des-kriegs-goya-und-die-gegenwart/)参照。このページでは、展示物の一部や展示の様子を写真で見ることができる。写真家Mykhaylo Palinchakのウェブサイト(https://palinchak.com.ua/projects)も参照。
*18 以下では、「グロスの眼差し」が「今日までその効力を何一つ失っておらず、今日もなお極めて説得的である」と主張されている。Pay Karstens im Gespräch mit Sigrid Brinkmann: «Georg Grosz-Museum in Berlin. Dada an der Tankstelle», Deutschlandfunk Kultur, 01.02.2022, https://www.deutschlandfunkkultur.de/tankstelle-wird-zu-georg-grosz-museum-100.html.
実際、この美術館も、展示を通じて現在を思考する場になる野心を抱いているようだ。美術館のウェブサイトには、次のような記述がある。「(…)この美術館は、一人の芸術家の歴史化に寄与するのではなく、彼の好戦的な個性にふさわしく、世代間や政治的陣営間の活発な交流を促進し、現在の社会的諸課題に立ち向かう」*19。特にソヴィエトロシアへの旅を扱った第二回特別展は、そのような試みを根本に少なからず宿していた。そのカタログには、ウクライナを攻撃する現在のロシアの前身であるソヴィエトロシアを取り上げること、さらに「長い間解決済みとされていた共産主義のアジテーション芸術を蒸し返すこと」*20への批判を見越した上で、次のような、自ら論争の場となる決意表明ともいえる記述が載っている。
しかし、グロスに取り組むことは、そうした反論に耐えることでもあり、くたくたになるまで向き合うことでもある。そして、時の経過とグロスの芸術的または個人的発展に先入観なく取り組む人は、現在への認識も手に入れることができる*21。
今後、この美術館はいかに「グロスに取り組」み、さまざまな意見に「くたくたになるまで向き合」い、グロスの制作物のアクチュアルな作用の可能性を引き出すのか、それによってグロスと彼の制作物はいかなる現在を照らすのか。期待が膨らむと同時に、美術館のみならず、来館した鑑賞者個々人も考え続けねばならない。
*19 ダス・クライネ・グロス・ムゼウムのウェブサイト(https://www.daskleinegroszmuseum.berlin)内にある項目«Mitmachen»の文中。
*20 Ralf Kemper: «Vorwort», in: Das kleine Grosz Museum (Hrsg.): Ausstellungskatalog 1922 – George Grosz reist nach Sowjetrussland, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 2022, S. 7.
*21 Kemper: 2022, S. 7.
*
[図4]カフェで一服。(2022年6月5日筆者撮影)
[図5]カフェの内側からの眺め。(2022年6月5日筆者撮影)
二階の特別展を堪能したら、一階へ戻り、常設展を通り抜けて入口と同じ扉から展示室を出る。特別展カタログを購入し、それに目を通しながらカフェで一服するのもいい[図4、図5]。時間は夕方ごろになっているだろうか。美術館を出て、来た道を戻るのではなく、ビューロウシュトラーセをさらに西へ進む。高架を走る電車に乗るという手もある。道は途中でクライストシュトラーセ(クライスト通り)に変わる。ヴィッテンベルガープラッツ(ヴィッテンベルク広場)に着くと、通りはさらにタウエンツィーンシュトラーセ(タウエンツィーン通り)に変わり、まわりは突如として高級な雰囲気が漂う繁華街になる。1907年にオープンした高級デパート、カー・デー・ヴェーをはじめ、大小のお店が並び、(ウィンドウ)ショッピングをする人々が行き交う。目抜き通りクーアフュルシュテンダム、通称クーダムまではもう一直線だ。そこにあるカイザー・ヴィルヘルム記念教会は、戦争による破壊の痕跡を、さらにその広場には2016年12月19日の事件──トラックがクリスマスマーケットに突入し、犠牲者が出た──の痕跡を残している[図6、図7]。ポツダマープラッツや、グロスの美術館がある下町を思い出しながら、この、グロスもしばしば描いた場所に、美術館で見た彼の素描画や水彩画をフィルターのように頭の中で重ねてみよう。それらは完全に合致するわけでも、完全に異なるわけでもないだろう。グロスが描いた1920年代を痕跡として、あるいは空気のなかに残しつつ、ナチの時代や戦争、戦後の分断と統合、移民の増加、そして最近では新型コロナウイルス感染症流行など、さまざまな経験をしてきたベルリン、さまざまな時間をパッチワークのようにとどめた国際都市ベルリン──そこにどのような現在が見えるだろうか。
[図6]タウエンツィーンシュトラーセ(タウエンツィーン通り)から眺めるカイザー・ヴィルヘルム記念教会。(2021年11月26日筆者撮影)
[図7]クリスマスマーケットが開かれ、イルミネーションが輝くクーダム。(2022年12月8日筆者撮影)