ミシェル・フーコー、経験としての哲学 方法と主体の問いをめぐって
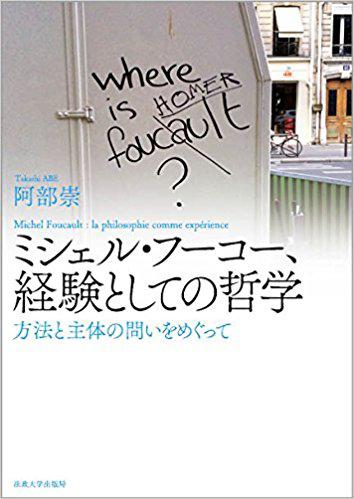
本書は、フーコー研究者の阿部崇による初の単著であり、2006年にパリ第10大学に提出された博士論文を日本語で書き改めたものである。この本のなかで阿部は、「ミシェル・フーコー」という文字列で名指される一連の思想の形成過程を、時系列順に論じている。著者は、しばしばなされるような、事後的に見出された一貫するモチーフによってフーコー思想の全体像を一挙に提示するという方法は採らない。過去の著作や仕事を単純に肯定し続けるのでもなければ、全面的に放棄するのでもなく、絶えずその都度その都度の「現在」の視点からそれ以前の自己に向き合い、絶えざる捉え直しを敢行することによって新たな方法論を生み出し続けていく思想家フーコーの在り様を、阿部は丹念な研究によって描き出している。
この著作は大きく三部に分かれている。すでに佐藤嘉幸氏による書評(http://dokushojin.com/article.html?i=3159)があり、そこでも簡潔に議論の流れが示されているが、ここでも筆者なりに全体の見取り図を示すことにしよう。
第一部では、1950年代の批判的な心理学研究から出発して、彼が自らの「考古学」的な方法論を練り上げるまでの時代を扱っている。心理学の方法論についての研究でデビューしたのち、『狂気と非理性』(1961)から『言葉と物』(1966)にいたる探究活動のなかで、フーコーは或る時代の知的な活動を規定する条件を探求の対象として発見する。すなわちそれが、或る時代に属する主体が知的な認識活動を行う際にその認識のあり方を規定する歴史的な条件、「歴史的アプリオリ」である。
第二部では、『言葉と物』から『知の考古学』(1969)にいたるまでの数年間(1966-1969)、この短い期間に格別の注意が払われている。この時期にフーコーは、「歴史的アプリオリ」という概念が「認識する主体」と不即不離の構造を持ってしまっていることによって、自身の研究の射程が制約されてしまうことに自覚的になっていく。彼は、博士論文『狂気と非理性』の副論文として提出した『カントの人間学』という論文のなかですでに、認識の対象が人間による認識行為それ自体によって作り出される「人間学的構造」において、認識の領域全体が人間の有限性という限界のうちに閉じ込められてしまうことへの疑念を表明していた。その後、『言葉と物』で古典主義時代のエピステーメーについて触れた箇所で、やがて消え去るであろう「人間」という形象をフーコーが論じたとき、「認識する主体」さえもが、同時代の言説によって歴史的に構成されるものである、と相対化するための地平が拓かれたのである。『カントの人間学』や『言葉と物』といった著作のなかで暗に表明されていた立場を捉え返していくなかでフーコーは、主体の認識に先立ち、主体そのものを構成する「言表」あるいは「言説」といった探求の対象を発見することになる。このようにして、『知の考古学』は書かれるのである。
第三部では、『知の考古学』以後のフーコーが自らの思想のなかに「系譜学」と呼ばれる方法論を導入していく様子が描かれる。彼は、主体を経由することなく描き出された言説の布置関係のなかに「権力」という分析対象を発見する。ここで発見される権力概念は、主体を経由せずに見出されるという点で、ふつう考えられているものとは趣が異なる。それぞれの言説に内在し、言説同士の関係を規定する権力。それは、どのように私たちの生に働きかけるのだろうか。フーコーはこの権力概念を、マキャベリ的な「トップダウン」式の権力図式に対抗して書かれた反マキャベリ的な文献の「ボトムアップ」式の権力図式を援用することで描き出している。抑圧して従わせるのではなく、便宜を図って自由を提供する「自由主義的」な権力の様々な機能の分析がこうして1970年代以降のフーコーの主題となっていく。以上のような思考の地平もまた、探求の対象から主体を一旦除外することによって言説というレヴェルを発見した『知の考古学』までの仕事を自ら捉え直すなかでフーコーが見出したものなのである。
以上のように、本書ではフーコー思想の布置の変遷が大づかみに描き出されている。それは、特定の概念について細かく註釈を加えながら進められているわけではないが、フーコーが遺した分野の多岐にわたる、これまた膨大な量のテクストを渉猟した筆者だからこそ可能な強度を、本書の議論は維持している。
とはいえ、あとがきで筆者自身が述べているように、著者が博論を執筆していた当時と比べると、フーコーの著作・講義録の出版状況も大きく変わり、それに伴ってフーコーの思想の変遷がどのようなものであったかについての認識もある程度人口に膾炙している。『言葉と物』において論じられた認識する主体にとっての「歴史的アプリオリ」、すなわちエピステーメーの探求から、『知の考古学』以降における、主体から切り離され、むしろ主体を構成するような身分を与えられた「言説の存在条件」探求へ、という図式そのものに目新しさを認めることは難しい。しかし、むしろそのような共通認識が出来上がった状況だからこそ、単なるフーコー解釈に局限されない、著者の丹念な研究の独創性も認めやすくなっている。
本書の白眉となるのは第二部の議論である。冒頭にも述べたように、はじめからフーコー思想の全体を包括するような大局的な視点を想定するのではなく、それをあえて放棄し、その都度その都度のフーコーの思想の布置を捉えようとしているがゆえに、事後的な観点から「フーコー」という思想家を捉えようとしたときには消え去ってしまうもの、それ自体は概念として自立することなく、別の仕方で表されたフーコーの思想に吸収されてしまったもの、フーコー自ら放棄したいくつものプロジェクトがいかにその都度のフーコー思想を賦活していたかが読み取れるようになっている。
とりわけ興味深いのは第二部第二章の議論であり、放棄された「ダイクソロジー」という概念をあえて採り上げることによって、フーコーの思考の些細な、しかし前期と後期の差異をもっともよく象徴することになる思想の裂け目を見出している。フーコーが『言葉と物』を回顧的に捉え直しながら、まったく新たな仕方で『知の考古学』の方法論を打ち立てたということは先にも述べた。この経緯を、「ダイクソロジー」を始め、レーモン・ベルールとの対談や「文学言語」について探求するプロジェクトのような、あまり顧みられることのないテクストの瓦礫をひとつひとつ拾い上げることで阿部は説得的に示して見せるのである。これらの議論の詳細は、ぜひ本書を手にとって確認して頂きたい。出来合いの鋳型に特権的なテクストを流し込んで作った「フーコー」のイメージに頼ることなく、あらゆる言表を蒐集し、いちからフーコーという思想家を立ち上げてみせた筆者の姿勢にも、学ぶべきところの多い著作である。
(田村正資)