研究発表パネル 日本映画における衣裳
日時:2020年12月20日(日)10:00 - 11:30
- 近代京都画壇と映画衣装──甲斐庄楠音を通して/太田梨紗子(神戸大学)
- 時代考証にみる甲斐庄楠音と溝口健二/小川佐和子(北海道大学)
- 小津安二郎作品における森英恵の衣裳/辰已知広(京都大学)
【司会】木下千花(京都大学)
【コメンテイター】小澤京子(和洋女子大学)




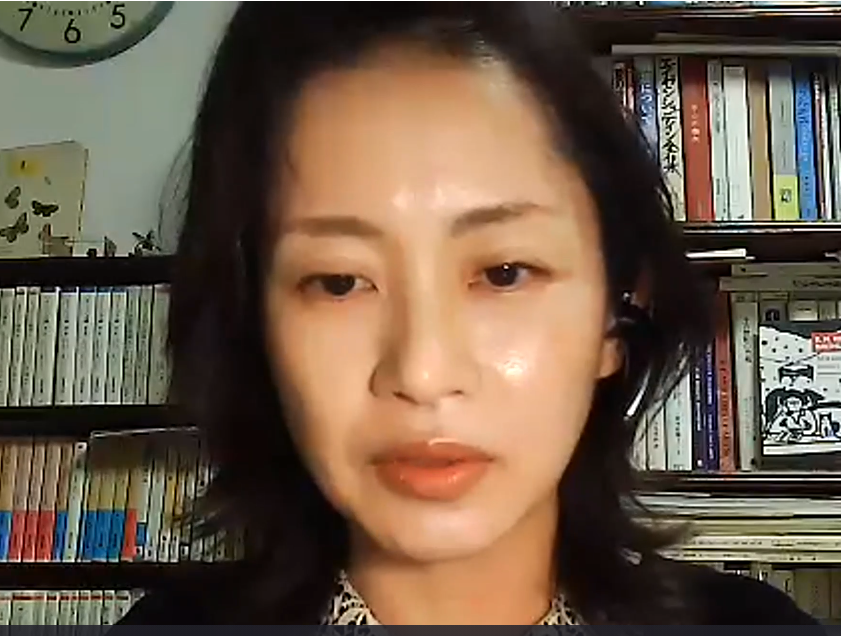
本パネルは、司会の木下千花氏の導入によると、1970年代より映画理論研究において女性研究者を中心に提題された、映画中の衣装を女性表象として扱った議論、またカルチュラル・スタディーズにおけるファッション研究といった文脈の下に置かれる。さらに、和装と洋装の混在、研究者のバックグラウンドの多様性といった日本国内の研究を困難にしかねない事情も、かえって領域横断的な考察の必要性を証し、研究の沃野を指し示すものとして展望された。具体的には、甲斐庄楠音(1894-1978)を取り上げた2名の発表と森英恵(1926-)に関する1名の発表を軸に議論が進む。
太田梨紗子氏は、第一に都市・京都におけるコネクションとコレクションを基に、甲斐庄の日本画から時代劇映画の衣装考証へという活動の拡がりを説明した。1930年代に向けて、東京における歴史画の流行や江戸趣味の一環としての琳派回帰などの伝播、考証資料の豊かさや映画産業の立地といった当地のメリット、さらに染織コレクションや歌舞伎を題材とした研究サークルの存在などが、甲斐庄の活動の展開を支えたという。当時の日本映画界が時代劇を多く制作した背景には検閲も挙げられようが、空襲被害が比較的軽微だったこの都市で、甲斐庄と映画衣装の時代考証は、戦前と戦後の落差を感じさせない、どこか超然とした貫戦期的ストーリーを織りなす(実際には戦中困窮していたと、次の発表者小川氏はいうが)。太田氏は第二に甲斐庄における蝶のモチーフを挙げ、森との接続を図った。スクラップブックの調査からこのモチーフに洋の東西をまたぐ諸要素を認め、また萬鉄五郎(1885-1927)の《風船をもつ女》(1913)という補助線から婦人運動の要素も読み込んだ。女優が被る紗、障子に張られた和紙、いや映画における第四の壁たるスクリーン、さらに遡って絵画画面に映る蝶たちは空間も実体も伴わない記号と化す(《女と風船(蝶々)》(1929)の現物はすでにない)ゆえに、その像には複数の意味をもたらす平面が重畳するといえよう。
小川佐和子氏は、甲斐庄による映画考証という公的生活の実態、およびそれと女形の実践という私的生活との往還に迫ることで、彼の内的一貫性を論証した。甲斐庄の行った考証は、衣装の形状や意匠を検証するに止まらず、小道具、着付け、結髪、身振りや歩き方の指導にも及んだという。甲斐庄はすでに1925年頃には映画雑誌を通じて関心を高めていたというが、画業においても上記アイテムの総合を試みていたならば、その際蓄積された資料や経験が、活人画を通じて映画画面にスムーズに活かされるだろう(静止画から動画へという時間軸上の展開にどう対処したかは別であるが)。活人画における女形は本人を含めた出身学校の同窓生や上記研究サークルの参加者などで行われたらしい。身体をもつ演者と作中人物とのマッチングは、特に異性装において一見必然を欠くかに思われるが、幼時より女装の手ほどきを受けた甲斐庄には、自身のセクシュアリティも含め何らかの蓋然性も見えただろう。いずれにせよ、描く者が、演じる者となって描かれる存在と化す。その過程は、例えば彦根屏風のイマジュリィをスクラップブックに貼り込み、それを『女と海賊』(伊藤大輔監督、1959)の考証に用いたという過程にも並行する。描かれたものが、本来の文脈から切り離されて寄せ集められ、描く者において新たに描かれる存在の構想へと着火する。こうした記号のサイクルにおいて、甲斐庄は画業・映画考証を通じて自らの肉体的特徴から乖離することで、描かれるべき対象としての「女の魂」に接近したのだろう。
辰已知広氏は、森英恵が1954年から映画衣装を手がけた作品中、小津安二郎(1903-1963)映画5作品(1957-1962)特に『秋日和』(1960)を分析する。「個性や表情や主張を」欠いた「ちんまりと、保守的で、ちょっと弱」い洋装の「全身無地の女」(中野翠『小津ごのみ』2008)という小津作品中の女性たちへの評価の一方に、「着替えること」という主題を掲げた蓮實重彥『監督 小津安二郎』(1983/2003)の評を挙げ、作品分析に繋ぐ。『秋日和』で森の担当は助演の岡田茉莉子(1933−)であったが、「ビジネスガール」としてのモノトーンの衣装と普段着との対照、また友人の遺した未亡人の再婚話を進めることでその娘の結婚話を進めようとする男たちに臨む際のツートーンのワンピース、娘の結婚式でのピーコックグリーンのドレスなど、ストーリー展開上の要所における選択に、小津映画での反復を超えた新しいスタイルの導入が認められる。結果的に、小津の描く懐古的かつ「神話的」な衣装スタイルを存置しながら、「確実に進む現在という時間」を並置・比較する効果をもたらしたという。後の欧米でのオートクチュールでの活躍と並行して、国内で広範な支持を得た多角的な事業展開に鑑みると、テレビの解像度に頼れなかった当時、森は細部を映せる邦画における衣装を、流行を通して新たな女性像を発信する媒体と認識しただろう。本発表は蝶の柄や田中一光(1930-2002)による蝶を象ったロゴタイプとは接続しなかったが、欧米と国内に向けたイメージの使い分けなどの視点から、森と蝶のモティーフあるいは映画との関係がさらに探究されよう。
コメンテーターの小澤京子氏は、甲斐庄のスクラップブックに関して上記のような各図像の文脈からの剥奪と創造性に関する議論に言及した。太田氏が、京都画壇内、画壇と映画産業、蝶に集約される比較文様史上の洋の東西、男女……に認めた領域横断性、つまり横の拡がりを示したのに対し、小川氏が甲斐庄という一人の人物における絵画と映画に共通するモティーフ、描画と映画と「自作自演」の女形を貫いた実践の一貫性、つまり縦の軸を示したという対比をも示した。さらに時代考証から逃れて現代を反映する衣装に関して、川久保玲(1942−)や三宅一生(1938−)に比べ言及が少ないという森(対象の性差と同時に、おそらくは先述した多角経営とそれゆえの大衆性も与ろう)を追究する意義に言及した。小澤氏は、『雨月物語』(1953)の監督溝口健二や甲斐庄にとって女性の衣装が特権的であったこと、また小津作品中の儀礼で男性がモーニングばかりであったことを超える、男性衣装固有の役割を問うたが、太田氏は『雨月物語』源十郎の巴紋にみる象徴性、『旗本退屈男 謎の怪人屋敷』(1954)早乙女主水之介の小袖由来の紋様にみるジェンダー攪乱の契機を挙げ(上薗四郎氏は甲斐庄が小袖を着て遊んだエピソードを伝えている)、辰巳氏は前期小津映画における学生服の群造形や後期におけるブリティッシュスーツなど、画面内で「丁寧に」背景化する操作を挙げた。また小澤氏は、甲斐庄における女形の実践と絵画・映画のモティーフに見られる共通性が、スクラップブックに示される構図や身振りを軸とした超域的な類似性と同根のものか問うたが、小川氏は、有名な論争を行った土田麦僊(1887-1936)とも共通する、複数のモデルから長所を寄せ集めて人物を美化するというスクラップブック的な(ゼウクシス的ともパノフスキーの命名によれば選択説とも呼べる)操作の中に、土田のような造形上の理想ではなく「女の魂」へのアプローチを求めるという甲斐庄の独自性を挙げた。
また大貫菜穂氏からは蝶のモティーフの重層性について、源豊宗氏が挙げた歌舞伎の場合と大正期の女性表象の場合のように使い分けがないか確認があったが、太田氏から多義的な作用を同時に行う旨の返答があった。関根麻里恵氏からは小津映画の男性衣装もまた状況の予告という役割を担いうるかが問われ、辰巳氏から着替えのテーマなどが挙げられた。木下氏から、同じく考証の経験がある鏑木清方(1878-1972)と甲斐庄との関係が確認されたが、小川氏から鏑木による和装女性が写真のスクラップブックにあること、太田氏から甲斐庄と鏑木の直接の接触は確認できていないが北野恒富(1880-1947)、西山翠嶂(1879-1958)を含む美人画一般への関心と、吉川観方(1894-1979)、岡本神草(1894-1933)との関係が示された。
パネル概要
本パネルは、日本映画の衣裳と衣裳担当者の仕事に着目し、映画研究を行う重要な手段のひとつを呈示することを目的とする。小川は日本画家の甲斐庄楠音をテーマに、様々な表現媒体において才能を発揮しつつ、時代考証家として溝口健二監督作品の映画衣裳を担当した彼の映画界における活躍の場とあり方を、映画史の視座から検証する。太田も甲斐庄楠音に焦点を当て、彼が手掛けた溝口監督の作品における衣裳のデザインを詳細に分析し、当時の美術界における潮流を含む絵画史を念頭に、その特殊性、独自性を考察する。一方辰已は、ファッションデザイナーとして国際的に活躍した森英恵がキャリアの初期に膨大な数の映画衣裳を手掛けていた事実に着目し、彼女が映画製作における技術者と同等の立場で映画産業に関わっていた事実と共に、小津安二郎作品における彼女の仕事とその映像への貢献について考察する。これらの発表は、日本映画史における時代劇、現代劇、両方を概観し、映画製作の裏方としてあまり注目されてこなかった映画衣裳担当者という存在に目を向けることを可能とする。そして、衣裳担当者の実態、仕事内容、実際の作品を明らかにすることにより、日本映画の新たな側面を披露、映画史の新しい構築への可能性を検討する。
近代京都画壇と映画衣装──甲斐庄楠音を通して/太田梨紗子(神戸大学)
甲斐庄(荘)楠音(1894-1978)は大正期の京都画壇で活躍した画家であり、その後は日本映画の衣装考証家として活動したことで知られている。ただし、衣裳考証家としての実態は未だに美術史・映画史双方の研究史において等閑視され続けてきた。しかし、昨年、楠音が衣装考証を担当した『旗本退屈男』シリーズの衣装が大量に発見されるなど、これまでの想定以上に多くの映画に携わっていたことが明らかになりつつありある。本発表では、楠音が画家から衣装考証家へ転換するにあたって、画家時代に経験した当時の画壇の潮流や習得した知識がその土台となったことを具体的に指摘した上で、溝口健二監督作品『雨月物語』(1953年公開)を中心に衣装考証家としての楠音の特質を改めて考察する。まず、楠音の画業に着目し、従来の映画研究では画家個人の素質として捉えられてきた楠音の歌舞伎・浮世絵への傾倒や時代考証の見識が、実際は当時の京都画壇の一潮流の中で育まれていたことを実証的に明らかにする。その上で、楠音の絵画作品≪女と風船(蝶々)≫において女性の霊魂の象徴として捉えられている蝶のモチーフが、『雨月物語』の女性の霊の衣装においても同様に用いられていることを確認する。そこから、楠音と溝口との関係を通して、近代京都画壇の素養が結果として映画衣装において流入したのではないかということを提示する。
時代考証にみる甲斐庄楠音と溝口健二/小川佐和子(北海道大学)
本発表は、大正期日本画家の甲斐庄楠音(かいのしょうただおと)と溝口健二監督の創作に通底するモティーフに着目することで絵画と映画の協働について検討する。甲斐庄は、戦前から60年代後半までおよそ30余年にわたり、溝口の明治物・芸道物・歴史物映画や伊藤大輔をはじめとする時代劇映画の時代考証を多く手がけてきた。映画界における彼の業績は、栗田勇による甲斐庄の伝記、新藤兼人による溝口の伝記、近年では池田祐子の研究等からその一端が明らかとなっているが、その半生を映画界に捧げたことで甲斐庄は美術史においては「大正期の退廃的な異端画家の一人」、映画史においては「裏方の絵師」という位置にとどまっており、壮年期から晩年にかけての彼の仕事はほとんど評価の対象とされてこなかった。本発表では、日本画にとどまらず、写真や舞台、そして映画など多様な表現媒体に関心を抱き、実践もしていた甲斐庄の創作活動を概観しつつ、表現媒体の日本画から映画への移行、表現手段の絹本着色から時代考証・風俗考証・衣裳考証への移行がどのようになされたのかを検討する。本発表は、2020年7月に発表した拙論「絵師と映画監督:時代考証にみる甲斐庄楠音と溝口健二の通底性」(谷川建司編『映画産業史の転換点経営・継承・メディア戦略』所収)の内容にもとづくが、笠岡市立竹喬美術館に所蔵されている甲斐庄のスクラップブックの調査内容を新たに盛り込み、画家の創作過程について検討を加える。
小津安二郎作品における森英恵の衣裳/辰已知広(京都大学)
これまで日本の映画研究者があまり研究対象としてこなかった映画衣裳に焦点を当てる。ファッションデザイナーとして名高い森英恵(1926-)は、1954年より十数年に亘りフリーの立場で映画衣裳製作を行っていた。最も多くの作品に関わった映画会社は日活であるが、その他四社すべてにおける何らかの作品にもかかわっていた。特に、1960年代の松竹において活躍していた大島渚、篠田正浩、吉田喜重といった監督においては、個人的な繋がりから多数の作品に関わっていたのに加え、小津安二郎による『東京暮色』、『小早川家の秋』、『秋日和』、『秋刀魚の味』の四作品における女性衣裳を製作したことが現時点で判明している。本発表ではまず、松竹衣裳部の歴史及び職務内容に言及し、続いて森が製作したとされる小津作品の衣裳を指摘し、分析することにより、小津の世界観を映像化するにあたって森がどのような貢献を果たしたかを明らかにする。また、日活作品に登場する森の衣裳や森の衣裳デザイナーとしてのスタンスと、小津による作品での衣裳や「作家」小津に対する森のスタンスとの比較を通じて、日本映画製作における映画衣裳デザイナーの姿を浮き彫りにする。