シンポジウム マルグリット・デュラスと〈声〉の幻前──小説・戯曲・映画
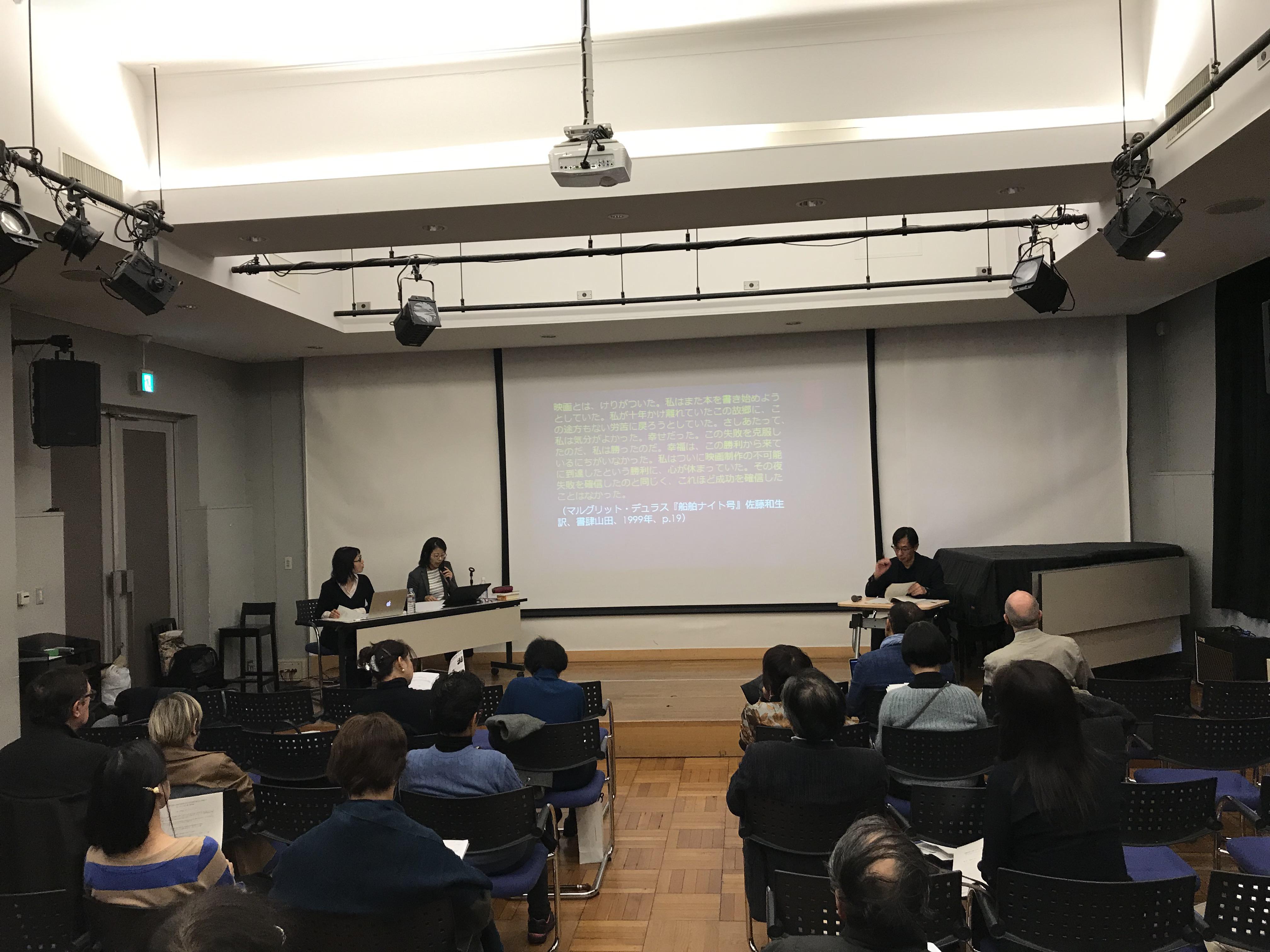
日時:2018年12月1日(土)10:30〜18:00
場所:アンスティチュ・フランセ関西(京都)、稲畑ホール
プログラム:
10:30-10:40 イントロダクション
10:40-12:10 I. 虚空と沈黙 Le silence et le vide
森本淳生(京都大学人文科学研究所)
「夜明けの光」のセレナーデを歌うのは誰か?──『かくも長き不在』における〈声〉の幻前
Qui chante la sérénade de « Des rayons de l’aurore » ? - la Voix-fantôme dans Une aussi longue absence
立木康介(京都大学人文科学研究所)
声なき身体、静かなる犯罪──『イギリス人の愛人』に寄せて
Corps sans voix, crime silencieux - quelque réflexion sur L’Amante anglaise
13:30-15:00 II. 映画と〈声〉 La Voix et le cinéma
関未玲(愛知大学)
デュラス、声を巡るエクリチュールの試み──声の現前と不在の間で
Duras, le défi de l’écriture autour de la voix - entre la présence et l’absence de la voix
橋本知子(京都女子大学)
声とまぼろしの風景──デュラス、足立、ストローブ゠ユイレ、ポレにおける移動撮影
Voix et travelling : la chevauchée fantomatique chez Duras, Adachi, Strauc-Huillet et Pollet
15:20-16:50 III. 新たな視座へ向けて Vers une perspective nouvelle
澤田直(立教大学)
どのように呼びかける(呼ぶ)のか──マルグリット・デュラスにおける名前の力
Comment (s’)appeler ? : la force du nom chez Marguerite Duras
ジル・フィリップ(ローザンヌ大学)
声に対するある種の違和感?
Une certaine gêne à l’égard de la voix ?
17:00-18:00 全体討議
デュラスにおける<声>──それは必ずしも「外部性をはらんだエクリチュール」vs「自我の直接的現前としての声」の二分法に限定されない、とシンポジウム序章で確言される。会話、歌、叫び、電話や録音装置といった20世紀的テクノロジーに媒介される声など、デュラスには様々な位相の声が登場する。また映画に傾倒する70-80年代には、映像と音声とは乖離をきたし、画面に姿を現さない声という脱身体化がなされるが、一方で身体に回帰する声もまた現れる。「わたしが表現しようとするのは、書く時にわたしが聞いているものなのです、つまり、わたしが内的朗読の声と呼んできたものです」とデュラス自身が言うように、同一性と他者性、音声性と書記性、声と文字とが相互浸透している。中間地帯をただよい、生と死を行き来するかのように現れては消えるデュラス作品の声に迫るべく、その「幻前」について六人が発表を行った。
シンポジウムではデュラスを専門とする者と必ずしもそうでない者とが混在するよう登壇者構成がなされ、従来のデュラス研究を継続し、さらなる先鋭化を図ると共に、また別の視点からデュラス作品を読解する試みがなされた。
森本淳生は、映画『かくも長き不在』(1961)のアリアに注目し、それがデュラス的空虚の象徴であると指摘する。カフェの女主人テレーズはナチス収容所で消息を絶った夫の帰還を待ちつづけ、ある日、アリアを口ずさみ、夫と類似することのない記憶喪失の浮浪者に、まさに類似しないがゆえに、夫の影を見る。テレーズは他のデュラスの登場人物たち同様、三者関係によってしか愛せない。記憶喪失の男という頭部の空虚が、満たされないテレーズの内部の空虚と合致し、彼女の中に外部と通底する絶対的な欠如が穿たれるのであり、よって夫への二者関係的愛は、過去を失った浮浪者の欠如へと向かう。アリアを歌うのはこうした欠如の声であり、実在するものに由来しない幻の声に他ならない。
立木康介は、『ヴィオルヌの犯罪』(1967)における女性の享楽を精神分析から論じる。実在の事件を元にしつつも、小説で殺害されるのは夫ではなく妻の従姉妹であり、聾唖者という声を持たざる者に設定されている。倦怠期を迎えた夫婦におこる事件で、なぜ従姉妹が殺されなければならなかったのか。犯行を上手く説明できないでいる妻クレールは、ミントあふれる庭にたたずむ歓びを語る。「ペパーミントla menthe anglaise」は「イギリスの愛人 l’amante anglaise」と誤られ、ことばの横滑りは、通常の言語に依らない非ファルス的享楽を示している。実際デュラスは、女性が「場所」ひいては「自然」と意思疎通できると述べ、庭での歓びはそうした女性と沈黙との融合を示している。解決の糸口がないまま終わるこの作品の、血染めの犯行現場を、発表者は非ファルス性、ファンタズム、母娘関係から洞察し、またデュラスにおける女性の狂気が、沈黙ということばと声のない状態で繰り広げられる点を強調する。
関未玲は、声への言及を年代を追って概観し、「声の自律性」という今ではよくしられたデュラス作品の特色がどのような過程で現れてきたかをたどる。デュラスの映画に対する見解は両義的である。映像の即時性は想像力を狭めるものとして否定されると同時に、その直接性ゆえ文字よりも有効にイマージュを伝えるともされる。しかし映画『船舶ナイト号』(1978)の「失敗」を契機にエクリチュールがふたたび志向されるようになり、以後、物語の中の「語る声」によってイマージュの現前が目指される。デュラスのゆらぎは、自伝的作品の中で過去が虚構化していくことに対する迷いでもある、とするアラゼの言が引用され、彼女のゆらぎに耳をすますことは、よって、声のもたらす幻への迷いに耳を傾けることである、と結論づけられる。
橋本知子は、デュラス『トラック』(1977)における声を、ストローブ゠ユイレ『早すぎる、遅すぎる』(1982)、ポレ『地中海』(1963)、足立正生『略称・連続射殺魔』(1969)に対置させ、内在的に考察する。いずれもヴォイス・オーヴァーは、時に映像に重なり合い、時に離れ、ことばの響きの物質性そのものによって風景を前景化させる。見慣れたはずの場所は異化され、パリ郊外の冬空にせよ、旋回するカメラの捉えるバスチーユ広場にせよ、葡萄色の海にせよ、60年代の日本列島にせよ、記憶や幻影など、映されるもの以外/以上のものを見せようとする。同軸上移動のカメラによってそれはさらに強まり、観る者は、画面外からやってくる声、その出どころを明らかにしない脱身体化された声に導かれて、カメラの動きと擬似的に一体化し、躍動という運動性を与えられる。『トラック』のラスト、緩慢なベートーヴェンにあわせて、前へ、前へと進むカメラが真正面から映し出す空の、その白さ(スクリーンの隠喩でもある)は、擬似一体感によってまた別の風景を立ち上がらせようとする試みの極致となっている。
澤田直は「固有名詞」「反復と抹消」「呼びかけと命名」に注目する。リチャード/リチャードソン、シュタイン/シュタイナー/オーレリア・シュタイナー、アンヌ/アンナ/アンヌ・マリーのように、デュラスでは名前が反復され、変容していく。同一人物ではないが完全に別人でもない「重ね合わせの原理」とデュラスが呼ぶこうした登場人物たちに、一貫した現実性は与えられない。アイデンティティの否定あるいは実体の浮遊性としての固有名詞は、しかし、複数の無名者たちに唯一の名を与え、光をあてる役割をもつ。映画『セザレ』(1979)では「セザレ」「セザレア」の名が執拗にくりかえされ、呪術的反復によって、ユダヤの女王ベレニス、さらには何万人ものユダヤ女性の総体を回帰させようとする。無人の、廃墟のような光景に、画面外から響いてくる声は、死者たちを召喚する死への呼びかけであり、エクリチュールを推進する死の欲動の一側面でもある。
ジル・フィリップは、「声の作家」デュラスにおいて声の使用法が一貫しているわけではないことをまず指摘する。にもかかわらず明らかなのは、声が感情表現ではなく音響的要素へと収斂していく点である。それはあくまでも身体から断絶した声であり、映画が声を脱身体化しえる点で、デュラスの関心は小説から映画へ移行していったのだった。よって中性的で、虚ろな、感情表現に乏しい「演じない声」が目される。しかし情動と感情に魅力と嫌悪を感じていたデュラスは、一方で感情の不在を声に求め「感情の廃棄」を図ると共に、他方では感情の表出も望んでいた。このパラドクスの美学的解決が「感情を不在という様態において現前させる媒体としての声」であり、聞こえはするが存在しない声、そうした声を現前させること、幻としての声(voix-fantôme)である、と結論づけられる。
全体討議にはデュラス協会副会長のジョエル・パンドン゠パジェスも加わり、六つの発表を補完する形で、声が作品や作家像などデュラス個人にとどまるものではないことを指摘した。晩年のパートナー、ヤン・アンドレアに向けて発せられた声が、書くことを牽引したのであり、作品の通奏低音ともなっている。こうした「発話の対象を含めた上での声の問題系」が示唆された。
2011-2014年にはガリマール社プレイアッド叢書から全集が出版され「殿堂入り」を果たし、国際シンポジウムがフランス内外で定期的に開催され、また数多くの伝記が書かれているデュラスのその全体像は、輪郭がとりにくくなくなってきている。けれども、あるいはそれ故に、デュラス作品を決まった枠組みの中に固定させないよう、多彩な声のあり方に注目し、新たな読みを提示しつづけることが重要である、そう再確認させるシンポジウムであった。
(橋本知子)