ノーベル文学賞を読む ガルシア=マルケスからカズオ・イシグロまで
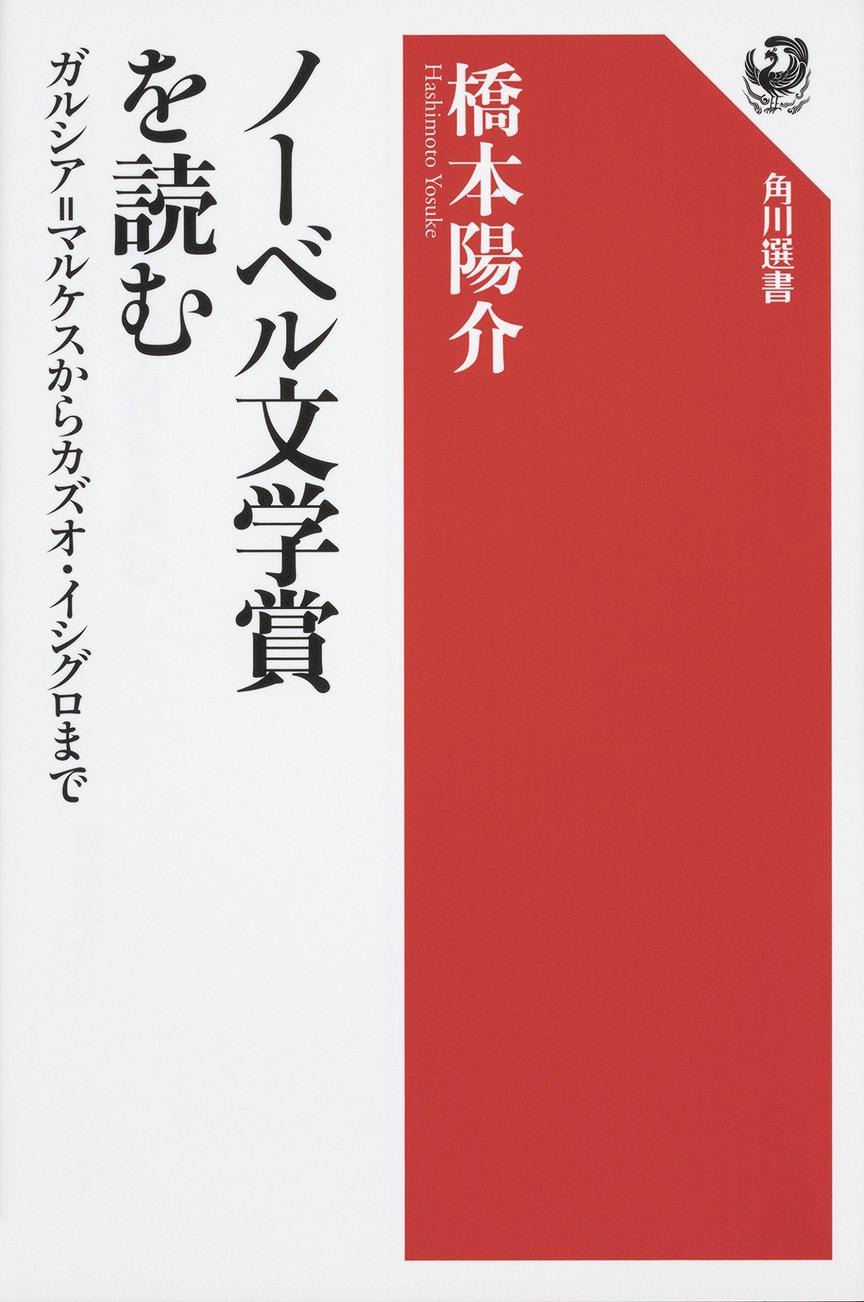
近年は秋になると、村上春樹がノーベル文学賞を受賞するか否か、というニュースを目にするのが恒例となりつつある。ノーベル文学賞は、もちろん世界で最も権威ある文学賞の一つであるが、その選考はスウェーデン・アカデミーという機関が独占的に行なっており、受賞者の地域的な偏りや政治性の強さなどが指摘されることも多い。また、アカデミー会員の夫に持ち上がった性的暴行疑惑等によって、2018年の受賞者発表は見送られることが決定しており、アカデミーへの信頼そのものが揺らぐ事態にも発展している。 しかしながらこの文学賞が、多くの人々にとって、世界の優れた作家について知り、その作品に目を向ける良い機会となってきたことは確かであろう。
本書は、1980年代以降のノーベル文学賞受賞者を、年代ごとに数名ずつ取り上げ、その小説の技法を紹介していく形で構成されている。まだその作品を読んでいない人のための入門書として書かれているので、作品内容への詳しい言及やディテールの分析は行われていないが、小説言語の研究者である著者がそれぞれの作品から引用する文章は、どれも個性的かつ魅力的である。邦訳の短文ではあるのだが、各々の作者の感性と言語表現の独創性が透けて見え、読む者の心をぐっと掴むような文章が集められている。筆者は、これまでの受賞者に共通する要素としてマイナー性、文化的越境性、エスニック性などを挙げつつ、とりわけその小説言語の独自性を強調しているが、個々の作家の小説言語の魅力を分かりやすく伝え、その作品への興味を引き出していく本書は、まさに幅広い層に向けた読書入門として適したものであると言えよう。特に、筆者と縁の深い高行健について論じた章は読み応えがある。
ただ、大江健三郎を研究する者としては、「意識過剰な文体」で「情けないオレ語り」を繰り返す「日本的」な作家という、本書における大江の評価には、やや賛同しかねることを申し添えておきたい。作家の分身とも言える主人公の自己語りや、とくに理由のない(というよりは、理由を解明することのできない)自殺というモチーフが、大江の小説作品に通底するものであることは確かだ。しかし、もしそれを「日本的」と捉えるのであれば、大江はそのような「日本的」オブセッションに自覚的に対峙すると共に、様々な文学理論や国内外の作家・知識人から刺激を受けながら、その文体やナラティブを大きく変化させ続けてきた。本書で取り上げられているエリアス・カネッティ、ガルシア=マルケス、莫言らも、大江に影響を与えた作家達だ。個人的には、大江も他の受賞者達同様、独自の小説言語を探求すると共に「越境」を志向した作家であり、その作品は「世界文学」として読まれる価値があると考えているのだが、如何だろうか。
(菊間晴子)