白い壁、デザイナードレス
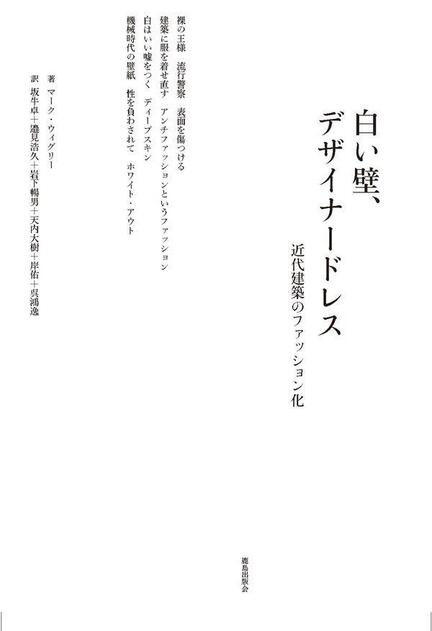
堆積した雪によじ登って掘り下げる
要約の困難な書物である。坂牛卓による冒頭の紹介文、邊見浩久による巻末の解題にもあるとおり、本書は建築史上のある特権的なシーンを10回撮影しなおしたものである。登場人物や舞台設定がその都度変わるから、リプレイではなくリテイクである。
10回カメラの位置もセットも変えねばならない物語が、建築のモダニズムと白の間にあり、黒衣としてファッションが介在する。元々の台本では、建築のモダニズムとファッションの双方を動かす黒幕として白がいたはずなのだが、一方の主役が「干され」、他方の主役とこれを支える白という「リメイク版」が世に流通してきた。当時の台本を取り戻し、黒衣だったファッションをもう一人の主役に引き戻し、元の構図を取り戻す「ディレクターズカット」を作るため、「リメイク版」の綻びを10回探ったといえよう。
白は装飾を脱ぎ捨てること、過去と断絶することであるという「リメイク版」の主張はこれまで無数に繰り返されてきたが、そうした否定の契機としての位置づけは、白をそれ自体として捉えることの困難さをも示していよう。例えばデザイナーの原研哉は『白』(中央公論新社、2006)を、黒い文字を載せる基盤として、四角く囲まれた空白として、自ら取り囲む赤い円とともに旗の象徴作用の融通無碍として、「無数の答えを蔵している」問いの豊饒として描く。冒頭から白について、存在というよりも特権的な感受性の対象であると主張するから、白とは対象と自らの間に現象する認識の枠組みであるという理解ともとれよう。
この見解を百の対象に適用した『白百』(中央公論新社、2016)で、白はデザインの対象、行為、主体を語るメディアとして役を果たす。骨、漆喰、壁、ミコノス島の家、羊、白衣……といった白い表面をもつ対象への考察が、いつしか方寸、正方形などの形態的原理、推敲や掃除などの行為、「わたし」や友人の死を綴る「エンボス」など主体を描くエッセーに展開していく。もし原の言う白が認識の枠組みとして有効であるのならば、そこに歴史的にか、より普遍的にか、ポジティヴな意義を読み取る必要が生じる。
その意義を別の側面から提示した例として、モダニズムが席巻した20世紀建築、特に住宅の内部における白の振る舞いはどうだろうか。冷蔵庫を突破口として広汎な分析と議論を示した原克『白物家電の神話』(青土社、2012)で、氷を使わない電気冷蔵庫の「白」は、庫内と庫外、平滑な平面と曲面、衛生観念と冷気の連想にまたがり、『輝く都市』ならぬ《輝く台所》に到達する。
曰く、住宅裏手のポーチや屋外に置かれていた冷蔵函が、木目を備えた家具として屋内に迎え入れられたときには、耐湿・防水のため琺瑯引きされた内部こそが白く輝いていた。外面が琺瑯引きされた機種も、家政婦のいる家庭にあってピアノのような、女主人の重厚な家具として出発した。しかし清潔かつ謹厳な白衣の神話と冷気の連想とに支えられた、冷却・断熱性能と白の連関から、平滑で鮮やかで丸みを帯びた、継ぎ目のない陶器皿のような扉が宣伝され始める。ここに冷蔵庫は、伝統的な家具から軽やかな進歩と潔癖な輝きをもった「親愛なるささやかさ」を示す白物家電へと変身を遂げ、同じ20世紀初頭の『流線型シンドローム』(紀伊國屋書店、2008)と並行して「障碍因子」の駆逐、モダンライフの「審美的」階級闘争に棹差したという。
さて20世紀初頭の建築の外面、白い壁に戻ろう。ウィグリーも白の積極的な役割を見いだすべく、ニコラウス・ペヴスナーやジークフリート・ギーディオンの歴史編纂によっていわば消去されたヘルマン・ムテジウスのテクストから、著者不明のパンフレットの文章にまで分析の範囲を拡げる。モダニズム建築が裸というよりも、流行を拒むアンチファッションに身を包むことになったのは、制定した本人はすぐに違う生地を試用し始めたにも関わらず、白い継ぎ目のない壁が制服となったからである。制服への流行の導入は、監視を喚起する。監視カメラに写る青白い亡霊のように、流行とその媒体または要因としてのドレスは白い壁に、そして建築家自身の身体に、何度でも復活する。
例えばテイク1にて、ゴットフリート・ゼンパーからアドルフ・ロースに継承された、吊された織物に囲まれたものとしての室内空間の位置づけ、すなわち衣服としての建築観は、ル・コルビュジエによって女性の衣服(いや、衣服を着た女性か)への欲望の隠蔽物としてアプロプリエイトされた。
しかしル・コルビュジエ自身は、標準化された規範的な対象(たとえば制服)による形状は生活の更新に消費されるが、そのような対象で構成されたある特定の作品は永遠性を獲得すると述べ、建築を量産品と一品生産との緊張関係の内に位置づける。身体を包むコミュニケーションの手段としての衣服、私室を取り巻く織物、建物を取り巻く近代のコミュニケーション世界といった「外面」の原型を、彼は『東方への旅』で観察したバルカン半島の民家に見いだした。そこに見る崩壊した白い壁を、近代の工業化された手段で(つまり装飾芸術として)再構築しようとするのが『今日の装飾芸術』というわけである。
──このようなストーリーが、テイク2以降、ギーディオン、ヴァルター・グロピウス、ルイス・サリヴァン、アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ、ヨゼフ・ホフマン、ポール・ポワレ、マルセル・ブロイヤー、リリー・ライヒ、オットー・ワーグナー、アメデ・オザンファン、フェルナン・レジェ、ピエト・モンドリアン、テオ・ファン・ドゥースブルフ、ブルーノ・タウト、アドルフ・ベーネ、ヘンリー=ラッセル・ヒッチコック、ヤコーブス・ヨハネス・ピーター・アウト、ヘンドリク・ベルラーヘといった脇役たちに彩られながら描かれていく。もちろんル・コルビュジエは全章に登場するが、一方でルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエはヴァイセンホーフジードルンクのディレクターとしてのみの限定的な扱いに留まるし(索引にも載らなかった)、フランク・ロイド・ライトも限定的な扱いを受けている。
様々な立場から本書の議論に対応できようが、個人的には、服装改革運動の意義は、色彩や装飾という以上に身体の形態面における解放にあったと考えられる一方で、建築においてこれに相当する要素をどう考察されるべきか、白という色彩を基調とした本書では当然ながら未検討である点が気になる。おそらく、左右対称のファサード構成や室配置などから解放されたことがこの要素に相当するのだろうが、そのこととコルセットなどとをどう重ね合わせればよいか、パズル的に思考実験することが可能かもしれない。解題にウィグリー自身の考察とともに挙げられた、この2年ほど我々の鼻梁に密着して口元を覆っている布切れに関しても、同じ系列で考察できないだろうか。
また、服飾史の中で上記ストーリーがどれほど重要性を帯びているのか、あるいはもっと重要な動きの中の一翼として位置づけられるのかという点も、筆者の知識が追いつかないながら考えたい点である。
なお筆者は、近代日本では分離派建築会の展覧会(1920-1928年)で初めて展示アイテムとなり、現代となっては美術館の収集・展示対象にもなっている白模型と野外博物館、近代の植民地都市をめぐる考察も最近行っている(まもなく日本建築学会より発表される)。
最後に、近い話題を扱った書物として、筆者は未見であるが、現在はペンシルヴェニア大学で環境建築デザインを専門としているWilliam W. BrahamによるModern Color/Modern Architecture: Amédée Ozenfant and the Genealogy of Color in Modern Architecture, London: Routledge 2002がある。おそらく他にもあると思われるが、それらについては後の検討としたい。
(天内大樹)