インタビュー2 あいだをつなぐ──オペラ研究と現場、ヨーロッパと日本、音楽と言葉 長木誠司(東京大学教授)
オペラの現場との出会い
──音楽やオペラの現場に関わり始めたのは、いつ頃でしょうか?
まあ学生時代からね、オペラ作ってたりしたの。サークル活動の一環でそういうものに触れる機会が、高校のときにあって。僕は学芸大の附属だったんだけれども、教育大の附属もオペラ作ってて、ふたつの高校に交流があった。『オペラの20世紀』(平凡社、2015)のあとがきにも書いたけど、高校入って、結局歌わなかったけどドン・ホセの代役かなんかやらせられて。2年目は指揮やって《カヴァレリア・ルスティカーナ》の棒振ったりとか。3年目は受験勉強しながらクラリネット吹いたりとか。中学のときはオペラなんてとんでもないみたいな話で、吹奏楽やってたんですけどね。当時は、オペラはかなり異常な世界だった。今よりもいっそう特殊な世界で、歌つけてやるなんてバカみたいとか思ってた人がほとんどで、僕もそう思ってたし。触れてると何となく洗脳されてくるもんだから、今は特に異常なことと思わなくなってきたけど。

長木誠司氏
やっぱり70年代の終わりって、クラシックのなかでも、まだまだそういうもの観る人はかなり特殊な人だったと思う。映像もそんなにないし、LPで聴くぐらいで、ワーグナーなんか5枚ぐらいを10回くらい表裏変えながら聴かなきゃいけないとかさ。対訳みながら聴くなんて、そうとうな物好きじゃないとやらない世界だった。
僕が高校を卒業する年度、75年だったかな。そのときにメトが初めて来たのね。それは大変な騒ぎだった。その辺りからいわゆる歌劇場の来日引っ越し公演っていうのが始まって、それで初めてオペラ面白いと思い始めた人多いんじゃないかな。それまで日本人のやるオペラってやっぱり借り物で、なんかこうわざとらしくてね、あんまり興味持てなかったけど。「本場のもの」観せられて、これはすごいなって思ったことはあったよね。バイエルン国立歌劇場が高校のとき、74年かなんかに来るのかな。サヴァリッシュが《ワルキューレ》やったり、クライバーが《ばらの騎士》振ったりしたときだよね*1。その辺から、オペラってのはこういうものだったんだなっていうのがわりと身近に分かるようになってきた。今だったら映像ですぐ分かるけど。
*1 1974年9月、バイエルン国立歌劇場が来日。《ワルキューレ》《フィガロの結婚》《ドン・ジョヴァンニ》の指揮はヴォルフガング・サヴァリッシュ、《ばらの騎士》はカルロス・クライバー。
──なるほど。
実際、声だけで聴いてた部分も多いしね。こっちもオペラ興味持ち始めたときにそういうものが来たので、まあタイミング良かったかもしれないと思いますけどね。でも作ると観るのでまた違うからね。作るとなるとさ、高校のオケなんか全然楽器揃ってないから編曲とかしなきゃいけないわけ。で、ここオーボエがないからどんな楽器に振り分けるとか、ティンパニ借りてくるとか、あるいは、響きの薄いところをピアノで代用するとか、そんなことやってると、楽譜書いたり楽器法学んだりとかの実践的な能力がつくんだよね。それが今度は、聴く上で非常にためになるっていうかね。
当時、高橋悠治(1938~)が小林秀雄のことを批評して*2、これは物を作ったことのない奴の言葉だとか書いてあって。そうだよな、大事だよな、物作んなきゃいかんよな、と思ったことがあってさ。そういうのもちょっと影響してたかもしれないけどね。70年代ってのは高橋悠治が日本に帰ってきて、トランソニックとか始めて、それこそ頭でっかちな部分と創作の実践って部分と、一体になってやり始めて、そこに政治も絡んでたみたいな時代だったけど。ちょうど世の中がノンポリになりつつあるときで、遅れてきた、ちょっと左翼じみた高橋悠治なんかが発言力あって面白かった時代でもあったから。林光さん(1931~2012)なんかもその頃一緒に彼らとやってて。その辺の情報発信は面白かったですよね。いわゆるオペラと、それからアンチオペラみたいな、林さんのこんにゃく座みたいな新しい発想の音楽舞台みたいなのもちょうど出てきて、音楽劇みたいなものが身近になりつつあった。そういう意味でもタイミングがちょうど合ったかなって感じでしたかね。
*2 高橋悠治「小林秀雄『モーツァルト』読書ノート」(1974)
──その頃に触れたオペラは、イタリア・オペラやワーグナーなどですか?
僕ワーグナー大嫌い(笑)。だめだ。イタリア・オペラで、プッチーニとかヴェルディとかが1番多かった。ワーグナーはたとえ好きでもなかなか観る機会はなかったんじゃないかな。サヴァリッシュの《ワルキューレ》が来たのと並行して《リング》をやり始めようなんていうのがあって、朝比奈隆とかがステージ・コンチェルタントでやったりとか、二期会が何年かおきに少しずつやってたかな。ドイツ物って、日本人による上演もそんな多くなかった気がしますね。中学校のときに《ナクソス島のアリアドネ》の初演を若杉弘さんがやったかな*3。日本語でやったけど、全然歌詞聞き取れなくて。当時字幕もないしさ。日本語上演と原語上演のちょうど端境期だったんだけど、まだまだ日本語上演が多くて。で、難しいオペラっていうか、馴染みのないオペラって日本語で歌ってた時代だったんだよね。だけど、それでもなんか全然聞こえないしさ。で、日本人のオペラ公演に行くとさ、だいたい失望して帰ってくるっていうのが(笑)。ドイツ物はやっぱり、そもそも舞台が少なかったんですね。
*3 1971年7月、R.シュトラウス《ナクソス島のアリアドネ》、指揮:若杉弘、訳詞:中山悌一、後援団体:二期会
まあそれは昭和音大のデータベースでどれくらいあったか分かるけど。でもまあ今ほどやっぱり盛んではなかったかなって感じですね。上演団体も藤原歌劇団と二期会くらいしかなかったしな。
現代オペラとの出会い──ボン留学でのこと
──現代のオペラに触れるようになったのは、いつ頃からでしょうか?
それは、かなりあとなんだよね。大学院に入ってからかな。僕、卒論はベルクで書いて、その辺でようやく20世紀のオペラが視野に入ってくるのよ。《ヴォツェック》もそこまで観たことも聴いたこともなかったし、《ルル》も三幕版ができたてほやほや。ちょっと話題にはなってたけど、当然観る機会もないし、音だけで聴いて。よく聴いてたのはミトロプーロスのモノラル盤だったりしてね。いい演奏だったけど、ほとんど今となっては遺物だけどさ。
新ウィーン楽派とか聴き始めたのは、高校2年くらいからで、けっこう聴くの遅いんですね。で、大学入ってからいろいろ聴くようになって卒論もそれで書いたりなんかしたけど、やっぱり現代オペラは、日本のもの以外はまず実際に観ることできないでしょ。ときどき東京室内歌劇場がやってるくらいしかなくて。そういう学生のときの経験から、あとでなんかお手伝いすることが結びついてんだけど。だけどそこもフル編成のオケでできてなかったから、編曲版とか。オルフとか、フランス6人組とか、プーランクのもやってたけど、やっぱりフル編成のオケでは観たことなかったですね。メノッティの《電話》なんてピアノ伴奏でしか弾いたことなかったし、プーランクの《声》もまずオケではやらない。《カルメル会修道女の対話》なんて絶対やんなかったし。今でもやってないかもしんない。バルトークの《青ひげ公の城》とかを、ときどきコンチェルタントでやってたくらいかな。
──確かに少ないですね。
だから、実際に20世紀オペラに触れたのは留学したときで86年以降なんですよ。一応20世紀オペラの最初の方くらいは音だけでは知ってたけど、それじゃ、しょうがないなと思って留学したんだけどね。そしたらなんかもう行ったらすぐに、ハンス・ツェンダーの《スティーブン・クライマックス》っていうジョイスの『ユリシーズ』か。6月16日だっけ、ブルームの日をテーマにしたオペラが、その前日の6月15日に初演されたのね。それがフランクフルトであって*4。僕はマンハイムのゲーテにいて、フランクフルトはすぐだったから観に行って。6月5日くらいにマンハイムに着いたばかりでそれ観て、もうなんかすごい圧倒されちゃって。字幕もないし、やってることはなんかよくわかんないんだけど、解説だけ見て、ものすごく面白かった記憶があって、それから割とすぐハマったんですね。
*4 Hans Zender(1963-2019)《Stephen Climax》1986年6月15日、フランクフルト歌劇場初演
その年にザルツブルクの音楽祭にも初めて行ったんだけど、ペンデレツキの《黒い仮面》の初演を観た。で、そういうチケットはさすがに売れ残っててさ、買えるの。カラヤンとか《フィガロの結婚》とか《ドン・ジョヴァンニ》とか絶対買えないんだけど。クプファーの演出で、ハリー・クプファーって人の名前も初めてそこで知った。なんでこれがそんな評価されてるのかも基準も全然わからなかったけど、すごく面白い舞台だった。その辺が、最初に現代物観るって機会でしたかね。
──修士論文は、シュネーベルだったでしょうか?
ディーター・シュネーベル、そうそう。ほんとはそういうね、オペラなんか何さ的なものの方が、最初は好きだったわけ。当時は現代物とか研究してると、そっちの方が進んでるよねみたいな感じだったからさ。そういう実験的なものが好きで、調べようと思って、でも観ることできないからドイツに行ったんだけど。でも行くと、普通のオペラもめちゃくちゃ面白いわけね。で、そういうのも一緒に観だすとだんだん観るレパートリーが増えてくる。とにかく毎日いろんなものやってるからさ。
僕は留学先がボンだったけど(1986~88年)、語学研修はマンハイムだった。マンハイムに着いて一週間くらいでもうシーズンが終わっちゃったからさ。行ってすぐ観たのは《神々の黄昏》だったんだよ。着いた次の次の日に、シーズン最後の《リング》連続上演の《神々の黄昏》だけ間に合ってさ、行ったのよ。マンハイムの歌劇場はペーター・シュナイダーがシェフで、留学一発目のオペラだったよね。二発目がツェンダーで、三発目が《黒仮面》だったからさ、めちゃくちゃだよね、なんかもう。
──なかなかすごい(笑)。
そのあとボンに行くと、ボンのオペラ座は、割と保守的だったのね。ちっちゃいオペラ座なんだけど、当時首都だったからお金がけっこうあって、いい歌手が来てたんだけど。で、隣のケルンとデュッセルドルフの歌劇場が、毎日、演目変えてやってたからさ、夜はそっちに車で遊びに行っていろんなの観てたっていう記憶。まあ両方ともね、すごい舞台ってのはないんだよ、それなりの舞台。でもポネルが演出してたりとかするから、最高級じゃないけど、上の下くらいの水準が毎日あって割と面白かった。そこで、いろんなもの観た記憶があって、その辺が初めて、ちゃんとオペラ観始めたって感じですかね。
──オペラと、いわゆる現代音楽の演奏会とでは、オペラによく行かれたでしょうか。
どうだろう、まだ演奏会のほうが多かったかもしれないね。ケルンは現代音楽盛んだったから、シュトックハウゼンもまだバリバリやってたし、WDR(西部ドイツ放送)の演奏会とかオケも含めて現代物多くて、半分半分かなあ。ただ新しい舞台あったら必ず観ようと思ってたから、新作はだいたい観てた。ルールとかザールあたりはいろんな街あるじゃない。そういうとこでとっかえひっかえ現代音楽祭みたいなのやってて、けっこう足繁く通った。ヴィッテンとか、エッセンのフォルクヴァングとか。そこでロバート・HP・プラッツ(1951~)みたいな作曲家と知り合ったり、それから現代物ばっかり弾いてる、奥さんのピアニスト、クリスティ・ベッカーの演奏会を何回も聴いたり。モーツァルトとかオペラの古典を観るよりも、現代物があればそっちに行ってた感じはあるな。
──当時、作曲家とか指揮者とか、作る側との接点はいかがでしたか?
個人的になかなか知り合いになる機会はなかったけど、WDRに日本人の人が一人入っていて、岸浩一さんというんだけど、その方のツテで、ちょっと会ったことあるとか。それと、師のマルティン・ツェンク*5っていう先生がいろんな人呼んでくるのよ。エルンスト・クシェネク(1900~1991)を呼んできたり。もう90歳近くで、よく来たなと思うんだけど。それからツェラーンに関する作品展みたいなのやってて、そのとき、ペーター・ルジツカ(1948~)を呼んできて。ルジツカがまだベルリンのインテンダントやり始めて間もないころで、ゲルト・アルブレヒトといろいろ面白いことしていた時期だったから、話してもらったりとか。
*5 Martin Zenck(1945~)、1982~85年、WDRの現代音楽部門プロデューサー、その後ボン大学の客員講師、1989年よりバンベルク大教授(歴史音楽学)。2006年よりヴュルツブルク大。著書にKunst als begriffslose Erkenntnis. Zum Kunstbegriff der ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos(1977) 、編著にGewaltdarstellung und Darstellungsgewalt in den Künsten und Medien(2009)など。
──ボン大学の授業という枠組みですか?
そうそう、それでけっこう僕は影響うけたよね。いろいろ現場の人呼んできて授業やるってのは、こういう方法あるんだなっていうね。藝大ではついぞそういうものなかったからね。なかなか面白かった。それから有名なツェラーン研究家のベーダ・アレマンがボン大だったんだけど、ゼミに来てもらって音楽学ならぬ文学の講義始めたりなんかしてさ、そういうところも領域横断的で面白かったなと。ものすごく尊大な人だったけどね、俺こそツェラーンだみたいに喋ってたから、何じゃって思って。
まあ僕はけっこうツェンクって人には影響うけて、彼はまだそんなにちゃんとしたポストじゃなくて、ボン大のときはPrivatdozent、いわゆる非常勤講師みたいな感じで、僕が帰る年にようやくアーヘンで常勤ポストみつかったと言ってて。そのあとバンベルク行って、今もう退官しちゃったけど、書き物も多かったしね。いわゆるオルタナティブな世代の人で、60年代の終わりくらいに学生時代を迎えて、新左翼的な洗礼を受けた世代だから、やってることが過激なんだよね。アドルノなんて何さっていうのが一方にあって、でもアドルノ大事よねってのももう一方にあってさ。そう意味では、いろいろ薫陶を受けた記憶がありますね。
──なるほど。オペラのドラマトゥルクみたいな存在を意識し始めるのはどれくらいのころからですか?
どれくらいだろう、90年代になってからじゃないかな。ボン大のときはドラマトゥルクって言葉すらほとんど知らなかったし、それからそういう講座があることを知ったのはやっぱり帰国したあとかな。ほんとにオペラの研究やろうと思ったのは帰国したあとなのよね。『フェッルッチョ・ブゾーニ』(みすず書房)を書いたのは95年だけど、90年代前半に、実はこういうものがあったんだと思った。ドラマトゥルク専門の講座みたいなのが、シュトゥットガルトとかいくつかあるじゃない?そういうのを知ったのはその後。自分でそこまでやろうとは思わなかったけど。

『フェッルッチョ・ブゾーニ』(みすず書房、1995年)
ただそういうドラマトゥルクの教育受けた人が、いろんな歌劇場のプログラム冊子で書いてたりするのよね。それこそツェラーンの詩をどこか引用してて、だいたい同じようなとこ引いてきてるのよ。みんな同じようなことやってさ、僕も似たようなことをやってもつまらないかもしれないとちょっと思ったかな。でもまあ、オペラの世界でドラマトゥルクってものが認知され始めたのは、ドイツでもその辺りじゃないかな。それまでドラマトゥルクっていう名前は、プログラム冊子のなかに出てこなかったからね。
──なるほど。
やっぱりレジーテアーターとか盛んになってくると、ドラマトゥルクが必要じゃないですか。だから、それで目立ってきたってのはあるかな。ただ80年代は、レジーテアーターって、オペラのなかだとまだまだマイノリティだったの。90年代にだいぶん盛んになってきたよね、壁が割れたあたりがちょうど境目だったと思うけど、まだまだ古典な舞台作りが多かった。で、ちょうど留学してたときにミュンヘンの《リング》がレーンホフの演出で、それが87年だったかな*6。その辺で新しい、たとえば、宇宙船のなかの《リング》みたいな、なんでこうなってんのみたいなものがけっこう増えてきたって感じかな。だから80年代後半に増えたんじゃないかと思うけど、ちゃんとそれを意識し始めたのは90年代頭だったかなって気がする。まだまだ古典的な演出も好きだったし。金かかってるからね、古典的な方は。何年もやってて練れてるわけだし。そういう意味では、両方とも面白かった。
*6 Nikolaus Lehnhoff(1939-2015) 1987年、バイエルン歌劇場で《ニーベルングの指環》を演出。
ドラマトゥルクを勉強した人に初めてちゃんと会ったのは、2005年にベルリンに一年行ったとき。それまでなかなかそういう人と付き合いなかったんだけど、参加していたゼミでシュトゥットガルトで学んだ人と初めてちゃんとお話しする機会があって。若い女性だったけど、彼女はコペンハーゲン王立歌劇場でのコンヴィチュニー演出の《エレクトラ》を手伝った話をしてくれて。最初、アガメムノンが子供たちと風呂に入ってて、そこで惨殺される場面から始まるんだけど、そこから1時間40分のタイマーがゼロに向かって秒読み始めるんだよね。で、ちょうど、ゼロになったときに殺されて最後の幕が降りるという舞台。その作り方をずっとゼミで発表してくれて、あーこういうことやって、それをどうやって手伝ったかみたいなことからはじまって。
で、我々のときはやっぱり、まずドラマトゥルクってのがそんなにまだ認知されてなかったとおもうし、教育も今ほど盛んじゃないし、日本人の我々世代ってそれは意識できなかったかな。最近ほら、ドラマトゥルクのちゃんとした勉強してる人出てきてるじゃない、長島確さんとかさ。
──学会誌『表象』15の座談会「オンライン演劇は可能か 実践と理論から考えてみる」にも出てらっしゃいますね。
うん長島確さん。それから、横堀応彦くんなんかもその世代だと思う。その世代は、もう普通にドラマトゥルクがいてって感じの世代だと思う。僕らより上の世代だと、ドイツ文学者の内垣啓一などが最初の二期会の《リング》の演出やってたりするわけだけど、彼らはやっぱり演出家として関わるのであって、中間の存在ではないんだよね。そもそも《リング》を観たことある人がほとんどいない。それがまあ演出するみたいな感じだったけど。僕たちのときは、もっと普通のオペラ演出家は日本でも出てきたけれど、ドラマトゥルクはまだだったよね。
僕なんかは一応、たとえば日生劇場でドラマトゥルクっていうふうに肩書きでやったけど、なかなか演出そのものにタッグを組んでやるって難しいですね。僕が一緒にやった演出家はドラマトゥルクとやるっていう経験をもともと持ってないから、こっちのことどう扱っていいかわからない。だからこっちもなかなか口出せないっていうのもあって。
そもそも、劇場にドラマトゥルクっていう肩書きがないから、ドラマトゥルクの肩書きでギャラがでないんだよ。一応、肩書きドラマトゥルクで表向きは出てるけど、まあそのギャラとして、たとえば字幕制作とか、そういった現場のことやらないといけないこといっぱいあるんだけれど、それでギャラもらうってそんな感じになっていて。今、新国立劇場だって、ドラマトゥルクって立場はないもんね。まあコレペティトゥアはようやく採用されてるけど、ドラマトゥルクって人はそもそも名前がないよね。二期会とかで外のプロダクションもってくるときには、向こうの人がドラマトゥルクついてるから名前出るけど、日本の劇場にそもそも制度としてないから、ドラマトゥルクの教育受けてきても、日本だと仕事がないんじゃないかな。だから日生なんか少しやり始めて、なんとかしようとしてるけど、新国はまだまだそこまでいってないかな、やっぱり。
東京室内歌劇場──ドラマトゥルクとしての活動の始まり
──帰国されてから、プロダクションに関わった最初はいつでしょうか?
2000年代になってから。2000年代後半の、東京室内歌劇場に五年間くらい関わったんだよ。《ザ・芸者》(2007年上演、日本語台本・訳詞:長木誠司)が最初だったね。表象の卒業生が東京室内歌劇場の事務方に入っていて、なんか手伝おうかみたいな話になって。東京室内歌劇場のほかの人たちと、新しいオペラずっとやってきたんだったら、こういうことやったらどうと相談する機会があって、外から手伝う役みたいな委員になって、演目決めたりとかするようになったのが2006年くらいからかな。《ザ・芸者》やって、あと《アルチーナ》(2007年上演)っていうヘンデルのオペラ。バロックオペラとか日本でなかなかやらないから、そういうのやってみたらって。東京室内歌劇場は、現代物とバロック物ってまあ若杉弘さんの時代からね、両極でやってたから、それをもう少しブラッシュアップして現代的なものに変えていこうとしてやってったのが具体的には初めてかな。ちゃんとした仕事としてやったのはね。
──東京室内歌劇場には、どのような形で関わっていたんでしょうか。
プログラミングはだいたい僕が決めてました。もちろん最終的には合議で決めたけど案を出すのは僕で、途中からもう一人、フランス系がちょっと弱いから入ってもらって。それ以前に、ちょっとこれやってみたらって言ってやったのが、マデルナ《サテュリコン》(2004年上演)っていうオペラなんだよ。日暮里の、バーみたいな東京キネマ倶楽部ってところでやってなかなか面白かった。基本的にはそのあとから関わり始めたんだけど、ちゃんと名前出したのが《ザ・芸者》の2007年。それとヒンデミット《行きと復り》とマイケル・ナイマン《妻を帽子と間違えた男》とか(2009年上演)。ナイマンは、室内歌劇場はコンチェルタントで、ソウルでやったんだよね。せっかくやったなら日本でもやったらいいって言って。
リゲティ《グラン・マカーブル》(2009年上演、字幕原稿:長木誠司)は、ひとつのクライマックスだったかな。あれはお客さんの反応もすごく良くて、切符も売り切れてたからね。名前は知られてるけどできないような現代オペラってあるけど、特に劇場関係者はみんな待ってたような感じで、これやるんですかって反響が大きかったですね。
──プログラミングのほか、どの辺りに関わったのでしょうか。
そうそう、何をやるかっていうのを決めて、あと現場の人にこれどういう作品でみたいなことを教えていくっていうか。上演する意義とか、どういう所が大事だとか、オペラ史のなかでこういう位置に立っているみたいなこととか。あとはもっと細かい、演奏の仕方とか、演奏家を誰にするとかさ。歌手を選ぶときもオーディションに一緒に出たりなんかして、割と現場の近くではやってたかな。
──稽古にはだいたい出ている、という感じですか?
そういう感じね。まあ全部は出ないけどもちろん。まあ全部出るとうざがられるから(笑)。あとはイベントで、プレイベントとアフタートークとか。アフタートーク(ポストトーク)っていうのは、初めてやり始めたんだよ。やってるところ、それまでどこもなかったのね。演奏者とかみんなけっこうそこで話してくれて。化粧落として、さっそくなんかこう話しに来てくれるわけ。
2009年にフィリップ・グラスの《流刑地》やったよね。あのときは三浦基が初めてオペラ演出やって。彼は内野儀さんに紹介してもらって、誰かオペラやれるような演出家いないかねって言ったら、理論派に三浦っていう変な奴がいてって。《流刑地》はすごくいい舞台だったと思いますね。それで彼を交えてアフタートークとか始めて、それが最初だったかな。終わったあとに喋ってもらって。やる前に喋るのもいいんだけど、みんなが観たあとにそれについて議論するような場を設けたかったからやはりやりましょうってことになって、ずっとやってましたね。もともとはベルリン・コーミッシェ・オーパーの発想なんだけど。舞台終えたばっかりの歌手がやって来てさ、みんなで飲みながら一時間ちょっとくらい喋るの。今日は出来がどうだった、とかの話から始まってね。それも大事だろうなと思っていて、やりっぱなしってやっぱりつまんない。やったことの成果をどういう風に判断するか。客がどう観てるとか、聴いてるとか知りたいし。演奏家もどういうとこが難しかったとか、面白かったとかって話をみんな聴きたがってるし、本人も話したがってるところもある。やりっぱなしだと聴衆も広がらないし理解も深まらないから、話し合いの場はできるだけ設けたいと思って。
──アフタートークのこともそうなんですけど、作っていくなかで、演出家とのやり取りもけっこうあるんですか
ありますね。具体的にこうしろああしろっていうのは言えないんだけど、こういう材料があるとか今までこうやってきたとか、そういった情報っていうのはどんどん出していくような感じでしたね。まあ日生劇場なんかはそういうのを集めてくるスタッフがまた別にいて、ライマンのオペラをやったときは*7、二期会や日生の事務方のスタッフがかなり集めてきてくれてたかな。なかなか面白い経験でしたね。みんなで予めいろんな演出観るとか、出演する歌手の映像を一緒に観るとか。
*7 《メデア》2012年上演、ドラマトゥルク:長木誠司、画像は公演チラシ。そのほか、日生劇場にて《リア》を2013年に上演(字幕:長木誠司)

──音楽に関しては、指揮者などと、どれくらいやり取りがあるものですか。
そんなになかったかもしれない。音楽家は最終的にオペラの場合、集まるのは三日くらい前だったりするから。その前のコレぺティトゥアが歌手の前に音取るような現場には、ちょっと付き合いきれないので。練習のなかで指揮者と話す機会はあるけど、なかなか演奏に関してはどうのこうの口出すのは難しい感じでしたね。
──確かにオペラの場合は、指揮者っていうトップもいるから、演劇とかと違いますね。
そうね。だいたい音取りなんかは、ヨーロッパの場合は劇場付きのコレぺティトゥアがいて、その人が発音から音楽のスタイルまで全部教え込むんだよね。新しい作品のときは、半年間くらいかけて。そういうのが日本の場合ないから。コレぺティ付けられるって相当財力ないと劇場としては難しいので、歌手の人は自分のコレぺティを個人的に雇ってる場合が多いんじゃないかな。
その辺は制度としてだいぶ違うと思うし、やっぱり日本の人は忙しい。昼間は学校で教えてて、夜になってやっと時間できるみたいな歌手がほとんどだから、みんなでまとまって一斉にやるのがなかなか間際にならないと始まらない。歌劇場っていう組織があるかないかは、やっぱりオペラの場合は非常に大きなポイントだよね。二期会は、ほかの職業持ってる人たちがたまたま本番でやるって感じだから、それでずっと苦労してるし。それでもまあ、なんとかやっちゃうから、なかなか制度自体が変わっていかないっていう。
オペラを作る──新国立劇場《紫苑物語》
──新国立劇場での《紫苑物語》*8との関わりはどういったものだったのでしょうか?
*8 西村朗《紫苑物語》(2019)、作曲:西村 朗、台本:佐々木幹郎、指揮:大野和士、演出:笈田ヨシ、監修:長木誠司
あれはね、もともと東京室内歌劇場で西村朗さん(1953~)と作ろうってなったんですよ。でも、計画がとん挫してたんですが、どっかでやりたいねってことになってて、実は前の芸術監督で飯守さんに持ちかけたんですよ、で、飯守さんはすごく親身になってくれたの。これ絶対やりたいと。題材と、西村さんが音楽を書くってことでやりたいって言ってくれてたんだけど、新国は日本オペラをやめようかって言ってた時代で結局やらなかったの。日本オペラはお金かかるし、人入らないし、予算だけ食って大したことできないって。飯森さんはそれでもけっこうほめてくれたけど、最終的にやっぱりできませんってことになって、これはこのままかなってなったら大野さんが監督になったわけ。で、大野さんにメール書いて、実はこういう題材があって西村さんまで決まってるんだけど、やらない?って言ったら、大野さんがいやそういうの待ってたって。それで急に動き始めたっていう感じ*9。
*9 飯守泰次郎(1962~)は新国立劇場第6代オペラ芸術監督(2014~2018)。2018年9月からは大野和士(1960~)が新国立劇場オペラ芸術監督を務め、西村朗《紫苑物語》(2019)、藤倉大《アルマゲドンの夢》(2020)、渋谷慶一郎《スーパーエンジェル》(2021)などの世界初演・指揮を行う。
そこで、台本誰に書いてもらうかとか、演出だれにするとか。笈田さんの名前は私が出したんだよ。笈田さんいいんじゃないかって思うんですけどって言ったら、大野さんは笈田さんとやったことあって、それはぜひいいと。一番年長だったけど一番元気だったのが笈田さんだった。まあ身体の鍛え方が全然違う…。で、結局歌手は大野さんが決めたけど、ほかのスタッフに関してはいくつか案を出して、それで決まって。あれはほんとに四人最終的にいろいろ、台本ここはダメとか。
結局、二幕仕立てにしたけど、一番最初の原案は僕が書いてたものがあったんですよ。グランド・オペラ的に三時間くらいかかるものだったんだけど、長すぎるからもっと短くしようって。で、佐々木さんがプロフェッショナルに入って二幕仕立てにして、やっぱり一幕長くして二幕短くしてみたいな感じで。で、どこで切るかとか、前後入れ替えないと話が繋がらないとか。
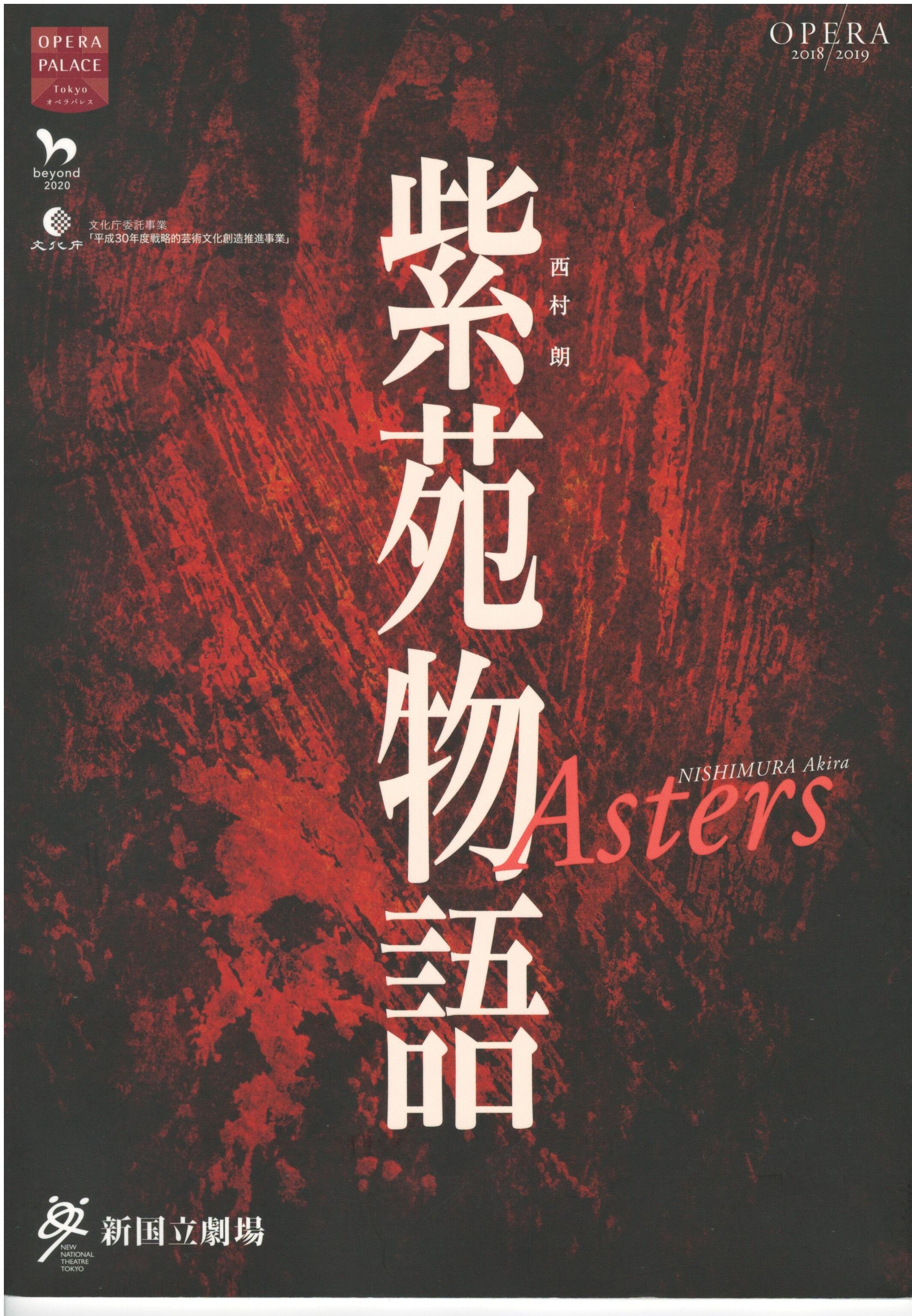
『紫苑物語』公演プログラム表紙より
現代オペラって、長いと二幕目みんな帰っちゃうから、ほんとは一幕で1時間40分くらいでマックスにする細川さんのオペラが一番いいんだけど*10、どうしても西村さんの場合は二幕にしかならないねって。そうすると、いろんなトピックをどこまで削るかとか、分かりやすいトピックを間に入れてくとか、話の展開や前後をどうするかってことを考えながら。だから本来二幕の頭にあったものを一幕に持ってきたりとか、みんなで考えて作った。大野さんもそれにかなり口を出して、かなり侃々諤々やったんですね。西村さんが最初に付けてきた合唱はけっこう単純で、歌のパートもあまり面白くなくて、それを僕がね、あの西村さんに、いやこういう音楽なんだよって久しぶりに五線譜で楽譜書いて送ったの。現代オペラの歌唱パートはこういう風に書かなきゃっていう(笑)。大作曲家に助言するような大それたこともやってましたね(笑)。
*10 細川俊夫(1955~)、作曲家。オペラ作品には《地震・夢》(2017-18、1幕、100分)、《海、静かな海》(2015、1幕、90分)、《松風》(2010、1幕、75分)、《班女》(2003-04、1幕、80分)、《リアの物語》(1997-98、2幕、100分)など。
──最初に長木先生が作った台本は、どのようなものだったのでしょう?
台本は作ったんだけど、ぽしゃったんですね。さすがにこっちも台本作ったことないから、ここはやはり詩人に任せた方がいいってことになって、西村さんと良くやってる佐々木さんに任せようと。僕の台本では、最初は、真ん中にインテルメッツォの笑劇入ったりしてたんですけどね。
──まさにイタリア・オペラ。
基本的にみんなで合意してたのは、あまり過激な台本じゃなくて、むしろ古典的な台本の方がこれまでなかったということ。オペラの作劇法って、これまでみんな新しいことやってるようでいて、結局そんなに新しくなくて、逆に基本的なことができてないと思って。本当はインテルメッツォみたいなのをあえて入れると面白いと思ったの。そこまではさすがに受け入れられなかった。まあ深刻なオペラでも笑いの要素がないとつまらない、みたいなことから始まって、あとは人物の捉え方とか、役柄の在り方とか、意味づけとか、四人で話し合って、佐々木さんがその都度書き直してたかな。佐々木さんが一番大変だったね。あーでもない、こーでもないってみんな言うから、結局全部書き直したりとか。それが西村さんの作曲段階に移っても続いたからね。西村さんも結局三回か四回くらい、全部書き直したんじゃないかな。
──えーー
音符の数も膨大なんだけど、場合によっては全部書き直すんだよね。あの速さは驚いちゃった。うちに第三版、第四版くらいもあるけど。結局、もともと第二幕の前奏曲がいま第一幕の前奏曲になってるしね。前奏曲長すぎるからこれ第一幕に置こうってことになって、そっちにまわして。
──『オペラの20世紀』や『戦後の音楽』(作品社、2010年)などの研究の蓄積と、《紫苑物語》のような具体的なオペラ作品は、どんな風に関わっていますか。
具体的にどうのこうのっていうのはなかなか難しいけど、オペラの構成の歴史っていうのはこっちも分かっていて、もう新しいものはないっていう感じがしてたからね。むしろオペラって一巡して、もっとストーリーがはっきりしたものとか、アデス*11みたいな、エンターテインメント的なものが増えてきたから、むしろそっちの方がよいという考え方が基本的にあった。あまり実験的なものはなかなか難しいというか、大概やりつくされちゃってるし。それからパフォーマンスみたいにほかのジャンルと合わせてもあまりうまくいかないっていうのも、何となく分かってきたんだよね。
*11 トーマス・アデス(1971~)、オペラ《皆殺しの天使》(2018)など。
だから実験オペラみたいのも、オペラとしてやる以上は、ある程度古典的な作風にした方が絶対に面白い。それから声の扱い方みたいなのも、あんまり声、声したものじゃない方がいんじゃないか。つまり古典的なコロラトゥーラがあったりとか。かなり難しいコロラトゥーラが入った日本のオペラってないから、そういった方向でやってみたらっていうのがあって。
これが90年代くらいに作ってたらもっと突拍子もないものができたかもしれないんだけど、今の時代だと、そういうものじゃない方がむしろ新しいっていう考え方はだいぶ言ったんですよね。西村さんに頼むってそういうことだって思ったしね。つまり西村さんはそんなに実験的なことをやるわけではないだろうし、音楽の作り方も東洋とかいろんなものが入ってくるから、オリエンタリズム的なものをあんまり出すのはつまらないっていうか、わざとらしい。それをやろうとして今までいっぱい失敗してきたから、日本日本したものも必要だけど、あんまり縛られない抽象的な要素が入ったものの方がいいって言うので、『紫苑物語』みたいのを選んできたわけ。あれは日本の話だけど、すごくユニバーサルな内容だと思うんだよ。日本じゃなくて、アジアのどこかでもいいみたいなところもあるしね。音楽の作り方も、日本ではなくてアジアみたいなもの、ヘテロフォニーみたいなものを取り入れてっていう形にもなって、その方がむしろ面白いんじゃないかなと思っていて。
これまでなかったものを作ろうっていうのは基本にあるんだけど、必ずしも全て実験的なものではなくて、これまでなかった「組み合わせ」でやってみようって感じかな。そういう所はだいぶ主張して、実現できたんじゃないかと思いますよね。大野さんも、基本的には同じような考え方。あれだけいろんなものを振ってるとさ、下手に新しいものを作ってもだめなんだってことは分かってると思うから。
──なるほど。
その後の、藤倉大(1977~)の《アルマゲドンの夢》(2020、新国立劇場制作)は、もう少し別のスタンスで藤倉さんはやってるよね。もっとポリティカルな要素を入れたりとか。ただ、なんていうんだろうな、ギラギラとしたポリティークはないんだよね。これもやってみました、これも必要だからやってみました、みたいな。我々の世代からするとそういうのって許せないことだけど。営業ポリティクスみたいな(笑)。まあなんでもできちゃうからね、藤倉さんは。去年なんかは広島のAkiko’s Piano[ピアノ協奏曲第四番(2020、広島交響楽団委嘱・世界初演)]を作って、それなりの主張を持ってもできるんだけど、どこまで真剣に考えてるんだかよく分からない、みたいなところもある。そういうノンポリティクス、そういうのもすごい才能なんだけどさ。でも、その延長線上で今度はオペラもやる、というのはたぶん西村さんにはできない。我々の世代は、はまらないとできないから。だから、そういうポリティカルなものは我々はやめましょうと。
とにかく『戦後の音楽』を書いたとき、オペラのことをだいぶやって、今までどういう苦労してきて、どういう風な言葉の扱いにしてきたとか、日本語をどういう風にやってきたとか、そういうものはだいぶ西村さんには言ったんだよね。佐々木さんもそういうこと良く分かっていて、どこにどういう言葉遣いをするとか、あるいは韻を踏むとかから始まって、これまでのことをふまえながら、それなりの情報も僕からあって、みんなでオペラのテキストを作ったりしたと思いますね。

『戦後の音楽』(作品社、2010年)
──《紫苑物語》は、かなり人も入っていましたね。
そうだね。ほとんど売り切れ状態に近かったと思いますけどね。あんなに入ったの初めてですね、現代オペラで。てか創作オペラで。創作オペラって嫌な言葉だけどね。まあ日本のオペラでね。あれは大野さんの就任がひとつの売りだったってこともあるけど。
──石川淳を原作に、というのも長木先生のアイディアですか?
そもそも《紫苑物語》でというのが僕のアイディアだったんですよ。石川淳は、ほかの長い作品は無理だけど、《紫苑物語》って長さもちょうどいいじゃない。それでもけっこう長くて、あの二分の一くらいだと一番いいんでしょうけど。三島はあれだけもてはやされるのに、石川淳はある意味、忘れられてる作家だし。
《紫苑物語》の世界は幻想的なものもあるし、いくつかの世界が同時進行するようなこともあるから、オペラにすると面白いと思っていて。同時進行みたいなことはもうちょっと入るといいと思ってたの。たとえばふたつの舞台が同時に進行するような。最初は言ってたんだけど、なかなか実践には移せなかったかな。主人公の屋敷と裏世界、つまりもうひとつの別世界が一緒に舞台上で進行するようなことも、最初は考えてたんですけどね。なかなかそれを台本化するのは難しい。オペラってちょっと、物語を展開させるにはあまりにも時間が短いっていうかな。一応、四重唱ってことで、ふたつのペアを一緒に歌わせるところまではやったんだけどね。場面として重ねるのはなかなか難しかったなあ。
──新作のネタはけっこう探されてたんですか。それともたまたま…
そうね、西村さんに頼むときにいろいろ探してて。《紫苑物語》に関しては誰でもいいから、これやるといいなとは思ってた。ほかにもいくつか案はなかったわけではないんだけど、ダイナミックな筋展開でオペラになりそうなものはそんなに多くなかった。かつ、もともと戯曲じゃないのは。戯曲になるとさ、たとえば三島の戯曲って特殊例かもしれないけど、オペラにするときに一字一句変えるなって遺族が言うわけ。でね、大変なことになるわけよ。
池辺晋一郎さん(1943~)が《鹿鳴館》(2010、新国立劇場にて世界初演)をやったけど、あれもね、言葉が多すぎてさ。多すぎるっていうか喋らなきゃダメでしょう、歌にしないで。僕それ大嫌いなのよ。オペラのなかでなんで喋るんだと。松村禎三(1929~2007)もみんなそうで、音符書かずに言葉だけが並んでるっていう感じになって。戦後オペラ観てるとそういうのがあまりにも多すぎちゃって、それはやめようって。喋りまくりはやめて全部音符をつける。とにかく、全部音符にする。で、どんなに難しい音型でも必ず歌わせる形にまずしましょうっていう前提で始めたんですよね。そうするとやっぱり台本化がかなり大変になってくる。ただ、芝居だかオペラだか分かんないっていうオペラではなかったと思いますね。とにかく歌ばっかりのオペラにしたくて、まあなったと思いますね。
──新しいオペラを作ってみたいっていうのは、前々から考えていたんでしょうか。
それはずっとあって。特に新国が始まってから毎年制作されるっていう建前だったじゃない、それにどっかに絡みたいなあとは思っていたけど。だけどまあこっちも当時若かったから、なかなかそこに口出しはできなかった。だから、同世代で大野さんなんかが監督になったから一緒に話せるけど、なかなか上の人に出すのは難しかったかなと思うよね。西村さんは、彼の方がちょっと上だけど、同世代という意識が強いから、そういう世代的な問題も絡むかな。
ヨーロッパの劇場みたいに、ドラマトゥルクがいてさ、その人たちが題材をいつでも出してこれて、それが劇場単位で具体化して議論できるっていうある程度組織的なシステムがあればよいけど、日本ではなかなかないから。で、結局個人的な繋がりとか、そういうことでしかオペラの制作ってできないと思うんだよね。だからたまたま作曲家がいい台本作家、というかいい作家と出会って一緒に作ろうってことになってったらいいと思う。
実は、表象に赴任してすぐに、野平一郎さん(1953~)がオペラを作りたがっていて、松浦寿輝さんに紹介したの。松浦さんもすごく乗ってくれて、制作まで行きそうになったんだけどね、結局台本化しなかったよな。双方乗り気だったんだけどね。そういうことは、自分じゃないにしてもやっていいと思っていて、オペラを書けそうな人なんだけど書いたことはない人に、道を作るのもやってみたいと思ってる。
──松浦先生のリブレットがどんなものになっていたか、とても気になりますね。
オペラ──日本とヨーロッパの間で
──先生が表象にいらっしゃった頃に話が戻ってしまうんですが、ノーノ《プロメテオ》の秋吉台での上演は、どういう関わりだったのでしょう。
あれはね、やることはもう細川さんが決めてたけど、テキストが大変じゃないですか。マッシモ・カッチャーリが編集したベンヤミンとか、ヘロドトスとか。演奏家はアンサンブル・モデルンで来て、指揮者まで決まってた。もちろん電子音響エンジニアも向こうから来て、上演するのは分かってたけど、作品理解がなかなか難しかった。これはすごく大変な作品だなと。
僕もまだ、当時は実演を聴いたことがなくて。話はいろいろものでは読んでたし、どんな作品かイメージあったんだけど、ちゃんとテキストを見てなかった。で、見てみたら大変で、ちょうどいい機会だから、表象にいろんな言語できる人いるし、竹峰くんなんかベンヤミンとか当時から専門じゃない。だからちょっとゼミでやろうかってことになって、テキスト全部分担決めて、授業としてやったんですね。
学生のみなさんに全部プログラムも分担して書いてもらったし、テキストも全部分担して訳してもらったの。ライブ・エレクトロニクスのこともみんなで調べて、音響技師ハラーのドイツ語文献も僕が訳したりなんかして。つまり、作品を舞台でかける上で、できるだけちゃんと理解できる形でゼミをやった。それを全部プログラムに入れたっていうような感じ*12。あれはいい経験だったかな。みんなで制作に関われたかなっていう感じで、なかなか面白い経験でしたね。みんなで聴きに行ったしね。
*12 ルイジ・ノーノ《プロメテオ――聴く悲劇(トラジェディア・デル・アスコルト)》は、1998年に秋吉台国際芸術村のオープンに合わせて日本初演。プログラムに竹峰義和による翻訳や論考なども所収(画像:表紙・目次)。
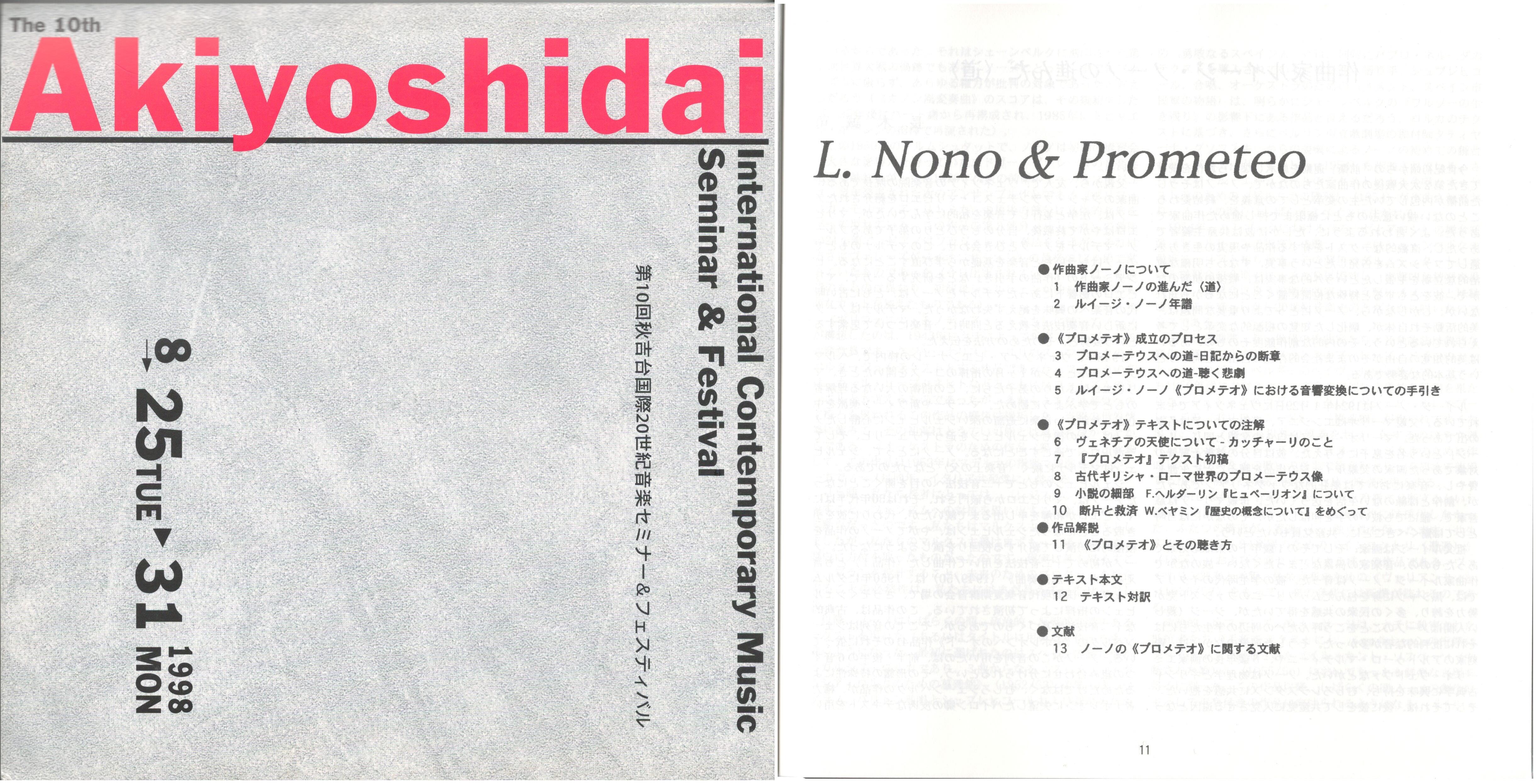
──《紫苑物語》は新作ですけど、長木先生が今までかかわってきたオペラ上演って、やっぱり日本初演いかにするかっていうのがすごい重要なところなんだなって思いました。今まで日本でされたことないからどうやるのかってときに、研究者の力はすごい大きいんだなって。
僕なんかがやってるのは、結局ね、ヨーロッパの現状に追いつけみたいな話になっちゃうからあんまり好きじゃないんだけど、ツィンマーマンをやったり、リゲティをやるのは、やっぱり知らないとだめだと思うわけ。つまり、ヨーロッパだと、三、四年に一回くらい、しょっちゅうやってるんだよ。だけど、一回もやったことないとさ、その前は知ってて、その後もなんかぽつぽつ知ってるけど、真ん中にあるミッシングリンクみたいなでっかい作品って、結局誰も企画しない。歌劇場の底力がないとできないし、お金かかっちゃうからそれだけの財力や基盤も必要だし、練習時間とかもちゃんと用意しないといけない。だけど、これは知らないと次の段階に行けないよね、みたいな作品がいくつかある。
たとえば《グラン・マカーブル》はその後のオペラ創作を決めたような作品だから、知らないといけないと思うんだけど、そういう企画がないんだよね。で、やっぱりそこは日本の研究者として、これまでヨーロッパで勉強してきたし、日本に伝えなきゃいけないっていうのはあるわけね。それは研究者に対してもそうだし、もちろん実践の人にも、ちゃんと観てもらわないといけないなっていうのはあってね。
──うんうんうん。
それでリゲティや、特にツィンマーマンはそういうところがあって、《ある若き詩人のためのレクイエム》もそういう感じで*13。サントリー芸術財団用の企画なのでお金もつくし、この際採り上げるならこれかなと。それから、《シュティムング》もそうだったんですけど、声ってものを考えるときに、60年代終わりの実験を見過ごしたらできないっていうのはあって、そのときに、同じ年のふたつの作品を同時にやるのがいいなと思った。今の時代の音楽を理解する上で絶対必要なものって何かなって。そこに抜けてるところを、少しはモノの見えてる人間は用意しないといけないと思っていて、特に若い人にとってもね。
*13 サントリー芸術財団・サマーフェスティバル2015「プロデューサー・シリーズ 長木誠司がひらく 拓かれた声/封じられた声──ケルン1968/69」で、B.A.ツィンマーマン《ある若き詩人のためのレクイエム》日本初演、シュトックハウゼン《シュティムング》などの上演を企画。画像は公演パンフレットより。
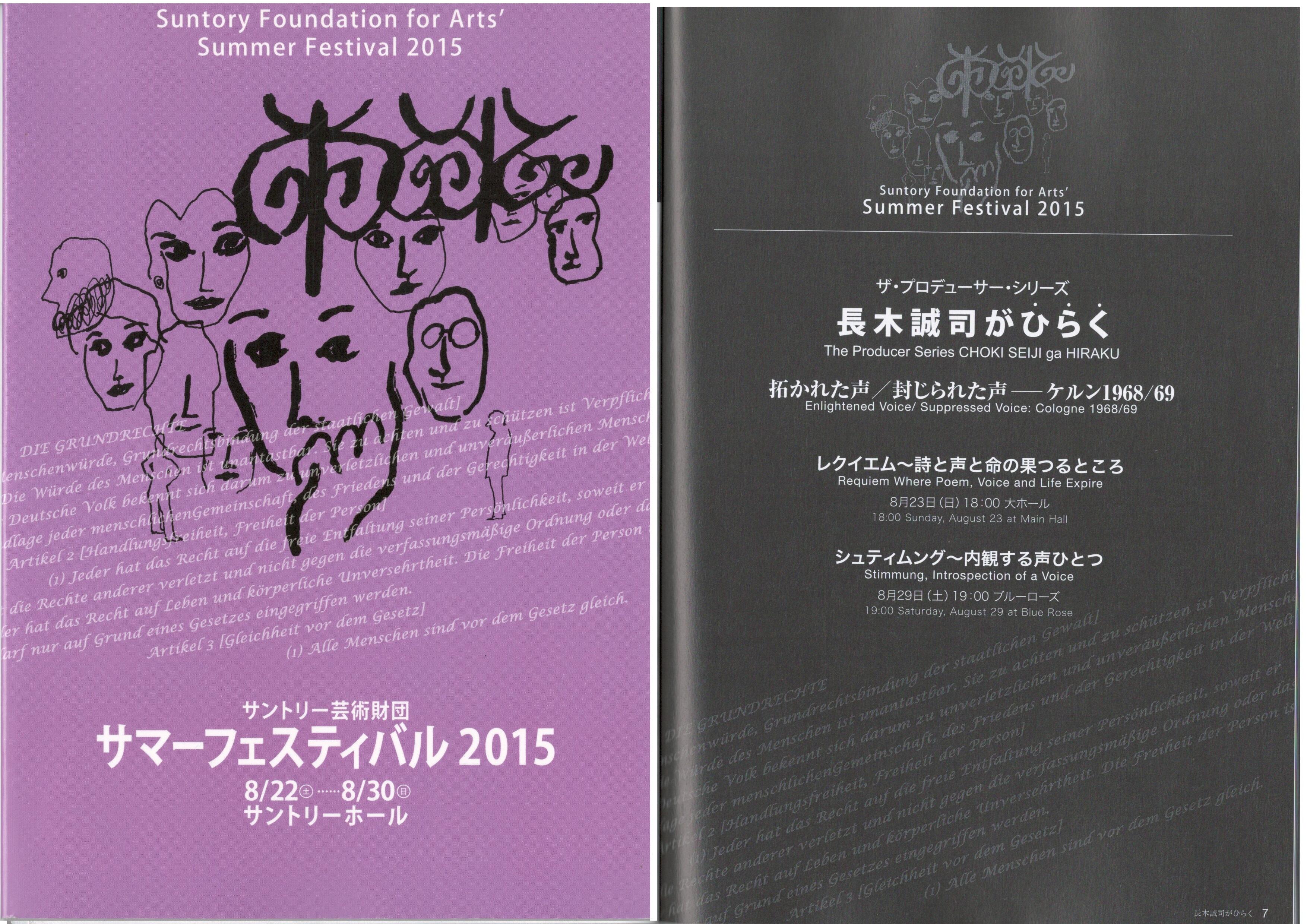
やっぱり僕が研究始めたとき、何が大変かっていうとまず語学やること。語学やり始めてようやく基本的な文献を読んだりさ。基本的な作品は、レコードがまだ多くないから、日本盤なんかでは当然聴けない。でもそういうのも聴かなきゃいけない。そういう経験ってさ、ヨーロッパに留学したとき、同僚の学生さんはみんなとっくにやってるんだよね。こっちがやっと追いついたところに彼らはふつうにいてさ。そういう経験はつまらないと思うんだよ。つまり、同じところにいつもいないといけないと思うわけ。そういう意味では、そういう環境を作らないといけないなってしみじみ思った。だから少なくとも、一度は作ってみんなと共有して、あーこれがあるから次はこれがあるんですね、あるいはこれがあったからこれがあったんですねみたいな、脈絡は作りたいと思って。それを基本的な考えにして、いろんな作品を選んでたってことはあるんですよ。
それは東京室内歌劇場のときもそうだったし、《紫苑物語》は今の創作はどうあるべきかっていうことだったけど、ツィンマーマンもそういう意味では、ミッシングリンクだなと思っていて。あれがあると次の所へ進めるんじゃないかっていう感じなんですね。そこはやっぱり一番大事かなと思っている。なかなか現場の人ってそうしたスタンスでものを見てないから、そういうのをやるのはやっぱり研究者なのかもしれないな。そんな風に軸足を置けるんだったらやらなきゃいけないと、僕なんかの立ち位置はそういうところかなと思ったりしましたね。
──レクイエムの上演も、字幕を付けてというのがすごいアイデアでしたね。原島大輔さんが字幕を。
あれは、ドイツ人が聴くときと日本人が聴くときでは全然違って。ぼく最初に聴いたときに、ドイツ語全然分かんないじゃんって。テキスト見ながらだってドイツ語を聞き取れなかったり、聞き取れないのはドイツ人も同じなんだけど、聞き取れないレベルが違うじゃない?片言でも聞き取れるけど、それは日本人じゃわかんないじゃん。だとするとちょっとつまんないから、聞いて分からない程度に、読んでも分からない程度にしたっていうのはそういうことなんだよね。字幕は見えるんだけど読みきれない、それがちょうどドイツ人があのレクイエムを聞いてるんだけど聞き取れないくらいのレベルかなと。あの作品は、混沌としてて、所々聞こえたり聞こえなかったりするところが、大事なところだから。そういう混沌を視覚的に作るってことが大事かなと。その意味ではうまくできたとは思ってるんだけどね。
レクイエムはフランスのストラスブールで最初に観たんだよね。あれはちょうど留学した86年の9月。ストラスブール・ムジカという音楽祭が現代音楽ばっかりやっているとこで、ベルティーニがケルンのWDRのオーケストラ振って、まずそっちでやる。で、そのあとケルンに戻ってきてそこでもやったんだけど、フランスでの反応とケルンでの反応と全然違うんだよね。フランスのストラスブールはちょっとドイツ語できる地域だと思うんだけど、バイリンガルみたいなアルザスの街だから、でもなんかみんなキョトンとしてるんだよね。ケルンだと大反響と言うか、燃えに燃えるわけ。サントリーもそんな感じの大反響だったけど。やっぱ言葉がある程度分かって聴くのと分からないで通り過ぎるのとでは全然違うなと思っていて。サントリーの反応はむしろケルンの反応と似ていたから、これはよかったかなと思ったんだよね。ストラスブールのときは1回目だったから僕もほんとよくわからずきょとんとした感じで。どこが面白いんですか、みたいな感じだったけどね。
ストラスブール・ムジカっていい音楽祭で、ブーレーズが来て《二重の影の対話》かな、クラリネットの。ブーレーズが操作卓の前に座っていたんだよね。同時進行のライブ・エレクトロニクス、つまりコンピューター使って同時にフィードバック音響変換していくのを初めて観た。あのときほかにもいろいろやっててけっこう面白くて、ヨーロッパの現代音楽って全然下火になってないと思ったんだよね。日本は、80年代真ん中になるともうヨーロッパなんて終わっちゃってますよみたいな話になってて、でも行ってみたら全然違ってて、これはいろいろ学ばなければいかんなと思ったんだよね。観たこともないものを観られるからちょっといいかなっていう感じで行ったら、ストラスブールも良かったし、ダルムシュタットも、ドナウエッシンゲンも熱気があってね。日本では、現代音楽の演奏会っていつも同じ200人ぐらいの人が来ることになってたから、もうこれ駄目なんじゃないかと。ヨーロッパもだめで日本もだめならもうおしまいだと思って行ったら全然そんなことなかった。ヨーロッパの音楽祭とか現代音楽祭は、いろいろ政治的な力が関わってのことなんだけど、まあ客は繋ぎ止められていてけっこう盛大になってることが分かった。ちょっと日本で言われてることと話が違うぞと。
当時インターネットも何もないから知らないわけよ。たまに入ってくる文字情報しかない。だからそこが一番の驚きだったですね。やるものやるもの、我々が日本で聴いてたいわゆる現代音楽の名作じゃないのよ。シェルシとか、ツィンマーマンとか、そういう点と点をつなぐ部分をいっぱいやってて、それが日本にいると分かんなかったっていうことが、自分でこういうことやってみようと思うようになった大きなきっかけではあるかな。同じ環境にはなれないっていうのは当然なんだけど、あまりにも有名なものしか来ない、名の知られたものしかやらない。そういうんじゃないよねっていうのがあって。そういうのではなくて、それを埋める大事な作品を日本でやらないと歴史が線に見えてこない。それが必要だと思っているんです。
──《紫苑物語》にせよ《レクイエム》にせよ、作ってみてそれが歴史の見え方にフィードバックされることや、新たな着想が生まれるということはありましたか?
そこまでは行ってないかもしれないな。これはもう基本的にベースとして知っておくべきだなという感じだったかな。でも《紫苑物語》は、西村さんの新しい面が見えたということはあった。こういうことができる人なんだなと思ったし、学ぶものが多かった。でもなかなか歴史につなげるところまではいかないかな。本当ならばこういう機会がもっとたくさんあって、穴埋めが進んで現代まで線がつながるなら、こういうものもありうるんじゃないかっていう発想が生まれるかもしれないけど、まだそこまでは行ってないな。
まあ日本では日本のやり方があるとはもちろん思うんだけれども、これまで知っている現代音楽の世界はあまりにも穴が多かったということはずっと思っているんです。僕は最初の本の『前衛音楽の漂流者たち もう一つの音楽的近代』(筑摩書房、1993年)が、シェルシとかツィンマーマンとかブゾーニとかさ、ほとんどマイノリティばっかり扱って、その路線は全然変わってないんだよね。そういうものをちゃんと知らなくちゃいけない。自分でも知りたいと思うし、実際に聴いてみたいと思うし。でも、そういうことやってる人はみんなそうなんだろうね。片山君*14とか、結局はああいうことやってるのは自分が日本の戦時中の音楽を聴きたいからだよね。昔聴きたいなーと思っていた音楽を彼は今聴けてるからいいなと思うんだよね。そういうのが分かるとやはり歴史の幅が出てくると言うか深みが出てくると言うこともあるしね。理解の形が多分違ってくる。やはり必要なんだなと確信を持てたかな。
*14 片山杜秀(1963~)、著書に『音盤考現学』(2008)、『鬼子の歌 偏愛音楽的日本近現代史』(2019)など。
表象文化論との関係
──表象文化論研究室ができたころのことも、お伺いできればと思います。
まあ最初からいる人間じゃないからね。蓮實重彦さんとか渡邉守章さんとかが作ったときのことは僕はわからないし。渡邉さんの演出いくつか観せてもらったけど、それくらいの世代なので。もともと表象ってとこは大学の外でなんかやってる人たちが多かったし、特に渡邊さんとかは、演出いろいろなさってたからね。そういうことは本郷の先生たちはまずやってなかったような感じだったから、駒場の先生の売りっていうこともあったんだろうと思いますしね。まあそれが一種、伝統になっちゃって。まあ全員が全員そういうことやってるわけではないけど、ある一定の人数そういうことをやってる人がまあとりあえずいたって感じ、ですかね。
──渡邉先生の舞台ご覧になったというのは、駒場に着任してからですか?
いや、まだ学生時代だね。『繻子の靴』とかさ、それから『アンドロマック』とかいくつか観たんだけど、細かいところほとんど忘れてしまっていてですね(笑)。
──蓮實先生の授業などは?
蓮實さんの授業は、ひとつふたつ取ってました。ちょうどノリノリの時期でしたからね、お二人ともね。本郷に進学しちゃったから駒場の二年間だけでしたけど、それが77年と78年かな。当時はもう駒場の先生たちもゼミとか持ち始めてたから、一般教養の授業のほかにゼミみたいなものに出ることはできたんですね。蓮實さんのゼミはたしか映画を年間に200本だったか観ないといけないというのであって、それはとてもできないなと思って出なかった。そこまで映画に情熱なかった、こちらも。
──上の世代の方で、どなたか影響を受けたということはありますか?高辻知義先生や秋山邦晴さんなどの活動はいかがでしょう。
高辻さんは僕が表象に入る前、個人的には知ってたんだけど、僕はドイツ文学者だと思ってたんだよね。いろんな翻訳とか論文とか書かれていて、お世話になったかな。それを見たというのはあるんですけど、お仕事を客観的に見るっていうことはしてないかもしれない。高辻先生はやっぱりワグネリアンでワーグナーの解説者みたいなところがあるじゃないですか。そういう意味ではやっぱり僕ワーグナー嫌いだったからちょっと距離はあるかもしれないけど、やっぱりいろいろ学ばせてもらった。アドルノの翻訳とかでお世話になったかな。音楽之友社の『不協和音』とか『音楽社会学』とか訳されてたんじゃないかな*15。
*15 『不協和音 管理社会の音楽』(三光長治・高辻知義訳、音楽之友社、1971)、『音楽社会学序説』(渡辺健, 高辻知義訳、音楽之友社、1975)。いずれも平凡社ライブラリーとしても刊行。著書に『ワーグナー』(岩波新書、1986年)など。
あの世代ってアドルノなんてみんな読まなかったから。当時は、アドルノって左翼がかってたと思われてたと思うんだけど、読むこと自体タブーになってた。美学なんかもっとすごくて、なんでこんなわけのわからないもの読むんだって庄野進さんとか怒られてたらしいから。でもそういうものを率先して読めるものに訳してくれたっていうところで、高辻さんはとてもいい仕事をなさってたと思うんだけど。ワーグナーに関しては三宅幸夫さんなんかと一緒にやってた作品研究だよね。ドイツ音楽関係の仕事はよく知っていて学ばせてもらったということはあるけど、逆に客観的にどういう位置づけかってことはあんまり考えたことがなかったかな。
それより秋山さんなんかは、表象じゃないけど、逆に現代音楽にべったりすぎちゃって僕は実はあんまり好きじゃなかったんですよね。ほとんどスポークスマンになってたから。価値基準もはっきりしてたし、前衛の人で、三枝さんなんかと大喧嘩するような感じだったから。三枝成彰さん(1942~)がヴォコーダーを使った《ラジエーション・ミサ》っていう曲を作ったんだけど、その初演のときに二人が客席とステージ上で大喧嘩してさ。お前はナチだとかお前こそ独裁者だとか。これ論争になってるのかって(笑)。まあでもね、秋山さんはそういう意味では前衛寄りの現代音楽のスポークスマンで、価値観がちょっと狭い気はしたかな。もう調性音楽も変わってきたし、ドイツでも変わってきてたし、秋山さんはそこら辺どう思っていたかは知らないけど、三枝さんみたいな人は全然ダメで、大衆寄りな曲を書く人は全然ダメで。あの世代の現代音楽関係者はみなある程度そうだったとは思うんだけど。やっぱり、あの人は典型的な批評家だなって思ったんだよね。研究してるんじゃなくて。自分のいいと思ったところには突っ込んでいって、突き進むっていう感じで。
僕はそうじゃなくて、基本的には三枝さんだって嫌いなんだけど、研究として、自分の価値観じゃないところの物もちゃんと見ないといけないなと思ってたかな。ダメだと思うけどでも研究はするかな、と。『レコード芸術』なんかでけちょんけちょんには書くんだけど、そういう世界も実はありだなとは思うんだよね。あってまずくはないし、ないと逆に前衛もないからね。相対的なものだから。ただ僕はあんまりスポークスマンにはなりたくないなとは思ったかな。のめりこんじゃって批判力が逆に薄らいじゃうのも問題かなと。
秋山さんの映画に関する仕事はまた別の所にあって、スポークスマン的な所はちょっと薄らぐと思うけども。現場の情報持ってるじゃない。そういうところから物を言えるというのはすごいと思うし、それをちゃんと満遍なくと言うか距離を置いて自分の研究の素材として使うといいと思う。だけど、秋山さんはそうじゃなくてのめり込んでいる部分があったと思うな。高辻さんは逆に言うとそういうところはあんまりなかったな。現場にそんなに関わらなかったからとは思うんですけど。研究対象はワーグナーだし、もう100年前の過去の人だしね。だからある意味、距離を十分に取れるというわけで。秋山さんは一緒に行ってる感があったからね、作曲家と。セクトの作曲家たちと一緒にやってる感があった。
──先行する世代の方で長木先生の現場との関わり方と重なるような方があまり思いつかず、あえてお二人の名前を出してみたのですが、お話を伺ってなるほどと思いました。
音楽学ってやっぱりマイナーで、だいたい初期は演奏家とか音楽家から嫌われてたのね。音楽を言葉で語るなんて、あるいは音楽を研究するなんてって言われて何も認めてくれなかったところがあって。特にクラシカルな音楽界はね。音楽学が研究のジャンルとしてあって、現場と交わりながら距離を置くことができるんだということが、僕の上の世代にはなかなかなかったかもしれない。そういう立場やスタンスを取れる人はなかなかいなかったかもしれない。徳丸さんは、そういうところがあったかもしれないけど。自分でも三味線を弾き出したりなんかしてたから。そういう人はなかなかいなかった気もするな。みんな大学で研究としてやるか、日本音楽の人もね。たとえば小泉さんみたいな民族音楽から入ってきた人は、実践やりながら研究もするっていう、そういう人かな。むしろ西洋音楽の研究者にはちょっといなくて、彼のような方法が音楽学全体にやっと敷衍してきたっていう感じじゃないかね。小泉さんの存在っていうのはある意味大きかったと思うんだよね*16。
*16 徳丸吉彦(1936~)、著書に『音楽とは何か 理論と現場の間から』(2008)など。小泉文夫(1927~1994)、著書に『おたまじゃくし無用論』(1973)など。
研究・教育・現場
──最近では、現場との関わりを前面に押し出した駒場の芸術創造連携研究機構での活動も盛んですね。
やっぱり若い頃にモノを作るっていうことは大事だと思うんだよね。どんな分野でも必要じゃない。たとえば理科系だって、デザインひとつ取ったって、研究所入ったって必ずやるじゃない。研究発表のパワポの作り方ひとつにしても、デザインの感覚は絶対に求められるし。物を作る感性とか、もちろんお仕着せものでも、でき上がったものから作るにしても、どう組み合わせるかっていうことはやっぱり大事だと思うし、そういうところで自分のアイデアをちょこっと加えるとかできたらやった方がいいと思う。そういうことって若い頃にやっておいた方がいいと思うんだよね。
総合大学って世間的には先生の言うことを聞いてって感じだったじゃない。ずっと座学ばっかりだったけど、実際にこういうことをやってみるといいみたいなヒントを与えてものを作ってもらうと、みんなよくできるんだよね。音楽の授業しか僕は知らないけど、去年はコロナ禍で合唱の授業とかできなかったから、オンライン基本で作曲の授業を三つか四つやったんだよね。で、コンピューター使ったりとか、自分の声使ったり、どこか音を拾ってきて組み合わせて変調させてたりとか、そんな授業をしてると、みんな面白いものを作ってくるんだよね。去年は、松平敬さんにも来てもらったんだけど、彼はけっこう驚いてて。東大生の発想は面白い、音大ではちょっとないねなんて話をしてた。皆さん、それなりに物を作ることへの欲求はあると思うんだよね。授業のなかでそういうものを発散させる場がなかったから、表象では時々やってたけど、もう少し全学的にまとめてやってみようと。
芸術関係で面白いことをやってる研究者でも、学部が違うと全然情報が回ってこないから、そこを連携して情報交換することから始めて。あとは研究機構だから、学際的な研究とアートを結びつけて、そういう研究成果を授業に落として行くみたいな場が必要だよねとずっと話していて。まあ、そこにお金を出してくれる企業はまだなかなかないんですけどね。音楽は「かけはし財団」っていうローランドの財団が出してくれて、そのほかお金を出してくれるところ探してるいるんだけど。そういうことが総合大学でも大事であることを認識してもらう意味で、シンポジウムとかを今度やるわけなんですけど*17。
*17 東京大学芸術創造連携研究機構(機構長:長木誠司)の発足シンポジウム「学問と芸術の協働 ―アートで知性を拡張し、社会の未来をひらくー」(2021年3月20日・21日 オンライン)。
それは学生さんのためにもなるし、長い目で見ればそういう人たちが卒業して将来いろんなジャンルで活躍するときに絶対力になると思うので、是非やりたい。ものを作るということね。東大生は基本的にこれをやれって指示したら相当うまくできても、自分でなんか考えてなんかやれって言ってもできないと思ったんだけど、こういうアート関係やったら割と自由な発想でやってくれるから。それってやっぱり新しい自分の発見じゃないけど、こういう一面もあったのかということを分かっただけでもいいと思うし、こういうことを大学でやってもいいんだということをちゃんと理解してくれるともっと別の道も開けるのかなと思う。オペラ観せてる授業もあるんだけど、途中で客席のみんなが笑ってるのをビデオで観て、オペラって客席で笑っていいんですかって訊いてくる学生がたまにいて、いいに決まってるじゃんって。そうやって堅苦しく考えている人もなかにはいるんだよね。こっちが考えてもみないことを縛りに感じてる人がいると思うと、そういうのをちゃんと外してあげたいとも思う。専門的なところに行ってもそういうことを踏まえて考えてくれる人がいればいいかなと思ってます。アートってそういう意味で一番自由じゃないですかね。何やってもある意味認めてくれるじゃない。こういうのも面白いって言えるのはアートの分野ぐらいしかないから。ほかの分野でこれ面白いからやってみたら人殺しちゃったみたいなことでは困るけれども、アートはそれがまずないと思うから。ま、わかんないけどね(笑)。
──最初におっしゃっていた高橋悠治が小林秀雄を批判したこと、そこに尽きますね。作ってない人に批評ができるのか研究ができるのかというところですよね。ちなみに、研究と批評の関係についてはどのように考えていらっしゃいますか。
けっこう難しいからちゃんと考えたことはないけど、批評は昔からある種仕事としてやってたんだよね。ただ研究することと批評することで、何が同じで何が違うかということは常に何となくは考えていますね。つまり、研究することにおいて批評的な観点というのは必要じゃないですか。人でもいいし作品でもいいし、単に好きなだけではできないよね。それはどのように評価してるかということと常に関わってくる。好きなものを常に研究してるわけではないし、好きなものは研究しない方がいいという話もある。ある程度距離を置いて見られるようなものしか研究の対象にはならないから、その距離の置き方という点において批評眼というのが関わってくる。
音楽の場合だと、文字による作品を対象にするわけではなく、基本的に音を相手にするのだから、そこで何か言葉を見つけなくてはならない。音楽に対する言葉というのは必ずしもひとつではなくて、いろんな対応の仕方があるんだよね。演奏会について書く場合でも、これがどういう演奏だったかというのは、必ずしも音楽そのものを言葉で表さなくてもいい。演奏会全体の感想が、音ひとつひとつのものじゃなくていいから。しかしその演奏会をどういうふうに書くか、どの視点でどの角度から言葉を見つけるか、なのよね。ときによっては作品それ自体の言葉かもしれないし、演奏家についての言葉かもしれないし、演奏会全体あるいはその演奏会の意義についての言葉かもしれない。どこに焦点を当てるかによって言葉が変わる。言葉は自由じゃないわけよね。つまりある程度語彙に限りがあっていうか。音楽はイメージの制限がないけど、言葉には語彙の制限があるから。でもある程度、それがどこに当てはまるかを考えなきゃいけなくて。それを見つけないと。やっぱり音楽を直接体験するのとはちょっと違うというのかな。距離を置くということだと思うんだよね。
聴いてるときに感じていることと言葉にしているときの感覚って必ずしもいつも同じではないと思っていて。言葉って見つけて書くわけだから、それによって逆に、遡及的に音楽の体験に反映されて僕はこういうふうに聴いてたんだというふうになっちゃうわけ。それが批評の世界だと思うわけね。こう聴きましたと言われてすんなり腑に落ちるような言葉が見つかれば、そう聴いてたんだなと言うことになる。だから聴いているときは何も考えないで聴いてるんだけど、あとから考えるとこういう風に聴いたかなっていうことに当てはまる言葉を探すっていうか、そういうことなんだよね。
何年か前の自分の仕事見てさ、本当にこう聴いてたのかなってわかんなくなるんだよね。やっぱ歳が変わるとさ、同じもの聴いてても感覚が変わってきちゃうっていうのは当然だし、過去のものを想起してみるときでも変わってきちゃうからさ。まあ最終的にはわかんないよね、音と言葉はどう対応していたのかっていうことは。でもそのときは多分そう聴いてる、と思ってそういう言葉を選んだわけだから。でもそういうときにやっぱり言葉が介在するっていうことはどっか突き放して自分じゃないものと向き合わなくちゃいけなくなるから、それがある意味必要だし面白いもんだとは思うんだよね。だから言葉にしてみることっていうのは大事だと思ってて。聴いたもの、観たもの、読んだものについて。
──いろいろな研究の手法とか経験というのは、言葉を見つけるいくつかの文脈を豊かにしていくことにつながるということですね。
いろんなものに対するいろんな感じ方というのが研究をすると目に触れるわけだよね。必ずしもそこに自分が共感するとは限らないけど、そういう体験をした人がいるって言うことは分かるし、そういう言葉の使い方、そういう事象と言語の絡み合いというのは一応経験することはできるからね。自分が今度は何か感覚したり経験したりするときに、こういう風に観たものをこういう風な言葉にした人もいたなっていう感覚もまたどっかに身についてるわけだよね。それは鵜呑みにする必要もないけどでも、そういう経験が増えるということはやっぱりモノと向き合うとき、特に言葉がない世界と向き合うときには重要になるかなとは思うね。経験ってそういうものじゃないの。結局、言葉にするしかないし、言葉との対応というのは、どっかで過去のものから学ぶと言うか、そこから感じたものを自分なりに咀嚼してくると言うか。そういうことじゃないかなと思うんですよね。それでもって自分とモノとの間に距離ができると思う。好きなら好きでいいけど、言葉はいらないとかなっちゃうとそれはまた別の世界で、ちょっと違うかな。やっぱり言葉は他者だからね。他者を交えて何かをやるということがすごく大事だと思いますね。
──さいごに、表象文化論ならではの、研究と現場との関係のあり方は、今後どんな形があるでしょうか。
難しいね、すごく。逆にどういうのがあったらいいと思う?たとえば、音楽に関してはさ、あんまりそういうの多くなかったよね。もう少し音楽の概念を広げて、パフォーミング・アーツとかまで含めたダンスとかそういう形で音楽を考えたり、そういう形で現場の人を講師に招いたりとか今まで以上になんか一緒にやってみたりとかあってもいいかなって思いますけどね。体を動かす実験は、少なくなってるんじゃないかな。前は野村萬斎さんが来てたときなんかもあったしね。ちょっとここのところ少なくなっちゃって。まあコロナで全然できないわけだけどさ。もう少しそういうのを、表象のなかで積極的に見つけていくことがいいのかな。逆に言うとそういう伝統が潰えつつあると言うか。機構ができたからそれと連携してやるというのもあるかもしれないしね。今は声出したりするというのはできないけど、ちょうど新国なんかとの繋がりはできたから、なんか一緒に仕事ができたらいいと思うんだけどね。これまでもゲネプロ一緒に観に行ったりとかそういうことはしてるんだけどさ。やっぱり制作の現場の人を呼んできて何かお話聞くというのは大事かもしれないですね。
──たとえば《プロメテオ》で、それだけ授業でやられていたというのは面白いですね。
体を動かしたりとかそういうことだけじゃなくて、本当に創作現場への携わり方って、いろいろやり方はあると思う。そういう意味では何らかの創作の現場で、たとえばテキスト訳したりとかあるいは演奏家と話し合ったりとか、そういうことができたらいいかもしれないな。どうやってそれこそものを作っているかっていうのを知るっていうのは大事かもしれないな。見学させてもらったりとか、実地で、教室を出て見に行ったりっていう場があるといいかもしれない。大学のなかに閉じこもって、あるいは大学に誰か人を呼ぶって言うだけじゃなくて、こっちから出かけて行って制作の現場を見るとか。オペラに関しては、それくらいはすぐできると思うんだけど、それをやってみてもいいかもしれないですね。
実際に《紫苑物語》作ってるときは、大野さんとか笈田さんとか呼んできて、駒場のなかでシンポジウムみたいなことやったけど。やっぱり教師にできるのは、教師の人脈みたいなものと学生さんや大学の講義内容を結びつけることで、そのチューターみたいなことはいくらでもできるから、これから活かしてみたいですね。あんまり大きな展望じゃないかもしれないんだけど。
──いえ、本日はお忙しいなか、濃密なお話をありがとうございました。
(2021年3月17日収録、聞き手:白井史人、原瑠璃彦 構成:白井史人)