シンポジウム 皮膚感覚と情動:メディア研究の最前線
日時:2023年11月11日(土) 16:00-18:20
【登壇者】
飯田麻結(東京大学)
平芳裕子(神戸大学)
渡邊恵太(明治大学)
水野勝仁(甲南女子大学)
【コメンテイター】高村峰生(関西学院大学)
【司会】難波阿丹(聖徳大学)
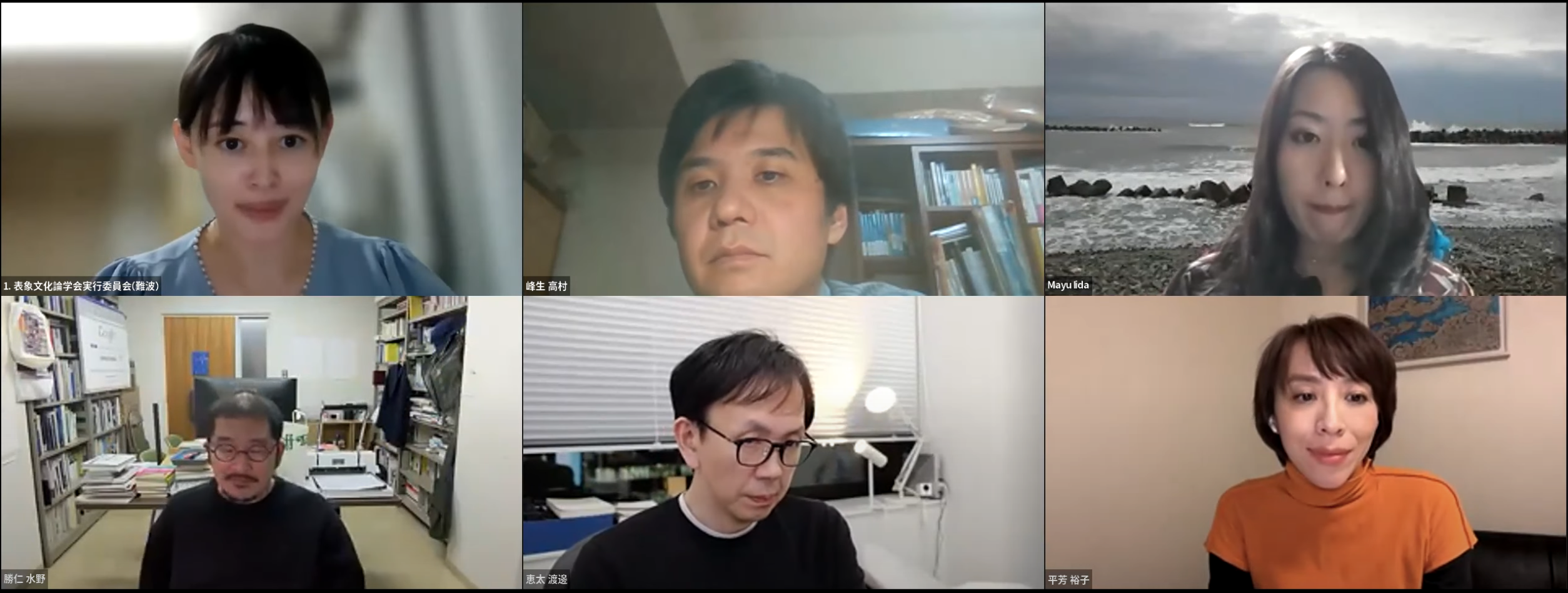
表象文化論学会では、実演や製作にかんする知見に富むパフォーマーやクリエイター(寄りの研究者)と、理論的なアプローチを生業とする研究者のコラボが珍しくないが、本シンポジウムもその系譜に連なるものとなっている。登壇者のうち渡邊・水野氏が前者、飯田・平芳氏および司会の難波氏とコメンテーターの高村氏は後者だろう。オンライン報告とは一見相性が悪そうな皮膚や触覚というテーマのもと、多様な背景をもつ登壇者たちがどのような化学反応を起こすかもまた、本セッションのみどころの一つだ。
詳細は概要欄に譲るが、本シンポジウムの全体像について難波氏が述べた点を簡単に補足しよう。まずスクリーンをめぐる環境が、1985年のWindows1.0を嚆矢とするデジタル・シフトによって、遠近法ベースの視覚モデルから積層平面ベースの皮膚感覚モデルへ移行したことが示された。次に伊藤亜紗やLynette Jonesを引きつつ、「ふれる」「さわる」「Tactile」「Haptic」といった用語を整理したうえで、触覚が情報伝達の速度で視覚にまさり、より感染的なコミュニケーションを可能にすることが強調される。それは次の飯田氏の議論へとつながっていくが、それを媒介するテクノロジーの意義への目配せは、本シンポジウムにおける平芳・渡邊・水野各氏の議論の重要性をあらためて示唆するものであった。
飯田氏の報告は、聖セバスティアヌスの殉教の像、Facebookの「大切だね」ボタン、スパイクタンパク質のデフォルメ化されたイメージという、印象的な3枚の画像の提示から始まった。氏は3つの画像に、1)身体へのウイルスの侵入の、「痛みと治癒」「快楽と免疫の自律性」への読み替え、2)「情動的なホモフィリー」概念 = ハートを抱く当該画像がユーザーに同質の感情をもつことを促し、曖昧さを特定の対象に還元・包摂するという文脈化の重要性、3)視覚と触覚の混乱 = 極小ウイルスの棘のイメージと喉の痛みの結びつけや、自分自身がウイルス化する感覚、周囲の空気(air/atmosphere)やそれに触発された実力行使が我々の身体を脅かすという曖昧な状況に対する恐怖を読み取る。これらを補助線にパンデミックから情動を再考するなかで、重要になるのが接触(contact/touch)の制限である。ジェンダーの観点では触覚は親密性やケアのイメージによって女性化されており、客観性や距離感を含意する男性的な視覚と対比される。隔離状況下では後者の既存の特権性がますます強化されることになるという指摘は、フェミニズム研究を専門とする報告者ならではの識見がなせる技だろう(パンデミックによって意識される、個としての生物と脆弱性をも共有する相互依存的な共同体のあいだの揺らぎというバトラーの引用もしかり)。同じく複数世界の形成に言及する今日の情動論(Affect Theory Reader 2, 2023)の論調が退潮していることを指摘したところで、議論は全体討議へと持ち越された。
続く平芳氏は、衣服が皮膚の拡張であるとするマクルーハンや胎盤の代わりに身体を覆うものだとするルッチオーニの言葉を示しつつ、じつはこうした言説とは逆に、西洋においては皮膚感覚と衣服の関係が遠かったことを指摘する。それは提示された19世紀の女性のドレスからも明らかで、(布地への個人的な嗜好を除けば)衣服はむしろ身体を拘束して造形するものであった。それは裁断と縫製の技法によるところが大きく、同時期の日本が布地を直線的に裁断する一方、西洋では身体を計測して曲線的な裁断がおこなわれていた。だがこの傾向は20世紀に入ると変化を見せはじめる。報告者はデザイナーたちの意識が「形としての身体」から「面としての皮膚の広がり」へと移ったことを、三つの観点から説明する。まず「皮膚に広がるファッション」の背景には、ジャージなどニッティング技術の普及があった。また近年の三宅一生作品やSOMARTAが展開するシームレスな衣服は、中世ヨーロッパにおいて描かれていた着脱可能な皮膚を彷彿とさせるが、これらはコンピュータによる型紙作りや3Dプリントに支えられている。次に「皮膚と感応するファッション」の例として、ユニクロのヒートテックやエアリズムが俎上に載せられる。後者のキャッチフレーズである「着ていることを忘れてしまうような」という表現は象徴的だ。最後に「快感を引き起こすファッション」では、ジェラートピケのような「スムーズィー」な着心地が強調される。こちらは「触りたくなる」ことがセールスポイントとなっており、ほかにも「ふわふわ」のペンケースや「もちもち」なぬいぐるみなど、ここ最近の触感重視の傾向は顕著だ。ただ氏はこれらの変化がパンデミック下の在宅勤務の増加などによって促進されたことは認めつつも、現象自体は以前から進行しており、インターネットの普及などデジタル化の影響によるところが大きいとする。その典型例としてあげられるのがメタバースやゲームにおけるアバターのスキンだ。私たちはバーチャル世界においても、本来必須ではない人間用の衣服をなぜか求めてしまう。その反面、それらと現実世界におけるリアルな皮膚感覚には乖離が生じている。ここでもまた、身体と衣服のあいだでの触発(アフェクト)し/される情動的なコミュニケーションが引き起こされているが、氏はそれこそが快楽の源泉となっていると述べた。
渡邊氏は国内のインタフェース研究の最前線にいるといっても過言ではないが、非会員のため今回はじめて氏の研究内容に触れる聴衆も多かったと思われる。それを意識してか、氏の報告は主著『融けるデザイン』をもとにこれまでの取り組みを振り返りつつ、インタフェースとインタラクションの具体例を多数交えた実演的なものだった。そこで鍵となるのは、報告中に何度も言及された「自己帰属感」である。インタフェースは技術の発展とともにより間接的になっており、現在は操作者と対象の間に複数の情報処理装置が介入する形態となっている。UIデザインの文脈では、それらを極力「透明」にすることが理想とされてきた。報告者は自己帰属感がそれを可能にするとし、その例としてダミーカーソル実験が紹介された。ダミーのカーソルの数が増えても操作者には自分のカーソルが自明な一方、同じ画面を見ている他の人間にはそれがわからない。これはまさにカーソルが自己の身体の延長として機能している事例と言える。ゼロ年代には操作時の「サクサク感」やスムースなアニメーション効果が重視されていたのに対し、iPhoneはそれらの代わりにこのような自己帰属的なUIを高度なレベルで実装することに成功した。そのタッチスクリーンは、操作主体と対象のあいだの多くの処理過程を文字通り透明化したのである(逆にフィードバックの遅延やランダムな作動は、UI自体の生命性を感じさせる)。ここから報告者は自己帰属感は五感を超越するものであり、むしろ本当のリアリティのために視覚や触覚は必須のものではないことを強調する。物理的な存在であるかデジタルなのかを問わず、操作主体の身体感覚との連続性こそが今後のUI設計に求められるとして報告は締め括られた。
最後に水野氏が、タッチスクリーンをつうじて「データに触れる」という錯覚について報告した。今回氏は渡邊氏の議論をベースにそれを拡張するかたちで話を進めたが、この錯覚という部分にかんしては「自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲い」という小鷹研理の表現を引用して、渡邊氏がいうところの自己帰属感がネガティヴに捉えられる文脈にも踏み込んでいる。錯覚であることが感じられないほど自然ならば、そもそも自己帰属感自体が快感として認識されないのではないか、カーソルはむしろ透明化されていないUIの一部だからこそ意義をもつのではないかという主張は、(直接的な言及こそないものの)Bolter&Gromalaのいう鏡としてのインタフェースを想起させる。氏もまた当学会の会員ではないが、今回の内容はこのように少なからず会員にも馴染みのある概念と接続されていた。自己の感覚と連動しながらも身体イメージは存在しないカーソルという中途半端な存在が、独特のしかたで操作主体と対象を媒介しているのに対し、次にあげられたラバーハンド錯覚は直接的な身体的現象である。こちらはゴム製の手という「情報としての身体」が、生身の手から視覚的な手(ラバーハンド)へ固有感覚をドリフトさせている。日常において不透明なカーソルとの相互作用を続けた結果、今日ではVisual Hapticsのようにカーソルの動きに対しても、我々はある種の錯覚を感じるようになっている。氏はこれを不随意な経験によって「自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲い」の外に出たためであるという。その感覚がコンピュータ側に帰属していった結果、ついにはラバーなしのインビジブルハンド錯覚さえ生じるようになる。こうなるともはや物理性は重要ではなく、主体とUIの連動性の上げ下げによってコンピュータ上でも同種の効果を再現できる。ここで氏は冒頭で触れた画面スワイプの事例に立ち戻り、渡邊氏も述べていた(サクサク感に優越する)「ヌルヌル動く」感じが、自己帰属感よりも「画面帰属感」によって生じているのではないかと述べる。そして操作主体の行為によって画面が変化するというよりも、画面の変化によって行為が起こるという逆転現象を例に、「半自己」としての皮膚が曖昧化するという「ミニマルセルフ」の概念を提示して議論が閉じられた。
四人の論者が展開した考察は、領域の幅だけでなく各自の専門においても基礎から最先端までのレンジをカバーする濃密なものであり、触覚と情動にかんする我々の認識を何段階も押し上げた二時間であった。しかし同時に、それらの全体像を瞬時に把握してそれぞれに的確なコメントを返すには、各分野についての非常に高度な知見が求められる。その意味で高村氏をコメンテーターに迎えられたのは幸運だった。氏のコメントは各報告に対する精緻な整理と質問部分にわかれるが、ここでは後者にフォーカスして振り返る。まず飯田氏に対しては、途中で時間切れとなっていたAffect Theory Reader 2の退潮傾向について補足説明を求めた。続いて平芳氏の報告について、かっこよさやかわいさの多様性という点について問題提起がされた。またユニクロの下着のように着ている感覚がないことと、渡邊・水野両氏がいうUIの透明性のあいだにある種の関連性が感じられるとともに、それが我々の身体自体の道具化という読みにもつながりうるという指摘もなされた。渡邊氏にかんしては、とくにファミコンの話に触れ、スーパーマリオなどゲームのリアリティとVRなどによる没入感のちがいについて話が広がった。ちなみにマリオとゲームにおける没入感については、Colin Creminが“Molecular Mario: The Becoming-Animal of Video Game Compositions”(2016)で興味深い分析を展開しているので、関心がある向きは一読されたい(ドゥルーズ=ガタリやマッスミを引用しつつ、まさに情動・身体性・デジタル化が俎上に載せられている)。最後に、水野氏が述べたカーソルとリアルな指型のポインタでは前者の方が自己帰属性が高いという点について、そこには我々が考える自己の延長のイメージに根本的な抽象性があるのではないかという興味深い分析がなされた。
この後各氏から応答があり、若干の残り時間でフロアにも質疑が開かれた。紙幅も残り少ないのでいくつか抽出するにとどめるが、飯田氏からはAffect Theory Reader(2010)と同2でイントロダクションのタイトルが“An Inventory of Shimmers”から“A Shimmer of Inventories”に逆転しており、情動論の目録を提示しようとした初巻に対し、続編ではその企図がすでに熱を失っているように読めるとの回答があった。またじつはそもそも転回と呼べるほどの新しさは見出せず、むしろその点を過度に強調することの危険性についての言及もあることが述べられた。平芳氏からは、SNS上のイメージに比して現実でのかっこよさの重要性が低下しており、むしろ見られなくていい場面が増えたことて気持ちがいいファッションが広まりつつあるという応答があった。フロアからはVisual Hapticsにみられるように、むしろ視覚が触覚を飲み込んでいるともいえるのではないのかという指摘があり、これについて司会の難波氏が両者の分離が難しいことにふれつつ、遠隔か近接かでのちがいもある視覚的な世界観ではとりこぼしてしまう経験があることを強調した。また高村氏からは、iPhoneのスクリーン操作のように触覚がメディアの側に取り込まれてしまい、むしろ経験の多様さが失われてしまっている反動で、ヨガやマッサージといった身体的な活動の人気が活性化しているのではという応答があった。
最後に、シンポジウムではあつかわれなかったが重要だと思われる点について、筆者の視点で二つ補足しておきたい。一つは全体を通してデジタルとアナログ(と便宜上しておく)の対比が強調されていたことである。少なくとも視覚にかんしては、両者を分離するのではなく、そのあいだでのグラデーションに目を向けるべきという立場もあり、触覚に対しても本当にデジタルでしかできないことがあるのか、あるいは完全な代替が可能なのかどうかはまだ検討の余地が残っていると思われる。もう一つは頻出したオノマトペだ。「もちもち」「ふわふわ」「サクサク」「ヌルヌル」など、数値化はおろか日本語に通暁するものにしか伝わらないであろう表現に頼らざるをえないというのは、触覚がいかに主観的でドメスティックな経験なのかを物語っている。他方で飯田氏が指摘したように、反ワクなどの陰謀論者を筆頭にファクトよりもネットをつうじたある種のエコーチェンバーによって強化された「知」は、数値化された「エビデンス」を過度に誇示している。パンデミックがほぼ過去のものとなった今、個人的な経験としての触覚の多様性の回帰は、こうした情動的感染を沈静化するワクチンになりうるのではないだろうか。また最後のフロアからの質問や高村氏のコメントと同様のことを、筆者も以前別の場所で難波氏の報告に対して問うたことがあり、この問題はある程度普遍性をもっていると思われる。今後解決すべき課題として共有しておきたい。冒頭で述べた通り、多彩な研究者が「接触」によって化学反応し、当初の聴衆の期待を上回る地平を見せてくれた。今後もこうした異分野間でのコラボレーションの継続と、展開された議論の深化に期待したい。
本シンポジウムは、皮膚(触覚)のテクノロジーを、新しくとらえなおすことを目的としている。従来の超越論的美学は、視覚と聴覚を特権的な感覚として重視してきた。ジョナサン・クレーリーが『観察者の系譜』で論じたように、「近代的主体」は視覚の受肉というかたちで想定される。そして、主客を分離し、対象を記述する距離のテクノロジーである視覚によって、「触覚」は近位感覚として把握されてきた。近位感覚に重きをおく非-二元論的哲学やミメーシス論は、触覚的近接性および準-近接性に特徴づけられる視覚的「触覚」を皮膚感覚が本来ない場所に想像し、イメージと対象とが似通っているという視覚的な相似性や対象との心理的距離の近さを「触覚的」と読みかえてきた経緯がある。
しかしながら、2000年代以降、このように距離の近さという視覚的な観点から解釈されてきた「触覚」ではなく、視覚とは異なる情報伝達のシステムを備えた皮膚の技術が到来している。テレフォニーの技術発展に動機づけられ、コミュニケーションの障害になりうる距離と時間を可能な限り克服し、思考や感情を無媒介的に他者と共有するという主客融合的な皮膚感覚がさまざまなメディア、デバイス上で重要な知覚となりつつある。
そして、これは「触発(アフェクト)し触発(アフェクト)される」という、「情動」的なコミュニケーションが優勢になっていることを意味する。「情動」は、主体と客体、そして心身二元論に拘束された視覚的な秩序をのりこえて、非-二元論的な語り、皮膚感覚的な語りの可能性を開いている。また、「情動」の観点から、主体から分離した対象を科学的に記述するというふるまいでは理解しがたい、今日的なソーシャルメディアプラットフォーム上の群衆行動を理解することも期待されている。
2007年4月にアップル社が発表したiPhoneは、キーボードの代替としてのタッチスクリーンを備え、ユーザーは地続きの「世界の皮膚(World Skin)」(Mark B. N. Hansen, 2006)から他のユーザーに過剰に接続される、即時応答のインターネット空間へと開かれた。更に2017年に登場したiPhone Xのフルイッドインターフェイスは、タッチ操作を前提に、ポインタがスクリーン上の物体(オブジェクト)の形に合わせて変形し、パララックス(視差効果)によって、平面においてもバーチャルな皮膚感覚の表現が洗練されつつある。
いまや運動の力と質が、圧覚、痛覚、温覚、冷覚等の複合的な体性感覚においてインタラクティブに流通する皮膚の平面こそが、情報を瞬時に、しかも大規模に感染させうる今日的なメディアプラットフォームや、デバイスのスクリーンのモデルと考えられるだろう。
本シンポジウムは、多彩な学問領域から第一線の研究者をお呼びし、皮膚という沈黙の器官がもたらす複合的な感覚、そして感染していく「情動」について、さまざまに触知してみたい。