映画と黙示録
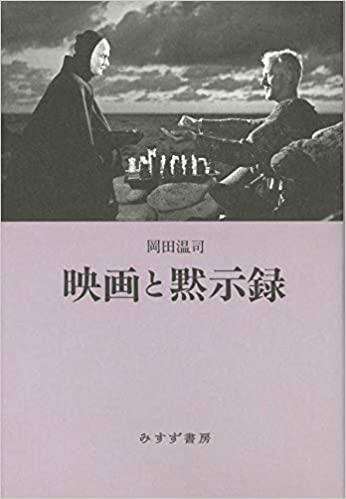
新型ウイルスが世界中に蔓延し、さまざまなニュースを前に、「まるで映画のような」とふと感じた人々は少なくはないだろう。例えば、映画「コンテイジョン」が10年ほども前に制作された作品にも関わらず、「まさに予言の書」のようだと話題になったことは記憶に新しい。未知の新型ウイルスが世界中へと広まっていく様や感染者増大を示す数々のグラフやイメージの氾濫、デマや買いだめによるパニック、医療関係者への視線など、私たちをこの春翻弄したその多くがすでに何年も前に想像されていたことに対して驚いた、というわけだ。
しかしながら、さながら「世界の終わり」のイメージを細かに想像し、描写するという行為は、聖書の黙示録を筆頭に何千年も前より、すでに少なからぬ人々の想像力の糧となってきた、ということを、このような状況へと我々が陥る少し前に出版された本著は思い起こさせてくれるだろう。新型ウイルスに限らず、世界を強制終了させてしまうような厄災が訪れるのではないかという想像は、本著が示す通り、映画のなかにおいてもう数十年にわたり様々な形で変奏されてきた。むしろ映画が登場して以来、そのパニック映像によって導かれるある種のカタルシスは、人々が求めて止まずにきたことである。けれども、この状況を経験してしまった私たちは、もはやカタルシスを感じることはできず、また「今後、これ以上何を語ることができようか」(そのような思いは、著者の数多くの書籍を前にした少なからずの読者がこれまで抱いたことがあろう)と、立ちすくむだろう。
だが本著において瞠目すべきは、あらゆる年代の「黙示録」的な作品を縦横無尽に語り尽くした筆者による主張である。本書の第四章「9・11 ビフォアー/アフター」において筆者は、9・11の以前と以後で映画は大きく変わっただろうか、という問いに対し、「大きく変わらない」と断じる。すでにテロ以前にも、ツインタワーはテロリストたちの標的となり、またはカタストロフの悲惨さを物語る手段として使用されてきた。さらには「聖戦」や「正義」という名は称揚され、内なる敵を探し出すという姿勢が取られてきた。その頻度や濃度に多少の差はあれ、「デジャヴ」感は否めない。もし、変わったものがあるとすれば、「ポスト黙示録的なディストピアの雰囲気」がますます色濃く前景化し、「キリスト教原理主義的な宗教色」が漂うものが増えてくる点だとしている (147-148)。
現実の方はどうだろうか。医学的な根拠はもちろんあるが、不特定多数の人間が出入りする店の前に置かれた消毒用のアルコールやマスク未着用のものを排除するような「決まりごと」は、医学的な処方にしたがっているというよりは、形骸化し、むしろお清めやお祓いのように、いっときの安心を得るための呪術的な効果の方へと傾倒していると言えないだろうか。科学が発展し、医療が驚くべき進歩をみせた現代においても、未知なるものを前にした我々がやはり宗教的なものへと立ち戻り、行動的規範と信仰が混合したものであれ、安寧を感じざるを得ないということへと気づいた現在において、「黙示録」を紐解きながらそのイメージの変奏を分析する本著のアクチュアリティがいやましに高まるのである。
(福田安佐子)