「世界」文学論序説 日本近現代の文学的変容
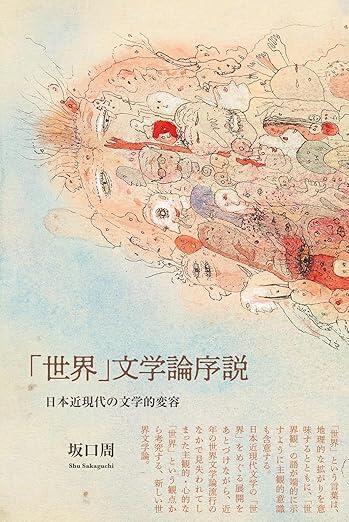
アメリカの大学における比較文学科には「理論」と「世界文学」の二つの顔があり、大学によって力点の違いがある。今世紀に入り「イエール学派」や「デリダ派」といった呼称とも結びついた「理論」派はかつての勢いを失いつつあるなか、それと入れ替わるかのように世界文学論は活況を呈してきた。2003年のデイヴィッド・ダムロッシュ『世界文学とは何か?』(国書刊行会、2011年)を皮切りに、2006年にはエミリー・アプターの『翻訳地帯──新しい人文学の批評パラダイムにむけて』(慶応義塾大学出版、2018年)、2013年にはフランコ・モレッティ『遠読──<世界文学システム>への挑戦』(みすず書房、2016年)、2015年にはレベッカ・ウォルコウィッツ『生まれつき翻訳──世界文学時代の現代小説』(松籟社、2021年)といった国民文学を乗り越える世界文学研究・翻訳研究が現れたのである。
本年2025年には──本稿執筆時の4月の時点においてすでに──、日本を起点とする世界文学についての重要な三つの著作が刊行されている。沼野充義との対談を含むダムロッシュ『世界文学講義』(東京大学出版)は、2017年の東京大学における連続講義を単行本化したもので、日本文学を直接的な影響関係のない世界文学との比較の場に開いている。福島亮大『世界文学のアーキテクチャ』(Planets)はゲーテの世界文学論を起点に、西洋、中国、日本の膨大な量の小説を「人類の思考システムの歴史」として横断的に考察した浩瀚な書物である。そして、坂口周による本書は、日本近現代文学を考察対象としながら、日本と世界の接触面における「世界」の両義性を、語りや視点の問題とも結びつけながら論じている。
「世界」の両義性とは何か。一方では客観的、物理的に存在する「世界」がある。これは地球規模の広がりのこととは限らず、国家や国語が「世界」として意識されることもある。明治、大正時代の作家たちが「世界」と出会い、それを表現のうちに取り込んでいった経緯については今更説明する必要はないだろう。他方で、文学作品や作家が、それぞれ独自に「世界」を持っていると言うこともできる。「世界観」などと言われるような、主観的で交換不可能な、内的で独自な外部世界の見え方である。坂口の著作は、一見「世界文学」とは無関係に見える、ミクロで特殊な複数の「世界」を「世界文学」という国民文学を超えた単一性とつなげることによって、三人称と一人称の語りなど、文学の装置の二重性、ひいては自己意識の二重性や、内と外の「自然」の二重性といった、近現代文学が課題として取り組んできた主題系を構造的かつ歴史的に考察することを可能にしている。このような試みは、本書でも言及されている柄谷行人の『日本近代文学の起源』における風景論を応用、発展させつつ、21世紀の世界文学の流れの中に再文脈化させるものだと評価することもできる。この点で注目すべきは、本書でもっとも長い第四章「感情移入の機制」である。坂口はここで主体と客体の距離を保った「同感(sympathy)」とは区別される客体への没入をともなった「感情移入(empathy)」を議論の枠組みとしつつ、小説における「描写」や「距離」の問題に切り込んでいる。
本書で取り上げられる作家は、志賀直哉、正岡子規、夏目漱石、森鷗外、島村抱月、国木田独歩、大江健三郎、村上春樹、小川洋子など多岐にわたり、これらの作家についての各論をここで一つ一つ紹介することはできないが、議論はテクストの豊富な引用を含み、しなやかで切れ味鋭い。個人的には、村上春樹における象の消滅をサルトル的な想像力の消滅と捉えて「象」と「像」を重ね合わせた読解に、視界が晴れ渡るような感動を覚えた。終章では情報記号論を参照しつつ、ビデオゲームをプレイする人間の身体と、それによってコントロールされるゲーム内の主体の二重性を<経験的―計算的二重体>と呼び、「それは本を読む行為とどれほど異なる体験なのか」と問いかけている。このように本書は分量的には大正期の作家たちに多くのページを割きながらも、その問いを現代から未来のフィクションをめぐる議論一般へと開いている。
留保の余地なく称賛できる、「即座の古典」といっていい一冊である。時に議論は深く複雑な事象に分け入っていくが、具体例と一般的な考察の往還が見事になされており、一歩ずつ足場を確認しながら読み進めることができる。が、ときに、あっと驚くような跳躍・発展とその説得力の強さに驚かされもする。本書が広い層の読者に刺激を与えることを期待したい。
(髙村峰生)