松本俊夫著作集成 Ⅱ 一九六六─一九七一
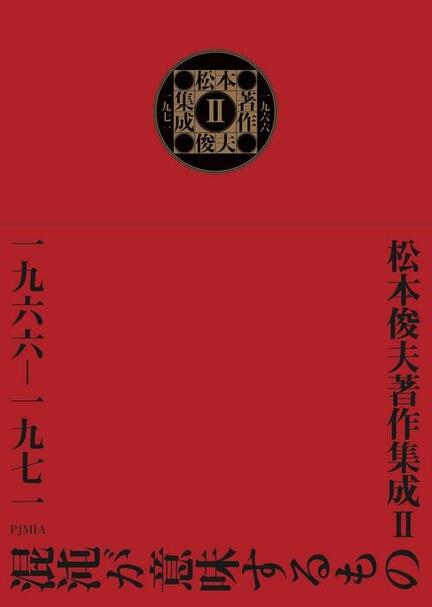
本書は、映画監督・映像作家として『薔薇の葬列』(1969)を始めとする劇映画や数々の実験映画・記録映画を制作すると同時に、戦後日本における映画言説の前衛的な傾向を理論的に先導した、松本俊夫の著作集成シリーズ(全四巻)の第二巻である。第一巻(森話社、2016)が対象とした1953~1965年までの期間に続けて、本書は1966~1971年までの期間に書かれた松本のテクストを網羅的に収録している。
松本は生前に六冊の単行本を出版しており、なかでも第一著作集『映像の発見』(1964)は、執筆された時代のコンテクスト——1950年代の左翼記録映画運動における共産党の文化政策との対立——を超えて、普遍的な映像論として幅広い読者を得ている。その一方で、これらの単行本は松本が執筆した膨大なテクストの一部に過ぎず、その執筆活動の全体像は長らく明らかになっていなかった。埋もれたテクストを発掘し、執筆された時代のコンテクストを踏まえ、より包括的かつ精密に松本のテクストを読み解くことが必要とされていた。この著作集成シリーズは、松本の執筆活動を包括的に明らかにするという目的のもと、初出を底本として編年体で収録することを編集の基本方針としており、本書では第二著作集『表現の世界』(1967)、第三著作集『映画の変革』(1972)、第四著作集『幻視の美学』(1976)に収録されたテクスト52本に、単行本未収録のテクスト71本を加えている。
1960年代から1970年初頭にかけての社会的混乱の中で、映画はさまざまな形で変革の予兆をスクリーンに映し出していた。この時期の松本は、共産党の政治主義に対立する映画作家の運動組織として発足した「映像芸術の会」の破綻や、ラディカルな運動として展開した「鈴木清順問題共闘会議」をめぐって大島渚との激しい論争に直面することになる。このような映画運動に対する挫折や幻滅を経験するなかで、松本はアメリカを中心としたアンダーグラウンド映画(実験映画)やエクスパンデッドシネマ、東欧や第三世界の新しい劇映画、ジガ・ヴェルトフ集団の政治映画などに、不可視的な変革の可能性を見出してゆく。そして松本は、これらの動向に呼応するようにして粟津潔、飯村隆彦、武満徹、勅使河原宏、中原祐介、山田宏一らとともに、越境的な映画雑誌である「季刊フィルム」(1968~1972)を刊行してゆく。本書は、松本による映画批評や、松本が深く関わった映画運動を通して、戦後日本における映画および芸術の激動期を照らし出すものである。1970年代の蓮實重彦の登場による映画言説の転換以前において、何が時代の問題とされていたのか——そのことを理解するうえでも本書は助けになるだろう。
なお、著作集成シリーズとしては、1972~1979年までの期間を取り上げる第三巻、1980年以降の期間を取り上げる第四巻の刊行が予定されている。
(阪本裕文)