パネル3 ドキュメンタリーにおける主観性 ──もう一つの視座と系譜学をめぐって
日時:2020年8月10日(月)14:00 - 16:30
・エッセイ映画作家としてのヨリス・イヴェンス──1950年代叙情的エッセイ映画時代の作品にみられる主観性/東志保(大阪大学)
・高嶺剛のドキュメンタリー映画における「復帰」へのいらだち/松田潤(一橋大学)
・水俣ドキュメンタリーの働きかけ──「記録」によるマイナーシネマ的な主体感形成/洞ヶ瀨真人(中部大学)
・ "The Technologies of the Self: Rethinking Japan’s ‘Self Documentary’ since the 2000s”/馬然(名古屋大学)
【司会】洞ヶ瀨真人(中部大学)
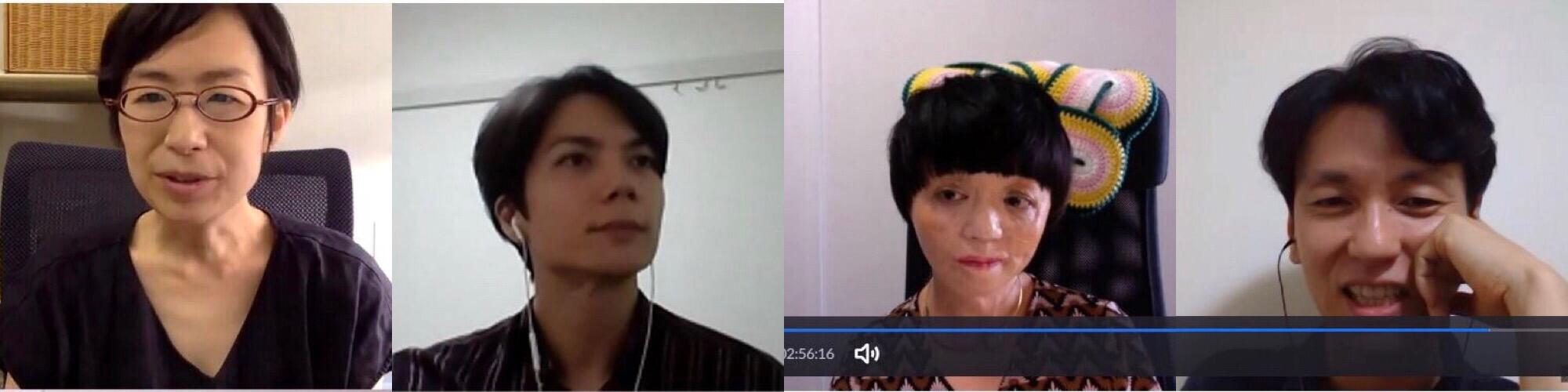
本パネルでは、各発表者がおもに戦後のドキュメンタリー映画における「主観性」をそれぞれの関心にそって論じた。作家や地域、時代など主題は多岐にわたり、非常に充実したパネルであったと言える。
最初の発表者である東氏は、近年研究が進んでいるエッセイ映画という観点からヨリス・イヴェンスの1950〜60年代の作品群を考察した。ハンス・リヒターによって提唱されたエッセイ映画と呼ばれるジャンルは、フィクションとドキュメンタリーの境界を横断し、アーカイブ映像の使用や作家の主観性の反映などの反省的な性質をその特徴とする。ティモシー・コリガンによれば、これらの映画は1920〜30年代のドキュメンタリーと前衛映画が交差した作品に起源を持ち、それらがバザンやアストリュックなどの戦後のフランス映画批評によって再び見出され、戦後の実験映画に繋がるといった歴史的経緯をもつ。
このようなエッセイ映画の文脈や50年代のフランスの短編映画制作状況をふまえ、東氏はおもに都市を扱った『セーヌの詩』(1957)、『ヴァルパライソにて…』(1963)、『ロッテルダムユーロポート』(1966)が、イヴェンスの初期作品群のモチーフを継承しながらも、自己言及性やヴォイス・オーヴァーのコメンタリーによって作家の主観性をもち、それまでのスタイルを刷新していることを明らかにした。
例えばそれは『セーヌの詩』に登場する画家やカメラマン、『ヴァルパライソにて…』における自己言及的かつ詩的なコメンタリー、『ロッテルダム・ユーロポート』で提示されるアーカイヴ映像を利用した都市の歴史への参照などに見てとれる。
こうした具体的なテクスト分析を行ったうえで、東氏はそこに20年代の作品においてカメラ=私として一体化されたものの自省性を見出し、単なる主観性ではなく、その自己反省性が表現されていると結論づけた。
続いての発表者の松田氏は、沖縄出身のドキュメンタリー映画作家である高嶺剛の初期作品の分析を通じて、作家の主観性とそこから見出される本土復帰「批判」の意義を明らかにした。ここでの主観性とは、マイケル・レノフによって論じられた「新しい主観性」と関わっている。レノフの議論に従えば、おもに1980年代以降に制作されたドキュメンタリー映画における主観性とは、それ以前の主観性とは違い、私的なものを公的なものに重ね合わせることで生まれるものであるものであり、その背景には社会運動による政治から「アイデンティティ」による政治へと移り変わった文化的風潮の変化がある。松田氏はこのような「新しい主観性」を『オキナワン ドリームショー』(1974)や『オキナワン チルダイ』(1978)における「復帰へのいらだち」のなかに見出した。
施政権返還前後を舞台に撮影された『オキナワン ドリームショー』では、すべての風景がスローモーションという独特の時間性のなかに置かれ、基地や沖縄の風俗を強調したり、エキゾチックな眼差しを注いだりすることなく、「等価」に存在していることが指摘され、それは日常の中に「風景の死臭」を嗅ぎ取るという高嶺の主観性に立脚された方法であることが論じられた。
また、『オキナワン チルダイ』では「チルダイ」という時間をキーワードにモンタージュされたさまざまな映像---地面でだるそうに寝ている犬、怠慢な動作で草刈りをする農夫や神隠しにあって森をふらふらとさまよう少年---とリンクしない音声が注目された。それは意味に還元することのできない音素にまで分化された吃音やラジオニュースの語りである。これら音声は沖縄語の残骸や占領の痕跡を残しながら、映像と統合されることなくそれ自体で自律的に存在することで、音とイメージの間に間隙を生み出し、時間イメージを形成することになる。
このように松田氏は、高嶺の初期作品を考察することで、「復帰へのいらだち」という作家の主観性に基づいた方法を見出し、そこで視聴できる沖縄の死者や「難民」化していく人々の声を論じた。
三番目の発表者の洞ヶ瀬氏からは、まずはじめに水俣病を論じるうえでの問題点が指摘された。水俣病のような公害被害を論じる際、多くの場合、加害者/被害者の対立図式によって語られるが、実際には被害者が声をあげればあげるほど企業から恩恵を受けてそこに暮らす市民から反発されることになる。対立図式を強化するような被害の告発や代弁といった方法を避け、加害者/被害物にあてはまらない「市民」に対して、どのように問題を訴えかけていくか。このような問いを解決するためのキーワードとして今回の発表ではマイナーシネマの概念が援用された。
マイナーシネマとは、ドゥルーズ・ガタリのマイナー性に依拠した概念である。ドゥルーズ・ガタリによればマイノリティとは、数の大小によって決まるものでなく、公理の有無で定義される。そのため、マイノリティは数値化の支配から逃れ、公理に反する力を持っている。この議論を発展させたギャリー・ジェノスコは、マイナー性を映画のなかに見出し、意味や物語に還元されずに、マイノリティーのマイナー性を保持したイメージや音声をマイナーシネマとして論じた。このような映画は、マイノリティの主観性を物語化することなく描写し、彼/彼女らのマイナー性を観客の思考や感覚に訴えかけることができる。
洞ヶ瀬氏は、こうした理論的整理を行った後で、『111---奇病15年のいま』、『水俣—患者さんとその世界』(1971)、『阿賀に生きる』(1992)をとりあげて、患者の呼吸音や企業の重役につめよる被害者の叫び、住民の喪失感を伴う身体を緻密に分析し、意味や理性ではなく、観客の感覚に訴えかけるマイナーシネマの力を提示した。
最後の発表者の馬然氏は、2000年代以降の日本のドキュメンタリー映画を「セルドキュ」(セルフ・ドキュメンタリーの略称)という視点から論じた。セルフ・ドキュメンタリーとは1970年代に原一男や鈴木志郎康によって先駆的に試みられた、集団制作に依拠しない個人的な美学と製作モードを持った映画のことである(例えば『極私的エロス 恋歌1974』)。マーク・ノーネスによれば、このような映画は、それ以前のドキュメンタリー映画とは異なり、撮影する主体が対象に「共感」するのではなく、撮影主体と対象が一体化するといった特徴を持っている。90年代には、そのことがより先鋭化され、個人とパブリックとの間に断絶が起こり「政治なき政治」の時代を迎えた。
このようなコンテクストの中で、馬氏は近年の日本とアジアのドキュメンタリーを映画理論/批評に限定することなく、社会・政治・メディア環境などのより広く複雑なネットワークの中で生成される「私」の表象として捉えることを提唱した。
また、馬氏は「セルドキュ」を分析する理論的な概念としてミシェル・フーコーの「自己のテクノロジー」を紹介し、この概念を使用して、言説的な表象、身体-情動、およびメディアインフラの重なり合いのなかで現れる「私」の集合体を把握するというビジョンを提示した。今回の発表では、時間の都合上、具体的なテクスト分析が行われることはなかったが、近年の重要な「セルドキュ」作品として小田香の『ノイズが言うには』(2010)や松江哲郎の『Identity』(2004)といった作品の名前があげられていたことを付言しておく。
最後の質疑応答でも問われたが、今回のパネルでは、発表者のあいだで「主観性」という言葉の扱われ方に違いがあったように思われる。しかし、それを否定的に(あるいは程度の問題として)捉える必要はないだろう。今回、各発表者が取り上げた主観性は、それぞれの時代や地域に形成されたヴァナキュラーな主観性であり、パネル全体は、そのマッピング作業とも言える非常に意欲的かつ重要なものであった。
パネル概要
映画研究者マイケル・レノフが指摘するように、「主観性に対する抑圧は根強く、思想的に追い立てられてきたのがドキュメンタリー史での実状だった―それでも主観性がドキュメンタリーに属するものから消えてしまったということは決してなかった」。このパネルでは、現代のドキュメンタリー映画における主観性の問題を改めて議論の俎上にあげることを主目的とし、グローバル文脈での歴史系譜と地政学を共に注視しながら、映画研究、映像研究、文化研究が重なり合う場に浮上する新たな理論的視座に焦点をあてたい。
東は、オランダの映画作家ヨリス・イヴェンスを中心に、1950年代から60年代のエッセイ的な映像制作を論じる。イヴェンスの主観的な映像制作をヨーロッパ前衛映画の歴史に接続するその観点は新しい試みである。松田は、1972年の「沖縄返還」の文脈下にある高嶺剛の二本の初期作品を取り上げる。時間性の観点から高嶺の風景への取り組みを捉える松田の議論は注目に値するだろう。水俣病のドキュメンタリーを考察する洞ヶ瀨の議論は、被害者側の主観性を表現しようとする試みに着目する。主観の問題を被写体となる当事者や環境、観客を横断する視座で捉える観点が注目点である。馬は2000年以降の日本の「セルフドキュメンタリー」に着目する。新世紀に向けた技術的・社会的な「自己」の組み込みに着目するその議論では、松江哲明や小田香作品における身体と性の問題が焦点となる。
エッセイ映画作家としてのヨリス・イヴェンス──1950年代叙情的エッセイ映画時代の作品にみられる主観性/東志保(大阪大学)
エッセイ映画という用語は、1920~30年代のドキュメンタリー映画の興隆を受け、ハンス・リヒターによって提唱されたと言われている。その後、この用語は、アレクサンドル・アストリュックやアンドレ・バザンによって、戦後の新しい映画の動向を指し示すものとして再び取り上げられるようになった。このような、エッセイ映画の歴史的な文脈は、1920年代の前衛映画運動のなかからドキュメンタリー映画制作を開始し、その後も戦後の映画の新しい表現を貪欲に吸収しながら作品を発表し続けたヨリス・イヴェンスの軌跡とも重なるものである。しかし、イヴェンス研究の第一人者、トーマス・ウォーが指摘するように、イヴェンスはエッセイ映画の作家として十分に認識されていない。たとえば、時代的にエッセイ映画との強い関連性がみられるはずの1950~60年代のイヴェンスの作品がエッセイ映画の例として扱われることはほとんどなかった。そこで、本発表では、ウォーが「叙情的エッセイ映画」と呼ぶ、1950~60年代のイヴェンスのいくつかの作品を取り上げ、エッセイ映画作家としてのイヴェンスという一面に光を当ててみたい。そして、初期の前衛映画の時代からイヴェンスが重視していた主観性が、いかにエッセイ映画の語りによってアップデートされたのか、検討する。
高嶺剛のドキュメンタリー映画における「復帰」へのいらだち/松田潤(一橋大学)
本発表では、施政権返還前後の沖縄を舞台に撮影された高嶺剛の初期ドキュメンタリー作品を対象にする。1960年代末期、「核抜き・本土並み」を目指した祖国復帰運動の要求を決定的に裏切る形で沖縄の施政権返還が実現されることが明らかになっていた。高嶺は『オキナワンドリームショー』(1974年)で「日本復帰」前後の沖縄の「風景の死臭」を嗅ぎ取り、風景の特権化を排してすべての風景をスローモーションの中で「等価性」のもとに配置し直す作業を行なった後、次作の『オキナワン チルダイ』(1979年)では、「日本復帰」に象徴される「時計の時間とオキナワンタイムのせめぎ合いを風刺をこめて」描き出している。両作に通底しているのは、高嶺の「復帰へのいらだち」である。それは「復帰」という物語へ飲み込まれていく中で風景に意味が与えられ、「沖縄的なもの」が称揚されたり、逆に原日本のイメージが発見されたりするような、風景の序列化や特権化へのいらだちであり、またチルダイという独特の時間感覚が敷き均されてしまうことへの抵抗感でもある。本発表は、高嶺の初期作品に風景の特権化や時間の均質化に抗う契機を探求し、「復帰」批判を行ったことの意義を分析する。その際、ジョナス・メカス作品の影響を確認した上で、映画における非物語的なもの、「難民」化していく人々、夥しく登場する動物や物、説明を排した風景などに着目し、「日本復帰」という主体化=従属化から逃れゆく非主体的なものたちの共同性について考察する。
水俣ドキュメンタリーの働きかけ──「記録」によるマイナーシネマ的な主体感形成/洞ヶ瀨真人(中部大学)
本発表では、「水俣病」とされたメチル水銀中毒公害についてのドキュメンタリーにみられる、被害者の苦境を伝える映像技法について議論する。
水俣病が露呈させた問題は、毒物を流した加害企業と被害を受けた周辺住民・自然環境の表面的な関係性以上に根深い。被害者補償の訴えは、企業に支えられる労働者市民には営利活動を妨げ生活を脅かすものに見えるため、大多数を占めるその市民と少数の被害者間の諍いも生み、対立関係を錯綜させた(高峯2017)。また、その訴えは日本経済の根幹企業の障害ともなるため、高度成長期の世論の価値観からも乖離した(小林2015)。こうした公害病を囲む厳しい環境から「不可避的に促された語り」(Marran 2017)となるためか、被害者の苦境を訴えるドキュメンタリーの多くには、単なる告発ではなく、G・ジェノスコ(2018)がガタリ思想のなかで着目した、映像などの非シニフィアン記号の効果によって精神病を患う少数者の感覚を一般民衆の主体感にも生じさせる「マイナーシネマ」的描写が先駆的に見られる。
発表では次の作品の試みに着目し、それが「民衆のなかにマイナー主義的な生成」を促す力といかに重なるか検討したい。胎児性患者の鼓動が語りかける『111』(1969)、株主総会の騒乱を音声で増幅した『水俣・患者さんとその世界』(1971)、被害者の暮らしの美しさを描いた『阿賀に生きる』(1991)などを参照する予定である。
The Technologies of the Self: Rethinking Japan’s ‘Self Documentary’ since the 2000s/馬然(名古屋大学)
When Japanese postwar documentary was seeing its beginning of an end for a golden time in the 1970s, the first-person ‘private film’ (puraibeto firumu) burst onto the scene with its new working mode, aesthetics, and politics—Hara Kazuo and Suzuki Shirōyasu stood out as two of its most important pioneers (Nornes). This project highlights Japan’s vernacular mode of ‘self documentary’ (serufu dokyumentari, short as serudokyu) since the 2000s and considers it one contemporary development of the ‘private film’. However the personal and the private may characterise documentary-making in Japan nowadays, many ‘serudokyu’ are considered solipsistic and socially-naïve, which may partially explain why many of these films are not attracting much academic or critical attention home and abroad. While contemporary ‘serudokyu’ has been thinly adorned with theories of identity politics and rarely engaged with practices of empowerment, I suggest we could extend our critical horizon and grasp the ‘serudokyu’ by looking at the technosocial assembling of the ‘self’ into the new millennium, which arguably intersects with the multifarious articulations of the ‘self’ in Japanese popular culture within the digitalized, transmedia environment. Specifically, foregrounding works by filmmakers such as Matsue Tetsuaki and Oda Kaori, this study focuses on the issues of body and sexuality, and is particularly interested in interrogating the politics and aesthetics apropos the production and circulation of erotic and queer feelings in the everyday.