| トピックス | 3 |
|---|
シンポジウム「社会制度としてのロシア文学――作者・読者と読書の社会史」
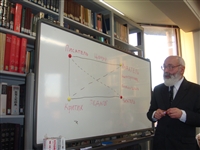
2010年12月17日、東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学研究室にて、ロシア語によるシンポジウム「社会制度としてのロシア文学――作者・読者と読書の社会史――」が開催された。現代ロシアにおける「文学の社会学」の代表的研究者アブラム・レイトブラト氏の来日を記念したもので、早稲田大学・大阪大学・北海道大学における氏の講演ツアーを締めくくるものであった。プログラムは以下のとおり。
- はじめに「文学は私たちがいかに読むかである――制度とテキストの間で」沼野充義(東京大)
- 基調講演「社会制度としてのロシア文学――19~20世紀初頭のロシア文学に即して」アブラム・レイトブラト(ロシア国立芸術図書館)
- 研究報告1「ペテルブルグの生理学と文学」大野斉子(青山学院女子短大)
- 研究報告2「19世紀後半の社会システムにおけるロシアの絵入り雑誌」巽由樹子(日本学術振興会)
- 研究報告3「20世紀初頭ロシアの探偵・冒険文学における日本のイメージ」久野康彦(放送大)
- 研究報告4「ソヴィエト批評における「読者」(『静かなドン』結末をめぐる論争)」平松潤奈(東京大)
ほかの国々の文学と同じくロシア文学に関しても、その社会的受容・流通の研究は、ここ数十年で大きく進展した。英語圏では、ウィリアム・トッドの『プーシキン時代におけるフィクションとイデオロギー』(1986)や、ジェフリー・ブルックスの『ロシアが読むことを学んだとき』(1985)が嚆矢となり、日本でも関心が深められてきたことは、若手~中堅研究者による本シンポジウムの各報告タイトルにみてとれよう。レイトブラト氏は、19世紀からロシア革命までの文学を専門にし、その流通や人気に関する計量的調査と、著作権や検閲などの制度研究をとくに多く手がけている。その著書『ボヴァーからバリモントまで』(1991)『プーシキンはいかにして天才となったか』(2001)は、革命前のロシア文学を学ぶ者にとって基本文献といってよい。
今回、大野氏は1840年代の「生理学もの」などの挿絵、巽氏は19世紀後半における絵入り雑誌、久野氏は20世紀初頭に廉価で大量に流通した探偵小説と、いずれも「純文学」とは異なる大衆的読み物を対象に、社会的メディアとしての文学を論じた。個別の作家論が頭打ちになるなか、このようなメディア論・制度論的アプローチは、近年の日本における革命前のロシア文学に関する研究で、主要な潮流をなしている。平松氏が扱ったソヴィエトの公式文学になると、われわれの考える「芸術性」に叶う作品がほとんど存在しないため、こうしたアプローチはいっそう必然的である。
ただし、ロシアにおける「文学の社会学」には、旧西側諸国とは異なる事情もある。レイトブラト氏の今回の来日で筆者が最も印象づけられたのは、そうした歴史的背景であった。シンポジウムの基調講演でレイトブラト氏は、「社会制度としての文学」を、作者・出版社・批評家・読者を頂点とする四角形として説明した。この四極がそれぞれ自律的なものとして関係を結ぶ体制が、19~20世紀初頭のロシア文学では機能していた。しかし、と、講演の終わり近くになって氏は言葉を継いだ。ソヴィエトではこの四極すべてが国家に占有されることとなった。作者や批評家は国家が求めることだけを書き、すべての出版社は国有化され、国家の求める読みかたを読者は植えつけられた。国家に従わない言葉は、現れる場所を失ったのである。
それに伴って、スターリン統治下のソヴィエトでは、読書の多様性を示すような社会学的調査は許されなかった。「文学の社会学」にかぎらず、計量社会学や世論調査は、スターリン死後の「雪どけ」期の新たな文化だったのである。レイトブラト氏が長らく勤めたモスクワのロシア国立図書館で、「文学の社会学」に類する研究が着手されたのも、1950年代後半であったという。氏自身は1949年生まれでポスト「雪どけ」世代にあたるが、筆者が今回、氏に強く感じたのは、「雪どけ」の精神を引き継ぐ異論派知識人の気骨であった。たとえば、ソヴィエトでは作者・出版社・批評家・読者のすべてが国家化された、というまとめは、いささか単純ともいえる。作者は自作を公刊するために出版社や政治家と折衝を重ねたし、後期ソヴィエトでは地下出版も盛んだった。筆者のそのような質問を頑として撥ねつけた氏の姿勢に、ソヴィエト時代の生きた記憶をみてとらずにはおれなかった。
レイトブラト氏にはもうひとつ、現代ロシアを代表する文化評論誌『新文学展望』の書評・書誌欄編集者という顔もある。1992年の創刊以来(氏は93年に就任)、旧西側の人文学ディシプリンのとりいれという点で、ロシアで突出した役割を果たしてきたこの雑誌の歴史的背景にも、氏の来日を機に思いを馳せた。ロシア文化にとってユダヤ人問題はかねて宿痾であったが、「雪どけ」挫折後のソヴィエト知識人は、ロシア民族派とユダヤ系知識人とを両極に分化した。前者の極端な例がソルジェニーツィンであり、後者の例としてはソヴィエト記号論の領袖ユーリー・ロトマンなどを挙げることができる。『新文学展望』は後者の流れに属しており、ソヴィエト時代に「コスモポリタニズム」を弾劾されたユダヤの面目を保って、きわめて国際的にひらかれた誌面を展開している。編集陣には、ロシアから旧西側諸国へ移住した学者が多い(2006年に本学会の第1回大会で基調講演をしたミハイル・ヤンポリスキー氏(ニューヨーク大)もそのひとり)。一方で、民族派の流れをくむ雑誌や研究機関も存続し、その一部は現政権と強固に結びついている。『新文学展望』のほうには、編集長イリーナ・プロホロヴァの弟で、現代ロシア最大の新興財閥のひとつを率いる富豪ミハイル・プロホロフという後ろ盾がついているが、関係の深いモスクワのロシア人文大学やサンクト・ペテルブルグのヨーロッパ大学は、プーチン政権以来、政府から苛烈な介入を受けてきた。
筆者がロシア文学研究の世界に足を踏み入れたのはソ連崩壊後であり、上記のようにいくぶん「野蛮」なロシアの学問環境にときに辟易はしても、ソヴィエト時代からの歴史的流れのもとにそれを理解することは、感覚的にはなかなか難しい。今回、古きよき知識人気質を偲ばせるレイトブラト氏をとおして、そうした流れをひとつのライフヒストリーとして実感できた気がする。(報告:乗松亨平)
(シンポジウムの各報告は、ロシア語の論文集にまとめられた。ご希望の方には謹呈さしあげるので、東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学研究室(slav(a)l.u-tokyo.ac.jp/(a)はアットマークに読みかえ)までご連絡されたい。また、本シンポジウムは、科学研究費補助金(課題:「グローバル化時代における文化的アイデンティティと新たな世界文学カノンの形成」、研究代表者:沼野充義)および東京大学文学部布施学術基金の助成により開催された。)