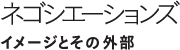パネルB「ネゴシエーションズ」は、コメンテーターに林道郎氏を迎えて、芸術と社会や歴史との関係を検討したパネルである。司会の松岡新一郎氏が初めに述べたように、従来の芸術研究では、まず作品の形式的特徴を分析する様式史があり、それに対抗する形で、作品制作のコンテクストを重視する研究が登場した。「イメージとその外部」という副題を持つ本パネルは、それらに対して、作品を、それだけで自立する存在でもなければ、社会や歴史といった外部の反映でもなく、むしろ、その外部とネゴシエート(駆け引き)するエージェントとみなすことによって、作品と社会や歴史との間にある複合的な関係に注目しようとする試みであった。 最初に発表した加治屋健司氏は、アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグの芸術の自律性の議論を検討した。ニクラス・ルーマンの社会システム論を用いて、グリーンバーグの自律性とは、50年代半ばまでは、社会に対する自立(自律)ではなく、社会の中の自律と捉えることができると論じた。また、グレゴリー・ベイトソンの関係性に関する議論を用いて、美的判断を包摂する重層的なコンテクストに対するグリーンバーグの関心を分析した。 次に発表した近藤學氏は、アメリカの画家ウィレム・デ・クーニングが制作中の作品を別紙に写し取り保存していたことに注目して、そのトレーシングによって構成される「アーカイヴ」の問題を検討した。マイヤー・シャピロの議論を参照しながら、デ・クーニングによる筆触の強調を、社会の産業化に対するオルターナティヴな生産を示すものと捉えた上で、画家の「アーカイヴ」の取り組みを、過去の記憶が主体の「自由」な行動を可能にすると考えるアンリ・ベルクソンの記憶論を用いて検討した。 最後の発表者の堀潤之氏は、ゴダールの歴史叙述には、二つの方法——厳密な記録装置としての映画が捉える証言の「アーカイヴ」と、映画が遭遇し損ねた歴史に漸近する「モンタージュ」——があると論じた。60年代末のシネトラクトの頃から始まったモンタージュは、複数の出来事の間に関係性を発生させる「歴史の反復」という視点をもたらしたと述べ、それが作品の主導原理を構成している『アワーミュージック』の分析を行った。 林氏は、加治屋氏に対して、作品から遠心的に視点を広げていく思考は、ヴェルフリンなど美術史ではよく見られるものではないかと指摘した後、グリーンバーグとルーマンの自律性の議論の間に照応関係はあるのかどうか質問した。加治屋氏は、グリーンバーグは、作品の価値を扱った点、そして、作品と時代の趣味との間の相互作用を重視した点でヴェルフリンと異なるとし、グリーンバーグにも、50年代半ばまでは目的論に捉われない側面があるため、ルーマンとの並行関係が見出せると述べた。 近藤氏が発表の最後に「ベルクソン的な自由を実現するために、デ・クーニングは、記憶の外化に他ならないトレーシングという反ベルクソン的な方法を用いざるを得なかった」と述べたことに対して、林氏は、それは時代的条件の変化かどうかと質問した。近藤氏は、ベルクソン自身、記憶が物質的に外化される時代にあえて記憶のあり方を示したと応じた。また、1870年代以降、作品の制作過程を記録する彫刻家や画家が登場した事実を指摘し、デ・クーニングはそうした系譜に位置付けられるとも述べた。 堀氏に対して林氏は、二つの方法は同等ではなく、二つめの方法が一つめを前提とする位階関係があるのではないか、また、ゴダールのモンタージュとベンヤミン的な歴史の救済とはどう関係しているかについて尋ねた。堀氏は、二つの方法は相互補完的だとした上で、映画に対する「信仰」をあえてモンタージュで壊す緊張関係の上に『映画史』が成り立っていると述べた。また、ゴダールのモンタージュは、ベンヤミン的な救済と近しいことを認めながらも、論理的に詰めていくのは難しいと慎重な姿勢を見せた。 質疑応答では、いずれの発表もメルロ=ポンティ的な「認識のアナロジーとしての芸術」という視点を共有しているのではないかという指摘があった。それに対して林氏は、むしろ違いを見ていく必要があると述べた上で、ポスト・メルロ=ポンティ的な、言語の媒介を経た知覚のあり方について触れた。会場からはその後、ゴダールにとっての歴史叙述の意味やそれを解釈する際の問題点に関する質問や、初期グリーンバーグがシステムを作らずに行った美術批評の重要性に関する指摘が続いた。 3人の発表はいずれも、芸術家や批評家の試みが、社会や歴史との関わりの中で生じながらも、それらを利用しながら自らの表現をいかに作り上げていったのかを考察するもので、芸術と社会という大きな問題に新鮮な視点を提供したと言えよう。本パネルは、白熱する議論や質疑応答のため大幅に時間を延長することになり、また、会場に入りきれないほど立ち見が出る結果となったが、それは、とりもなおさず表象文化論的な視覚研究に対する関心の高さを示していた。
「ネゴシエーションズ——イメージとその外部」芸術は真空の中で作られるのではない。作品であれ、批評であれ、そこには社会や歴史など、そのコンテクストが消しがたく刻み込まれている。従来、コンテクストから芸術への一方向的な影響として捉えられがちだった両者の関係であるが、本パネルでは、個別の諸事例を可能なかぎり精密に検討することから出発し、それらがどのような形で社会や歴史といったコンテクストと関わるのかを、イメージそれ自体が持つ構造と論理の水準において明らかにすることを試みる。イメージが、そのコンテクストによって重層的に決定されるのみならず、むしろ、能動的なやり方でそれと駆け引き(ネゴシエーション)をおこなって作品を編制していくメカニズムを、映画、美術、批評といった多様な表象文化を取り上げながら考察し、イメージとその外部の関係を議論するさいの理論的なオルターナティヴの提唱を目指す。 加治屋健司 「誰が芸術の自律を恐れるのか——ベイトソン、ルーマン、グリーンバーグ」20世紀アメリカを代表する美術批評家のクレメント・グリーンバーグ(1909—94)のモダニズムとフォーマリズムは、1970年代以降、様々な芸術家や批評家、研究者の批判の対象となった。本発表は、とりわけ社会史的な研究の再検討に焦点を当て、グレゴリー・ベイトソン(1904—80)やニクラス・ルーマン(1927—98)の議論を参照しつつ、芸術の自律性を始めとするグリーンバーグの議論の再定式化を試みる。芸術の社会性に関して、従来の社会史的な方法に代わるアプローチを社会システム論的な立場から検討したい。 近藤學 「ウィレム・デ・クーニングの「アーカイヴ」——制作プロセスの記録と時間の政治学」戦後アメリカ美術を代表する画家の一人ウィレム・デ・クーニング(1904—97)は、その長い生涯を通じ、自らの制作の諸段階を、さまざまな手段を用いて執拗なまでに記録・保存・再利用していた。本発表ではこの「アーカイヴ」構築に注目し、〈生産行為の時間性〉という視点から考察を加える。一見するとごく私的で風変わりなデ・クーニングの実践が、じっさいには広範な文化的含意を備えたものであったことを指摘しつつ、芸術と社会の複雑な関わり合いの一端を示してみたい。 堀潤之 「ゴダールと歴史のモンタージュ」ジャン=リュック・ゴダール(1930—)は『映画史』(1988—98)で、映像と現実、とりわけ映像と20世紀の歴史が取り持つ関係を独自の観点から考察している。本発表では、『映画史』に顕著な「歴史のモンタージュ」と名付けうる歴史叙述の手法が、五月革命時に撮られた匿名的なシネトラクトから最新作『アワーミュージック』Notre Musique に至る作品群でどのように変奏されているかをたどることを通じて、この手法の方法論的な可能性を探ってみたい。
[ホームへ戻る]
|