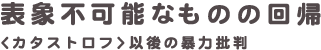パネルAは、立命館大学の田崎英明氏をコメンテーターに迎え、中島隆博氏の司会のもとに進められた。 各発表では、神的暴力やアウシュヴィッツの表象をめぐるデリダとナンシーの議論に始まり、鈴木清順の映画やルイジ・ノーノの音楽を経て、ベルリンのホロコースト記念碑をめぐる論争に至るまで、幅広い対象やトピックをもとに、〈表象不可能なもの〉の表象の可能性と不可能性をめぐってさまざまな考察が展開されたが、そのすべてにおいて暗に問われていたこととは——たびたびパネルのなかで言及された、アドルノの有名なテーゼに倣っていえば——「アウシュヴィッツのあとにアウシュヴィッツについて表象することは野蛮か」という問題であったといえよう。そして、そこで共有されていたのが、たとえばアウシュヴィッツの表象を禁止し、カタストロフの記憶を特権化する身振りによって忘却・抹消していくかわりに、表象行為に必然的にともなう暴力性を認識しつつも、あえて〈表象不可能なもの〉を表象するという課題を引き受けなおすという積極的な姿勢にほかならず、それぞれ発表者は、ナンシーの表象概念や、〈声なき声〉による喪、「対抗記念碑」などを論じるなかで、〈表象不可能なもの〉にたいするありうべきオルタナティヴな表象形式を模索していたように思われる。討論では、まずコメンテーターの田崎英明氏によって、すべての発表において〈ミメーシス〉の問題が深く関わっており、表象の暴力と表象を禁じるロジックの暴力とがミメーシスしあうというアポリアのなかで、証言の可能性を奪われた失われた〈死者〉をミメティックなかたちで救い出すことが問われていること、そして、そのためには、アガンベンの「能動的なメランコリー」や、ベンヤミンの「触覚性」という概念が示唆となるのではないかという指摘がなされた。さらに、発表者とコメンテーターのあいだでの議論や、会場からの質問によって、個別な事例を普遍化することや、過去に対する責任の主体をめぐる問題について、個々の発表の論点が掘り下げられることとなった。
「表象不可能なものの回帰:〈カタストロフ〉以後の暴力批判」〈表象不可能なもの〉をどのように表象するのか──「ポスト近代」を画す表象の問題とは、おそらくこのような問いに集約することができよう。20世紀以降のわれわれの時代は、この〈表象不可能なもの〉が二つの世界大戦、アウシュヴィッツ、ヒロシマを経て、9・11にいたるまで、さまざまな〈カタストロフ〉として絶えず回帰して止まない時代である。こうした〈表象不可能なもの〉は途方もない暴力でありながら、しかしなお、危機の証言として、死者の追悼として、記憶の芸術として、つねにわれわれに「表象すること」を課す。本セクションでは、〈表象不可能なもの〉が表象の限界において課す暴力の表象/表象の暴力を、暴力批判(ベンヤミン)の試みのうちに位置づけ、〈カタストロフ〉における表象の問題について、新たなパースペクティヴを開こうとする。 宮崎裕助 「神的暴力の正義、超表象の悪──デリダとナンシーにおける「アウシュ ヴィッツ」の表象」ジャック・デリダの『法の力』(1990)は、ナチズムの「最終解決」が、近代の「神話的で表象的な暴力の極限点」を指し示すことで、逆説的にも、ベンヤミンが神話的暴力と対置していた「神的暴力」の窮極的な顕現に酷似してくるというアポリアを指摘している。本発表は、この問題提起を継承することで、近年ジャン=リュック・ナンシーが提唱した「超表象」の概念(「禁じられた表象」2001)との関連を探りながら、現代思想が「アウシュヴィッツへの問い」として切り拓いた共通の問題系を解明しようと試みる。 多賀健太郎 「喪の証言性をめぐって——声・記憶・神話」表象という語が再現や代理をも想起させる以上、表象をめぐる問いには不在や死の契機がたえず絡み合うことになる。〈カタストロフ〉以後における、表象不可能なものを表象しようとする要請を、声・記憶・神話のプロセスに沿って再検討し、死者の喪に服することと死者について証言することとのあいだに横たわる距たりとその交錯の両義性を浮き彫りにすることで、死を合理化・儀礼化しようとする身振りにひそむ暴力性を探る。 香川檀 「ドイツのホロコースト記念碑論争と〈対抗記念碑〉」2005年5月、ベルリンにホロコースト中央記念碑が完成した。この記念施設をめぐっては、90年代半ば以来、負の過去を想起するにふさわしい造形とはいかなるものかをめぐって論争が展開されてきた。本発表は、その論争を参照しつつ、現代アートが提案する「対抗記念碑」のレトリックを図像性、文字性、空間構成などの面から考察したうえで、そこから抽出される「対抗性」が、落成したピーター・アイゼンマンの記念碑デザインにも見出されることを明らかにする。
[ホームへ戻る]
|