第16回表象文化論学会賞
【学会賞】
星野太『崇高と資本主義 ジャン=フランソワ・リオタール論』(青土社)
【奨励賞】
相田豊『愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学』(世界思想社)
鈴木亘『声なきものの声を聴く ランシエールと解放する美学 』(堀之内出版)
【特別賞】
該当なし
【渡邊守章賞】
田中純
【選考委員】
- 石田美紀
- 加藤有子
- 竹峰義和
- 谷昌親
【選考委員会】
2025年5月18日(日) オンラインミーティング
【選考過程】
2025年1月21日から2月14日にかけて、表象文化論学会ホームページおよび会員メーリングリストをつうじて会員から候補作の推薦を募り、以下の著作が推薦された(著者名50音順)。
【学会賞候補作】
- 相田豊『愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学』(世界思想社)
- 片桐悠自『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』(鹿島出版会)
- 鈴木亘『声なきものの声を聴く ランシエールと解放する美学』(堀之内出版)
- 田村正資『問いが世界をつくりだす メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論』(青土社)
- 福尾匠『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』(河出書房新社)
- 藤城孝輔『村上シネマ 村上春樹と映画アダプテーション』(森話社)
- 星野太『崇高と資本主義 ジャン=フランソワ・リオタール論』(青土社)
選考作業は、各選考委員が候補作それぞれについて意見を述べ、全員の討議によって各賞を決定してゆくという手順で進行した。慎重かつ厳正な審議の末、学会賞は星野太氏の著作、奨励賞に相田豊氏と鈴木亘氏の著作をそれぞれ推挙することが決定された。また、渡邉守章賞に関しては理事会からの推薦をもとに書面にて討議し、田中純氏による表象文化論学会および学術的発展への貢献に対して推挙することが決定された。
【受賞者コメント】
【学会賞】
星野太『崇高と資本主義 ジャン=フランソワ・リオタール論』(青土社)
このたびは第16回表象文化論学会賞という栄誉ある賞をいただき、たいへん光栄に存じます。まずは、今年の学会賞に拙著を推薦してくださった方、そして何より、審査の労をとってくださった審査員の方々に御礼を申し上げます。
個人的な感慨を申し上げますと、今回の学会賞受賞は本当に思いがけないことでした。ここ数年、表象文化論学会ではもっぱら裏方仕事に専念しており、とくに昨年企画委員長を拝命してからは、学会の事務的なことにばかり時間と労力を割いてきました。そうした経緯もありましたので、今回思いがけず、自分の研究者としての仕事を学会賞というかたちで審査・評価していただいたことにたいして、あらためて身が引き締まる思いです。
このたび学会賞をいただいた『崇高と資本主義』というリオタール論は、遡れば20年近く前に書いた修士論文がもとになっています。その意味で、自分にとってこれは紛れもなく過去の仕事です。その一方で、リオタールについては折々の機会に論文やエッセイを書かせていただく機会があり、そのつど自分の過去の研究をアップデートする幸運に恵まれました。そうして長い時間をかけて、今から20年前に仕上げた論文をブラッシュアップしたのが、今回の本ということになります。
いましがた「20年前」ということにわざわざ触れたのは、それがちょうど、この学会が設立されつつある時期のことだったからです。当時、自分は駒場の表象文化論コースの大学院生でしたが、そのときの雰囲気は今もよく覚えています。そこには、当時40代半ばだった田中純先生を中心に、「表象文化論」を看板に掲げた新しい学会を立ち上げるのだという静かな熱気が渦巻いていました。もちろん、当時のわたしはそれを横目に眺めているだけでしたが、学会というアソシエーションを立ち上げるにあたって取るべき「戦法」の数々を、学会の設立に尽力された先輩方の仕事から学べたと思っています。
自分がその出現を目撃した表象文化論学会も、来年で設立から20年を迎えます。自分にとって、狭い意味での専門性に閉じることなく、さまざまな分野の方々が集まるこの表象文化論学会は、いつも実りある研鑽の場でした。なかば形骸化したプロトコルからなる学会も珍しくない中で、この学会に来ると、いつも刺激的な発表や議論を目の当たりにすることができました。今回学会賞を受賞した本もまた、まさにここに集う方々の批判に耐えうるようなものとして、そのようなものであろうと努めて、改稿を重ねてきたものです。
その表象文化論学会で、このたび本書にこうした賞をいただけたことは大きな喜びです。今後も裏方仕事だけでなく、引き続き研究にも邁進していきたいと思います。最後になりますが、本書の担当編集者である青土社の菱沼達也さんをはじめ、わたしの仕事をさまざまなかたちで支援してくださっているすべての方に御礼を申し上げたいと思います。このたびは本当にありがとうございました。
【奨励賞】
相田豊『愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学』(世界思想社)
この度は、「表象文化論学会奨励賞」という栄誉ある賞を賜りまして、誠にありがとうございます。思考と表現を愛し、探求するものの一人として、これ以上ない栄誉に感じております。学会に携わる皆様に心より御礼申し上げます。
とりわけ、選考委員の先生方に対しては、感謝の念に堪えません。今回賞を頂いた私の本は、少し変わったテーマを扱っています。それは、南米ボリビアの街場の音楽家たち、しかも今となってはうだつの上がらない音楽家たちの音楽観を追求するというものです。おそらく選考委員の先生方のどなたにとっても専門からほど遠いこの本を読み、なにがしかの面白さを見出してくださったことに私はこの上ないよろこびを感じています。
もっとも、私としては今回の賞は、私自身に当てられたものというよりも、私のような研究をするもの全員を肯定し、励ますためのものなのだと受け止めています。というのも、今回の受賞は、すでに10年以上にわたる表象文化論学会学会賞の歴史の中で初めて、日本と欧米以外の地域について扱った著作の受賞であり、いわゆるフィールドワークの成果を中心とした著作としても初めての受賞だからです。このことは、表象文化論学会というもののただでさえも広い間口をさらに広げ、私と同じような研究をするものを大変勇気づけることになると思います。
これは私にとっても大きな希望です。かつて、表象文化論学会の名付け親でおられる渡邊守章先生は、表象文化研究が表象文化研究たる所以の一つとして、おのおのの研究者にとっての「偉大なテクスト」を見つけ、それに取り組むことを挙げられました。おそらくこの場におられる方々、全員の胸にこの「偉大なテクスト」はあることと思います。そして私にとって、たまたま、この「偉大なテクスト」とは、まさにボリビアの音楽家たちの日常の会話、世間話、昔語りの中に現れる言葉の数々でした。
今改めて考えると、この「偉大なテクスト」は、どのようなものでもいいわけです。ペルーの現代料理人の紡ぐテクストの中にそれを求めてもいい。アフリカの喧噪の中に聞こえる罵り言葉でもいい。もちろんマラルメのひらめきに満ちた詩の一節でもいいし、あるいは、日本のテレビ番組の間に挟まれる広告のキャッチコピーでもいい。そうやって、みなが世界中から「偉大なテクスト」の断片を持ち寄り、この表象文化論学会の場で、頭を突き合わせて、批評し合う。そのようなことが実現したとき、「偉大なテクスト」そのものさえ凌駕するかもしれないような、新しい驚異的で崇高なことばがこの表象文化論学会から生まれてくるように思うのです。
まさにこのような期待を込めながら、そして改めて自分自身もその中で仕事に邁進していくことを誓いながら、この度の受賞のご挨拶とさせていただきたいと思います。この度は誠にありがとうございました。

【奨励賞】
鈴木亘『声なきものの声を聴く ランシエールと解放する美学 』(堀之内出版)
このたびは、拙著『声なきものの声を聴く──ランシエールと解放する美学』を、第16回表象文化論学会奨励賞に選んでいただき、まことにありがとうございます。身に余る光栄に存じます。選考委員の先生方をはじめ、選考に携わってくださった方々に心よりお礼申し上げます。
『声なきものの声を聴く』は2020年度に東京大学大学院人文社会系研究科に提出した博士論文がもとになっています。学部から博士課程修了まで、一貫して指導にあたってくださった小田部胤久先生をはじめとする、東京大学美学芸術学研究室の先生方、博士論文を素敵な本に仕上げてくださった堀之内出版の野村玲央さんとデザイナーの川添英昭さん、本書の校閲や印刷、流通に携わってくださった皆様、刊行後、学会誌『表象』や『REPRE』など各種媒体で本書を紹介・書評してくださった皆様、合評会やワークショップを企画してくださった皆様、そして何より、本書を手に取り読んでくださったすべての方々に、感謝申し上げます。
「本書を手に取り読んでくださったすべての方々」、といま申しましたが、博士号取得という制度の中で書かれ、学術書として刊行したこの本は、実際、ささやかながらも私自身には思いもよらなかった読者の広がりを、幸運にも見ることができました。飲み屋のカウンターで隣り合わせた初対面の方が、その場で本書をネット注文してくれたこともあります。近所にある馴染みのお店に献本したところ、来店者がそれを読み、反応をくれたこともあります。飲み友達に本書のことを話したら、次に会ったときに感想を伝えてくれたこともあります――と並べていくとお酒関係ばっかりなのですが、それはともかく、本書が業界や専門性の枠を超えた読者を持ち得たことは、著者として、そしてランシエール研究者として、何よりの喜びです。本書の論点の一つはまさに、読むことのそうした広がりにあるのですから。
いや、およそ本というものはそのような思いもかけぬ広がりに開かれたメディアなのでしょう。そして以上のような実感は、まさに表象文化論学会が表象文化論学会として存在することの意味を、私に思い起こさせます。設立趣意文を引用すれば、わたしたちは「専門家集団による硬化した組織体からははるかに遠ざかり、関係性のネットワークを絶えず組み直し組み替えてゆく自由な運動体でなければなりません」。
私は現在、ランシエール研究に加え、落語やお笑いなどにも研究関心を広げる試みを続けています。それを通じて、この「自由な運動体」の一助となるべく、今後も精進する所存です。改めまして、この度はまことにありがとうございました。
【渡邊守章賞】
田中純
このたびは実質的に初回となる渡邊守章賞という大変名誉な賞にご推薦いただいた学会理事会の皆様、ご審議いただいた学会賞審査会の皆様にまず厚く御礼申し上げます。学術研究と舞台演出の両面で大きな業績を残された渡邊先生の名を冠した賞に自分がふさわしいかどうかははなはだ心もとないのですが、学会に対する貢献をお認めくださった皆様のお心をありがたく感じ、賞をお受けすることにいたしました。
わたし自身はじつは渡邊先生から直接教えを受けたことはありません。しかし、恩師の師でいらっしゃるため、ここでも「渡邊先生」と呼ばせていただき、先生をめぐる思い出や個人的な感慨をお話しさせていただこうと思います。
渡邊先生に最後にお会いしたのは2017年3月に五反田のゲンロン・カフェで催された浅田彰さんの還暦パーティーの折りでした。そこにはわたしが昨年評伝を刊行した磯崎新さんもお見えになっており、渡邊先生と磯崎さんが浅田さんや坂本龍一さんと一緒に並んでいる写真がたしかネット上にあったはずです。くしくも、この日は渡邊先生と磯崎さんの席の近くの、アテンド係のような座席がわたしに割り振られていた記憶があります。わたしの『磯崎新論』も今回の授賞理由のひとつだったとすれば、あの日のそんな出来事にも何やら縁(えにし)のようなものが感じられ、このお二人と坂本さんがすでに亡くなられてしまったことが、とても信じられない思いがいたします。
渡邊先生は表象文化論学会の設立時に、「学会の賞味期限は20年」といった趣旨のご発言をなさいました。それはわれわれ後続の世代に対する叱咤激励だったのでしょう。そろそろその節目の年に近づいていますが、今回の大会のパネル数は過去最多と聞いており、表象文化論学会および表象文化論の賞味期限、消費期限は切れるどころか、新陳代謝によってあらたな始まりを迎えているように感じます。それはパネルの内容やシンポジウムのテーマからも窺えることでしょう。それゆえいまは、2000年代半ばに学会を作るという決断をしたことは間違っていなかった、と信じられるように思います。
じつは最近、やむにやまれぬ必要があって、渡邊先生が訳されたポール・クローデル『繻子の靴』岩波文庫版の「あとがき」を読んでいたところ、渡邊先生がある言葉を繰り返し使っていることに気づきました。何だと思いますか?──それは「取り返す」という言葉です。演劇の言語や身体性を「取り返す」という課題について、渡邊先生は三度語っていらした。わたしにはこれがとても印象深かったのです。それはその「取り返す」という言葉に、けっしてあきらめきれない思いのようなものを感じたからでしょう。「取り返す」対象とは自分がかつて所有していた何かではないかもしれません。いまだかつてけっして手にしたことがなかったものを、ひとは「取り返そう」とすることがありうるからです。わたしにもまた、研究や著作を通じて「取り返す」べきものがあるように思われ、そのための情熱が自分にまだ残されているだろうか、と自問させられました。皆さんにはこの「取り返したい」という感覚をおわかりいただけるでしょうか? わたしには、「表象文化論」というジャンルを作ったときの渡邊先生たちには、学術の根源にある何かを「取り返したい」という情熱があったように思われてなりません。
表象文化論には芸術・文化の広義の批判・批評の前線であり続けるポテンシャルがあるとわたしは信じています。わたし自身も研究者としてはまだ現役ですから、何らかのかたちでそこに寄与したいと願うとともに、最後になりましたが、表象文化論学会の今後のいっそうの発展を心からお祈りしております。
このたびはほんとうにありがとうございました。
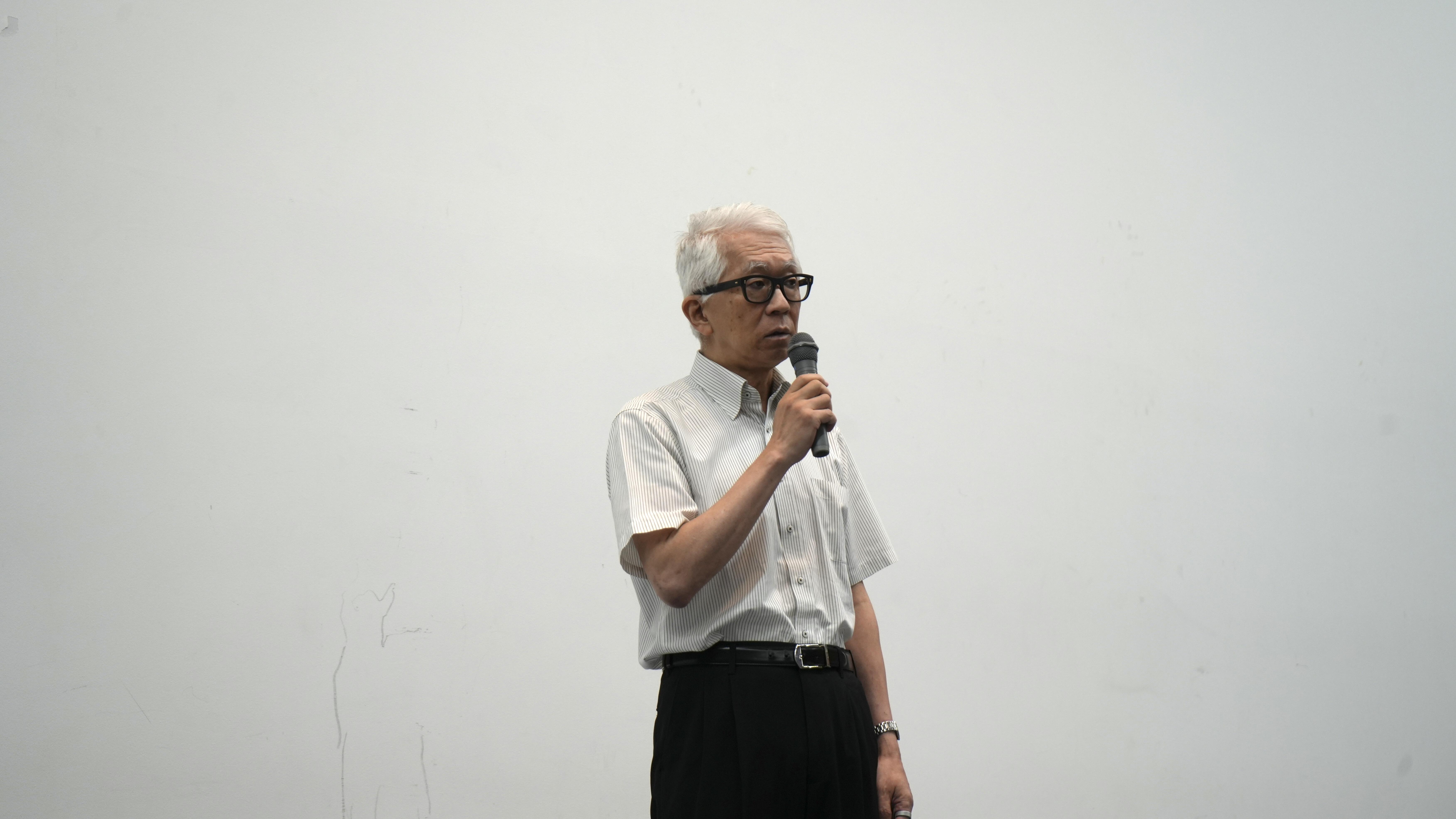
【選考コメント】
・竹峰義和
今年度に初めて表象文化論学会賞の選考委員を担当し、7本の候補作を読んだが、質の高い力作揃いで、いろいろなことを勉強させてもらった。惜しくも受賞には到らなかった候補作も、それぞれ学術的意義のあるたいへん優れた仕事だという点を、まずは強調しておきたい。
学会賞に選ばれた星野太氏の『崇高と資本主義』は、ポストモダンの思想家というレッテルで片づけられがちなリオタールの哲学を、「崇高」と「資本主義」との、あるいは美学と政治との交錯という観点から、そのアクチュアルな射程を示したものである。きわめて明晰な文章によってリオタールのテクストを読み解いていく手さばきは鮮やかの一言であり、読後に霧が晴れたような快感を覚えた。
奨励賞に選ばれたうちの一点、相田豊氏の『愛と孤独のフォルクローレ』は、読物として抜群に面白いだけでなく、文化人類学の魅力とエッセンスが詰まった一冊である。異文化に直接身を置き、さまざまな人々と交流を重ねながら方法論や仮説を練りあげていく著者の姿から、文献を読むことだけが表象文化論研究ではけっしてないことを改めて認識させられた。
もうひとつの奨励賞受賞作、鈴木亘氏の『声なきものの声を聴く』は、ランシエールの美学・芸術論が現実にたいする実践的応答をなしているという点を明らかにしたものである。精緻なテクスト分析から導かれる洞察は説得力があり、充実した註からも学ぶところが大きかった。
渡邊守章賞に選出された田中純氏の卓越した業績と学会への多大な貢献については、改めて記すまでもない。近著『磯崎新論』をはじめとする田中氏の著作の数々は、表象文化論を志すすべての研究者にとってつねに模範でありつづけている。また、田中氏の長年にわたる尽力なくしては、本学会がここまでの発展を見ることはけっしてなかった。この場を借りて心からの感謝の意を表したい。
・加藤有子
表象文化論学会という超領域的学会の賞は、学術書と創造性の境界を試す格好の場なのかもしれない。文体や著述スタイルに個性を強く反映させ、それぞれの領域における学術論文の在り方にも挑もうとするかのような意欲的な著作が並んだ。普遍的価値とされてきた価値が揺らぎ、先行きがますます不透明になった時代精神の反映だろうか、方向性はさまざまながら、著者自身がいま立つ世界を出発点に、対象を見据えようとする姿勢が強く出ていたようにも読んだ。著者個人の「わたし」とその経験を強く出す著作も多かった。一方で、学術書は一定のルール内の著述である。学会賞ということを鑑み、さまざまな創造性もその一定の枠のなかで評価することは意識した。いずれの候補作も優れた力作であり、そのなかから受賞作を選ぶことは困難な作業であったことは言うまでもない。
ランシエール論とリオタールの崇高論は、対象となる思想家の性質を差し引いても、混沌たる現実に向き合う真摯さ、その狙いを達成するためのテーマ選択と論旨展開の正鵠さにおいて抜きんでていた。いずれも両思想家がこんなに面白いものだったのか、という興奮も与えてくれた。
近代美学の一大テーマである崇高論が、リオタール、あるいは、リオタールを論じる著者を媒介に、資本主義を土台とする現今の政治を考える欠かせない鍵として立ち現れるのが、星野太『崇高と資本主義』である。崇高概念と重なる性質を前衛と資本主義に見出し、両者の共犯関係を指摘しながら、批判をも自身を強化するために呑み込む資本主義を批判する可能性を、一貫して探ったリオタール像が浮かび上がる。終盤で現代の「加速主義」を扱うところもよかった。影響力を持つ新しい思想的流れを、学術書で素早く歴史的に位置づけ、批評することの意義は大きい。
構成も効果的で、1章からのちの章に向かって線的かつ有機的に、無理なく論が展開し、議論の説得力が増していく。決して単純ではない内容を、安易に平易化することなく、しかし、現実に呼吸する読者に届く言葉とリズムで伝える文章力も秀でている。
鈴木亘『声なきものの声を聴く――ランシエールと解放する美学』も、文学、美学における議論を、現代のいまの政治性の問題に呼び起こし、それを通してランシエールを再評価するものである。混淆性をキーワードに、ヒエラルキーの解消、平等の実現をめざすものとしてリオタールの実践を読み解く。序論で明確に狙いが示され、ランシエールの思想の魅力を余すところなく読者に提示し、引きつける。解釈、その説明、それを支える文章、文体、構成、いずれも極めて明晰である。美学、哲学の領域で、ランシエールを通して、平等な関係性と民主主義を徹底的に志向し、自己充足的なゲームではなしに、いまの状況を変えようと真摯に向き合う。希望を抱かせる良書であった。
相田豊『愛と孤独のフォルクローレ――ボリビア音楽家と生の人類学』は、つながりや関連性を重視する文化人類学の在り方自体に真っ向から疑問を呈し、孤独に注目していく点に、著者のオリジナリティとセンスを感じた。この問題意識の出発点となるのも、2010年代以降、東日本大震災以降の日本社会で「きずな」や「共生」が濫用された言語状況である。その疑問を、著者自身が演奏者として関心を抱くボリビアのフォルクローレを通して、現地フィールドワークをベースに解決しようとする力作だ。現地ミュージシャン、楽器製作者、木材提供者の生活にすっと入り込み、観察する語り手=著者の魅力が充溢している。
構成も独特で、方法論の失敗も含めて、時系列的にすべて自分の体験を書き出していく。ゆえに、研究者の書いたすぐれたルポルタージュ文学としても読める(最初の空港到着のシーンは、情景が視覚的に浮かび、引き込まれた)。そして、これは著者の構想とも外れていない読みであると思う。学術的な枠組みにとらわれず、思うままに著者が書いた次作を読んでみたいとも思わせる、魅力的な一冊だった。
・谷昌親
昨年に引き続き、今年も候補作が7作となり、それなりの数であったため、すべてを読むのにはかなりの労力が必要になったが、幸い、それぞれ読み応えのある著作であり、純粋に読書として愉しめる時間をおおむね過ごすことができた。今年は、7作のうち4作がいわゆる現代思想の領域を扱っていたため、研究対象となる思想家はそれぞれ別であっても、関連するところがやはりあり、そのあたりを読み解くおもしろさがよい方向に働いということでもあったようだ。
以下、受賞作を中心に、簡単にコメントを記しておきたい。
まずは、学会賞を受賞した星野太さんの『崇高と資本主義 ジャン=フランソワ・リオタール論』について。今回の候補作のなかで、研究としてのレベルの高さを感じさせ、本としてまとまりがあり、独創性も感じさせてくれたのがこの著作であったことはまちがいがない。タイトルにもあるとおり、崇高と資本主義という観点からリオタールを論じているが、崇高と資本主義という一見相容れないように思われる2つの要素の関連を探る展開はスリリングでもあり、そのなかで、リオタールの思想の揺れも射程に入れつつ、美学と政治のかかわりを解き明かす手つきは鮮やかであった。
少し気になったのは、「大幅な加筆訂正を施しており、ほとんど元のかたちとどめていない」ということではあるが、それぞれの章について初出の文章があり、そのせいか、同じような説明の繰り返しがときどき出てくるという点だ。たとえば、一九八五年にポンピドゥー・センターで開かれた「非物質的なものたち」展についての論考はこの本の特色のひとつでもあるが、章が変わってまた同展示についての説明があったりで、ややくどい印象を抱いてしまう。
さらに、これはないものねだりであり、私の個人的な好みということだろうが、リオタールの思想を受けとめたうえで、星野さんご自身がどのように考えるのか、といったあたりをもう少し読みたい気もした。もちろん、研究書としては、リオタールの思想について独自の視点からまとめることですでに意を尽くしてはいる。しかし、本書の終盤で「非人間性」に関連して「幼年期」のテーマが出てくるが、星野さんはその「幼年期」をどのようにとらえているのか、あるいはその「幼年期」という「瞬間」を救うとはどのような営為につながると考えているのか、そのあたりをできれば次の著作で読みたいものである。
いずれにしても、昨年は学会賞が該当作なしになってしまっただけに、今年はこの『崇高と資本主義』のような候補作が出てきてくれたことを喜びたい。
さて一方の奨励賞だが、まずは相田豊さんの『愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学』について書いておこう。今回の候補作のなかでも、最も共感を抱きつつ読み進めることができた一冊だった。南米ボリビアでのフィールドワーク、それも現地のフォルクローレ音楽をみずから学ぶというフィールドワークをとおして、「共生とつながりの学としての文化人類学」が「孤独の学」になりうるのかという問いを追求していく過程が丹念にたどられている。それはまた、一般には他者とのつながりという観点から語られがちな音楽のあり方のうちに、「反抗」という要素を見出していく過程の記録でもある。
現代思想を扱った候補作と較べるなら、フィールドワークの記録という性質からではあるが、あまりに自分語りになっており、論理的な展開などが物足りないといった感想ももちろんありうるだろうが、たとえばレヴィ=ストロールの場合ですら、『悲しき熱帯』なしに後年の彼はありえなかったはずある。相田豊さんの今後の仕事におおいに期待したい(ただ、老婆心からひと言付け加えさせてもらうなら、反復を見据え、尊重することは大事だが、反復の魔に呑み込まれないようにしてもらいたいものである)。
さて、同じく奨励賞が贈られた鈴木亘さんの『声なきものの声を聴く ランシエールと解放する美学』であるが、これはジャック・ランシエールの思想のあり方をしっかり見据え、それを実に端正なポートレイトのように描き上げた著作と言えようか。読者に対する気配りも十二分になされ、非常に読みやすい本である。もちろん、ランシエール研究としての独自性も充分に感じられる。ただ、その独自性を鈴木亘さんは、「ランシエールが先行する、あるいは同時代の作家や思想家をいかに批判・再解釈しているのかをテクスト内在的に検討」することで追及しようとする。そのため、つねに他の作家や思想家との関係でランシエールについて論じることなる。ランシエールとシラー、ランシエールとブルデュー、ランシエールとマラルメ、といった具合に。要するに、ランシエール単独のポートレイトというよりもツーショットのポートレイトが最初から最後まで続くのである。
こうした論じ方そのものが鈴木亘さんの著作のオリジナリティーでもあるのだし、方法論として必ずしも間違っているわけではないが、どこか焦点が定まりきらない印象を持ってしまうことも否めない。ランシエールにおける「平等という思想」に迫り、美学と政治を関係づけるのが本書の一番の狙いであるのなら、別のアプローチの仕方、要するに、あくまでランシエール単独のポートレイトを描く部分が、もう少しあってもよかったように思う。
受賞作についてのコメントは以上になるが、それ以外の候補作にも簡単に触れておきたい。まずは福尾匠さんの『非美学——ジル・ドゥルーズの言葉と物』について。審査委員会においても最も物議をかもしたのがこの著作である。たしかに、『声なきものの声を聴く』とは対照的に、読者に親切とはいいがたい書物だ。
「哲学とは何か」と問うために、映画という他者による触発を浮き彫りにし、哲学と映画の関係を考察するために、『千のプラトー』における「地層」の概念を導入する……。とりあえずはそのようにこの本の試みを説明できるだろうか。独特のドゥルーズ論であることはまちがいない。ただ、ある意味で、非常に偏ったドゥルーズ論でもあるだろう。ひたすら見通しがよくなるような整理整頓への誘惑を斥けるその姿勢には共感できるし、可能性も大いに感じるが、ドゥルーズその人にとっても重要であった〈と〉の問題を扱っている書物であるだけに、読者とのあいだの〈と〉にももう少し注意を払ってもらえたら、との思いがつのる。
現代思想を扱ったもう一冊は、田村正資さんの『問いが世界をつくりだす——メルロ=ポンティ 曖昧な世界の存在論』だった。これは非常に誠実に書かれた著作である。通常は現象学の哲学者とみなされるメルロ=ポンティのうちに、副題にもある「曖昧な世界の存在論」を見出そうという道筋をひたすらたどって行く。その歩み自体は好ましく感じられるが、それがどこまで田村さんならではの歩みなのかがいまひとつ伝わりにくかったように思われる。
残りの二冊、片桐悠自さんの『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』と藤城孝輔さんの『村上シネマ——村上春樹と映画アダプテーション』は、それぞれ建築、映画という他の候補作とは違うジャンルを扱った力作だった。片桐さんが描くアルド・ロッシの世界は非常に興味深く、日本とのかかわりなどもおもしろく読んだものの、これは建築という分野の特殊事情もあるのだろうが、ひとつひとつの建築作品についての資料や考察が細かすぎて、著作全体を貫く論旨が見えづらくなっていた。一方の藤城さんの著作は、村上春樹の小説のさまざまな映画化作品を論じていくというユニークなもので、一般にはあまり知られていないアジア映画なども射程に入っているのが特徴であり、映画化作品をとおして浮かび上がる村上春樹像にも興味を引かれた。ただ、次々といろいろな作品を扱うために焦点が定まりにくく、個々の映画化作品に対する姿勢にカルチュラル・スタディーズ的なところがあるため、結局、映画化の時点の時代状況をたどっているような印象を与えるにとどまってしまった面があり、そのあたりがもったいなかったように思う。
最初にも書いたように、今回の候補作のレベルは高く、充実した読書時間を持てたわけであり、そのことを著者たちに感謝したい。また、昨年に引き続き、選考委員会での議論をとおして、自分の読みや理解を深めたり、考え直す機会を持つことができたが、それは他の委員のかたがたと学会事務局のおかげである。この場を借りてお礼申し上げたい。
・石田美紀
場違いの選考委員をおこがましくも引き受けたのは、表象文化論学会賞の候補作を読むことで人文学の現在を知ることができると考えたからである。その思惑どおり、自分ではなかなか手にすることのない領域に向き合えることができた。いずれの候補作も学術・研究書として読み応えのある力作であり、一読者としてただひたすら楽しく、充実した時間をすごさせていただいた。著者の皆様に御礼を申し上げたい。
とはいえ、心血が注がれた著作から受賞作を選ぶことは、ただ楽しいばかりではない。とりわけ専門外の著作についてはどこまで、なにを判断できているのだろうかと、自問自答の繰り返しであったが、つぎの3点を自身の判断基準として、選考委員会の議論に臨んだことをお伝えしたい。ひとつは、専門家ではない一般の読者も読めるかどうか、である。ふたつは、その主題に取り組むことについての意義が明確に意識されているのかどうか、である。みっつは、著者と読者が生きているいまへの意識が感じられるかどうか、である。
これらの観点を選んだのは、学術的知見を学術界の外に届けることも人文学の仕事のひとつであると考えてのことである。表象文化論学会に限らず、多くの学会の学会賞候補作が学位論文の書籍化であるが、やはり一冊の書物として、学位論文の枠を超えた魅力も重要視した。
そして、本年度の選考委員会として「渡邊守章賞」を90年代から日本の人文知をリードされ、また個人的には『デヴィッド・ボウイ 無を歌った男』で衝撃を受けた田中純先生に贈賞する機会に携わることができたことも、大変意義深いことであった。
以下、簡単ではあるが、本賞・奨励賞受賞作について述べる。
星野太『崇高と資本主義 ジャン=フランソワ・リオタール論』(青土社)
リオタールの崇高概念を70年代から90年代の政治・経済状況に再度置き直し、芸術と資本主義の錯綜した関係から解きほぐしていく展開は滑らかで、説得的である。とりわけ第1部を構成する第1章から第4章がすばらしく、そこから導き出される「前衛芸術と資本主義という二者の共犯関係」は現在もなお継続している論点であり、21世紀の文化状況を浮き上がらせている。第2部はリオタールの監修のもとで1985年に開催された「非物質」展の資料を丁寧に読み込みながら、日本で十全に知られているとはいえないリオタールの活動に迫る。「非物質性」と「非人間性」、さらには「幼年期」というキーワードを軸にリオタールの思想を再検討したのちに、それらの概念と2010年代との接点、とりわけ加速主義との関連を探る意欲的なものである。ただそのいっぽうで、第一部を貫いていた見通しの良さと時事性とは少し水準の異なる別のタイプの記述になっており、議論が軽量化したようにも読めた。いつか、近い将来に第2部の論点に再度取り組まれることを期待している。
相田豊『愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学』(世界思想社)
文句なしに楽しい読み物であった。序章からすばらしい。著者がフィールドワークの対象に関心を寄せていく背景が、こまやかで個人的なエピソードとともに綴られ、読者のうちに好奇心を掻き立てたのちに、南米ボリビアのフォルクローレ音楽家の世界に誘っていく。しかしそれと同時に本論で検討されていく論点はちゃくちゃくと設定されている。すべてを読み終えてみると、著者が積み重ねる自分語りは、議論の核となるフォルクローレ音楽家たちの孤独とそのあらわれである「アネクドタ」の予告でもあったことが判明する。本作の構成は文化人類学では定番の手法であるのかもしれないが、その筆致は軽快で、余裕すら感じさせるものだ。そのおかげで、南米ボリビアのフォルクローレ音楽家たちの自尊心と競争という固有の話題は、孤独とつながりという普遍的な関心へと展開していく。議論の掘り下げと広がりが有機的に連関した見事な著作であった。
鈴木亘『声なきものの声を聴く ランシエールと解放する美学 』(堀之内出版)
ランシエールの思想を、政治と美学、そして声から整理し、フランスを中心とした現代思想におけるランシエールの位置付けを明晰に行っている。本作の軸足となるのは、「崇高」対「美」であり、具体的にはリオタールが「崇高なるもの」を呈示不可能性とみなしたことに対するランシエールからの手厳しい批判である。本作は、ランシエールとリオタールの両者の共通点をあえて見出すことはせず、両者の差異を際立たせていく戦略を採っている。はからずもではあるが、本作と学会賞受賞作は共鳴し、議論を形成していたのが印象的であった。なお、候補作7作のうち4作が思想の著作であった。固有名詞と論点を共有する4作は、さながら現行の思想地図といった様相を呈していたのであるが、本作は間違いなくそのハブとなっていた。また、無駄のない議論が本作の長所であるが、もうひとつの読みどころは注の充実ぶりである。議論の本筋のために削ぎ落とされていった論点の数々が拾われており、ひとつひとつが示唆に富む。そこからさらなる展開があるだろうと期待している。
【第16回表象文化論学会賞 渡邊守章賞 推薦書】
田中純氏は、その研究の中核をなすアビ・ヴァールブルク論(業績4、12)を始めとし、イメージ分析や視覚文化論に関わる一連の研究(業績7、8、11、14など)で、表象文化論の領域横断的な学術研究に顕著な貢献をなしてきた。また、その経歴の初期から継続して進められている建築、都市論(業績1、2、5、6、9)も、表象文化論が扱いうる研究領域をよりいっそう広げた研究として高く評価できる。それに加えて、デヴィッド・ボウイ、磯崎新などの評伝(業績3、4、10、13、15)も、氏の研究のスタイルを特徴づけるとともに、後の研究者にとって欠かせない学術的な資産として読み継がれることになるだろう。
他方で田中純氏は、2005年から2006年にかけて表象文化論学会の設立を準備する過程で主導的な役割を担い、学会設立から4年間、事務局長として学会の安定した運営形態を構築することに多大な貢献を果たした。その後、長期にわたって学会理事を務め、2018年から2021年には会長を務めた。会長在職中は、文化庁による「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付(2019年)および第25期日本学術会議新規会員の任命拒否(2020年)に学会として抗議する声明文を公表し、人文研究を担う学術団体として文化芸術政策に対して社会的アクションをとる責務を果たした。また、在職期間の後半は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行のなかで学会活動を継続するために尽力した。
以上の研究活動及び学会運営面での功績をもって、田中純氏は表象文化論学会賞渡邊守章賞を授与するにふさわしい寄与を表象文化論学会にもたらしたと捉え、ここに推薦する。
2025年5月21日
表象文化論学会会長 門林岳史
表象文化論学会 理事一同
別添資料:主要著作一覧および表象文化論学会役員歴
主要著作一覧
1.『残像のなかの建築──モダニズムの〈終わり〉に』(未來社、1995年)
2.『都市表象分析Ⅰ』(INAX出版、2000年)
3.『ミース・ファン・デル・ローエの戦場──その時代と建築をめぐって』(彰国社、2000年)
4.『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』(青土社、2001年)
5.『死者たちの都市へ』(青土社、2004年)
6.『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007年)
7.『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008年)
8.『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010年)
9.『建築のエロティシズム──世紀転換期ウィーンにおける装飾の運命』(平凡社新書、2011年)
10.『冥府の建築家──ジルベール・クラヴェル伝』(みすず書房、2012年)
11.『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』(羽鳥書店、2016年)
12.『歴史の地震計──アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』(東京大学出版会、2017年)
13.『デヴィッド・ボウイ──無(ナシング)を歌った男』(岩波書店、2021年)
14.『イメージの記憶(かげ)──危機のしるし』(東京大学出版会、2022年)
15.『磯崎新論』(講談社、2024年)
表象文化論学会役員歴
〜2006年 発起人
2006年〜2023年 理事
2006年〜2009年 事務局長
2018年〜2021年 会長