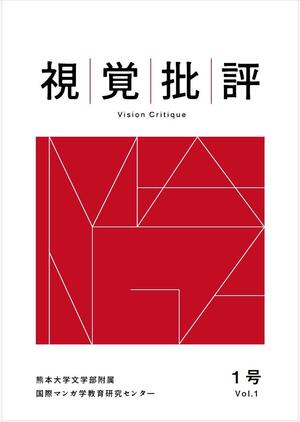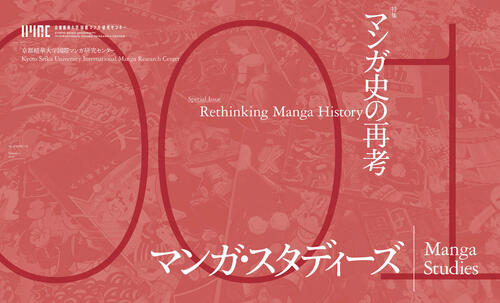『マンガ・スタディーズ』創刊 あるいはマンガ研究のこれまでとこれから
1. マンガ研究のこれまで
アカデミックなマンガ研究の場が制度として整備され始めたのはおよそ四半世紀前、2000年前後のことと言ってよい。それ以前の特に1980〜90年代には、広く評論家/ライター/マニア/コレクターといった肩書きのもとに活動する様々な書き手が雑誌を中心とした出版文化のなかでマンガをめぐる専門的言説を担ってきた。とりわけ1989年に手塚治虫が亡くなると、その功績を振り返るとともに戦後の日本マンガの文化的価値に注目するような動きが活発化していく。その後に代表的なマンガ評論家として知られることになる夏目房之介や、大学に所属してマンガを専門的に扱う研究者の先駆とされる竹内オサムも、こうした状況のなかで当初は手塚論を中心にその仕事を本格化させていった。とはいえ、2000年代の初め頃まで竹内のような例は珍しく、大学をはじめとする公的な研究機関においてマンガを専門的に扱うことは依然として例外的な試みにとどまっていた。
2001年に設立された日本マンガ学会は、こうした状況を踏まえつつより安定的かつ体系的な研究を可能にする場として構想されたものと考えられる。当時はマンガという大衆的な文化現象を扱うにあたって「学会」というアカデミックな制度を導入することに対する懸念も大きかったようだ。学会の設立趣意書には以下のような文言が見られる。
アカデミズムの場にマンガを持ちこむことは、アカデミズムという「権威」がマンガを「認知」するとか、アカデミズムの枠内に押し込める、といった営みではあってはならないはずです。そうではなくて、従来、この二つを縁遠いものにしてきた価値観や認識の枠組みそのものを、根本的に問い直す営みでなければならないでしょう。それは、急速に解体・再編の進む今日の人文・社会科学全体の動向に対しても、重要な貢献になりうるはずです*1。
*1 日本マンガ学会第1期役員一同「日本マンガ学会設立趣意書」2001年7月29日。https://www.jsscc.net/gaiyou/874
ここでは、学会の設立によってそれまで権威的な制度の外で発展してきた活動を「アカデミズムの枠内に押し込める」ことになってしまうのではないかといった懸念に対する応答が試みられている。その後のマンガ研究の歩みを見ればこうした指摘にも一定の妥当性があったようには思われるが、一方で、そもそも2000年代以降に活字の出版市場がかつての勢いを失っていったことは見逃せない。こうした状況では、マンガのような対象であっても専門的な言説を維持するために大学などの公的な研究機関の役割が重要になる。実際、ここ20年ほどで大学に所属するマンガ研究者の数は飛躍的に増加したように見受けられる。こうした過程を経て、学会と論文を中心とする学術的な制度はマンガ研究にとっても一定の意義を持つものとなってきた。とりわけここ数年は例えばマンガ学会の大会でも毎回30前後の個人研究発表が行われるようになっており、アカデミックなマンガ研究は安定期に入ってきたと言えるだろう。
こうした動向は表象文化論学会にとっても無縁のものではない。学会誌『表象』では、直近の17号から19号まで3号連続で特定の作品や作家を対象としたマンガ/コミックスに関する論文が掲載されている*2。8月に武蔵大学で開催された第19回大会でもマンガに関連した複数の個人研究発表が行われた*3。本学会は当初から視覚文化の一種としてマンガやアニメを扱う可能性に開かれていたはずだが、学会発表や査読論文の形でこれだけ安定的に成果が寄せられるようになったのはここ数年のことではないだろうか。
*2 渡部宏樹「刺青に突き立てられる刃 『ゴールデンカムイ』における皮膚上の記号作用とギャグの機能」『表象17』2023年、168-187頁/鶴田裕貴「二重化された予示 日本キャラクター論から見た「ハッピー・フーリガン」」『表象18』2024年、108-122頁/石岡良治「猫を描く 大島弓子作品における「メディウム」としての猫」『表象19』2025年、92-107頁。
*3 森田百秋「「NTR」はいかにして成立したか 美少女マンガ誌『コミックコーヒーブレイク』(富士美出版)の分析」/細馬宏通「1923年のマンガの書字方向とコマ配置 「日刊アサヒグラフ」紙面のレイアウト分析」/濱中麻梨菜「視覚表象の〈継承〉と〈逸脱〉 ハンダラ図像の派生形にみる政治性と行為性」。
さらに近年では学会をはじめとするアカデミックな制度のもとで活動を進めてきた世代の研究者が実質的な主体となる形で、マンガ研究に関わる新たな動きも活発化している。2022年10月に熊本大学に設置された「文学部附属国際マンガ学教育研究センター」の活動はその際たる例だ*4。同センターは教育や研究だけでなく関連資料のアーカイブ構築も行うことで、マンガ研究の新たな拠点となることを目指している。2025年3月に創刊された紀要ジャーナル『視覚批評』には一次資料を活用した論文も掲載されており*5、今後の継続的な研究活動が期待できる。
*4「熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センター」https://www.let.kumamoto-u.ac.jp/manga/
*5 特に以下を参照。池川佳宏「日本初のレディース・コミック誌『別冊女性セブン』はどうして生まれたのか 戦後マンガ史の大転換期・1968年」『視覚批評』第1号、熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センター、2025年、1-21頁。
一方、2000年代からマンガ研究をリードしてきた京都精華大学でも新たな動きが見られる。2000年に国内で初めてマンガ学科を設置した同大学はマンガ学会の発足に際しても主体的な役割を果たしただけでなく、2006年には大学が運営する施設として京都国際マンガミュージアムを開館、あわせて国際マンガ研究センターを設置するなど研究に対する積極的な姿勢を示し続けてきた。この度、同センターが創刊したオンラインジャーナル『マンガ・スタディーズ』は、こうした蓄積を踏まえつつマンガ研究の新たな四半世紀へと向けられた企画と言ってよいだろう。
2. 『マンガ・スタディーズ』創刊号
2025年6月に公開された『マンガ・スタディーズ』創刊号*6は「マンガ史の再考」を特集テーマとしている。第1号に含まれるコンテンツは2025年度内に随時公開される形となっており、現段階では「創刊の辞」「巻頭言」の他に4本のオリジナル論文と1本の翻訳論文が掲載されている。今後さらに1本のオリジナル論文と3本の翻訳論文が公開されるようだ。創刊号には私自身も論文を寄せているが、拙稿を含めて掲載された論文はいずれも従来のマンガ史研究において注目されにくかった領域に光を当てたものとなっている。
*6『マンガ・スタディーズ』第1号、京都精華大学国際マンガ研究センター、2025年。https://manga-studies.jp/index.php/journal/issue/view/1
「漫画/マンガ史の「死角」 楳図かずおのいる歴史のために」と題した拙論は、結果的にこの号の総論に相当するような内容となった。これまでにマンガ史の通史的記述を試みた代表的な著作を検討し、それらにおいて共通して見落とされる傾向にあった領域を明らかにすることを目指したものだ。論文でも指摘したように、資料の整理状況やマンガ史記述を担ってきた論者の関心を反映する形で、1950-60年代の少女マンガをはじめとするいくつかの領域がこれまでマンガ史の「死角」となってきた。『マンガ・スタディーズ』創刊号に掲載された他の論文の多くも、拙論で指摘した「死角」に関わる領域を扱ったものとなっている。こうした構成は事前に計画されたものというよりは、近年の研究動向を踏まえて「マンガ史の再考」というテーマを設定したことによる帰結と考えた方が良さそうだ。
例えば宮本大人「児童読物統制下の「教育的」漫画論 「沸騰」から「蒸発」へ(1)」は、まさに従来のマンガ史にとって大きな「死角」となってきた戦前戦中期の子供漫画に関するものとなっている。この分野の第一人者として知られる宮本による論文は、戦時下に行われた子供向け出版物に対する統制のなかで特に漫画に関する批判的言説がいかに形成されていったのかを詳細に検討している。「児童読物改善ニ関スル指示要綱」が通達された1938年前後以降の統制はマンガ史の展開にとって重要な契機とされてきたが、その内的な力学について十分には明らかになっていない。今回、数回に分割しての公開が予定されている本論文はその決定版となることが期待される。
あるいは松下哲也「武者小路実篤作、岸田劉生画『カチカチ山と花咲爺』のキャラクター表現 近代観相学にもとづく善と悪の表象」もまた、従来のマンガ史にとっての周辺的な領域を扱っている。20世紀初頭におけるマンガ的なキャラクター表現の成立を西洋由来の「美術」に関する理論との関係において明らかにしようとするこの論文は、戦前日本における「漫画」の位置付けにも関わるものだ。90年代以降のマンガ研究はいわゆる「ストーリーマンガ」のみに関心を向ける傾向があったが、かつて「漫画」というカテゴリーはかなり幅のある曖昧なものとして機能してきた。特に戦前には風刺/風俗画的な表現を指すことが多く、出版物に掲載される絵画的表現として挿絵などとも近しい領域となっていた。その担い手の出自も含めて、いわゆる「美術」との関係は現代の私たちが想像するよりもはるかに深いものだったはずだ。こうした状況に遡ることは、戦後に「大人漫画」と呼ばれるようになっていったような、「ストーリーマンガ」とは異なる流れの「漫画」を理解することにもつながるだろう。
追加の論文として11月の公開が予定されている森下豊美「久里洋二再考 日本におけるオルタナティブな漫画表現の試行と創造性」も、こうした非-ストーリーマンガ的な領域に注目したものとなりそうだ。久里洋二はまさしく「大人漫画」周辺の活動から出発しつつ、その後はむしろアニメーション作家やイラストレーターとして知られることになった人物である。その経歴自体が、1960年代ごろまで出版界で一定の影響力を持ちながら1970年代以降急速に衰退していった「ストーリーマンガではない漫画」を取り巻く状況の変化を示しているはずだ。
最後に、マンガ/コミックス史を最も大きな視点から捉え直そうとした論文としてEike Exner, “Phenakistiscope and Pantomime Cartoon: The Rise of “Stories without Words” amid the Nineteenth-Century Revolution in Visual Culture, Science, and Technology, 1832–1899”を確認しておこう。この論文は現代的なコミックス表現の源流を19世紀のヨーロッパで起こった視覚に関する文化的変容に求めようとしており、極めて表象文化論的な試みとも言える。日本マンガ史の研究者としても注目されているアイケ・エクスナだが、今回は19世紀後半に活躍したドイツの画家ヴィルヘルム・ブッシュのマンガ的表現に焦点を当てている。エクスナは、ブッシュが手がけた「パントマイム・カートゥーン」、すなわち文字情報を使わずに複数の絵の並びによって出来事を描く表現が現代的なマンガの源流となったという歴史観に基づき、その成立の背景をジョナサン・クレーリーが『観察者の系譜』で論じたような19世紀ヨーロッパにおける文化的変容に求めていく。すなわち、人間の視覚のあり方に関する認識の変化とそれに伴って登場したフェナキスティスコープに代表される視覚的装置による新たな経験が、絵を第一とする物語表現につながったというのがエクスナの主張だ。議論の詳細は論文に譲るが、広くメディア史的な観点から近代のマンガを位置付けようとした挑戦的な試みと言えるだろう。もちろん、錯覚によって静止画から滑らかな運動を生み出そうとした様々な視覚装置と静止画を順番に眺めていく「パントマイム・カートゥーン」の経験との質的な差をどう評価するのかなど依然として疑問は残る。それでも、ブッシュの仕事をコミックスの歴史の中に位置付けるとともにその文化的背景を広く捉えようとしたこの議論は、視覚文化としてのコミックス/マンガの歴史を研究する際の重要な足掛かりとなるだろう。
以上のように、『マンガ・スタディーズ』創刊号の内容はマンガ史に関する最新の研究動向を踏まえた学術誌に相応しいものとなっている。一方で、このジャーナルは誌面と連動した企画としてYouTubeチャンネルの運営も行っていくとのことだ。掲載された論文の著者による解説動画などが公開され始めており、一般の読者に向けた発信にも力を入れていこうという姿勢がうかがえる。近年のマンガ研究は学術的な堅実さと安定感を得た代わりに、かつての批評的言説が持っていたような活力をいくらか見失いつつあるかもしれない。今後は、逆に最新の研究成果を再びジャーナリスティックな場へと差し戻すことも必要になるだろう。本稿で取り上げたいくつかの試みが、そのような来るべき四半世紀への折り返しの契機として機能することを期待している。