映画の隔たり
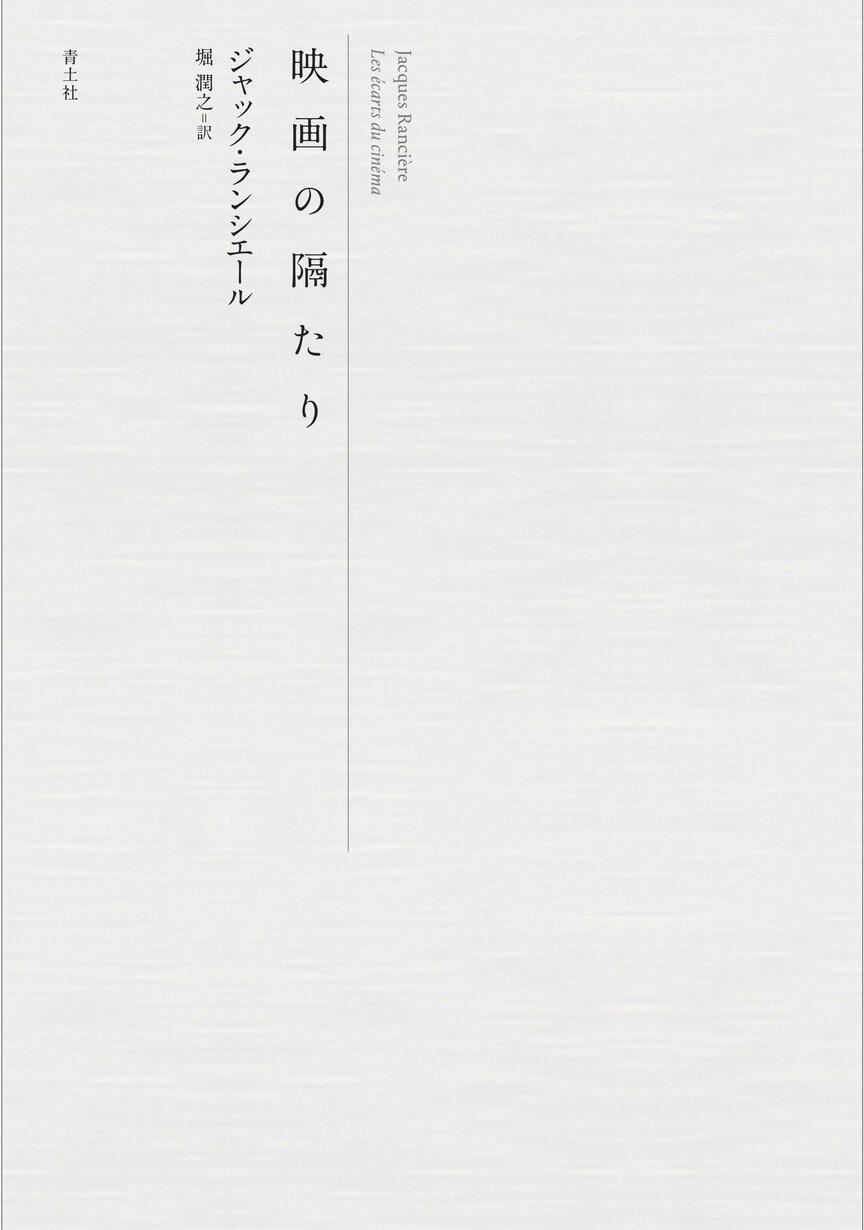
本書は、ランシエールの2001年の映画論『映画的寓話』(中村真人・堀潤之監訳でインスクリプトより近刊)の続篇にあたる著作で、主に2000年代に書かれた6篇の映画論が、映画と文学、映画と娯楽/思考、映画と政治というテーマ別の三部構成で収められている。
取り上げられているのは、ヒッチコック、ブレッソン、ミネリ、ロッセリーニ、ストローブ/ユイレ、ゴダール、ペドロ・コスタら著名な映画作家たちの作品群である。各章のより詳しい内容の説明は「訳者あとがき」に譲るが、とりわけ第一部「文学の後で」は、芸術の表象的体制と美学的体制の映画における絡み合いなど、ランシエールの芸術論の基本的な道具立てを存分に活用しながら、ヒッチコックの『めまい』(1958)とジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』(1929)を大胆に接続する論考と、ブレッソンの『少女ムシェット』(1967)をベルナノスの原作と対照させ、かつブレッソン自身の『シネマトグラフ覚書』に抗って緻密に読み解く論考を収めており、ランシエールの映画論の手つきに馴染むのには最適であろう。
なお、本書刊行後、東京の映画館Strangerにて、ミュージカル作品に比べて相対的に知られざるメロドラマ作品に焦点化したヴィンセント・ミネリ特集が開催された(2025年6月27日〜7月24日)。本書でも大きく取り上げられている『蜘蛛の巣』(1955)や『走り来る人々』(1958)を含む特集である。ランシエールの映画論は非常に精密な作品の読解に基づいている点が特徴的なので、こうした上映企画とも相性がいいはずだ。願わくば、第二部で扱われているロッセリーニの『ソクラテス』(1971)、『ブレーズ・パスカル』(1972)、『デカルト』(1974)のような、国内ではアクセスしにくいものにも上映やソフト化の機会が訪れてほしいものである。
(堀潤之)