ファッションセオリー ヴァレリー・スティール著作選集
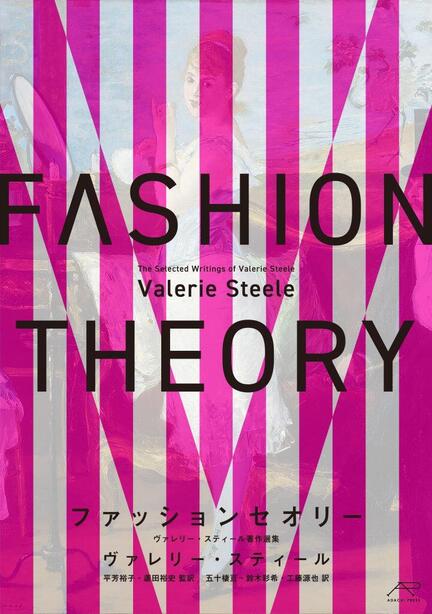
日本に限らず、ファッションは長らく正統な学術研究の対象として認められてこなかった。本書所収の「Fワード」で描かれる著者のイェール大学での経験──「学術界におけるファッションへの敵意」(p.4)──は、その困難を端的に物語っている。著者はその状況に抗しながら、1985年の『Fashion and Eroticism』を皮切りに、ファッションに関わる数多くの著作を発表してきた。2003年にはFITミュージアム(ニューヨーク州立ファッション工科大学ミュージアム)の館長兼チーフキュレーターに就任し、『The Corset: Fashioning the Body』や『Gothic: Dark Glamour』など25以上の展覧会企画も行っている。学術研究と実践を両輪に服飾史を批判的に問い直しつつ、ファッションを文化研究の中核的な主題へと押し上げてきたのである。さらに1997年にはファッション専門の学術ジャーナル『Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture』を創刊し、編集長としてファッションを国際的に議論するプラットフォームを確立した。
本書は、世界的にファッションスタディーズを牽引してきた著者の成果から精選された17篇を収める日本独自の選集であり、同時に四十年以上にわたる知的な探求と挑戦の軌跡でもある。多様なトピックを通じてファッションを「理論的に語る」営みが邦訳された意義は二重にある。第一に、著者がファッションスタディーズの制度的基盤を築いてきた国際的な貢献を辿ることができる点、第二に、日本において議論がなお途上にあるファッションスタディーズにおいて、参照すべき歴史的かつ実践的事例が多数提示されている点である。
本書は全四章からなり、それぞれが「セオリー」としての異なる側面を照らし出している。「1. ファッションとは何か」では、ファッションスタディーズがいかに学問的周縁から生まれたのかを跡づけ、あわせてファッションがミュージアム制度のなかでどのように位置づけられてきたのかを検証し、学問的対象としての方法論を考察する。「2. 近代社会とファッション」では、ダンディズムやコルセット論争、エドゥアール・マネ《ナナ》の分析を通じて、近代社会に端を発するジェンダー規範や階級、都市文化の諸問題を描き出す。「3. ジェンダーとセクシュアリティ」では、フェティシズムやパンク、ファッション史におけるクィアの位置づけを取り上げ、衣服や身体のイメージが権力構造を批判的に読みかえる過程を検証する。そして「4. 服の見方、イメージの読み方」では、ガブリエル・シャネルやカルバン・クライン、日本のファッションデザイナーらを題材に、ファッションを神話化する作家主義的言説を批判的に解体し、衣服が映画スターのイメージや政治的象徴を形成するプロセスを読み解く。
では、本書に冠されたファッションの「セオリー」とは何か。それは、第一に、学問やミュージアムにおける周縁化の構造を可視化する制度批判としての理論。第二に、衣服の文化的コードを読み解き、同時にその言説を批判する方法としての理論。第三に、ジェンダーやセクシュアリティを軸に、権力と欲望を再編成する装置としてファッションを捉える批評理論である。「ファッションセオリー」とは、衣服をめぐる社会的実践を批判的に読み解くための手がかりであり、同時に彼女が長年取り組んできたファッション展のキュレーションにおいて実践されてきた営みでもある。本書に示される展覧会の事例もまた、単に消費主義的な演出に依拠したスペクタクルではなく、制度や歴史を批評的に照射する場として構想されている。したがって、本書が提示するのは、ファッションを社会的・文化的・歴史的に読み解く批評の言語=セオリーである。それは制度や権力を可視化する方法であり、芸術や産業としてのファッションを相対化し、社会の諸相を解読するレンズとして位置づけ直す営みでもある。
(五十棲亘)