ドキュメンタリー写真を発明し直す
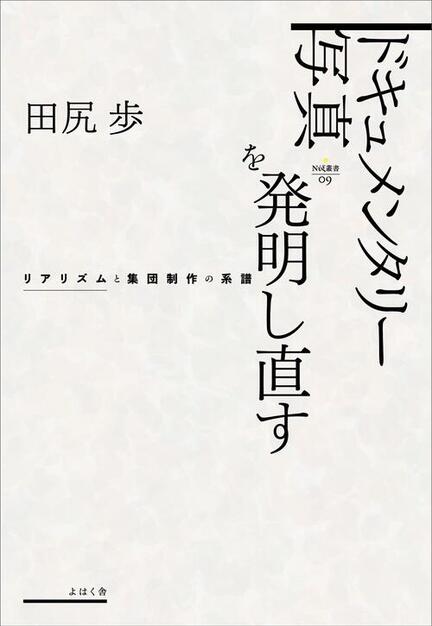
本書のタイトルの由来となっている、アメリカの写真家・批評家、アラン・セクーラの1978年の論文「Dismantling Modernism, Reinventing Documentary (Notes on the Politics of Representation)」は、どうしたらドキュメンタリー写真が社会的な批判力を持ち続けることができるかを問うたものであった。セクーラが同論を発表したとき、1930年代のフォトジャーナリズムの興隆とともにその形式が確立されたドキュメンタリー写真は、報道の手段としてすでに時代遅れのものとして多くの人の目には映っていた。他方で、当時広がりつつあったポストモダニズムの思想は、ドキュメンタリーのみならず、写真というメディウム自体に結びつけられていた客観性や真実性といった観念を疑わしいものとした。「写真が現実の記録でないとしたら、一体何なのか?」。この根本的な問いは、写真表現の多様化に拍車をかけ、そのことは結果として、写真が現代美術の一分野として受け入れられるのを後押しした。それに対して、写真と美術の結びつきを評価するどころか批判的に捉えるセクーラは、フレッド・ロニディアら友人の写真家たちの作品を手がかりに、「独占資本主義の増大する権力と傲慢への能動的な抵抗、政治的であると同時に象徴的でもあるような抵抗」となり得るような、アップデートされたドキュメンタリー写真の形式を模索したのだった(アラン・セクーラ「モダニズムを解体し、ドキュメンタリーを再創案する(表象の政治学についての覚書)」甲斐義明編訳『写真の理論』月曜社、2017年、65頁)。
このようなセクーラの問題意識を引き継ぎ、「ラディカルな写真実践」(23頁)としてのドキュメンタリーによる、新たな「リアリズム」の可能性を探究するのが本書である。セクーラの論文が1970年代後半に写真が置かれた状況に応答して書かれたものであるのに対して、本書が扱う対象は時代は1930年代から2010年代まで、地域はアメリカ、イギリス、ドイツ、日本と幅広い。第1章では、セクーラの写真理論と『フィッシュ・ストーリー』(1995年)を中心とする彼の作品が論じられ、第2章では1970年代前半にセクーラと親しい関係にあり、彼としばしばともに語られてきたマーサ・ロスラーの社会主義フェミニズムが考察される。第3章では中平卓馬の写真評論と2011年の写真集『Documentary』が「シュルレアリスム的実践」として論じられている。
つづく第2部では本書の副題にその語が使われている「集団制作」が主題となる。第4、5章で戦前のドイツ、日本、アメリカの労働者写真運動、第6章で1970年代イギリスの女性写真家集団ハックニー・フラッシャーズ・コレクティヴによる、労働や子育てなどに関して女性が置かれた状況をパネル展示によって啓発する「コミュニティ写真」、第7章では1960年代半ばから70年代初頭にかけての全日本学生写真連盟の活動に焦点が当てられている。元々博士論文として執筆された研究らしく、いずれの章でも主要な一次資料・二次資料が丁寧に参照され、それぞれの実践の文化的・政治的背景について言及されている。
セクーラにとってラディカルであるというのは、(最低条件として)左翼としての立ち位置を堅持することを意味した。田尻氏が取り上げる写真家たちは皆、時代や地域の違いこそあれ、多かれ少なかれマルクス主義の影響を受けており、その点ではセクーラと共通している。だが第4、5章で論じられる1930年代は、『ヴュ』や『ライフ』といったグラフ雑誌によってドキュメンタリー写真がこれからまさに「発明」されようとしていた時期であることを考えれば、第1部で論じられている写真実践で問題になっていることと、第2部のそれとのあいだでは無視できない相違があることにも読者は注意する必要がある。集団制作か個人制作かを問わず、写真の真実性という「神話」に依拠するドキュメンタリー写真は、セクーラやロスラーによって(ロスラーの有名な作品のタイトルから借りれば)「不適切な記述システム」とみなされた。だとすれば、集団制作への移行が、ドキュメンタリー写真に内在する問題を直ちに解決することはあるまい。他方で、集団制作という方式が必ずしも左翼の立場、反資本主義の立場から行われなければならない、というわけでもない(例えば、マルクス主義からは距離を置いた鶴見俊輔による「限界芸術論」はそのことを示唆している)。
日本における写真史の研究状況を多少なりとも知っている者であれば、このように互いに時代や地域の異なる様々な題材をなぜ一冊の本の中で論じているのか、その理由(の一部)を想像するのは難しくない。(やや新鮮味に欠ける第3章を除いて)それらはいずれもこれまでの日本語文献において見過ごされてきた、あるいは重視されてこなかった領域なのである。とりわけ、日本のプロキノ普通写真部とプロフォトについて論じた第4章第2節、そして、2021年に亡くなった写真史家の金子隆一が晩年に取り組んだテーマであった全日本学生写真連盟の「集団撮影行動」について、関係者へのインタビューも交えてその経過を追っている第7章は、日本写真史研究の基本文献として今後長く読まれるべきものとなっている。
1978年のセクーラの論文は、写真というメディウムが当時置かれていた状況に応答して書かれたものであることは述べた。だがドキュメンタリー写真がどうすれば社会において必要なものであり続けることができるか、というのは決して過去の問いではない。生成AIの普及によって、写真映像の真実性という、そもそも不確かな観念に致命的打撃が加えられようとしている。どんな残虐な写真を見せられても「どうせAIだよね」と自身を納得させ、何の心の動揺も生じない(あるいは少なくとも、残酷な絵画を見たときに感じる以上の衝撃は感じない)時代がまもなく訪れるかもしれない。そのような時代において、写真映像のドキュメントとしての可能性というのは、かつてないほど狭められている。しかし、だからこそ、その可能性の探究は喫緊の課題と言えるのである。
その意味で、本書で論じられている過去の事例は、いずれも現在的な問題として捉え直すことができる。だが、もしそのように捉えるのであれば、セクーラ、ロスラー、中平がそれぞれの仕方で行おうとしたドキュメンタリー写真の新たな形式の創出、そして、ハックニー・フラッシャーズ・コレクティヴや全日本学生写真連盟らの(匿名で作品を発表することを厭わない)集団的な写真制作実践が、果たしてどの程度成功していたのか、より厳しい目で問う必要があるだろう。田尻氏は「土門のリアリズム写真運動は失敗に終わったものの、この運動から東松照明や川田喜久治といった次世代の写真家が登場し、新しい集団的写真実践の到来を批評家たちに想像させた点において重要であった」(327頁)とし、その新しい集団的写真実践の一例である「全日〔引用者注:全日本学生写真連盟の略称〕は、すでに失効した土門らのリアリズムを批判して新たなリアリズムを希求していたと言えるだろう」(330頁)と述べている。だが、そのような一方的な乗り越えの構図で語ることは適切だろうか? このようなことを問うのは、何も土門の肩を持ちたいからではなく、写真作品の集団制作という現在では決して一般的とも、その有効性が広く承認されているとも言い難い方法を、それこそ「発明し直す」ためには、そこにどのような限界があったのかを明らかにすることが、その意義を示すのと同じくらい重要であるように思われるからである。そのためには、セクーラが過去のドキュメンタリー写真に向けたのと同様の批評的=批判的な眼差しが、1960年代の集団撮影行動にも向けられなければならない。それを行うのは本書の筆者かもしれないし、別の人間かもしれない。いずれにしても、学術論文として書かれた本書が新たな写真批評、さらには写真実践を生み出したとき、その意義は揺るぎないものになるはずである。
(甲斐義明)