「陰翳礼讃」と日本的なもの 建築と小説の近代
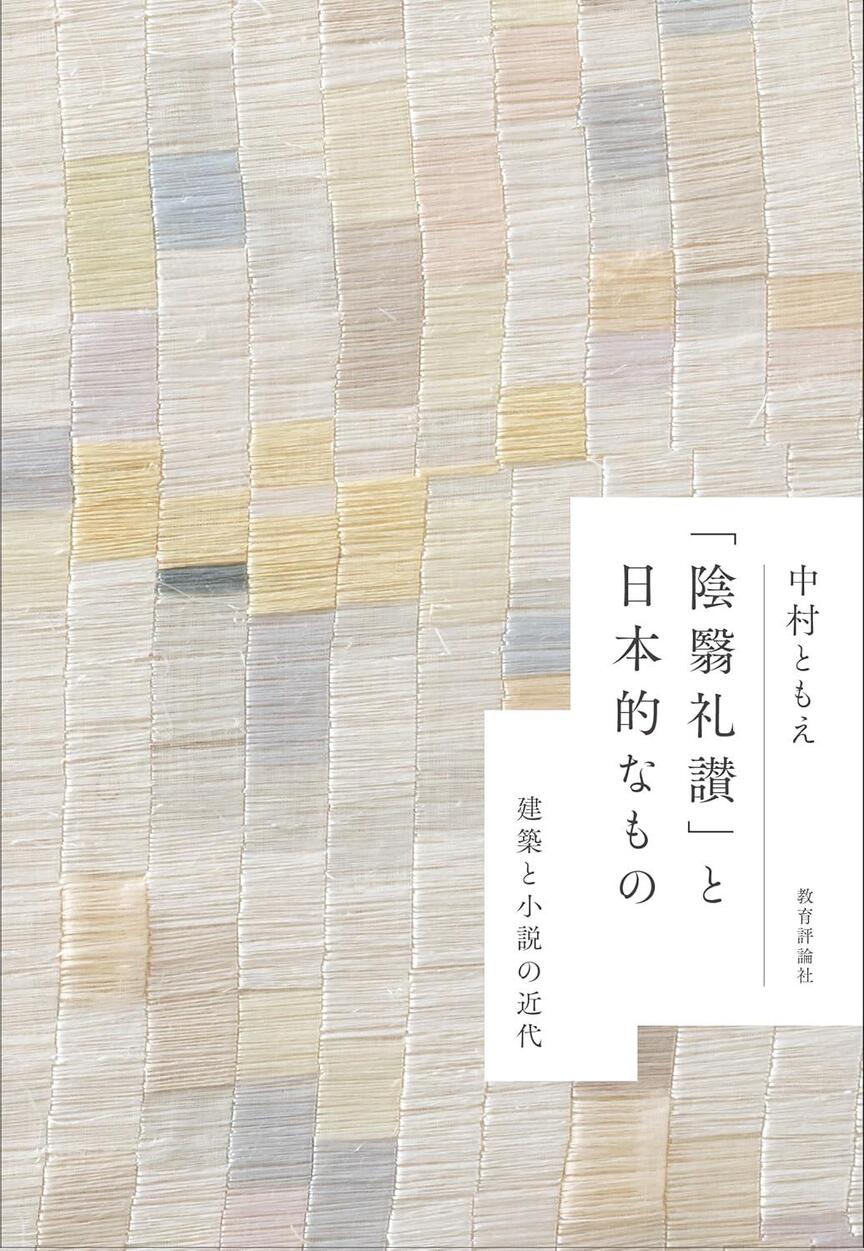
「陰翳礼讃」は言わずもがな、谷崎潤一郎が著した日本文化論である。しかし、「陰翳礼讃」を直接に論じた箇所は序章と終章のみで、谷崎ファンが本書を手に取ったら肩透かしを食らうかもしれない。1930年代に複数の作家たちが「建築を文学の修辞とすること」をした理由を分析するのが主な内容である。その代表的な文章として、議論全体の枠組を提示する役割を担っているのが「陰翳礼讃」論という位置づけだ。
1930年代の建築界では、世界の主流となった洋式建築をベースに「日本的なもの」の美意識を体現することが重要な課題とされていた。桂離宮を日本的美の象徴として称賛したブルーノ・タウトという触媒を経て、建築は「文化」をイメージ化する強力な比喩としてジャンルをこえて浸透したのである。1930年代には、「日本的なもの」(和洋の融合の美ではなく、洋の価値基準を取り入れた上でのオリジナリティ)の探究においては先輩格の文学者のほうが、逆に「建築の隠喩」を積極的に取り入れるようにさえなった。ちなみに本書で分析される主要作品は、石川淳『白描』、坂口安吾「日本文化私論」、横光利一『旅愁』、谷崎潤一郎『細雪』などである。これら散文作品は、建築の言説と交わることで、何を表現しようとしていたのだろうか。
本書の各章は議論としては独立しているので、関心の高い所から好きに読んでも楽しめると思う。が、どの章も結論らしい結論が見当たらないと感じて、少々戸惑う読者もいるかもしれない。個人的には、説明なしに専門用語を濫用しないことを心掛けた文章であることに加え、当の作家の自覚も疑われるような曖昧なテーマにおいては尚更、むりやり新奇な主張で結論づける仕方よりも、随筆的な読みやすさを併せ持っているところに好感を覚えた。だが終章を読んだとき、このような感想は的外れなのではと思い直した。小説家が建築を比喩的に書き入れることの意味について、各章の議論を刺し貫いている主張が忽然と姿を現した気がしたからである。
前提として、1930年代の建築界において、「日本的なもの」の実装をめぐって大きく二つの主張が生じていたことを確認したい。一つは当時、「帝冠様式」に代表されるように、古建築のいかにも日本的な屋根を再現して洋式建築に被せること、いわば意匠の仮面によって「日本趣味」を実現する立場。他方、優れた日本家屋はもともとモダニズムが是とする簡素で合理的な美を具えており、その構造的エッセンス(精神)を近代建築の素材に最適の形で実現しようとする立場である。後者の美的意識を勢いづけるきっかけとなったのが1933年5月に来日し36年秋まで滞在したタウトの発言の数々と、それに便乗した日本の識者による建築論の広がりである。
しかし、1930年代も後半になると、「日本」風を仮装する擬古主義も、合理的な美の追究の中に「日本」を見失いかねないモダニズムも、「日本的なもの」を掴み取るには不十分なことが認識されていった。たとえ両派を弁証法的に超克するなどのレトリックの上で理想の建造物を建立しえても、それはリアルな実現性のない建築論的な産物である。この時期、小説家たちが「建築の隠喩」に俄に惹かれるようになったのは、本来実体あるべき建築だからこそ、そのような〈実体化を拒む美〉の輪郭をかえって強く示しえたからではないだろうか。他の芸術に比べて最もイリュージョン度の低い建築という生活文化的リアリズムと最も観念性の高い言語芸術との出会いの意味は、おそらくこの逆説にある。
ひとつ例をあげよう。坂口安吾の「日本文化私論」は、タウトが評価した桂離宮の「日本」のイメージをひっくり返し、小菅刑務所、ドライアイスの工場、軍艦といった必要の美を持ち上げる露悪的な主張で知られている。著者によれば、安吾がいう「日本的」な美はそうした個々のモノを指していない。それは近代化によって喪失した伝統への「郷愁」を経験することで、はじめて欠如態として現われる「こと」としての情緒である。
そう考えると、改めてなぜ谷崎の「陰翳礼讃」論によって本書全体の議論がサンドイッチされているかがわかる。「陰翳」もまた実体ではない。明るさの欠如(翳り)という、逆説の言説によってのみ世界に同定されるものである。谷崎において「陰翳」が文章における「含蓄(ニュアンス)」の比喩ともなるのは、そのような実体のなさのためだ。そんな「ない状態」を可能にする「支持体」が、谷崎においては日本家屋という建築だった。逆にいえば、何もないところから明暗(陰翳)を作り出す容器としての建築なくして、欠如態としての暗がりは捉えられない。作家たちは、実体なき「日本的なもの」を取り扱い可能にするために建築の比喩を支持体として必要としたのである。
そして本書もまた、「陰翳礼讃」論がまさに支持体として機能する作りをしている。終章に至ってそのことに思い当たったとき、本書が主張することの陰翳の綾が浮かび上がってきた。先にランダムに読んでもいいのではと述べたが、その意味では、ぜひ、順繰りに最後まで読んでほしい書である。
(坂口周)