映画が恋したフロイト
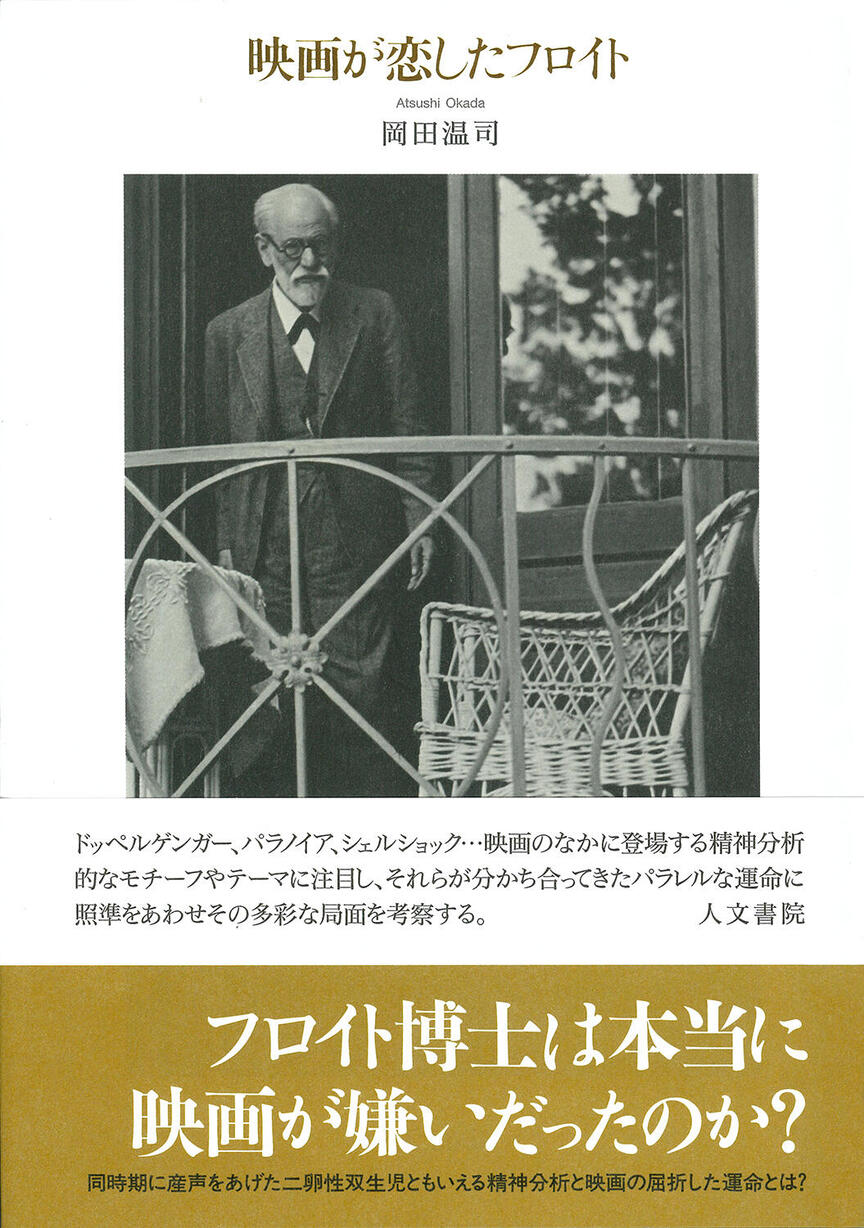
仮に『フロイトが恋した映画』という本があったなら、それは「映画嫌い」と言われる精神分析の始祖フロイト自身の映画観か、ラカン派・フェミニズムの映画論に代表されるような「精神分析は映画をどう読むか」という視点が採用されていたかもしれない。しかし、本書のタイトルは『映画が恋したフロイト』である。ここで主眼が置かれるのは、映画と精神分析の「両想い」(直接的な結びつき)というよりは、むしろすれ違う「片想い」(並行関係)である。すなわち、映画が惹かれ続けてきた精神分析的モチーフの系譜であり、著者が言うところの「精神分析と映画という二卵性双生児の屈折した運命」である。
映画はその創成期から夢や記憶の視覚化に挑み、サイコキラーや精神異常者をスクリーンに映し出してきた。新妻や夫が妄想に取り憑かれて心を病んでいく心理劇は「パラノイア女性映画」というジャンルを生み、屈折した母子関係、催眠や暗示、精神科医と患者、さらには戦場から帰還した兵士のトラウマ(シェルショック)も、映画の定番ネタとなった。本書は、主に1940-50年代のハリウッド作品を引き合いに出しながら、これらのテーマがどのように映像化され、定型化し、大衆文化の一部となっていったかを跡づけていく。
言及される数々の名作を私は必ずしも観てはいないのだが、著者はポイントとなる場面を要領良く叙述しており、映画史の専門家でなくとも想像を働かせながら読み進められる。また、複数の章にまたがって導きの糸の役割を果たしているのがアルフレッド・ヒッチコックである。彼の手がけたサイコホラーやサスペンスが、映画史と精神分析の受容史のどこに位置づけられるのかという観点から読むことも可能だろう。
本書は、著者が2015年以降に刊行してきた映画論の新たな成果であると同時に、2008年の『フロイトのイタリア』に続く2回目の「フロイトもの」でもある。著者のフロイトへのアプローチは常に迂回的だ。前書ではイタリアを介して、今回は「映画の側からの片想い」というユニークな視点を通じてである。行きたいと願いながらもなかなかローマに辿り着けなかったフロイトの姿を重ね合わせるとき、そこには確かに「フロイト的映画論」と呼ぶにふさわしい身振りが浮かび上がってくる。
(古川真宏)