存在論のフロンティア 自然・技術・形而上学
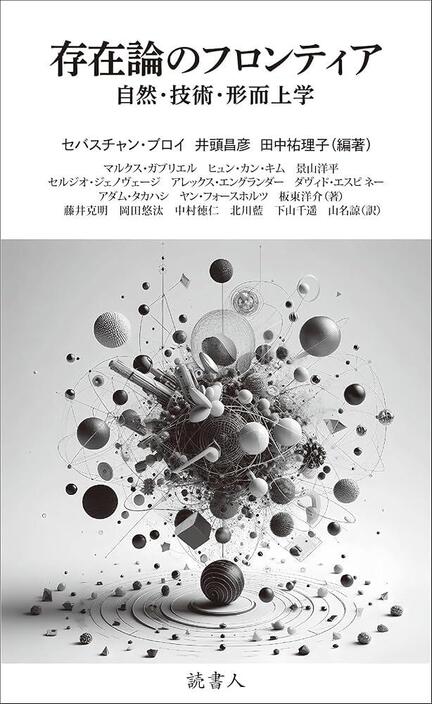
「「アンソロジー」(「花集め」)という複合語は西欧的な伝統に由来していることは否定できないが、その言葉がもつ精神は多くの形態をとりうるものであり、一つの特定の立場を反映するものではない」。本書の筆頭編者セバスチャン・ブロイ氏による「序論」に、このような印象的な一節がある(p. xviii)。
本書は、ブロイ氏とボン大学のマルクス・ガブリエル氏を中心に企画され、2019年にボン大学国際哲学センターで開催されたワークショップNature, Technology, Metaphysicsからの産物である。両氏の声がけによって「ドイツ側」と「日本側」から多様な「専門領域」に属する哲学研究者が集まり、2日間にわたって「自然・技術・形而上学」を論じた。それは「日本側」の参加者だけに限っても、互いに「分野違い」(たとえば「東洋哲学」と「西洋哲学」、または「英米哲学」と「大陸哲学」)としてあまり接触の機会もなかった者たちが、ただ「哲学」の一点を足場に対話できた、とても面白い場面だった。
本書の12本の論稿は「Ⅰ技術と存在論」・「Ⅱ技術と生命の倫理学」・「Ⅲ自然の概念と「私たち自身」の歴史的存在論」の三部に配置され、現在の世界を生きる「人間」とその「人間」が生み出す技術という存在、その二者の間を循環し続ける相互規定と変容の経験を論じている。つまり上述の対話からあらためて浮かび上がった共有の問いとして「ではそこで存在はどのようなものとなるのか」、「そのとき人間の生とは」、「そのとき人間の知とは」があり、それらの問いに向かうためにハイデガーやサルトル、コイレや荻生徂徠らの思考の現在性が──おそらくまさに「多くの形態」として──本書では再検討されている。この対話がより広く続けられるものとなるよう、微力ながら模索していきたい。
(田中祐理子)