文学理論の名著50
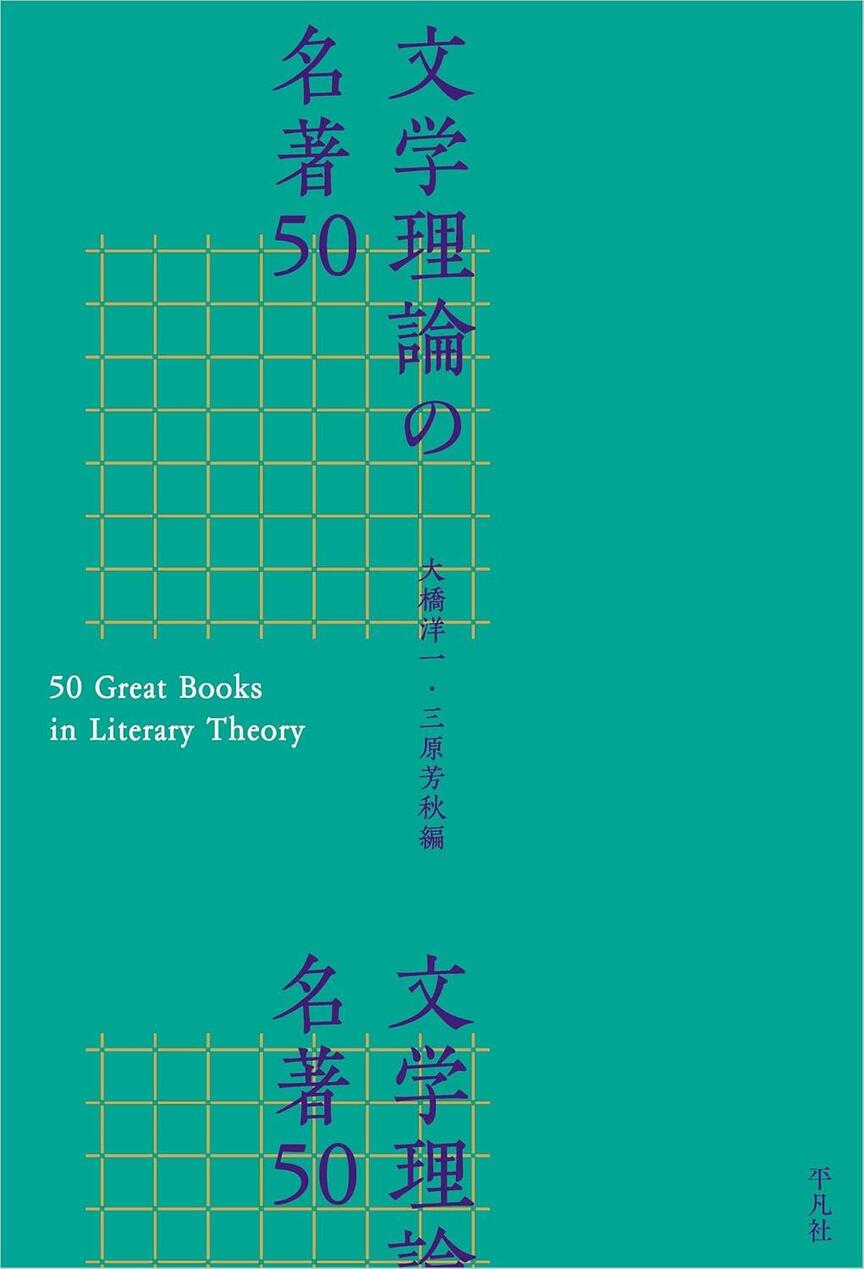
平凡社が四半世紀前に企画した「名著50」シリーズの「文学理論」が「周回遅れ」でようやっと読者の手元に到達した。「名著」の選書はなんら規範性をもつものではなく、「新たなスタンダード」といったよくある標語を掲げるものでもない。むしろ、「編者あとがき」の以下のような開き直りを多とするような読者を期待したい──「「●●年代の○○批評/理論を代表する作品」といった一般性によってではなく、(大橋先生による「はじめに」の言葉を借りれば)「そのどれもが、私たちの文学の読み方を根底から変えた」という単独性によって、それぞれの「名著」が読まれることが期待されるのである。つまり、本書が提示する「名著50」は「1+1+1+・・・」であって、その和が「50」であることに根拠はないのだ。むしろ読者のみなさんが本書の企てに参加し、この「50」の先に「+1+1・・・」と各自で足し算していくことによって、「文学理論」はその潜勢力(あるいは、ベンヤミン的比喩を用いるなら、「砕かれた器」の潜在的な全体性)をあかるみにだすことになるであろうと信じたい。ふたたび「はじめに」の表現を借りれば、「文学の読み方を変えた50人」を51人、52人とふやしていって、ついには自分自身をその戦列にくわえていくといった読みこそが、「文学理論」の「存える生(Überleben)」をたしかなものとするだろう」。
(三原芳秋)