| 座談会 | ページ1 |
|---|
学会誌『表象』刊行記念座談会
「新しいアソシエーションの形をもとめて」
| 桑野 隆(早稲田大学) | 中島隆博(東京大学) |
| 門林岳史(日本学術振興会特別研究員) | 宮崎裕助(日本学術振興会特別研究員) |
| 佐藤良明(広報委員会=司会) | |
佐藤 表象文化論学会は2005年度から準備段階の活動を始めて、シンポジウムやパネル発表といった活動を経てきたわけですが、今回学会誌『表象』の創刊にこぎつけました。これによって、いままで手探りでやってきたわたしたちの活動が、目に見える形象として構造化されたというか、その構成を一目で見られるブツとして手にとって眺められるようになったという印象ないし感慨があります。この機会に、わたしたちの学会自体のありかたも含めて、少々の議論ができたらと思って、きょうは編集委員のうち4名のかたに集まっていただきました。
桑野 実際には企画をはじめとしてすべて、若い人たちが中心になって作った学会誌なんですが、まずは私からお話ししましょう。「編集後記」にも書きましたが、『表象』は、会員の方に論文発表の場を提供するとともに、会員以外の方にも広く読まれるような雑誌でありたいというのが、当初からの方針であり、また期待でもあったわけです。こうやって、できあがった中身を見てみますと──また書店での売れ行きなどを聞いても──そのねらいが、かなりいい線で実現しつつあるんじゃないかと思っています。
また、今回組んだ「特集」ですが、新しい学会の創刊号としてきわめて重要な意味を持つようなテーマを正面切って掲げました。その中身も、学会外の方にずいぶんご協力いただいたおかげで充実したものになっていると思います。これは会員だけではとてもできなかったことで、ご努力いただいた方々に深く感謝している次第です。
佐藤 その特集ですが、表象文化論の立ち位置を宣言するような企画が組まれていますね。内容的に構成的にも、うまくデザインされているなあという印象なんですが、こういう形で結実した背後に、みなさんのどんな企てがあったのか、準備段階からのお話しを具体的に聞かせてくれませんか。
門林 この学会は2005年の秋に準備大会にこぎつけたわけですが、それに向けて戦略を練る段階から僕は関わらせていただいていて、幸運なことに、学会誌ができあがるところまで見届けることができました。当初から学会作りに関わっていた人たちが共有していた問題意識は、人文系の学会をどう再定義するかということだったと捉えています。
表象文化論というのは、もともとは、東京大学の駒場キャンパスの一研究室の名前だったわけですから、われわれが人文系学会を再定義するというのは、すごく不遜なことにも聞こえるでしょう。ですが、準備大会も、翌年の第1回大会も、それなりに華々しい成果を上げ、それなりの社会的注目を集めているということが実感できたなかで、それをどういうふうに学会誌という形にもっていくかという課題がのしかかってきた。つまり、この新しい学会をパブリッシュするための、ふわさしい形の模索をしていた。そんな折に、これは偶然ですが、たとえば『VOL』とか『RATIO』とかいった──それに『SITE ZERO/ZERO SITE』も出ましたね──新しい批評誌の創刊が相次いで、僕たちとしても自然と、これら話題の人文誌との比較においてみずからの構想を練っていきました。パブリッシュの形態にもいろんな可能性があり得ましたが、最終的には月曜社さんに販売元になっていただき、本屋さんに並べる、という比較的古典的なかたちにまとまった、という経緯です。
これは学会誌ですから、学会のなかでなされている研究活動が基盤になることはもちろんですが、そのうえで、いわゆる商業誌で展開されている批評活動とどういう距離をとるかということを考えたときに、その両者を別のものと考えるのでなく、できればうまく重ね合わせていきたいと考えました。これは表象文化論という場が、元来、商業誌での批評活動と近い位置にあったという歴史的な経緯もあってのことですけど。
商業誌でなされている「批評」と、大学のなかでなされている「研究」とは、 両者の間に実質的なリンクがあるにも関わらず、それぞれ別のところでやられているかのように長らく信じられてきた。そういう状況がネガティブに働いて、人文的な知を苦況に追いやってきたという経緯があるんじゃないか思うんです。それを打ち破るには、大学の研究自体を批評としてパブリッシュしていく方向を積極的に考えていかないといけないだろうと考えました。
言い換えれば、大学でやっている研究が──少なくとも人文研究に限って言えば──批評としての価値をもつように構想されていかなくてはならないし、他方では、いわゆる商業的なベースにのった批評活動も、よくよく考えてみるとそちらの世界で自律して存続しているわけではなく、いろんな側面で大学組織に依存している現状がある。学会誌が同時に批評誌としての顔ももって書店に流通する、その流れを作ることこそが、人文知をどのように再定義するかという、最初にお話ししたことを具現化するための一つのモデルケースになるのだと、そう考えて僕たちはやってきたんです。
佐藤 大学を中心にある種の、何というか「利権」みたいなものを守るべく作られている諸学会がどれもこれも閉鎖性に陥っている、そのいらだちを抱えて過去に飛び出した勇者たちの系譜というのが、日本の批評空間──70年代の『現代思想』以来の──を作ってきたと思うんですが、そうした運動が、いままた新しい世代を得て『表象』という名の下にふたたび盛り上がろうとしているということだと、僕は理解していますけど。
宮崎 誌面づくりの最初の案はすごくシンプルで、05年の準備大会と06年の創設大会でやったシンポジウムをそのまま取り込むという発想でした。「表象文化論」という名称は、いまでは聞き慣れないものではなく、学科や講座の名称としては全国のいろんな大学で使われるようになってきているんですが、学問的実体というか、どんな活動をするところなのかという最低限のコンセンサスすらないままに、なんとなく進行しているという状況がある。その一方で、「表象文化論」と聞いたときに、東大駒場キャンパスに過剰に結びつけられる傾向がいまもあると思います。過去には『ルプレザンタシオン』という雑誌を筑摩書房から出していたとか、講座『表象のディスクール』を編纂していたとか、たしかに過去の出版活動は「駒場の表象」でやっていたわけですね。そんなこともあって、「表象文化論」というと少なくとも出版やメディアのレベルでは駒場に過剰に結びつけられる面が大きくて、にもかかわらず名称としては全国に広がっている、そうした乖離を埋めることが、まずは自分たちの任務なのだろうと考えました。
それにはやはり学際性ということを考え直していかなくてはならない。表象文化論というのは学際性を謳うのには便利な名称なんですが、表象文化論に限らず、いまでは学際性自体があまりに安易に語られるようになってしまった。新奇な名前ばかりが氾濫して実質が伴わないという唯名論的な状況が大学制度のいたるところに見出されるわけです。では、表象文化論は何をすることから始めればいいのか。表象文化論という括りの内部に、これまでもイメージ分析や視覚文化論といったかたちで、特定の同業研究者の集まりの場はできていたんですが、もっと横断的な、人文知をそのまま見据えるようなところに表象文化論の一番基本的なコンセンサスがあったはずで、まずはそれを問い直すことから始めよう、と。そのことに応答しようとする気持ちをみんな持っていたということが、このような企画として実現したということなんだと思います。要するに「表象文化論」という名称は、人文知のミニマル・コンセンサスを探るための触媒のようなものとして活用できる。

会場風景
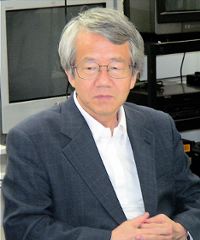
桑野 隆

門林 岳史