世界の終わりの後で 黙示録的理性批判
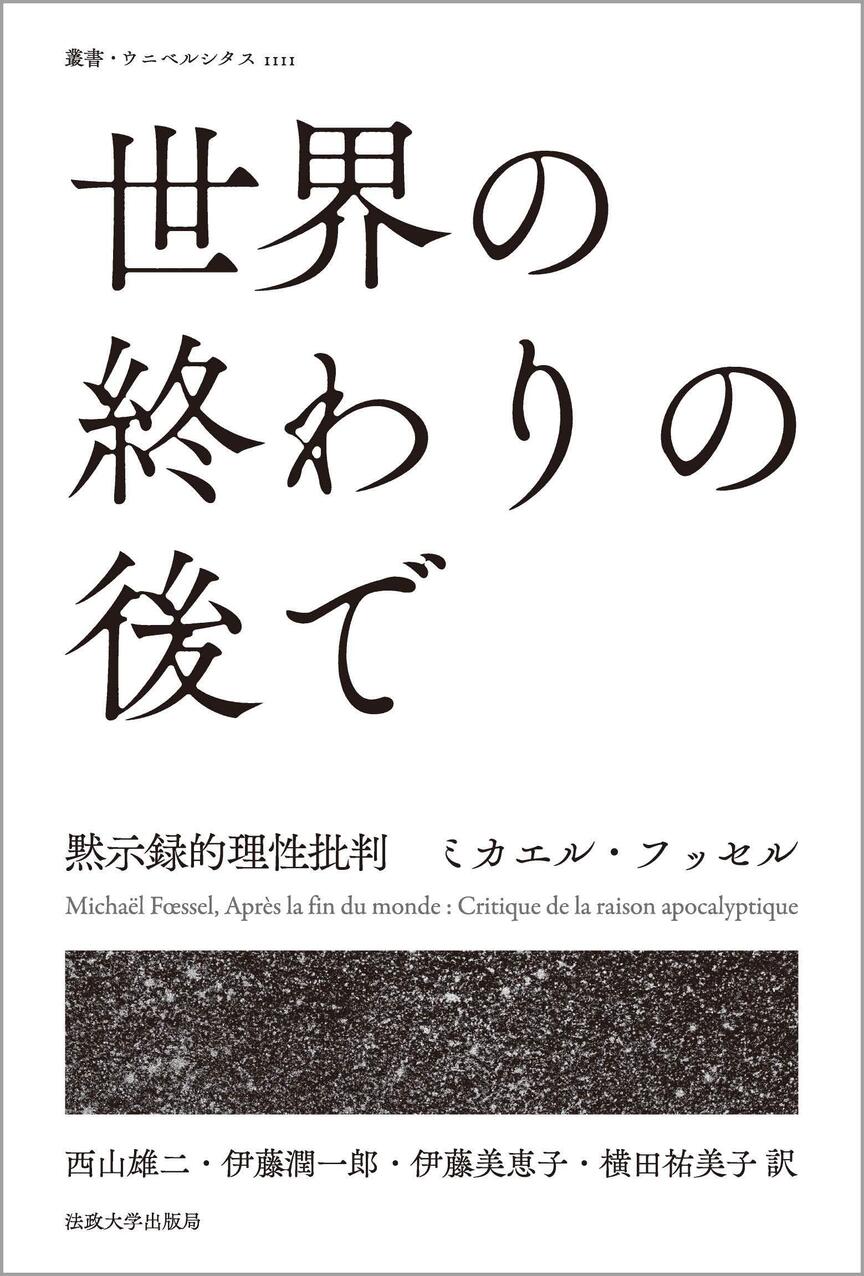
経済か生か──コロナ禍の現在、多くの思考がこの二者択一にはまり込んでいる。あたかも、経済を止めないようにすることと感染のリスクを避けることはアンチノミーであるかのように。しかし、ひょっとすると、そこで見えなくなっているのは世界なのかもしれない。経済を回すために必死になることも、生の保存を至上命題として生き延びに汲々とすることも、世界がそもそも不確定な場であることから目をそらすことなのかもしれない。
本書『世界の終わりの後で』の前半は、意味の秩序としての世界(「コスモス」)の崩壊に直面した近代において、いかなる思考が生まれたかを歴史的に検討している。そこで明らかにされるように、不確定で偶然的なものとなった世界を前にして、ときに近代の人々は自らの手で作り出した秩序に沿って生を導くことで偶然性を排し、またときには精神や生といった世界とは異なる場を探し求め、またあるときには世界の偶然性を世界の可能性と捉え返した。こうした類型化は、経済か生かという袋小路にはまり込んだ現状を俯瞰する視座を与えてくれるだろう。
むろん、本書の原書が出版されたのは2012年のことであり、コロナ禍が直接論じられているわけではない。けれども、次のような文言に出会うとき、本書が現在の私たちについて語っているかのような錯覚に陥らざるをえない。「各人が「免疫をもつ」ために十分な距離を確立するための配置は、〔……〕世界市民性の理念を無に帰してしまう相互不信の気風を帯びている」。
それゆえ、本書の後半で「相互不信」に抗して提示されるコスモポリタニズムに、現在の状況を打開する手がかりを見出したいと思うとしても無理からぬことだろう。ここでのコスモポリタニズムとは、簡潔に言えば、主体が世界の別のあり方を創設する可能性のことだ。世界の終わりとともに真の世界が訪れることを願う宗教的なアポカリプスでも、意味を充填してくれる何か(経済であれ生であれ)を信じることで世界の偶然性から顔を背けるのでもなく、世界が不確定であるからこそ、世界と人間の座標軸をともに転換する可能性を私たちが分かち合っているという経験から出発すること、これがフッセルの提示するコスモポリタニズムにほかならない。
カントと現象学の航跡を辿ることで明らかになるこうした見通しの成否については、私たち一人一人が考えていかなければならないが、少なくとも問うべきは、この世界のなかで別様な世界をつくる可能性を人間がもっているということは、一体いかにして示されるのかということだろう。フッセルは、カントが語る「進歩」を取り上げ、それが世界の不確定さを引き受けたうえでなお人間に可能なことがあることを知らしめる概念であるとし、これを「慰めのカテゴリー」と呼んでいる。私たちは、何らかの「慰め」がなければ、世界の不確定さを引き受けることなどできないのかもしれない。もしそうだとすれば、コロナ禍において何が「慰め」となりうるのだろうか。この「慰め」という概念の両義性にこそ、コスモポリタニズムの成否と、パンデミックから気候変動まで「世界の終わり」のイメージに取り憑かれた私たちの現在を思考する鍵があるだろう。
(伊藤潤一郎)