東欧文学の多言語的トポス
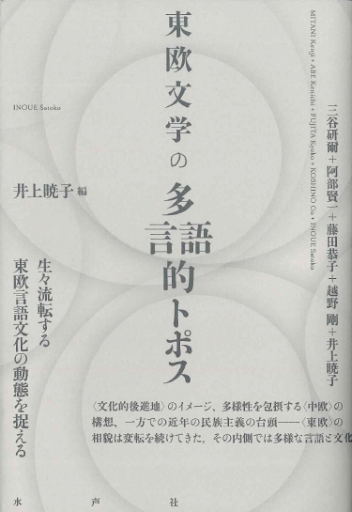
東欧をめぐる言説は多種多様なものがあるが、本書は「ゲルマン・ユダヤ・スラヴ文化の混成地域」という特性に依拠しつつ、「様々なずれ」を内包しながら発展してきた点に着目する。それは、国境線と言語境界線のずれであったり、国民と民族のずれであったりするが、その差異は「文化闘争のフロンティア」を引き起こす。様々なずれを有する社会においては、自らの正当性(正統性)を言語によって証明することがつねに求められるからである。2018年10月6日、東京大学本郷キャンパスで行われたシンポジウム「東欧文学の多言語的トポス 複数言語使用地域の創作をめぐる求心力と遠心力」の報告原稿5編からなる本書は、まさにこのような「ずれ」に焦点を当てた論考集である。
言語表現における「ずれ」は、しばしば「文学史」という場で議論がなされる。本書の第一部「地域文学史の記述」で扱われているのが、ボヘミアを舞台にした文学史の諸相である。文学史の記述単位は言語中心的なものとなるか、地域中心的なものとなるかでその性質が異なるが、そのずれが多層的に生じていたのがボヘミアという地であった。いうまでもなく、19世紀の「民族復興」という流れにおいて、チェコ語の共同体が躍進する一方、20世紀に入るとプラハのドイツ語話者は他地域へ流出する。ある意味で東欧の多言語的なトポスを代表する場である。東欧のある種の記号として位置付けられるのがフランツ・カフカであろう。ユダヤ系の出自を有し、プラハで生まれ、ドイツ語で執筆するカフカという存在そのものが文学史記述に問いを投げかけているからである。
三谷研爾は、そのカフカを出発点として、「プラハのドイツ(語)文学」という用語が成立・流通した経緯を検証する。同概念を1960年代に提唱したのはゴルトシュテュカーであったが、それは「ズデーテン地方のドイツ国粋主義に対置するかたちで仮構されたもの」として、近年ヴァインベルクとクラップマンは批判を加えている。都市プラハを相対化し、広域的なエリアとしてのボヘミアの捉え直しを試みるのだが、その際、ヴァインベルク、クラップマンが着目するのが「チェコ語文学」との関係であり、「地域の異質性」である。つまり、従来の地域文学史がある種の等質性を前提にしてきたのとは正反対の視座である。
次いで、阿部賢一は、プラハ学派、とりわけフェリクス・ヴォジチカの文学史理論とナードラーのドイツ文学史の記述の対称的、場合によっては相補的な関係に着目する。前者が言語の機能を重視する姿勢を取ったのに対し、後者が「種族」という枠組みを重視するという正反対のアプローチがほぼ同時代のプラハで生まれている。直接的な影響関係だけではなく、アンチテーゼとしての影響関係も視野に入れて研究を進めることが今後推奨される。
文学史記述における「ずれ」は同一の空間だけではなく、都市と地方のあいだといった空間的なずれの問題とも関連する。様々な資本とインフラが蓄積されている都市と、そうではない地方との関係性において、情報やイメージはどのように流通し、ネットワークが構築されたのか。またそのような状況において、文学はどのような表現を獲得したのか。第二部「「中心/周縁」モデルを超えて」では、このような問いを起点にして「地域内に存在する雑種的なもの」に光を当て、ブコヴィナ、極東/ベラルーシ、シレジアという三つの場が検討される。
藤田恭子は、ルーマニア領ブコヴィナのユダヤ系ドイツ語詩人を扱った論考で、詩人マルグル=シュペルバー(1898-1967)が1930年代前半の自分たちの状況を「四重の悲劇」と呼んでいた事例を紹介する。それは、第一に詩人であること、第二にユダヤ人であること、第三にブコヴィナでドイツ語で執筆していること、第四にブコヴィナに住んでいることの四点である。換言すれば、いずれも主流ではない、「周縁」であるという強い認識である。その際、詩人が参照するのは「故郷の風景」であり、ゲーテに通じる「原像Urbild」という概念だった。自然の制約を通して普遍性を探求する姿勢は、自らの位置を確認すると同時にゲーテとの関係性を構築する興味深いアプローチとなっている。
越野剛は、極東のウラジオストクとベラルーシというロシア文学の二つのオリエントを取り上げ、異文化の想像の事例を検証する。ムトフチイスカヤの『ミリオンカ、シー』(2009/2016)は、ウラジオストクを舞台にした冒険小説で、ロシア、中国、朝鮮、日本からの移民の子供が、海賊の財宝を狙う満州馬賊の襲撃に巻き込まれ、ミリオンカの地下では古代渤海帝国の秘密都市が隠されていたという設定である。それに対し、マルツィノヴィチの『墨瓦』(2014)は、ロシアと中国の連合国家によって支配され、言語と文化を失った近未来のベラルーシという設定である。全く異なる地域の作品であるにもかかわらず、ともに都市の中に中華街があり、その地下には滅んだはずの言語文化を有する都市が隠れているという点が共通しているのは極めて示唆的である。
井上暁子は、「経済的文化的後進地域」というレッテルを貼られた上シレジアのイメージについて、ドイツ語文学とポーランド語文学の双方から検討を試みている。具体的には、ハンス・ノヴァク、ゲオルグ・ツィヴィア共著によるドイツ語小説『亜鉛は金になる』(1937)とグスタフ・モルチネクによるポーランド語小説『ヨアンナ坑』(1950)の二作品における「精霊」、「鉄道」、さらに「多言語性」という三つのモチーフの比較分析が行われている。なかでも、興味を惹くのが、後者の作品中、フランス人鉱夫のフランス語とポーランド語、あるいは標準ポーランド語と方言が混在し、「人々や土地の暮らしに息づく「ことば」の中に、幾重にも折り重なる層」が確認できる点であり、論者はそこに「既存の言語的ヒエラルキーを転覆させる可能性」を読み取っている。
このように、本書に収録された五本の論考は、それぞれ対象としている地域や時代は異なるが、東欧の文学を題材にし、そこでの「ずれ」の力学を浮かび上がらせている。もちろん、本書は、東欧全域にわたる包括的な論考集ではない。だが、空間、言説の「ずれ」が「多言語性」、「雑種性」とも連結していること、さらにはこの地の研究においてはゲルマン系、スラヴ系の研究者の共同作業が不可欠であることを明らかにしている意義は大きいように思われる。
(阿部賢一)