眼がスクリーンになるとき ゼロから読むドゥルーズ『シネマ』
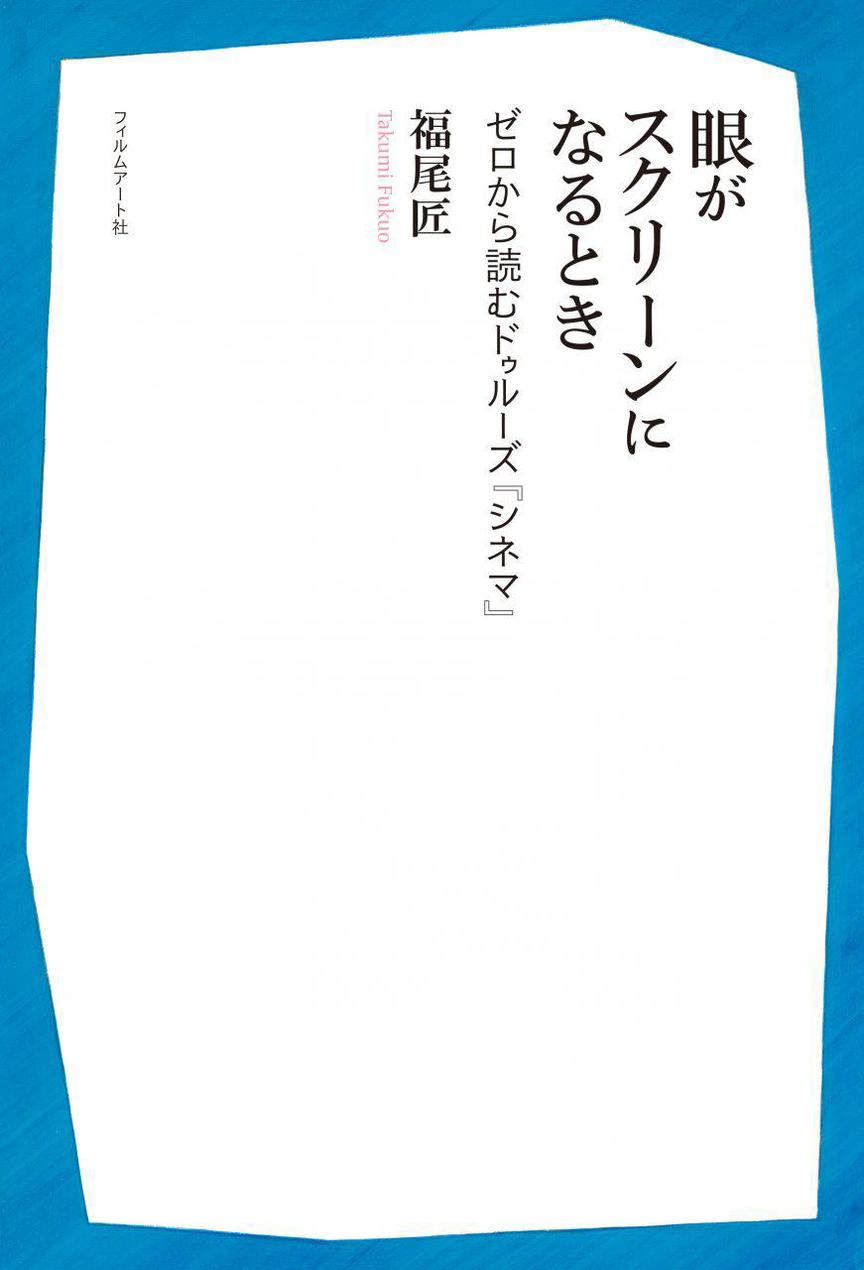
本書は、ジル・ドゥルーズの映画論『シネマ』を論じた著作である。「ゼロから読む」とある通り、『シネマ』の「入門的な解説書」として書かれているものの、本書の射程はそれにとどまるものではない。「ゼロから読む」という言葉には、イメージが「見たまま=リテラル」に現れる『シネマ』の「ゼロ地点」という意味も込められており、本書は「ゼロ地点」から『シネマ』という著作を見渡そうとする、ラディカルな再読の試みにもなっているのだ。
そうした試みを遂行するにあたって著者が取った大胆な戦略の一つが、「映画作家についても、作品についても、可能な限り一切の言及をしない」ことであった。膨大な作品への言及は『シネマ』という著作の魅力をなしているのは疑いえないが、それらの言及がともすれば、シネフィルでない読者を遠ざけ、体系的な理解を妨げかねないのも事実だろう。本書は、そうした個別の作家、作品への言及を放棄し、またドゥルーズによる章立てにも拘らぬことで、『シネマ』という著作の原理とそのポテンシャルを十全に解き放とうとするのである。その潔さと鮮やかさは称賛と嫉妬に値する(私はついつい作品への言及と原理とがどこまで分離可能なのかと考えてしまう)。
そうして映画作家、作品名が姿を消す一方で、質量ともに圧倒的な言及の対象となるのがアンリ・ベルクソンである。ベルクソンが「もののたとえ」としてフィギュラティヴに言ったことを「文字通り=リテラル」に受け止めるなかで、いかにドゥルーズがベルクソンから「逸脱」してゆくかを丹念に炙り出してゆくところは、はっとさせる指摘のオンパレードで、じつにスリリングである。なかでもドゥルーズの「物の知覚」とベルクソンの「純粋知覚」とのあいだのズレを浮かび上がらせつつ、そこを端緒に『シネマ』全体のロジックを浮かび上がらせてゆく部分は、オリジナルで刺激的な見解に満ちた本書の白眉であるだろう。ぜひご一読頂きたい。ああ、もう一度『シネマ』を読み直さねば!
(角井誠)