『ハッピーアワー』論
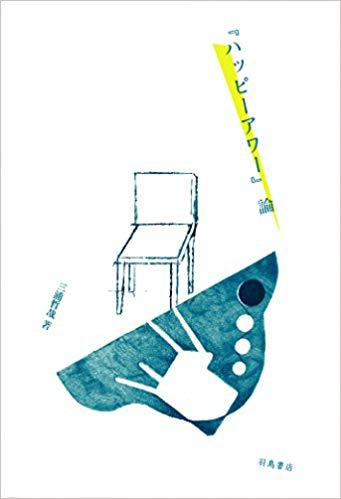
とにかくおもしろい。
「濱口竜介は、果たして映画の救世主なのか、それとも破壊者なのか」(23頁)という黒沢清の問いが全体にひびく。それはいいかえれば、「映画は人間関係を撮ることができるのか」という問いだ。
本書によれば、濱口の映画『ハッピーアワー』(2015)は、人間関係を「重心」の劇として具体化する。一本の映画をみたす重心の動揺を、著者はたしかな視線と言葉で分けていく。
急がず遅れず、速やかで厚みを失わない言葉の的確さがすごい。とりわけ人間の関係を言葉にするときの確かさにはぞっとさせられる。
たとえば、温泉旅館での「あかり」と「純」の真正面からの切り返しについて。「このように画面が連鎖するとき、純とあかりはまるで、二人だけの空間へと浮遊し、互いの視線だけによって支え合っているようにさえ感じられる。[……]「はじめまして」と言い合う二人を正面構図の対として示すとき、この「幸福」な均衡状態は最も純粋なものとなる」(53-54頁)。つづけてフェリーで発つ「純」と見送る「大紀」について。「陸側から純を撮り、船側から大紀を撮ったこのシークエンスは、「はじめまして」の場面と同様の、さらにさかのぼれば「正中線」を合わせるワークと同様の、正面構図の切り返しによって構成されている。二人のあいだ──陸と海のあいだに「重心」が生じ、それを互いに感知しあう「幸福な時間」が生きられ、去り際の残光のように強烈な余韻を残すのだ」(56頁)。このような適切さで、容易には言葉にできない画面の「意味」が、短く(短すぎず)言い当てられていく。
明瞭な文のひとつひとつは、読む者の目と体をみがき、映画にむけてひらく。そこに、自分とはなにか、人間関係における倫理とはなにか、という問いが、日常的かつ具体的に体感される。
巻末の「『ハッピーアワー』のあとに見たい映画リスト」も溌剌とした観察にみちている。装幀は、椅子の「重心」の傾きを静かにつたえてうつくしい。
(平倉圭)