| トピックス | 1 |
|---|
第5回表象文化論学会賞受賞
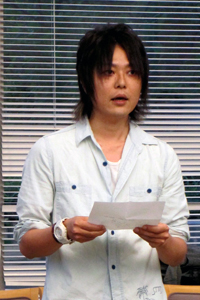
学会賞
千葉雅也『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社、2013年10月)
受賞の言葉
このたびは、拙著『動きすぎてはいけない』を表象文化論学会賞に選出していただき、誠にありがとうございます。刊行からそろそろ一年になるところですが、おかげさまで多くの読者に恵まれ、様々なご感想も拝見しており、大学院時代のドゥルーズ研究を総合したこの一冊が、あちこちで議論の叩き台になっていることを耳にするにつけ、さらなる勉学の意欲を新たにしております。
拙著のタイトルは、ドゥルーズのインタビュー集『記号と事件』での「生成変化を乱したくなければ、動きすぎてはいけない」という発言に対応するもので、ここに見られる「〜しすぎない」という表現、その「度合い」と「節約」の問題に注目するのだ、ということを宣言しているタイトルです。
哲学史的に言えば、ドゥルーズの背景のうちでベルクソン主義よりもヒューム主義に重心を置く、というのが拙著の特徴であり、また、ラカン派の精神分析の再解釈や、メイヤスーらの思弁的転回への接近など、要素は色々ですけれども、通底する執筆精神は、あの「〜しすぎない」という表現・言表をマスターキーとする「一点突破」だと言えるように思います。この方法こそ、東京大学の表象文化論コースで身につけた方法に他なりません。
学部から修士にかけてお世話になった中島隆博先生のご指導は、テクストの「固有語法・イディオム」を探しなさい、既成の理論の枠組みから逸脱するそれを追いかけなさい、というものでした。そこから発して理論の枠組みを(生成)変化させざるをえなくなるような、そういうイディオムはこれなのだと思い至るまで目を皿にして精読せよ、と。
博士課程においてご指導をいただいた小林康夫先生は、対象の「特異点」という言い方をされていました。小林先生の授業では、毎回の課題として芸術作品やテクストを掲げ、参加者に高速なブレインストーミングをさせ、様々に可能な特異点のあぶり出しを試みるというものでした。対象には真の特異点が唯一あるのではなく、アプローチの「別のしかた」によって異なる特異点が「仮固定」されるのだという、私にとって基本的な研究/批評の前提は、小林先生の緊張感あふれる「道場」によって鍛えられました。
こうした「イディオム分析・特異点分析」は、いわゆる「テーマ主義」と、それをふまえた「脱構築」のヴァリアントであり、私が学恩を受けた多くの方々に、ゆるやかに共通する方法であったと思います。
『動きすぎてはいけない』は、私なりに継承したつもりであるイディオム分析・特異点分析の一事例であり、従来のドゥルーズ研究において必ずしも前面に位置していたわけではなかったイディオム・特異点を、誇張的なしかたでクロースアップするという方法で書かれています。さらに言えば、哲学史的に「正嫡」であるような概念よりも、細かな「修辞・レトリック」のふるまいに執着し、それによって哲学史読解を(生成)変化させる、という方法です。
私はこれまで自分の専門を「哲学/表象文化論」と二重の表記をもって任じてきましたが、最近、狭義のディシプリンは何かというとそれは「修辞学」ではないのかと思うときがあります。私には、表現の形の違いはともかく言いたい内容が大事、というのではなく、些細な形の違いにこそ本質を従属させてしまう、という倒錯的な視点に倒錯的な喜びを感じるところがあるのです。拙著が、哲学研究であると同時に、というかそのことに勝って、倒錯的な修辞学の実験として読まれるならば、それ以上の(倒錯的な)喜びはありません。

奨励賞
田中祐理子『科学と表象──「病原菌」の歴史』 (名古屋大学出版会、2013年4月)
受賞の言葉
このたびは拙著に学会奨励賞を賜りまして、心よりありがたく御礼申しあげます。拙著は、一昨年末に主査・石光泰夫先生のご指導のもと、内野儀先生、金森修先生、田中純先生、橋本毅彦先生に審査をいただいた博士学位申請論文を本にしたものです。この学位論文を書きあげるまでには、昨今の大学ではなかなか難しいほど長い時間をかけてしまいました。学部生以来、個人的な関心にひかれるまま、医学史と思想史の狭間を歩くような我侭な研究課題を追いかけ続けたことを、厳しいご批正とともに、最後まで受け止めてくださった先生方にただ感謝する以外ありません。
そのような我侭な道を通ってきた者ではありますが、奉職し、真似事のようではあれ教育の仕事にも関わるようになると、しばしば同僚たちから、いかに「院生」というものが無礼であるか、特に社会人としても研究者としても、いかに「作法」を欠いた振舞いをするかについて、憤慨を聞かされるようになりました。そのたびに「それは私もやったことがある」と、身の縮む思いがします。「社会人としての作法」については紙幅が足りなくなるので措きますが、「研究者としての作法」という点に関して言えば、拙著は、個人が抱く何らかの問いや経験が一つの研究となるにはどのような「方法」と「かたち」が必要となるのかについて、文字通り手探りで求め続けた記録であるという気がしています。「もの」の周囲で、個人の知覚や認識が、いかにして「人間的知」というある共有の平面を形成することになりうるのか。誰とも知覚を共有しえない「変わり者」としてあり続けた人物から、知識というこの「共通の領土」をめぐる熾烈な争いを繰り広げた人間たちまで、恐らくは「科学的探究の一形式の展開に関する歴史的研究」とでも形容すべき本を書くための作業を通して、何とかその姿に接近しようと試みた対象たちから、私は個々の人間の経験と制度的知とのあいだに存在し続ける「関係」という物語を教えてもらいました。また同時に、その物語を読むための技術である「歴史研究」という方法それ自体の魅力についても、いくばくか学び始めたように思います。
繰り返しとなりますが、私はこの学びのために、本当に長い時間を使いました。今日の大学で、このような贅沢をゆるされたことは大変な幸運であったと痛感します。手探りで無作法な「研究」に迷走するばかりであった私の話に辛抱強くつきあってくださった石光先生と、そのような「研究」を本当に粗い段階から見守り、一冊の書物の形へとつながるまで導き続けてくださった名古屋大学出版会の橘宗吾さんに心から御礼申しあげます。そして、このように御礼を申しあげることのできる機会を与えていただけましたことに、深く感謝いたします。

奨励賞
杉山博昭『ルネサンスの聖史劇』(中央公論新社、2013年2月)
受賞の言葉
このたびは表象文化論学会賞奨励賞をいただき、たいへん光栄に存じます。選考委員の先生方の温かいコメントを拝聴いたしますと、この本はこれまで等閑視されてきた聖史劇というテーマの選択と、本邦初訳となる14本の上演時テクストの翻訳において評価していただけたようです。ただこれらは、かならずしもわたし個人の功績にのみ帰せられるわけではありません。
そもそもこの研究の端緒は、修士課程進学直後のころ、指導教員である岡田温司先生から「これを訳してみては」と見慣れない詩行を指し示された瞬間にありました。そのテクストこそ、この本にも収録した『ラザロの蘇生の聖史劇』でした。いまでこそ岡田先生の提案は、わたしの絵画史専攻の希望とわたしの小劇場観劇の趣味を止揚する、卓抜した身ぶりであったと理解できます。しかし当時のわたしには青天の霹靂でした。結局のところ、テーマ選択もテクスト翻訳も明確に外在的な契機に貫かれていたのです。
また当然のことながら、その後の研究も多くの方々のご助力あってのものであります。この本の元となった博士論文審査を担当してくださった篠原資明先生・桒山智成先生・黒岩卓先生、さらに出版に際してひとかたならぬお世話になった中央公論新社の郡司典夫氏とブックデザイン担当の細野綾子氏、専門外の内容であるにもかかわらず丹念に読んでくださった4人の選考委員の方々、この本の書評パネルで貴重なご意見をくださった松原知生先生・森元庸介先生、また「京都の翻訳工房」と呼ばれた某ゼミにて、忌憚の無い意見をぶつけてくれた先輩・後輩の皆様、そしてまずもって岡田先生に深くお礼申し上げる次第です。
謝辞を述べさせていただくべき方々のリストがほぼ無限に延びる一方、わたし個人の名前でこの賞をいただくことに戸惑いを覚えております。この違和感は、研究倫理の危機が叫ばれる昨今の情勢はもとより、さらにこの本のテーマそれ自体からフィードバックされたものかも知れません。そもそも聖史劇は上演時テクストの作者さえ不明であることが多く、まして各上演のキャストやスタッフとなるとその名前を追うことはほぼ不可能です。出来事の重みを固有名詞の網目で支えられないという状況は、歴史研究として小さくない障害であります。ただ9年前に『ラザロ』の開幕の天使に出会ってから、時折、無名性や匿名性のしなやかさとでも言うべき質感に触れられました。その柔らかい重みを後世に伝える幾ばくかの可能性を前にして、いまここでわたしにもできることと言えば、お世話になった方々の名前であらためて網を編むことではないかと思いました。皆様、このたびは、本当にありがとうございました。
特別賞
該当なし
(1)選考過程
2014年1月上旬から2月中旬まで、表象文化論学会ホームページおよび会員メーリングリストにて会員からの学会賞の推薦を募り、以下の作品が推薦された(著者名50音順。括弧内の数字は複数の推薦があった場合、その総数)。
【学会賞】
- 木村陽子『安部公房とはだれか』(笠間書院)
- 杉山博昭『ルネサンスの聖史劇』(中央公論新社)
- 田中祐理子『科学と表象──「病原菌」の歴史』(名古屋大学出版会)(2)
【奨励賞】
- 荒谷大輔『「経済」の哲学──ナルシスの危機を越えて』(せりか書房)
- 石田圭子『美学から政治へ──モダニズムの詩人とファシズム』(慶應義塾大学出版会)
- 木村陽子『安部公房とはだれか』(笠間書院)
- 杉山博昭『ルネサンスの聖史劇』(中央公論新社)
- 千葉雅也『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社)
【特別賞】
推薦なし
選考作業は、各選考委員がそれぞれの候補作について意見を述べたうえで、全員の討議によって各賞を決定していくという手順で進行した。学会賞については選考委員会の総意で、千葉雅也氏の著作に決定した。奨励賞については、最終的に候補に残った杉山博昭氏、田中祐理子氏の著作が甲乙つけがたいという判断により、これら2篇を選出することになった(なお、田中氏の著作は学会賞として、千葉氏の著作は奨励賞として推薦があったものであるが、選考委員会の判断により、すべての候補作を学会賞と奨励賞双方の候補とすることした)。
(2)選考委員コメント
内野儀
今回、学会賞・奨励賞の候補となった全六作について、簡単にコメントする。
わたし個人は、学会賞・奨励賞の区分は問わず、千葉雅也氏『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』、田中祐理子氏『「病原菌」の歴史──実在・表象・歴史性について』、杉山博明氏『ルネサンスの聖史劇』の三冊が候補になるだろうという予測のもとで、審査会にのぞんだが、他の三作が大きく劣るということではなく、それらも力作と評価できる。
まず、木村陽子氏の『安部公房とはだれか』だが、安部公房について、近年、日本語でまとまって論じられることはないという意味で貴重な出版である。ただ、学術的というよりジャーナリスティックな方法と記述であり、残念ながら、学会賞としてはふさわしくないと判断せざるをえなかった。
荒谷大輔氏の『「経済」の哲学──ナルシスの危機を越えて』は、「オイコノミア」からはじまって、「エコノミー」という語や概念について、歴史的に説き起こす第一章からはじまり、近代経済学の確立、そして主体概念における「経済」の問題と、議論は広範囲に及ぶ。そのかぎりにおいては興味深い本なのだが、「経済」の概念は当然、あまりに広すぎて、結局のところ、何が言いたいのかが判然としないという感じが最後まで残ることになった。
石田圭子氏の『美学から政治へ──モダニズムの詩人とファシズム』は、フーゴ・フォン・ホーフマンスタール、ゴッドフリート・ペン、T.E.ヒューム、エズラ・パウンド等とファシズムの関係をタイトル通り、丁重に論じた書物で、それぞれの詩人の作品や言説を通じて、ファシズムへの接近を跡づける方法や記述に、特に破綻はない。ドイツ語圏と英語圏を横断しているのも強みなのだが、正攻法すぎるという感じがどうしてもしてしまい、逆説的ではあるが、そこが本書の弱みになっているという印象である。
杉山博明氏の『ルネサンスの聖史劇』は、大部の本だが、聖史劇テクストの翻訳が占める割合が大きく、論考的な部分は233頁程度である。資料があまり残っていないイタリアの聖史劇について、先行研究を渉猟しながら、きわめて丁重に、それらを一方で総合しつつ、新たな視点を導入し、冒険することなく実証に徹している歴史研究である。そのため、禁欲的なあまり、社会や当時の政治状況へと話が広がっていかない記述は、本来的な意味で学術的であるのだが、おもしろみに欠けるという感じがどうしても残る。また、散見される現代批評用語の使用が、かえって、無理矢理感をだしていることも気にかかった。ただ、翻訳まで含み、重要な学術的貢献であることはまちがいない。
田中祐理子氏の『「病原菌」の歴史──実在・表象・歴史性について』は、科学史的な研究書であるが、「病原菌の表象=〈見える/見えない〉」をめぐる言説史でもあり、学会賞にふさわしい内容である。「歴史構築の〈現場〉に視線を差し戻す」という修正主義的意図や「歴史の社会構成主義的脱構築」による〈脱神話化〉という同時代の歴史研究の要請に真摯にこたえようとする意味でも意欲作である。特に、ジローラモ・フラカストロとアントニ・ファン・レーウェンフックについて論じた前半は、比較的わかりやすい「脱神話化」的記述になっており、このふたりがなぜ現在的(=「細菌学」の成立以降)に歴史的評価を得ることになったのか、十分な論証と説明が為されている。ルイ・パストゥールとロベルト・コッホを論じた後半は、このふたりの「細菌学」成立におけるさまざまなレヴェルにおけるかかわりを細部にわたって丁重に検証しており、「脱神話化」というよりは、より精密に歴史を記述するという内容である。そのため、「ふつうの歴史記述」ではないか、という疑義を呼び寄せる可能性が大きいが、わたし自身は大変興味深く読むことができた。
千葉雅也氏の『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』は、端的に快著である。学問手続き(先行研究への言及その他)を十全に踏まえた上で、また、ある特定の言語にとどまらないドゥルーズ研究史を幅広く押さえた上で、縦横無尽に、博覧強記に、必要な引用・言及をしながら、主題を検討していく著者の手つきは鮮やかとしか言いようがない。したがって、本書はドゥルーズ研究の世界的貢献であることは、門外漢ながらも容易に想像できる(即刻、何らかの外国語に──できれば著者自身の手で──翻訳されるべきである)。英語圏文献への目配りと日本における歴史的・同時代的文脈への配慮があることで、これまでのいわゆる日本における現代思想(現代思想研究)とは太い一線を画す論になっていると考えられるし、また、これまでの日本語で書かれたドゥルーズ論にありがちだった解離的とでも呼ぶべき晦渋な知的運動ではなく、あくまでも理性的かつ批評的な知的運動として展開する本書のエクリチュールは、啓蒙的という言辞さえも呼び寄せつつ、しかしあくまでも専門書であるという構えを崩すことはない。学会賞にこれ以上ふさわしい書物はないのではないか。
貝澤哉
推薦された候補作は、それぞれ扱う領域もアプローチもじつに多彩で読み応えがあり、純粋に個人的な読書の経験としてはさまざまな知的刺激を与えてくれたが、それだけに、これほど内容も方法も異質な著作群をあるひとつのパースペクティヴへと序列化する「賞」の選考という作業には、つねに「アカデミズム」や「学会」をはじめとする制度や権威の配置のなかに取り込まれる危険や困難をはらんでいるとも言える。
そうした観点から見るならば、千葉雅也氏の『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』が学会賞に推されたことはおそらく偶然ではないのだろう。ベルクソン的な「持続」と「流動」に依拠したこれまでの接続過剰なドゥルーズ理解に対して、ヒュームを出発点とする「離散的」で「中途半端」な「非意味的切断」というドゥルーズの可能性をあざやかに打ち出すこの著作は、《哲学・思想研究》や《表象文化論》などという狭隘で制度的な学問的枠組みや領土性に容易には回収されない柔軟かつ強靭で実用的な企図をそなえている点で、候補作のなかでは群を抜いていたと思われる。
田中祐理子氏の『科学と表象──「病原菌」の歴史』もまた、「細菌学」という学問的制度そのものの歴史性を、知覚の様式やそれを支えるテクノロジーの変容とともに描き出そうとした秀作と言えよう。しかし一方で、パストゥールやコッホといった学問の「父」のバイオグラフィーのみに焦点を合わせるその叙述法が、「細菌学」という制度自体の歴史性を問うという当初の意図を裏切って、本書を古色蒼然とした「科学史」的な偉人列伝に近づけてしまっているのではないか、という疑問をぬぐえなかったことも記しておく。
杉山博昭氏の『ルネサンスの聖史劇』は、豊富な資料を博捜しながらルネサンス期の聖史劇の上演のありかたを再現するという野心的な企てであり、火薬さえも使った大がかりな演出法や、その「演劇的リアリティ」の視覚的表象が他の造形芸術におよぼす効果の指摘など、興味のつきない著作である。だが、こうした実証的で資料的な細部の集積のなかで、ルネサンス聖史劇に見られるこれらの特徴をどのように読み解くのか、たとえば、火薬の爆発と「演劇的リアリティ」の氾濫にはどのような連関があり、私たちにとってどんな意味を持つのか、といった一般読者が感じるはずの素朴な問いが埋もれてしまっているようにも感じられた。いかにも博士論文のあり方を残したこうした手堅い叙述形式や学術的構成が、本書を一般読者から遠ざけてしまっているように見えるのが惜しまれる。
千葉文夫
今年度の審査員となり、文字通り選考の難しさを体験しました。選考の対象となった著作が多岐の領域にわたるのは、表象文化学会の特徴だといってよいはずで、あらかじめ覚悟はしていましたが、実際に候補作に接すると、どのような基準をもって応対すべきか終始悩みつづけました。自分の限られた専門領域の知識ではとうてい対応し切れない部分が多々あるわけで、最終的には一個のテクストのもつ力を直感的にとらえるのが一番誠実なふるまいなのではないかと割り切って考えることにしました。ただ候補作を読み進めるなかで、個々の著作がどのような領域を扱っているのかという問題とは別に、表象文化論的な考察の可能性に応答しようとする姿勢に触れえたという実感をもちえた瞬間がありました。そのような実感を中心とするコメントになります。
学会奨励賞として推薦された千葉雅也『動きすぎてはいけない』が学会賞の対象として扱われた経緯はすでに報告済みです。ドゥルーズの実践的な強い読みを示している点が審査員一致した評価であったと思われますが、自分としてはユクスキュルのダニとモナド=ノマドの暗い底をめぐる考察が今後どのような「実験」あるいは「作品」につながってゆくのか見届けたいという思いをもちました。学会奨励賞を受賞した杉山博昭『ルネサンスの聖史劇』および田中祐理子『科学の表象』は、前者はルネサンス文化研究、後者は科学史研究という異なる領域に属すると考えられるものですが、いずれも歴史的資料の新たな活用にもとづいて表象文化論を展開する可能性を感じさせる点に共通点を見出すことができるように思いました。前者は絵画と演劇が絡み合う興味深い主題を取り扱っていますが、大量の翻訳も含めて丁寧に材料を扱う手つきも印象的で、文字通り労作というべきものですが、なぜこの主題を扱うのかという点について踏み込んだ考察があればさらに刺激的なものとなりえたのではないかという感想をもちました。「病原菌」の歴史を検証する後者は、科学的知の成立条件をめぐる考察をおこなう前半部と、細菌学の父たちの足跡を追いかける後半部が異なるベクトルをもつ点も興味深く、著者はこの分裂をどのように生きているのだろうかという余計な心配が頭をよぎりました。荒谷大輔『「経済」の哲学』は刺激に満ちた野心的な論考ですが、著者が望むように「作品」としてこれを受け止めることができるかどうかは微妙なところで、たぶんそのあたりの説得力と表象文化論の可能性の問題はつながっているのだと思われます。石田圭子『美学から政治へ』はモダニズム詩人とファシズムの関係を追求する労作ですが、そのような関係をめぐる大きな構図と作品の個々の読みをどのように関係させるのか、書き直しを経て一個の著作として安定した形式を得た側面はあると想像されますが、「形態」「ゲシュタルト」「イメージ」の関連について考察をさらに深めることで表象文化論としての可能性をより実感させるものになったのではないかという感想をもちました。木村陽子『安部公房とはだれか』はマルチメディア的環境に作家をおきなおそうとする点で、現在の安部公房研究の流れに歩をあわせて、新たな作家像を印象づけることに寄与していると思われますが、安部公房自身のテクストの独自の分析という点で物足りなさが残りました。以上、著者のみなさんの今後の発展を祈ります。
中村秀之
今年度も意欲的な労作が揃って壮観であった。特権として与えられた知の愉悦と読みの快楽には授賞作を選り抜く義務が伴うのだが、こちらの仕事はさすがに手ごわい。それでも賞賛や留保やときに疑念のことばを活発に交わすなかで選考の道筋がおのずから整い、ご覧のとおりの結果に定まって肩の荷を下ろすことができた。賞の対象となった三作について私の思いを簡潔に述べる。
2013年は日本の若手研究者による画期的なドゥルーズ論が次々と刊行された「驚異の年」として記憶されるかもしれない。そのなかで千葉雅也氏の『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』は、ベルクソン的な「接続的ドゥルーズ」に対してヒューム的な「切断的ドゥルーズ」を前面に押し出し、ドゥルーズにおいてヒューム的なものがキメラ的に混在することの積極的な意義を評価した。全体として「批評的な現代思想」とでも呼ぶべきものの再生の企てと見たが、かつての先行者たちの「速さ」や「残酷さ」とは対照的な「クールさ」と「遅さ」のスタイルが、むしろ今日的な意義をもつと感じられた。表象文化論学会の主たる狙いが精密な学知とアクチュアルな批評や創造との間を架橋することにあるとするなら、本書はまさに学会賞にふさわしい優れたパフォーマンスといえる。ドゥルーズにならって「私たちは、権利上はつねにすでに狂っている」と大胆に言い切る著者が、論じられる内容と論じるスタイルとの緊張に満ちた新しい探究を今後どのように展開するのか、楽しみでならない。
杉山博昭氏の『ルネサンスの聖史劇』は、イタリア・ルネサンス文化の要所を占めながら知られること少なかった15世紀フィレンツェの聖史劇を対象とする。上演台本の文献批判やテクスト分析、上演の空間と装置や受容の様態の検討、同時代の図像との関係の考察を綿密に行ない、その全体像を見事に浮かび上がらせた。加えて聖史劇の台本14本をみずから翻訳して収録しているのだから贅沢でありがたい書物である。個人的にはユベール・ダミッシュなどの先例がある絵画と聖史劇との錯綜した関係に興味をそそられた。今後はそうした個々の論点を深く掘り下げる仕事をしていただけると、さらにありがたい。
田中祐理子氏の『科学と表象──「病原菌」の歴史』は、冒頭で「言説形成」ということばを登場させ、その注で『知の考古学』に言及しているけれども、ミシェル・フーコーの「主体不関与」の言説分析とはおよそ対極に位置するような、人間的主体としての科学者の活動の歴史として読める。私自身はたとえば『知の考古学』の荒涼とした美しさに魅了されるたちだが、科学の営みにおける知覚と表象の問題に焦点を当て、ブルーノ・ラトゥールの戦略的な議論にも誠実に対応して粘り強く論じ通した本書は、十分に説得的な仕事であると思われた。