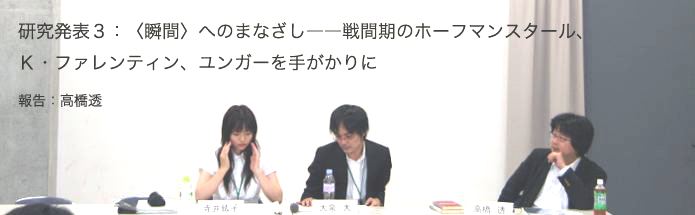| 第4回大会報告 | 研究発表パネル |
|---|
7月5日(日)京都造形芸術大学 瓜生山キャンパス 人間館4階NA402教室
研究発表3:〈瞬間〉へのまなざし――戦間期のホーフマンスタール、K・ファレンティン、ユンガーを手がかりに
〈瞬間〉を「見る」ということ——ホーフマンスタールのAugenblickの機能について
寺井紘子(京都女子大学)
瞬間の知覚と立体の知覚——E・ユンガーの知覚概念について
大泉大(早稲田大学)
【司会・コメンテイター】高橋透(早稲田大学)
ドイツの美学者カール・ハインツ・ボーラーは、その著『突然性』や『衝撃の美学』で、ポーから1920年代へと展開していく「瞬間性の美学」を周到に分析し、その分析対象となる作品群には、連続的空間・時間の秩序に綻びを生じさせる「瞬間の知覚」が叙述されているとした。本パネルでは、ホーフマンスタール、ユンガーが扱われた。これら三者は、芸術的実践、思想の細部、政治的信条を異にしながらも、部分的にではあれ共通した時代意識のもとで、こうした「瞬間の知覚」に重要な働きを見出していた。
こうした瞬間の知覚による「理性への反抗」は彼らにおいて具体的にどのように行われ、なにを生み出し得たのか。本パネルの二つの発表は、モダニズムの極点とも言える「瞬間性」を考察・検討することで、多様な視点が交錯する「瞬間」の問題圏を整理し、その可能性を追求した。(高橋透)
〈寺井紘子〉
歴史的理性の追い求めてきた客観的認識と普遍的価値を根底から否定し、理性そのものが虚偽であることを暴露したニーチェ的世界観を引き継ぐものとして、カール・ハインツ・ボーラーとフーゴ・フォン・ホーフマンスタールは、その美的態度を等しくしている。ボーラーは日常的経験世界の仮象性を突発的に暴露する瞬間を「突然性」〈Plötzlichkeit〉と名づけ、初期ロマン主義からシュールレアリスムに至るまでの「突然性」の文学的実践の系譜を追うが、彼がとりわけホーフマンスタールに見出した瞬間は、「突然性」の持つ破壊的性格を重視したものであった。ボーラーが取り上げるホーフマンスタールの三作品『第672夜のメルヒェン』『騎兵物語』『バッソンピエール公爵の体験』には、主人公が瞬間の体験ののちにその主体性を失い、破滅していくさまが描かれている。しかし、ホーフマンスタールは確かに、あたかもそれが本当のように思われている既存の秩序世界の虚構性を暴露する契機として瞬間を扱いはするものの、その一方で、その創作後期においてはむしろ、瞬間に、体験者の主体性回復の契機の可能性を見出していた。こうした瞬間は、芸術作品を場として生起し、芸術作品を「見る」ことで体験者には一旦は失われていた主体性があらためて獲得されることになる。これが窺える作品として、発表では『帰国者の手紙』と『ギリシャの瞬間』を取り上げた。そして、瞬間がその突発的、破壊的性格から重視されるのではなく、ホーフマンスタールにおいてはあくまでも、Augen(眼)でblicken(見る)瞬間<Augenblick>として機能していることを考察した。
〈大泉大〉
元動物学者であるエルンスト・ユンガーは『冒険心-形象と狂想曲』(1938)にジョウビタキの観察記述を収録しているのだが、彼はこの観察に当時の動物行動学と等しい解釈を加えている。すなわち、生物の知覚は、生物の器官とその外部との構成に応じて編成されるとの知見である。ユンガーはこの編成を統御する性質を「生の盲目性」と呼び、人間の「自我意識」もまたこの盲目性に統治されているとする。意識に見えない人間の動物的生が技術社会との間で紡ぎだす現実の意識への可視化こそ、ユンガーが30年代に企図したことである。ユンガーが衝撃の瞬間に照準を合わせるのは、この衝撃の知覚において、意識に対して見えないもの、動物が痕跡を残すからにほかならない。この痕跡を読む技法として彼が提起するのがステレオスコープ的知覚である。見えない図像から立体的な像があたかも現実的に現れてくる世界は、意識が表彰する世界のアナロジーと目されているからである。
〈質疑応答〉
・ホーフマンスタールが『チャンドス卿の手紙』で言語の限界性への意識を表明したことに関連して、そのような言語意識を持っていながら、なおあくまでも「見る」という瞬間を言葉でもって表そうとした彼の意図はどのようなものであったか。
―言語の限界性を意識しながらも、ホーフマンスタールの表現手段はやはりあくまでも言語であり、他の芸術(絵画や音楽など)に関心を向けることによって、彼は言語による表現の可能性を追究し続けた。とりわけ世紀転換期以降、オペラや戯曲など、舞台で上演されることを目的とした作品を積極的に手がけていることからも、自身の言語表現を「見る」表現へと置き換える可能性を模索していたことが窺える。しかし、文学作品としてそこに描き出そうとしたホーフマンスタールの「瞬間」が、実際舞台の上で観客が「見る」段階になったときにも、同じ作用を持つ瞬間として機能し得たかといえば、それは疑わしいと言わざるを得ない。そこには演者や演出家、舞台空間といった諸要素がかかわっているからである。
・なぜ瞬間が視覚的なものとして扱われるのか。
―『チャンドス卿の手紙』で言語の表現の限界性を表明し、さらにその自覚に立って言語表現のさらなる可能性を模索しようとしたホーフマンスタールにとって、他の芸術の表現手段は常に意識せざるを得ないものであった。中でも色彩と象徴を用いた造形芸術への関心は高く、実際の画家や絵画作品がしばしばモチーフとして作中に現れてくる。視覚という直接的知覚は、ホーフマンスタールにとって言語表現の可能性を探るうえで重要な意味を持っていた。それゆえ、「瞬間」もまた、Plözlichkeit(突然性)やEntsetzung(驚愕)ではない、「眼で見る」「瞬間」Augenblickとして、見る体験として描き出されている。
・ハイデガーあるいはシェーラーなどに見られる全体性への志向はユンガーにおいてどうなっているのか。
―この点はこれからの課題であるが、環世界はそれぞれ排他的に閉じていながら外部に対する調和を保つことを強調し、ユンガーにおいて、問題となったのは、意識と人間という動物が構成する環世界との間であっただろう。この点を考える際には『労働者』において動員された世界の表象/代行とされる形態概念の更なる検討が必要である。少なくともこの概念には全体性が賭けられていると考えられるからである。

寺井 紘子

大泉 大

高橋 透
高橋透(早稲田大学)
発表概要
〈瞬間〉を「見る」ということ——ホーフマンスタールのAugenblickの機能について
寺井紘子
ボーラーが〈Plötzlichkeit〉と名づけた、ある「瞬間」に「突然」襲ってくる美的体験は、理性的認識の限界の外で世界を知覚する一種のショック体験である。理性的認識によって確固たるもののように思われている秩序世界は虚構に過ぎず、この一瞬に世界はその仮象性を暴露する。このPlötzlichkeitが、啓蒙主義以来つねに規定されてきた理性の正当性を真っ向から否定し、理性的秩序の世界の裏に隠されている本来的な生の世界を明るみに出そうとしたニーチェに由来することは言うまでもない。
ニーチェの生の哲学の影響を色濃く示すホーフマンスタールに、ボーラーはPlötzlichkeitの文学的実践を見る。彼の様々な作品において、主人公を「突然」襲い震撼させる「美的瞬間」、日常生活の均質な経験空間に突如差し込むつかの間の閃光のような一瞬が描かれ、作品の重要なファクターの一つとなっている。興味深いのは、こうした瞬間(Augenblick)がホーフマンスタールにおいては常に、視覚的体験として描かれていることである。本発表では、ニーチェ的美的世界観の実践者としてのホーフマンスタールのAugenblickの機能に着目し、『ギリシャの瞬間』や『チャンドス卿の手紙』、『帰国者の手紙』に現れるAugenblickを考察する。そしてこの「瞬間」が、晩年の戯曲『塔』においていかに視覚的に表されようとしたのかを見る。
瞬間の知覚と立体の知覚——E・ユンガーの知覚概念について
大泉大
本発表はE・ユンガーの知覚概念を、視覚の側から検討する。兵士、昆虫収集家そして作家であった彼にとって視覚および対象の可視化は極めて重要な要素であった。また視覚はユンガーを時代の内に位置づける際の鍵でもある。衝撃の美学(ボーラー)、身体甲冑(テーヴェライト)といった概念装置による解釈の試みは、ユンガー作品から、いかなる熱によっても溶けることのない眼が読み取られることで成り立っている。一方でユンガー自身、写真論において明白であるように、近代技術が眼差しを身体の「感受性」とは離れた存在になし得たと考えていた。つまり、ユンガーは近代的生の形態としての甲冑化を、写真における視覚モデルに認めていたといえる。
それでいてユンガーは『冒険心第一版』において「ステレオスコピー」という知覚のあり方について論じている。19世紀にステレオスコープは単眼の視覚モデルから複眼を条件とする視覚モデルへの移行を体現した。だがユンガーが提示する「ステレオスコープ的知覚」は、視覚の複眼性ではなく知覚の輻湊、例えば、視覚と聴覚、視覚と嗅覚との輻湊を意図している。彼はこの知覚を、生のより深い享受のためにと提示した。本発表では、近代において不可避な視覚の甲冑化と、ステレオスコープ的知覚とがどのような布置にあるのかを分析することで、ユンガーにおける瞬間の知覚が「衝撃の美学」とは異なる文脈とどのような関連にあるのか検討したい。