二つの「この世界の片隅に」 マンガ、アニメーションの声と動作
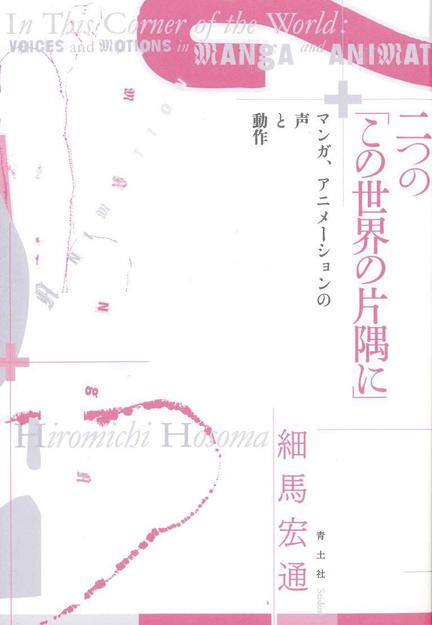
本書は、2016年に公開され、きわめて高い評価を獲得したアニメーション映画『この世界の片隅に』(片渕須直監督)と、その原作マンガ『この世界の片隅に』(こうの史代)を対象とし、2つの作品を、それぞれのメディア固有性に依拠しながら分析した作品論である。長年、人の身体動作や声のやりとりを分析してきた筆者による、作品の細部へと注がれるまなざしによって、マンガ/アニメーションのテクストは有機的に豊かなネットワークを紡ぎだすことになる。以下、本の構成を紹介した上で、その分析を具体的に紹介していこう。
本書は、「ことば」「かく」「くらし」「からだ」「きおく」という主題から二つの作品を論じた本編に、片渕須直監督と筆者の対談、『ユリイカ』(青土社)2016年11月号の「こうの史代特集」に掲載された筆者の論考を加えて構成されている。筆者のアプローチは、(アダプテーション研究にしばしばあるような)翻案された作品を原作と比較することよってオリジナル作品の独創性を確認していく作業ではなく、ベンヤミンの翻訳論を基底にして「原作の意図を異なる言語によって志向する行為」、すなわち、マンガ/アニメーションという異なる表現にある「翻訳可能性」から隠された「真の言語」を捉えようとする。
「ことば」の章では、マンガ版に並べられた3コマにおいて、すずの表情と姿勢の変化が「標準語/方言」の使用といかに連動しているのか、さらには文字テクストでは、メディアの特性として「標準語/方言」の間で二分される「ことば」が、アニメーションの「声」として演出=表現されると、「笑い」や発話の仕方によっていかに微細に中間領域が表現されているかが論じられる。「かく」の章でも、たとえば、周作のもとへ嫁いだすずが、手紙に自分の名前を書く3つのコマなどの細部が検証される。鉛筆を動かして自分の氏名を書くだけの行為だが、1コマ目から2コマ目の間にあった「動き」が、2コマ目から3コマ目には「停滞」しているように表現される一方、アニメーションはこの部分の動作を、嫁ぎ先の名字を書くときは慎重に、名前を書くときは軽快に表現している。「名前を書く」という行為を媒介として、一人の少女が「嫁ぐこと」を、マンガ/アニメーションがどのように表現しているのか、それぞれのメディアによる異なる表現技法が捉えられている。アニメーションがマンガの「3コマ」の表現をいかに汲み取ったかを経由することで、翻って原作にあった「運動」や「停滞」の意味を私たちは思考できるのである。
「くらし」の章では、特にマンガの表現分析の秀逸さが目を引く。落ち葉を集めたすずが、かまどの前で繰り返し作業をする描写、女郎・リンとすずが隣り合わせで並置されるコマの残酷さ、こうしたイメージやコマ構成から「代用品」としての自己の実存の問題が読み取られる。またマンガのコマに表現される警報の「う〜」というサイレンの紐は、吹き出しやコマを読み進める読者の「右→左」「上→下」への視線の動きを撹乱するようにコマを横断する。あるいは、サイレンや轟音を指し示す記号が、異なる場面を描写した2つのコマを同じ空間であるかのごとく覆うことによって時間感覚を狂わせる。こうした「音」は、「まるですずや周作たちの生活のリズムに割り入るように、読者の時間に割り入ってくるのだ」。物語内部の人物の「くらし」を破壊する視覚的記号としての「音」は、それを読み進める私たちの身体を揺さぶる契機として形態的に埋め込まれているのである。
「からだ」の章にある「風呂敷」に関する議論は、筆者の分析の精密さに圧倒される。ここでも焦点化されるのは、マンガにしてたった3コマに描かれた、すずが風呂敷を肩に背負うだけの行為──アニメーション版において筆者がまず引き込まれたのがこの場面だったという。「フル・アニメーション/リミテッド・アニメーション」と一般に理解されがちだが、あえて(制作コストを削減するためではなく)「2コマ打ち」や「3コマ打ち」が配置されることもある。詳しくは本書の分析を読んでいただきたいが、片渕監督は、「コマ打ち」によって描画間隔を絶妙に操作しながら、この場面のすずをアニメイト(生命を吹き込む)しているのだ。さらに本章では、両メディアにおけるすずの1本まつげの描写や動きにまで分析が施されている。驚くべき細部へのこだわりである。「きおく」の章では、アニメーション/マンガ版での思い出のあり方の違いから、「右手」の現れ方がなぜ異なっているのか、さらに両作品における「秘密」や「バケツ」の表現の差異が考察される。だが、ここでもっとも驚嘆するのは筆者の「手紙」についての論考だろう。アニメーション版のラストのコトリンゴによる「歌声」の正体とそのメッセージ、マンガ版における「手紙」の宛先の複数性、それが私たち読者と取り持とうとする関係性を鮮やかに言語化しているからだ。
スペシャル対談では、片渕監督が、徹底的に歴史考証・資料調査をして史実を(観客が気づかない細部にまで)再現するディテールへの執着が伝わってくる。本書の筆者と片渕監督に通底するのは、まさにこの「細部へのこだわり」である。また『ユリイカ』の論考は、単行本になる前の段階、すなわち雑誌『漫画アクション』に連載されていたときに、こうのマンガが与えられていった「居場所」と、連載という形式を通した独特の読書経験をつぶさに浮かび上がらせる。随所に散りばめられたマンガの図版は筆者の読解を手助けしてくれるし、何より楽しく読み進めることができる。とはいえ、できれば原作であるこうの史代のマンガと片渕須直監督のアニメーションを準備して、適宜、細部を見比べてみることをおすすめする。
パリンプセスト(Palimpsestos)とは、あるテクストにもう一つのテクストが重ねられ、新しいものを通して古い書き込みが部分的に可視化されることを表す。本書は、どちらかに独創力を見出したり、優劣をつけたりするのではなく、アニメーションを媒介したマンガ/マンガを媒介したアニメーションを思考する。それはいわば、それぞれのメディアにおける言語表現を照らし合わせることによって、その共鳴/反響を聴こうとする行為であり、両作品を相対化することによって、テクストに潜在化した「声」や「運動」を顕在化させる「パリンプセスト」としての批評実践なのである。静止画であるマンガを徹底して「観尽くす」ことによってコマ同士の関係性から人物の「動き」を立ち上がらせ、読者に「声」を届けること。あるいは、アニメーションの「運動」の分析の解像度を極限まで高めて、その感動がいかに作動しているかを実証すること。読者は作家と批評家が協働して創り上げた、新たな『この世界の片隅に』に出会うことになるだろう。
(北村匡平)