〈救済〉のメーディウム ベンヤミン、アドルノ、クルーゲ
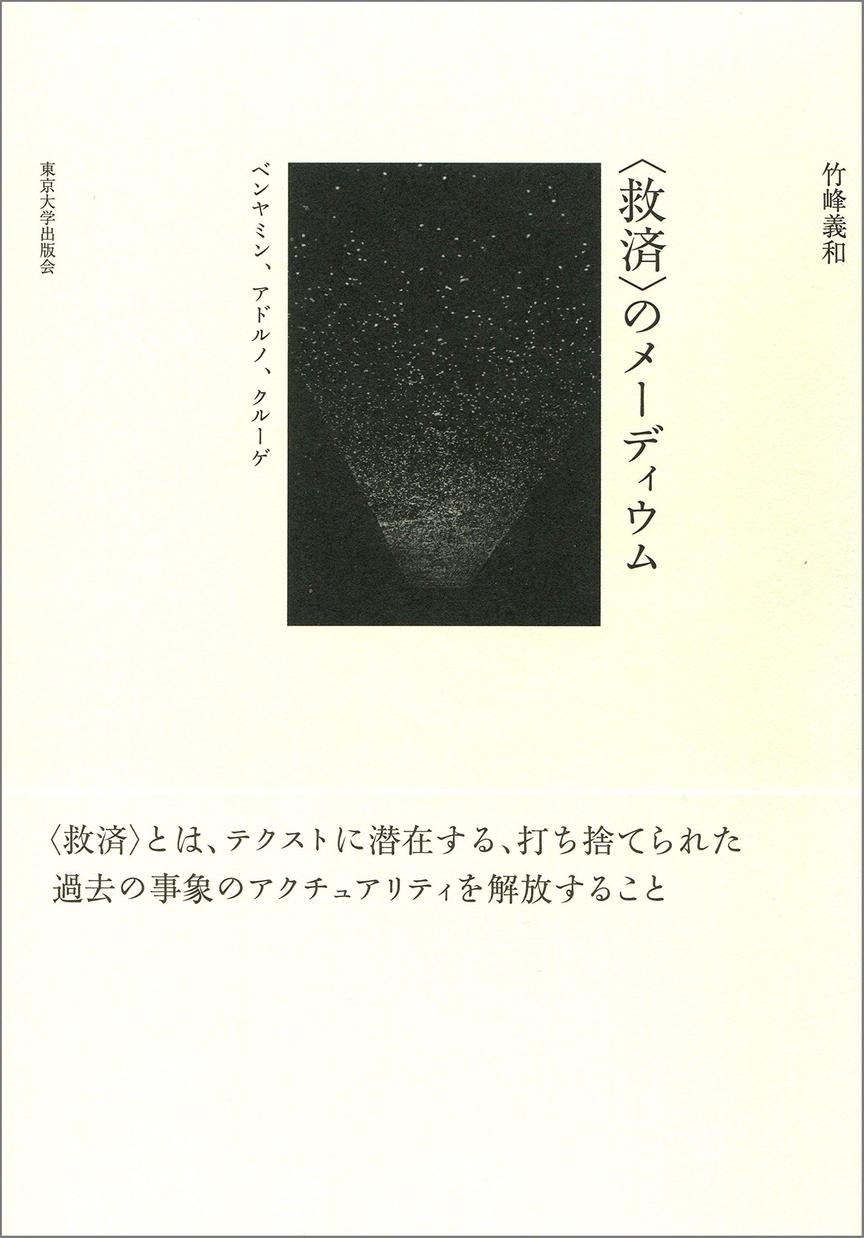
「大雑把に定式化するならば、〈救済〉とは、過去というカテゴリーのもとで棄て去られたさまざまなものが孕みもつ潜勢力を、〈いま・ここ〉において、未来に向けて再生させることであると言えるだろう」(本書445頁)。
「本書はこのような〈救済〉の概念を導きとして、ベンヤミンからアドルノ、そしてアレクサンダー・クルーゲへといたるフランクフルト学派の思想史的系譜を跡づけようとする試みである。その作業をつうじて、フランクフルト学派の「アクチュアリティ」を明らかにすることが本書の最終的な目標である」(本書5頁)。
そうして貫徹されるのは、「ベンヤミンの絶筆となった「歴史の概念について」(1940)で描写される「歴史の天使」が「顔を過去の方に向けている」ように、われわれの議論もまた、ひとまず過去へと遡行し、それぞれの思想家が執筆したテクストを内在的に精読すること」(本書5頁)である。
ベンヤミン「言語一般及び人間の言語について」(1916)から「ゲーテの『親和力』」(1922)、『ドイツ悲劇の根源』(1925)、「歴史の概念について」(1940)を経て「複製技術時代の芸術作品」(第二稿: 1936、第三稿: 1939)へ。アドルノ「外来語の使用について」(1934)から、「音楽の社会的状況によせて」(1932)、『シェーンベルクと進歩』(1940-1941)、『美学理論』(1961-1969)を経て『啓蒙の弁証法』(1941-1945)へ。そして、日本では軽視され続け、あくまでもニュー・ジャーマン・シネマの旗手として知られる人物。本書によってはじめて本格的な読みがおこなわれたことになる、ハーバーマスやアクセル・ホネットとは異なるもうひとつのフランクフルトの思考の継承者、アドルノの愛弟子、アレクサンダー・クルーゲの映画作品『石の獣性』(1960)からオスカー・ネークトとの二つの共著『公共圏と経験』(1972)、『歴史と我意』(1981)を経て、映像作品『イデオロギー的な古典古代へのニュース──マルクス‐エイゼンシュテイン‐資本論』(2008)、そしていまも続けられるクルーゲの実践へ。
一冊の本に封をされた1世紀の時間、それがたんなる単線的な時間ではなく、たとえばベンヤミンがいうような「土星──もっともゆっくりと回転する、廻り道と遅延の惑星」の、その痕跡であるならば、描かれた軌道を照らす光源はアドルノという個人の生涯であろう。アドルノを中心になされた布置は、「その思考を自家薬籠中のものとした」ベンヤミンや、はじめての出会いからして「ほとんど恋愛映画の一シーンを彷彿とさせるような」キアスム的交差で結び合わされたクルーゲとのあいだだけでなく、『ファウスト博士』をともに構想したトーマス・マンや「傷つける両目」の「背教者」との誹りを受けたアルノルト・シェーンベルクにまで、あたかも本書におけるクルーゲ論の鍵語のひとつである「絆関係(Beziehungsverhältnisse)」のように広がっている。
この本を手にとることは、フランクフルト学派の救済を求める苦闘の歴史を「追想」することである。だが同時に、それは著者の15年にわたる思考の軌跡そのものを、内在的に読み解くことでもある。実際、この試みを彩る無数の引用文とそこに埋め込まれた語彙で構成されたテクストのなかで、それらとは独立した「著者の肉声」として、最も多く発せられているのはおそらく、はじめに挙げた二つの引用──本論を挟んで断絶したあとがきと序論からの、しかし惑星の円環はおわりをはじまりに短絡させる──に見出されるふたつの言葉「アクチュアリティ」と「潜勢力」である。
実点と虚点、目次に書き加えられた言葉と抹消された言葉。両者は、本文で幾度も繰り返し用いられ続ける。フランクフルト学派の歴史が必ずしもズレや重複を孕まないものでなく、むしろ進んでは戻り、戻っては進むような、挫折と再起の連続体であったとしても、それを執拗に追いかけるこの本の、そうしたふたつの言葉には、確かに少しずつ、連続体の小さな亀裂をつうじて、「潜勢力」が充填され、「アクチュアリティ」が込められていく。あたかもそのためにこそ、「もっともゆっくりと回転する、廻り道と遅延」たらんとしているのだとばかりに。
楕円軌道の焦点は二つ存在する。重力を行使して全体を統御する恒星のみではなく、いまひとつのみえざる焦点をもって、土星は回転する。あたかも「歴史的唯物論」が「自動人形」と、それを操る見えざる「せむしの小人」をもって駆動するように。この軌跡の書が、ベンヤミンのいうように「常に勝たなければならない」という切迫した重荷を背負っているのかはわからない。むしろ、ここに記録されているのは、フランクフルト学派の思想家たちの、「対象を有機的な全体性から暴力的に引き剝がし、バラバラな断片へと裁断することで、「時間の経過がそれらにたいして執りおこなった批評的解体」のプロセスをみずから積極的に推し進めると同時に、凋落した廃墟としての作品のうちに隠れ潜む「新生」の契機を探りあてようとする態度」(本書438頁)なのであり、読者へと勧められるのは、そうした〈不実なる忠実さ〉の「パフォーマティブ」な〈批評=批判〉の実践である。
であるにもかかわらず、むしろであればこそ、あえてこのように問いかけねばならない。すなわち複製技術論の系譜と「翻訳者の使命」や「認識批判的序章」、「歴史の概念について」はほんとうに直接結びつくのか、と。たとえば、「星座」を構成する「理念は言語的なものであり、しかも、言葉の本質にそのつど含まれているあの、言葉を象徴となす契機」(『ドイツ悲劇の根源 上』浅井健二郎訳、ちくま学芸文庫、1999年、38頁)なのであり、翻訳のもつ唯一の力とは、「象徴するものを象徴されるものそのものにする」(『ベンヤミン・コレクション 2』浅井健二郎編訳、ちくま学芸文庫、1996年、407頁)ことだが、複製技術論で称揚される「断片」とそのモンタージュとはむしろ、これらにみいだせる「象徴(Symbol)」と対立する「寓意(Allegorie)」に近いものではなかっただろうか、と。
読みは開かれている。従来の読みに敬意は払えども、隷属する必要はない。著者が前著『アドルノ, 複製技術への眼差し』から一貫して、アドルノに複製技術の可能性を読み込んでいるように。引用のパッチワークや、誤解や拡大解釈すらも拒絶されてはいない。それが〈不実なる忠実さ〉を保っているかぎりは。本書とともに、真に「パフォーマティブ」に読むためにも、権威や慣習という名の擬似的な「客観性」にではなく、テクストそれ自体のうちに秘められている、「客観性」という言葉すらも相対化したうえでなおも残る「願い」に忠実であらんことを。
あるいは、研究という狭い枠組みを「爆破」して、すでに古びた理論としてではなく、いつもあらたに「潜勢力」を増大させ続ける実践の道具として用いられんことを。クルーゲもまた、2015年のヴェネツィア・ビエンナーレ──その総合テーマAll The World's Futuresにはベンヤミンやマルクス、ルイ・アルチュセールらが結びつけられていた──において、「イデオロギー的な古典古代へのニュース (Nachrichten aus der ideologischen Antike)」を出品し、〈不実なる忠実さ〉を貫いている。
アドルノは『否定弁証法』冒頭で、「具体的な哲学的思索に的確に達するためには、ひとは抽象の氷原を通り抜けねばならない」というベンヤミンの言葉を挙げている。本書においても、ベンヤミンからアドルノを経由してクルーゲへと至る迂回路は、具体的思索への解凍のプロセスでもあるように感じられる。ここでは、抽象にとどまるのではなく具体へと歩みを進めること、そして研究という囲い込みではなく世界へと「パフォーマティブ」な読解と実践の布置を広げることが目指されている。それこそが「フランクフルト学派の「アクチュアリティ」を明らかにすること」なのだから。
※本書であげられているクルーゲのテレビ番組の無料視聴が可能なホームページを付記するべきだろう。(http://magazin.dctp.tv/) また、You Tubeのヴェネツィア・ビエンナーレ公式チャンネルには、上記のクルーゲの作品も加えられている。(https://www.youtube.com/watch?v=gMkk1O420-E)
(高田翔)