| 研究ノート | 井上 康彦 |
|---|
撹乱する女たち
——ロザリンド・クラウス『独身者たち』について
井上 康彦
去年、半年間をかけて、ロザリンド・クラウスの『独身者たち』(原題 BACHELORS, 1999)を訳した。まだ編集者と交渉中で、出版がいつになるかは未定という段階だが、ここではこの本の紹介をする。
ロザリンド・クラウスは、ポストモダニズムの美術批評家である。『オリジナリティと反復』(1985)から『パーペチュアル・インヴェントリー』(2010)に到るまで、すべてはここからはじまり、ここに帰着する。彼女の美術批評の方法は、つねに「モダニズム」との距離から導出されている、という意味だ。
クラウスは、戦後のアメリカの美術批評界で圧倒的なヘゲモニーを握っていたクレメント・グリーンバーグ、そして彼が提唱する「モダニズム=フォーマリズム」の影響下で活動を開始したが、その後袂を分かち、彼女独自の批評理論を展開していく。「モダニズム」の批評論理とは、美術作品の個々のメディウム固有の特性を重視するもので、とりわけ絵画は平面性とその境界画定に還元され、抽象的な「純粋視覚」へと向かわねばならない、というものである。ここには戦後アメリカ独特の時代状況が反映されていて、「モダニズム」には、当時登場してきたポロックやデ・クーニングといった「アメリカ発の」抽象表現主義を喧伝するという側面があり、多分にナショナリスティックでマッチョなものでもあった。一世代後のクラウスは「モダニズム」の理論では説明のつかない作品を評価するためにこれに見切りをつけ、別の批評の可能性を探っていくわけだが、その際に重要な軸となるのが「アンフォルム」という概念である。「アンフォルム」とは、ジョルジュ・バタイユが『ドキュマン』で提唱したもので、これが、「モダニズム」によって抑圧されてきた美術のさまざまな可能性を開いてくれる、と彼女は考えるのである。実際のバタイユによる「アンフォルム」の記述は短く難解なもので、クラウスはこれを独自に解釈して自分の思考に採り入れている。クラウスの理解する「アンフォルム」とはどんなものか。彼女は、見方によって作品のコノテーションが変化する、ジャコメッティの《宙吊りの球》(1930-31)——「モダニズム」の立場からするとシュルレアリスムは価値の低いものであり、ジャコメッティを取り上げること自体に「モダニズム」への抵抗の異議が含まれている――をその好例として、「アンフォルム」をこう説明している。
「この作品おいて、アイデンティティの絶えざる交換によってカテゴリーのブレが生じるが、これこそがまさにバタイユがアンフォルムの一語で言わんとしているものである。それは、単に定義の領域がボヤけたり曖昧になったりするといった類いのものではなく、ほかならぬカテゴリーの論理のなかを滑り抜けるという戦略によって、定義自体を不可能にするものである。カテゴリーの論理とは、自己と他者との対立に支えられた自己同一性——たとえば男性や女性——にしたがって働くものである。男性vs.女性、ハードvs.ソフト、内vs.外、生vs.死、垂直vs.水平。」※1
「モダニズム=フォーマリズム」が重視する「フォーム」は、必ずしも実質的な形状だけを意味しない。むしろそれは、絵画なら絵画、彫刻なら彫刻、「地」なら「地」、「図」なら「図」といったアイデンティフィケーション、さらにはこれに基づく二項対立の知的な整理の仕方である。「アンフォルム」は、「○○vs.○○」という対立構造の成立を妨げるもの、知性では把握のできない「他者」として、機能していく。
こうして、クラウスの批評活動の軸となってきた「アンフォルム」の機能をジェンダーの文脈に特化して、女性作家に焦点を当てたのが、本書『独身者たち』である。1979年から1999年にかけて、散発的に書かれたエッセイをまとめたものなので、必ずしも一貫した体系をなしているとは言えないが、本書から敢えてひとつのテーマを読み取ろうとすれば、「アンフォルム」の概念を女性作家の作品に特化して適用した「ポストモダニズム・ジェンダー美術批評」ということになるだろう。
以下は、本書の目次と各章の概要である。
- クロード・カーアンとドラ・マール――イントロダクションとして(1999)
- ルイーズ・ブルジョワ――《小娘》としての作家のポートレイト(1989)
- アグネス・マーティン――/雲/(1993)
- エヴァ・ヘス――コンティンジェント(1979)
- シンディ・シャーマン――無題(1993)
- フランチェスカ・ウッドマン――課題集(1986)
- シェリー・レヴィーン――独身者たち(1989)
- ルイーズ・ローラー――記念品の記憶(1996)
クロード・カーアンは、シュルレアリスムの作家であるが、メインストリームからは外れた無名の存在で、研究者からも長らく忘れ去られてきた。彼女が残したセルフポートレイトの作品群は、自身の異性装と写真のトリック効果によって、アイデンティティが錯綜した像を生み出している。
性器を象った、ルイーズ・ブルジョワの彫刻は、ドゥルーズ/ガタリの言う「欲望機械」として機能し、統合された全身像の経験を解体させる。徹底的に孤立したブツとしての器官のリアリティが、抽象的な身体イメージを破壊するのである。
カンヴァスに細かいグリッドを描き込むアグネス・マーティンの絵画は、視る距離によって印象を変化させる。近距離で眼に入ってくるのはカンヴァスの生地や描線の擦れなどだが、ひとたび絵から後退すると、半透明の大気が、イリュージョンとして出現する。彼女の絵は、ユベール・ダミッシュが『雲の理論』で展開した議論——視覚の近代を統べる遠近法は、ブルネッレスキの実験によって実証されたまさにその瞬間から、「雲」という実測不可能な要素によって裏打ちされてきた、という論――と相即するように、或る一点から視えるスタティックな「フォーム」を不安定なものにする。
エヴァ・ヘス《コンティンジェント》(1969)は、半透明のグラスファイバーでできた8枚の膜を天井から吊るした作品である。この作品は、展示室の壁に対して直角に並置されているために、観者は膜の縁を視ることになる。視る角度によって様相を変えるこの作品が惹起するのは、絵画と彫刻という別々の鑑賞モードが侵蝕し合っているという感覚だ。メディウム間、カテゴリー間の境界がボヤけていくのである。
シンディ・シャーマンは、さまざまなメディアで構築されてきた「女」のイメージの構造を、批判的に暴き出していく。たとえば、《アンタイトルド・フィルムスティル》(1977-80)で、ハリウッド映画やヌーヴェル・ヴァーグの女性キャラクターに扮した彼女のセルフ・ポートレイトは、フェティッシュの対象として「女」を捉える男の視線を浮かび上がらせる。《名画(オールド・マスター)》(1989-90)では、彼女の身体に取り付けられた人工のボディ・パーツが重力を強調しているのだが、これは伝統的な西洋絵画が継承してきた美の垂直性を地に引きずり降ろす。また、彼女の作品で多用される光の反射は、実測的なひとつの視点から得られるゲシュタルト――欠陥のない完璧な形態――を侵犯する。彼女の作品に写し出される、脱フェティッシュ化された「女」の身体が、ファロセントリックな「フォーム」の生成の条件自体をなし崩しにするのである。
フランチェスカ・ウッドマンは、22歳で夭折した写真作家である。RISD(ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン)時代の作品には、授業で出された課題とおぼしきタイトルが鉛筆で付されているが、彼女はこうした課題を後の作家活動においても自らに課し、それを発展させていく。たとえば「Space2」シリーズ(1975-76)では、ガラスケースのなかで、板ガラスに押しつけられた裸の身体が写し出されている。たとえば「House」シリーズ(1976)では、廃屋の剥がれた壁紙に身を隠し、壁と同化した状態のウッドマン自身が写し出されている。こうした彼女の写真作品は、三次元の構造を二次元に落とし込む「写真」というメディウムの特性を効果的に利用し、確固とした身体の境界を曖昧に融解させていく。
シェリー・レヴィーンの《独身者たち》(1989)は、デュシャンの《大ガラス》(1915-23)に組み込まれた独身機械——憲兵、召使い、葬儀屋、警官、デパートの配達人——を、小さなガラス製の彫刻に作り替え、ひとつひとつをガラスのショーケースに隔離したものだ。この作品では、二次元の平面に閉じ込められていた独身機械を三次元の現実世界に組み入れると同時に、個々の独身機械を切り離すことで、自閉した《大ガラス》の内部空間で繰り返される欲望の循環を、他の欲望の系列へと解放していくのである。
ルイーズ・ローラーの作品は、通俗的な商品文化の様々なアイテムを寄せ集め、それを写真に収め、さらに文鎮型のレンズの形態に落とし込む、というものだ。これは、スペクタクル世界における芸術の様相を捉えている。スペクタクルの世界では、美術の制作活動の身振りすべてが、記号交換のひとつのトークンと化してしまう、という状況である。またこの作品では、文鎮型レンズが覗き穴と同様の働きをしているために、観者は窃視症者のように作品に対峙する構造になっていて、これを視る際には公共空間から締め出されるようになっている。
クラウスは、「統合性」や「支配」といった、ほかならぬ男の論理から排除され抑圧されてきた女性作家たちを「独身者」として選出し、その作品を詳細に描写していく。ここで取り上げられている作家たちが美術史に残した功績は無視できないものであるにもかかわらず、必ずしも日本で十分に認知されているとは言えない。だから本書の刊行から10年以上が経っているが、いまでも読まれてしかるべきものだろう。また、作品の具体的な記述から論を組み立てるクラウスの「批評」のスタンスは、いまでもなお鮮烈なものである。まず理論ありきで、美術作品をその理論に押し込めていくといったものが多いなか、作品に対する自らの感覚を書き付ける彼女の方法には、凡百の美術批評家にはない説得力がある。情報の奴隷になっていないからである。
井上 康彦(東京藝術大学)
※1 Rosalind Krauss, BACHELORS, MIT Press, 1999, p.7.
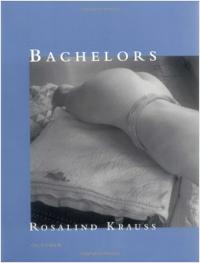
Rosalind Krauss, BACHELORS, MIT Press, 1999.