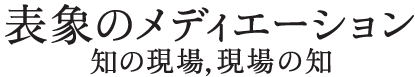発言者:古賀太(朝日新聞社文化事業部)/住友文彦(NTTインターコミュニケーション・センター)/
常石史子(東京国立近代美術館フィルムセンター)/三浦雅士(文芸評論家) 司会:佐藤良明(東京大学) 2005年11月20日(日) 13:30-16:30 18号館ホール  大学を現場に開いていかねばならないという主張は、人文科学の分野ですら、もはや新しいものではない。そしてそこにはつねに2つの前提があった。まず第1に、大学とはなにより「研究」(と教育)がおこなわれる場所であり、現場とはなにより「創造」(と享受)がおこなわれる場所であるということ。それゆえ第2に、大学とは主として「知性」が支配する領域であり、現場とは主として「感性」が支配する領域であるという了解である。 2日目のシンポジウム「表象のメディエーション−−現場の知、知の現場」は、大学(とりわけ人文科学の研究)と現場(とりわけ芸術の実践)の関係を主題にしていながら、しかしこうした2つの「伝統的」な前提とは異なる地点から出発し、また異なる地点を目指している。現場は「創造」の独占領域ではなく(ゆえに大学は「研究」の独占領域ではなく)、したがって現場にも大学とは異なる「知性」が存在する(ゆえに大学にも現場とは異なる「感性」が存在する)だろうという認識が、全体に通底する基本的な作業仮説であった。そのために導入されたのが「メディエーション」の概念である。 パネリストには、4種類の「メディエーション」に従事する4人の「メディエーター」が招かれた。「キュレーター」の住友文彦氏、「アーキヴィスト」の常石史子氏、「プランナー」の古賀太氏、そして「エディター」の三浦雅士氏である。司会は佐藤良明氏が担当した。
NTTインターコミュニケーション・センター学芸員の住友氏は、「現代美術」に付随する特殊なメディエーションの形態を強調した。たとえば、現代美術——いま現在おこなわれている表現行為としての美術——の展覧会をつくろうとするキュレーターは、超越的な立場からすべてを制御することができないだけではなく、純粋なリレー装置に徹することすらもはや不可能であり、否応なくそこに巻きこまれ、みずからが変化する事態までをも余儀なくされるだろう。住友氏によれば、現代美術のキュレーションとは絶えざる問い直しのプロセスにほかならない。 その一方で、人にしろ物にしろ、ともかく「対象」に語らせるためのメディエーションが存在する。東京国立近代美術館フィルムセンターの常石氏は、フィルムの修復というみずからの仕事に触れながら、この逆説的な媒介の快楽について語った。アーキヴィストにとっての「対象」は、スクリーンに投影されたイメージではなく、物質としてのフィルムそのものである。しかもそのフィルムは、たいていの場合あまりにも古いものであるため、アーキヴィストの透明な視線は、フィルムに刻印された図像のみならず、その傷にまで(場合によってはひたすら傷にだけ)さしむけられることになる。 とはいえ、メディエーションは定義上どうしようもなく「不純」な営為である。朝日新聞社文化企画局の古賀氏は、みずから立ち上げた「田中一光展」に即して、現場におけるメディエーションの野蛮ないかがわしさ(もちろんそれは知的な活気とまったく矛盾しない)を一挙に浮上させた。誤解をおそれずにいえば、それは「政治」(意思決定のプロセスの調整)と「カネ」(経済的な基盤の確保)の問題であり、「知」と「権力」の問題である(現場における権威をもっとも容易に保証することができるのは、依然として、専門家としての学者なのである)。 住友氏と常石氏は、どちらも東大駒場表象文化論の出身である。古賀氏も表象文化論でながく授業を担当した経験をもつ。そうした背景も踏まえたうえで、三浦氏は、ある種の総括として、驚くべき観点を提示する。表象文化論という学問領域は、「表象文化」の成立を前提にして成立した。そしていま、表象文化論は、芸術をめぐる知と現場のインターフェイスとして機能することを理念的な柱のひとつとしながら、あらたに「学会」を形成しようとしている。三浦氏は、それが(「学会」の)「始まり」であると同時に(「表象文化論」の)「終わり」を示しているという。しかし、そういいながら、三浦氏の語るヴィジョンがけっして暗いものでなかったことは付言しておくべきだろう。 フロアーとの質疑応答もおこなわれた。とりわけ興味深いのは、その過程で2つの両極的な見解が浮上してきたことである。なんだかんだいっても大学は現場に対してもはや圧倒的に分が悪いという経験的述懐と、ここで示された「現場の知」がじつは「知の現場」の方法論的基礎でもあるという分析的判断が、同じシンポジウムの聴衆からもたらされた。そうした反応を喚起することができたのは、たしかにひとつの「成果」といえる。同じテーマが現場の側から提起されたらどうなるか、想像してみるのも楽しそうである。
[ホームへ戻る]
|